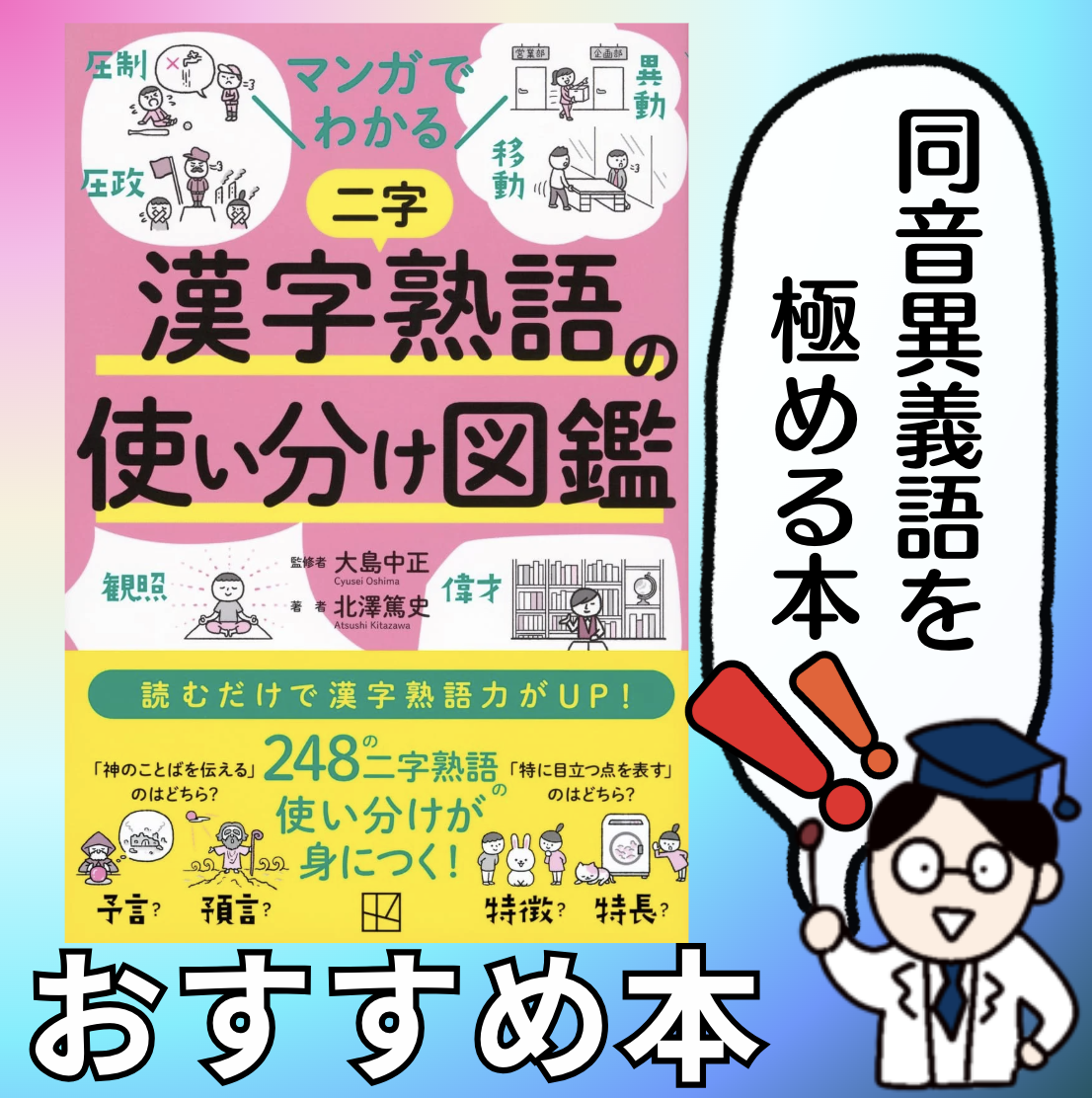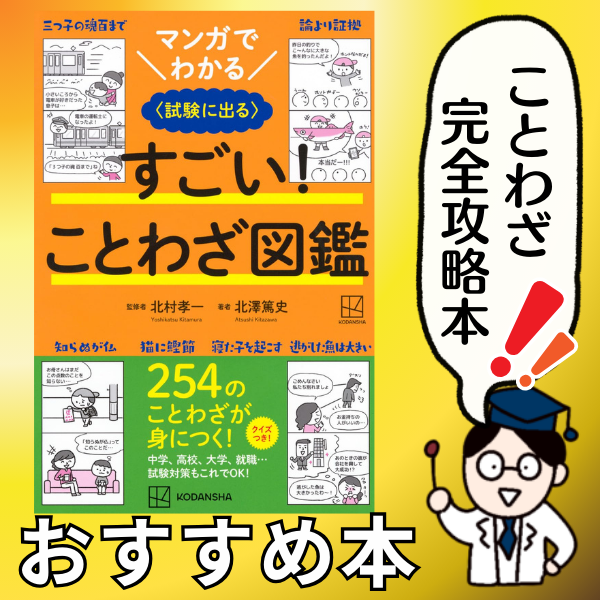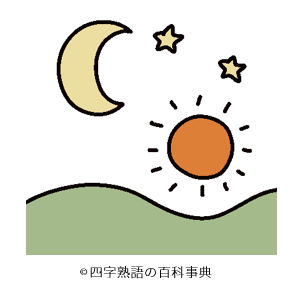『太平記』(たいへいき)は、日本の古典文学の一つで、軍記物語として分類される。全40巻から成るこの作品は、南北朝時代の約50年間(1318年から1368年頃)を舞台に、後醍醐天皇の即位、鎌倉幕府の滅亡、建武の新政の興亡、南北朝の分裂、そして細川頼之の管領就任までを描いています。表題の「太平」は、平和を祈願する意味合いを持ち、怨霊の鎮魂の意義も含んでいるとされています。
作者や成立時期については明確でなく、14世紀中ごろまでには成立していたと考えられています。円観、玄慧など室町幕府と密接な関わりを持つ知識人たちが編纂に関与した可能性が指摘されており、室町幕府の3代将軍・足利義満や管領・細川頼之も修訂に関わったとの見方もあります。しかし、この作品が一人の手によって短期間に書かれたものではないことは広く認知されています。特定の作者名として「小嶋法師」の名が挙げられることが多いが、詳細は不明であり、様々な説が存在します。
内容的には、南朝に肯定的な視点が強く、南朝側の人物が書いた可能性や、南朝への鎮魂の意味が込められているとも言われています。また、当時の社会風潮である「ばさら」や下剋上への批判的な視点も見受けられます。
後代の文芸、特に謡曲や浄瑠璃、草双紙などにも影響を与え、さらに戦後には、『太平記』を題材にした小説やテレビドラマも多数制作されています。