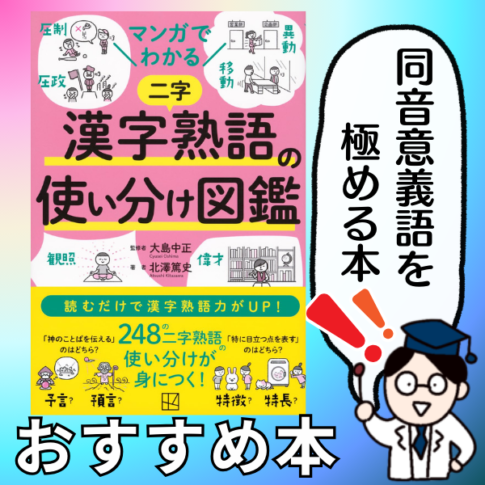四字熟語とは、四字の漢字で構成された熟語のことです。
この記事では、小学校で習う、よく使う有名な四字熟語を五十音順に掲載しました。
小学校1年生〜3年生までに習う漢字で書ける四字熟語は、「小学校低学年(1〜3年生)で習う漢字の四字熟語一覧」をご覧ください。
小学校4年生〜6年生までに習う漢字で書ける四字熟語は、「小学校高学年(4〜6年生)で習う漢字の四字熟語一覧」をご覧ください。
中学受験を目指している小学生の方は、「人気で有名な四字熟語を1000個」と「中学受験頻出四字熟語TOP100」をご覧ください。
当サイトの四字熟語を意味から確認した場合は、「逆引き検索一覧」をご確認ください。
【索引】小学生向けのよく使う四字熟語

| あ行 | か行 | さ行 |
| た行 | な行 | は行 |
| ま行 | や行 | ら行 |
| わ行 |
「あ行」小学生向けのよく使う四字熟語

合縁奇縁(あいえんきえん)
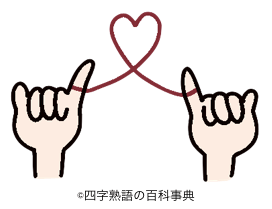
人と人との結び付きは、不思議な縁によるものだということ。
愛別離苦(あいべつりく)

親子、夫婦、きょうだいなど、愛する人と別れ別れになる苦しみのこと。
曖昧模糊(あいまいもこ)
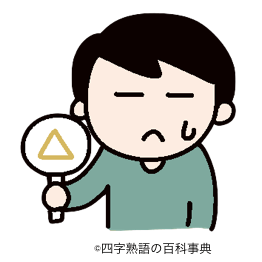
はっきりせず、ぼんやりしているようす。
青息吐息(あおいきといき)

非常に困ってしまって、苦しい息をついているようす。
悪逆無道(あくぎゃくむどう)

人の道に外れた、非常に悪い行い。
悪事千里(あくじせんり)

悪い行いや評判は、たちまち世間に知れ渡るということ。
悪戦苦闘(あくせんくとう)

一生懸命やってはいるのだけれども、相手があまりにも強いため、とても苦しい戦いをしていること。苦しい状態の中で、死にものぐるいで努力していることをいう。
悪口雑言(あっこうぞうごん)
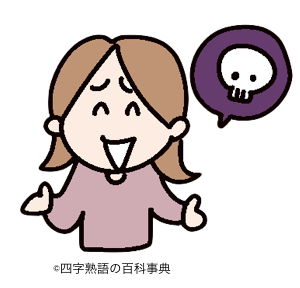
さんざんに、口汚い悪口を言うこと。また、そのことば。
阿鼻叫喚(あびきょうかん)

非常にむごたらしい目にあって逃げまどい、泣きわめきながら救いを求めているようす。
暗中模索(あんちゅうもさく)
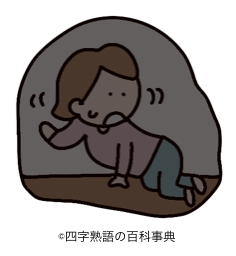
手がかりもなしに、あれこれとやってみること。
意気消沈(いきしょうちん)
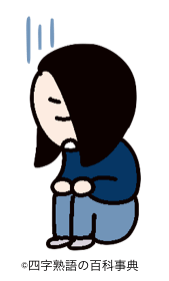
元気をなくして、がっかりすること。
意気投合(いきとうごう)

気持ちや考えが、相手とぴったり合うこと。
異口同音(いくどうおん)
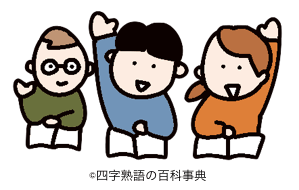
多くの人々が、一度に口をそろえて同じことをいうこと。
意志堅固(いしけんご)

物事をしようとする気持ちが、かたいこと。
意思疎通(いしそつう)

考えや思いが、相手に通じること。
意志薄弱(いしはくじゃく)

何かをやりとげようという気持ちが弱いようす。
意思表示(いしひょうじ)

自分の気持ちや考えを、はっきり表すこと。
医食同源(いしょくどうげん)

薬を飲んで病気を治すことと、日々バランスのとれた食事をすることとは、根は同じだということ。また、正しい食生活を送ることが、健康を守るために一番良い方法だということ。
以心伝心(いしんでんしん)
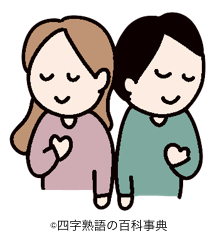
言葉でいわなくても、その人の気持ちがわかってしまうこと。もともとは仏教の言葉で、さとりは言葉では伝えることができない、心から心へ伝えるものだという意味。
韋駄天走(いだてんばしり)

非常に速く走ること。
一意専心(いちいせんしん)

ある一つのことだけに、ひたすら心を集中すること。ただそのこと一つだけに、熱中すること。
一衣帯水(いちいたいすい)
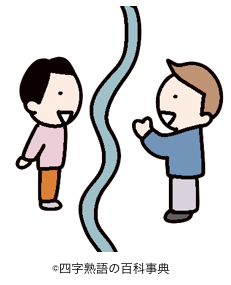
一筋の細い川ほどの隔たりがあるだけで、互いにごく近くに接しているということ。
一言居士(いちげんこじ)

何事にも、ひと言言わないと気がすまない人。
一期一会(いちごいちえ)
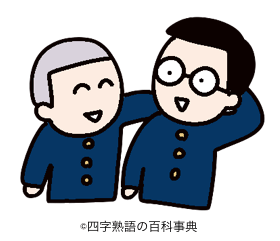
人と人との出会いは、一生に一度しかないこと。また、だからこそ大切にしなければならないということ。
一字一句(いちじいっく)
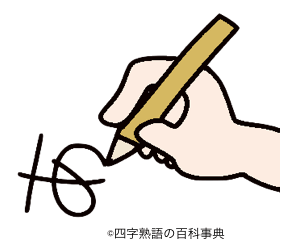
一つの文字と一つの句。ほんのわずかな文字や言葉のこと。
一日千里(いちじつせんり)

並外れて優れた才能をもっていること。
一日之長(いちじつのちょう)

知識や技能などが、他の人より少し優れていること。
一汁一菜(いちじゅういっさい)

非常に質素な食事のこと。
一大決心(いちだいけっしん)

非常に重要な決心。
一諾千金(いちだくせんきん)

ひとたび承諾したことには千金の重みがあるということから、約束は必ず守らなければならないということ。また、ほんとうに信頼できる確かな承諾や約束。
一日一善(いちにちいちぜん)

一日に一つ、よいことをすること。
一日千秋(いちにちせんしゅう)
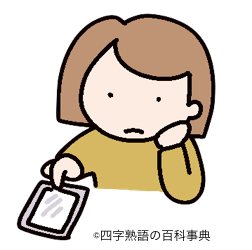
一日が千年にもあたるくらい、長く感じられること。ある特別な日が来るのを、じりじりとした気持ちで待っていることをいう。
一年之計(いちねんのけい)

一年間の計画。
一念発起(いちねんほっき)

心をすっかり入れかえて、今までしようと思ってもなかなかできなかったことに、一生懸命取り組む決心をすること。一大決心をすること。
一病息災(いちびょうそくさい)

病気が一つあるくらいのほうが、体に気をつけるから、かえって長生きするということ。
一部始終(いちぶしじゅう)

あるものの始めから終わりまで。最初から最後までの、細かな事情や内容をいう。
一望千里(いちぼうせんり)

ひと目で遠くまで、広々と見渡せること。
一枚看板(いちまいかんばん)
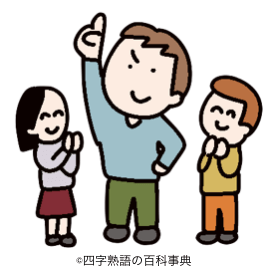
①大勢の中の、中心になる人物のこと。
②人に見せられるような、たった一つのもの。
一網打尽(いちもうだじん)

一回打った網で、すべての魚を取りつくすこと。えものや、悪いことをしているグループを、いっぺんに全部つかまえることをいう。
一目瞭然(いちもくりょうぜん)
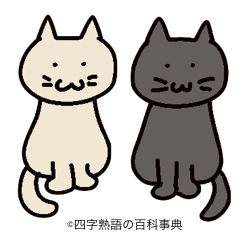
ひと目見て、はっきりとわかるようす。
一問一答(いちもんいっとう)

一つ質問し、一つ答えること。また、そのように質問と答えをくり返すこと。
意中之人(いちゅうのひと)
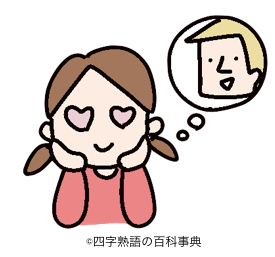
心に決めている人のこと。
一陽来復(いちようらいふく)

①冬が去って、春が来ること。
②悪いことが続いた後に、よいほうに向かうこと。
一利一害(いちりいちがい)

よいこともあるが、悪いこともあること。
一蓮托生(いちれんたくしょう)
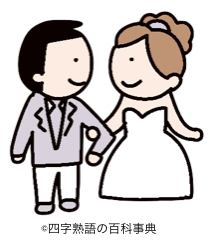
他の人と最後まで、行動や運命をともにすること。
一路邁進(いちろまいしん)

目的に向かって、まっすぐ突き進むこと。
一攫千金(いっかくせんきん)

一度に楽々と、大もうけをすること。
一家団欒(いっかだんらん)
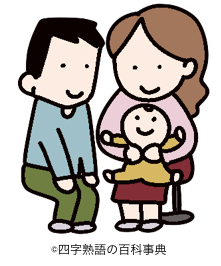
家族みんなが集まって、なごやかに過ごすこと。
一喜一憂(いっきいちゆう)

場面や状態がよくなったり悪くなったりするたびに、喜んだり心配したりすること。
一騎当千(いっきとうせん)
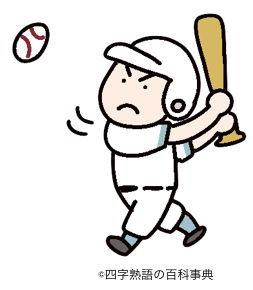
すばらしく強いこと。
一球入魂(いっきゅうにゅうこん)

野球で、投手が一球一球心をこめて投げること。
一挙一動(いっきょいちどう)

一つ一つの動作。ちょっとした動作。
一極集中(いっきょくしゅうちゅう)
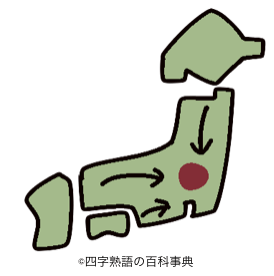
一つの決まった地域に、さまざまなものが集まること。
一挙両得(いっきょりょうとく)

一つのことをして、二つの利益を得ること。
一国一城(いっこくいちじょう)

一つの国と一つの城を持っていること。ほかから、あれこれ指図されることなく、しっかり独立していること。
一刻千金(いっこくせんきん)

ほんのわずかな時間だけど、多額な金銭に当たるくらいの価値があるということ。たった一時でも、何物にもかえられないくらい貴重な場合がある。
一切合切(いっさいがっさい)

何もかも、すべて。
一生懸命(いっしょうけんめい)

一生の命をかけるくらいの決心をして、あることに向かうこと。この上ないほど心をこめて、何かをすること。
一触即発(いっしょくそくはつ)
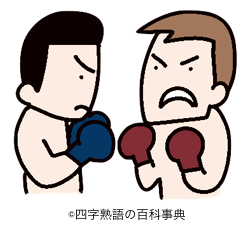
ちょっとさわっただけで、すぐに爆発しそうなこと。ちょっとしたきっかけで、びっくりするような大きな事件や戦いなどが起きそうなとても危険な状態にあること。
一所懸命(いっしょけんめい)

「一生懸命」のもとになった言葉。江戸時代より前は「一所懸命」だけが使われていた。今でも「一所懸命」を使う人がいる。
一進一退(いっしんいったい)

少し進んだかと思うと、また少し退くこと。状態がよくなったり悪くなったりすること。
一心同体(いっしんどうたい)

人と人との心がぴったり合わさって、一人の人のようになること。また、そうして、力を合わせることをいう。
一心不乱(いっしんふらん)

ただ一つのことだけに心が集中して、ほかのことには気持ちがぜんぜん向いていかないことをいう。
一世一代(いっせいちだい)
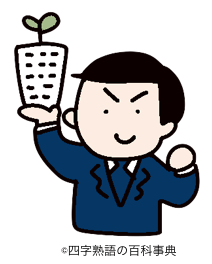
一生の内で、ただ一度だけであること。一生に一回だけというくらい、大切なことをいう。
一石二鳥(いっせきにちょう)
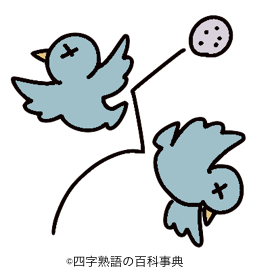
一つの石で、同時に二羽の鳥を打ち落とすこと。一つのことをすることによって、同時に二つの目的を果たせることをいう。
一体全体(いったいぜんたい)

強い疑問を表すことば。
一致団結(いっちだんけつ)
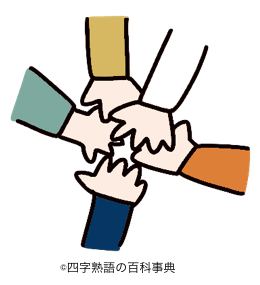
心を一つにして、みんなで協力し合うこと。
一朝一夕(いっちょういっせき)

一朝、また一晩といった短い時間。わずかな期間のこと。
一長一短(いっちょういったん)

あるところは長く、あるところは短い。長所もあれば短所もあるということ。いいところがある一方、欠点もあって完全ではないということ。
一刀両断(いっとうりょうだん)

たった一回振り下ろした刀でものをまっぷたつに切りはなすこと。細かいところなどにはこだわらず、こみいった物事を思い切りをよく整理したり、決めたりすること。
一発勝負(いっぱつしょうぶ)
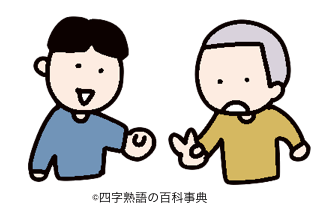
一回だけの勝負。
威風堂堂(いふうどうどう)

態度や雰囲気に威厳があって、りっぱなようす。
意味深長(いみしんちょう)

ある言葉や表現、または態度の裏に、表面にははっきりと表れない、深い意味や気持ちがこめられていること。
因果応報(いんがおうほう)
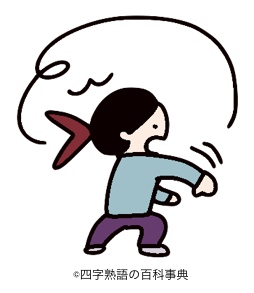
よい行いにはよい報いがあり、悪い行いには悪い報いがあるということ。
因果関係(いんがかんけい)

ある原因から、ある結果が生まれるという関係。
右往左往(うおうさおう)

どうしたらいいのかわからなくなって、右に行ったり左に行ったり、うろうろすること。何がなんだかわからなくなって、うろたえること。
烏合之衆(うごうのしゅう)
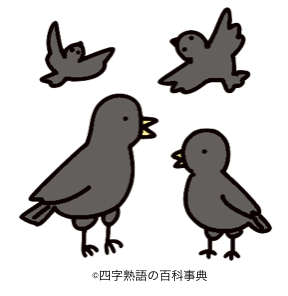
カラスの群れのように、ただ寄ってきただけのばらばらな人の集まり。
有象無象(うぞうむぞう)

数は多いが、どうでもいいくだらない人々。
海千山千(うみせんやません)

さまざまな経験を積んで、世の中を知り尽くし、したたかで抜け目がない人のこと。
有耶無耶(うやむや)

あいまいではっきりしないこと。
紆余曲折(うよきょくせつ)
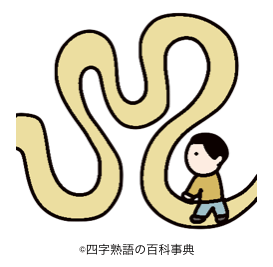
物事が複雑にからみあっていて、解決に時間や手数がかかること。
雲散霧消(うんさんむしょう)
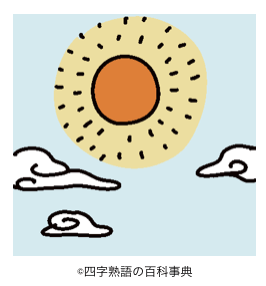
あとかたもなく消えてなくなること。
雲泥之差(うんでいのさ)

二つのもののちがいが、非常に大きいこと。
運否天賦(うんぷてんぷ)

運を天に任せること。
永遠不滅(えいえんふめつ)

いつまでもなくならないで続いて行くこと。
栄枯盛衰(えいこせいすい)
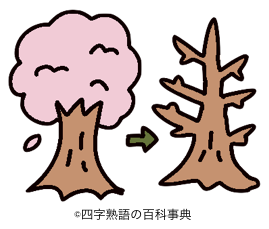
栄えたり衰えたりすること。また、それをくり返す人の世。
依怙贔屓(えいこひいき)
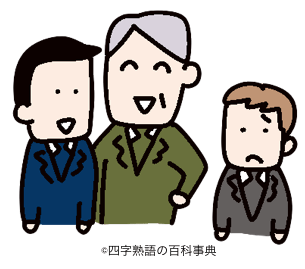
自分の気に入っている人だけを特にかわいがったり、面倒を見たりすること。
会者定離(えしゃじょうり)
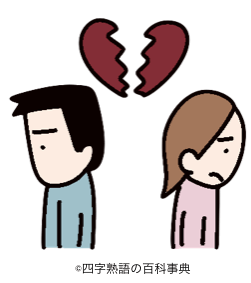
合った者は必ず別れる運命にあるということ。
得手勝手(えてかって)

人のことは考えずに、自分のことばかり考えて何かをすること。
岡目八目(おかめはちもく)

何かをしている本人よりも、それをそばで見ている人のほうが、物事の是非がよくわかるということ。
汚名返上(おめいへんじょう)
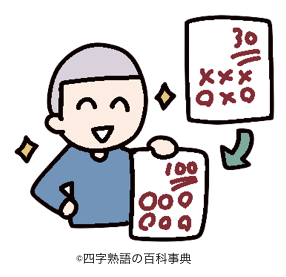
その人を傷つける悪い評判を取り除くこと。
温厚篤実(おんこうとくじつ)
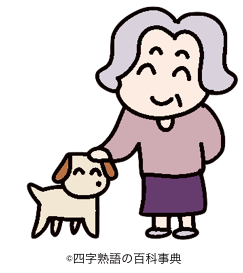
性質が穏やかで思いやりがあり、まじめであるようす。
温故知新(おんこちしん)

前に学んだことや昔のことがらをよく調べて、そこから新しい考え方や知識を見い出すこと。
音信不通(おんしんふつう)
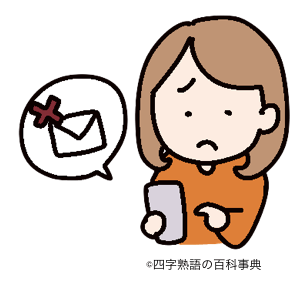
どうしているか連絡がないこと。また、連絡がとれないこと。