紅毛碧眼の意味(語源由来・類義語・英語訳)

【四字熟語】
紅毛碧眼
【読み方】
こうもうへきがん
【意味】
西洋人のこと。


それはつまり、「赤っぽい髪と、青っぽい目の人」を言うんやな。
西洋の人たちの特徴を言うんやな。
これは、「人の特徴を表すための便利な表現」なんやで。
西洋の人たちの特徴を言うんやな。
これは、「人の特徴を表すための便利な表現」なんやで。
【語源・由来】
「紅毛」は赤色の髪の毛、「碧眼」は青色の目。江戸時代は、ポルトガル人やスペイン人のことを「南蛮人」と言っていたのに対して、オランダ人のことを「紅毛人」と呼んで区別していた。後には、西洋人一般をさすことばとなった。
【典拠・出典】
-
【類義語】
・紫髯緑眼(しぜんりょくがん)
【英語訳】
foreigner
英文例
紅毛碧眼の人を見るのは初めてだった。It was the first time to meet a foreigner.
紅毛碧眼の人を見るのは初めてだった。It was the first time to meet a foreigner.
紅毛碧眼(こうもうへきがん)の解説
カンタン!解説
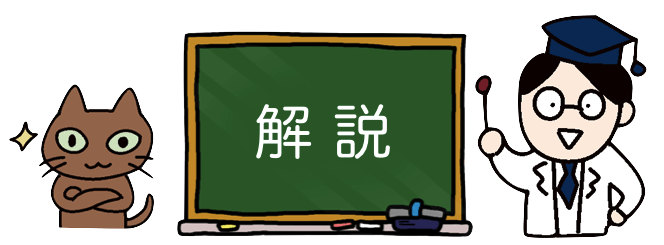
「紅毛碧眼」っていうのは、髪の毛が赤っぽくて、目が青い人、つまり西洋人を指す表現なんだよ。この言葉、江戸時代には特にオランダ人を指す呼び方として使われてたんだ。
それに対して、ポルトガル人やスペイン人は「南蛮人」と呼ばれていたよ。時間が経つにつれて、「紅毛碧眼」は一般的な西洋人を指す言葉になったんだ。
「紅毛」は髪の毛が赤い、という意味で、「碧眼」は目が青い、という意味だよ。「碧」っていうのは緑や青、あるいは青緑色を指すんだ。
ちなみに、この四字熟語は「碧眼紅毛」と言い換えることもできるよ。例えば、「紅毛碧眼の異国の人」って言うと、西洋人の異国人を指しているんだよ。
紅毛碧眼(こうもうへきがん)の使い方
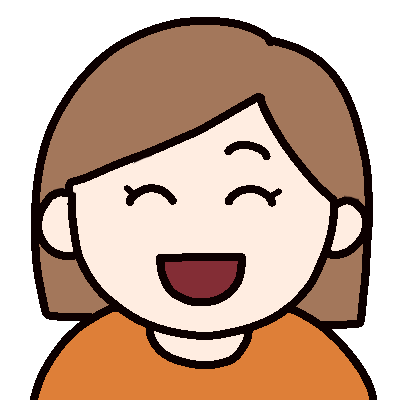
ねえちょっと聞いてよ!わたし、先週末に初めてアメリカ人を見たの!
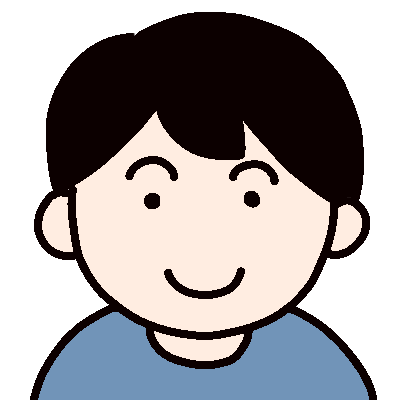
うちの町じゃ珍しいね
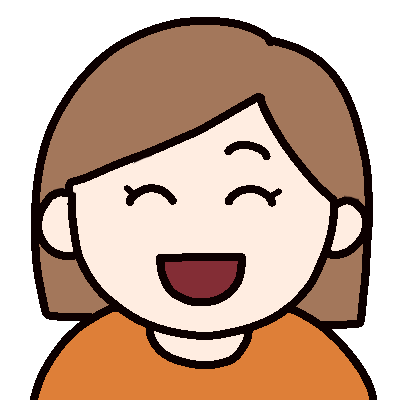
そうなのよ、昔は紅毛碧眼って言い方していたらしいけど、本当に目が青いのよ!本物見るのは初めてよ!
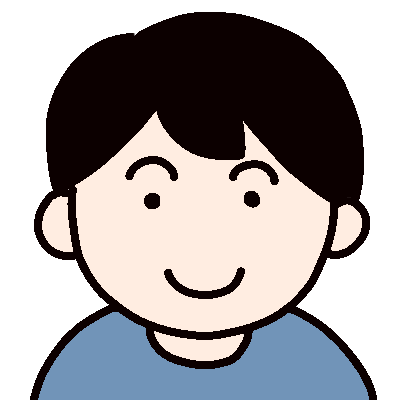
まあ、そこまでテンションあげなくてもいい気がするけど、よかったね
紅毛碧眼(こうもうへきがん)の例文
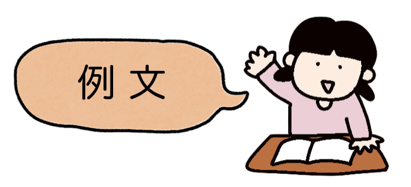
- 今では全然珍しくもなくなったが、昭和になる前には西洋人を見ることはほとんどなかった。そんな時代だから、西洋人の紅毛碧眼が、さぞ珍しかったのだろう。
- 先日、外国人に道を尋ねられた。簡単な英語だったので何とか意思疎通することができたが、間近で見ると、本当に紅毛碧眼なのだなと感心してしまった。
- 日本の伝説に残る鬼の起源は、日本に漂着した西洋人だったのではないかという説がある。鬼も西洋人も、紅毛碧眼な点が共通しているからだ。
- 金髪に青い目、というよりも紅毛碧眼といったほうが、なんとなく高尚な気がするのは、古い言葉だからだろうか。
- 江戸時代には西洋人と接する人は極めて限られていて、一般の人が紅毛碧眼の人たちに会う機会はまったくなかった。
紅毛碧眼の文学作品などの用例
- 紅毛碧眼の異国人が蝙蝠傘をさした日本の遊女と腕を組んで、悠長にそれを見物している。<長与善郎・青銅の基督>
- 予の業慾に憧るる心は、一度唐土にさすらって、紅毛碧眼の胡僧の口から、天上皇帝の御教を聴聞すると共に、滅びてしもうた。〈芥川龍之介・邪宗門〉





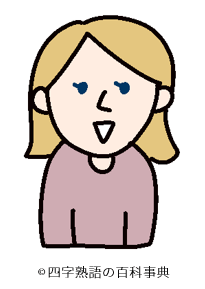





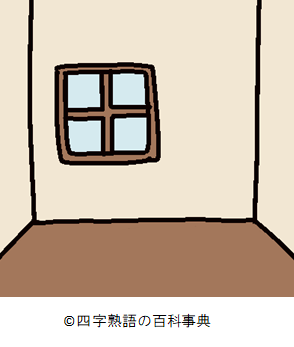
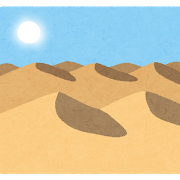
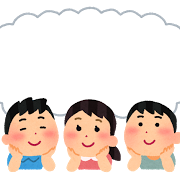


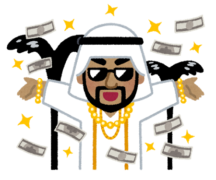




紅色の髪と青い目、つまり赤毛と青眼を持つ人を指す言葉だよ。