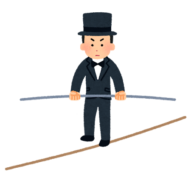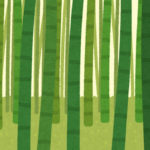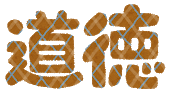【四字熟語】
橦末之伎
【読み方】
とうまつのぎ
【意味】
かるわざ。
【語源・由来】
竿の先で行う曲芸のこと。「橦末」は竿の先。
【典拠・出典】
張衡「西京賦」
橦末之伎(とうまつのぎ)の使い方
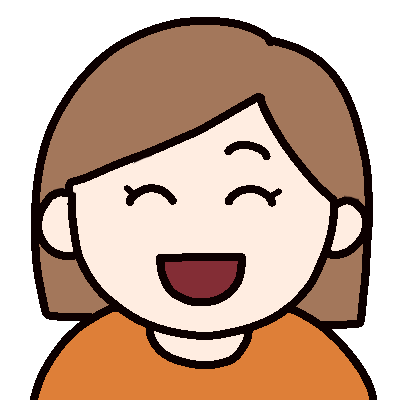
健太くん。あそこに大道芸人がいるわよ。
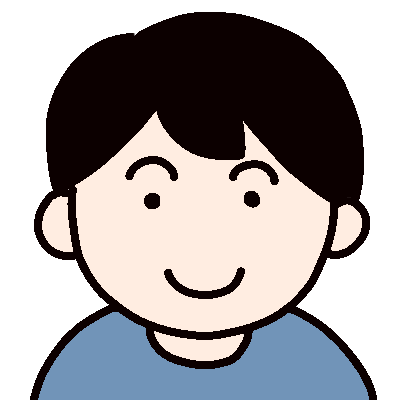
へえ。何をやってくれるのかしら?
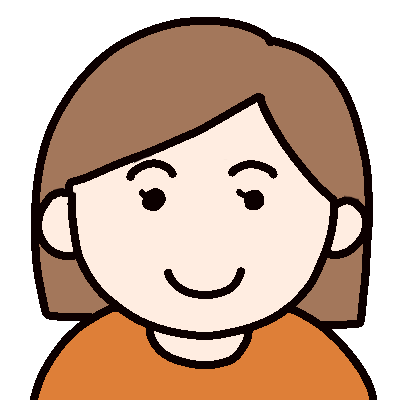
橦末之伎をやってみせてくれるらしいわよ。
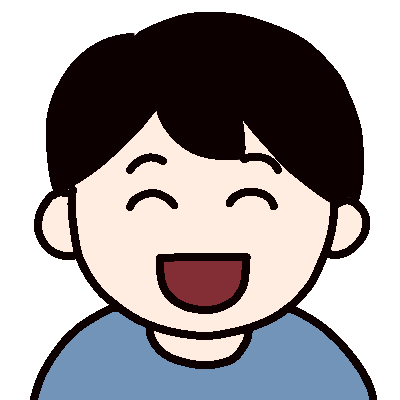
おもしろそうだね。一緒に見に行こうよ。
橦末之伎(とうまつのぎ)の例文
- 健太くんは、あこがれていたサーカスに弟子入りをして橦末之伎を覚えるために努力をしました。
- ともこちゃんは手品や橦末之伎が特技で、よく病院に慰問に行ったりして喜ばれています。
- ロープを伝って隣のビルに逃げるなんて橦末之伎のようなこと、僕にできるわけがないよ。
- 彼の橦末之伎は神業で、世界中にファンがいて、彼が来るのをいまかいまかと待っているんです。
- 橦末之伎のプロになるには、人が好きで体が柔らかく、とにかく動くことが大好きな人が向いているから、健太くんにはいいんじゃないかな。
まとめ
橦末之伎はもともと何かの儀式だったようで、紀元前2500年頃の前漢ですでに行われていたようです。