小春日和の意味(語源由来・英語訳)

【四字熟語】
小春日和
【読み方】
こはるびより
【意味】
冬のはじめのころの、春のようなあたたかい天気の日。
晩秋から初冬にかけて、特に立冬(11月6日)を過ぎてからの春のように暖かい晴れた日のこと。
注意 「春」の字に勘違いし、冬から春にかけての暖かい時期をいうのは誤りです。
暖かい陽気が続く11月頃の気候に使われ、「小春日和」「小春」の季語は冬となっています。
暖かい陽気が続く11月頃の気候に使われ、「小春日和」「小春」の季語は冬となっています。


それやったら、「冬になったけど、まるで秋みたいにぽかぽか暖かい日」ってことやな。
外に出てみると、まだ秋みたいなあたたかさがあって、気持ちいいって感じやで。
これは、「意外と暖かい日」を教えてくれる言葉やね。
外に出てみると、まだ秋みたいなあたたかさがあって、気持ちいいって感じやで。
これは、「意外と暖かい日」を教えてくれる言葉やね。
【語源・由来】
「小春」は陰暦10月の別名で、現在の太陽暦では11月に相当します。小春は「小六月」ともいいます。この頃は春のように穏やかな晴れの気候が続くことから「小春」といわれます。「日和」は晴れたよい天気のことを意味します。小春日和は「小春日」ともいいます。
【典拠・出典】
-
【英語訳】
Indian summer
saint martin’s summer
mild late autumn weather
mild late fall weather
calm autumn weather
balmy autumn weather
warm autumn weather
小春日和(こはるびより)の解説
カンタン!解説
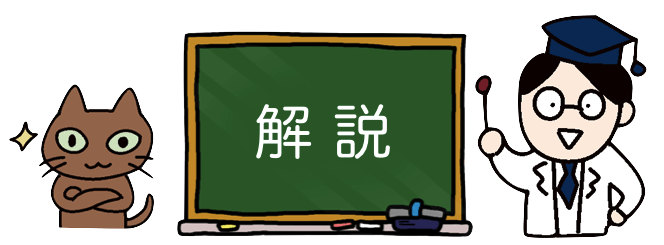
「小春日和」っていうのは、普段なら寒い冬の初めでも、ちょっと春みたいに暖かい日のことを言うんだよ。陰暦で言うと十月の頃に、特にいい天気で暖かい日を指すこともあるよ。
「小春」ってのは、陰暦の十月を指す言葉で、また、寒いはずの冬初めでも、ほんわか春みたいに暖かい気候のことも指すんだ。
それに対して、「日和」ってのは、空が澄んで天気が良い状態を指すんだよ。あるいは、何かをするのに最高にいい天気、って意味でも使われるよ。
だから、「小春日和」は冬の初めにも関わらず、暖かくて春みたいな天気の日、または、陰暦の十月頃の暖かい日、という意味になるんだ。もし小春日和の日があったら、外で遊びたくなっちゃうよね!
小春日和(こはるびより)の使い方
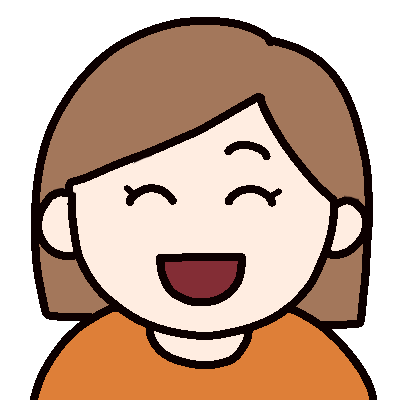
いよいよ12月に入って、今年はあと残り一ヶ月で終わりだね。
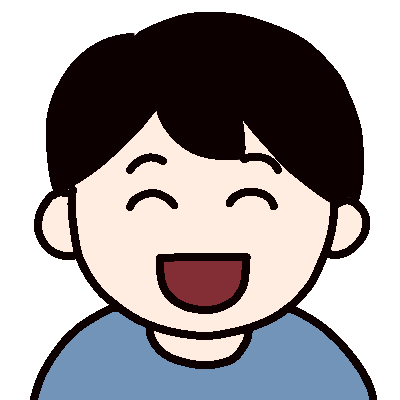
うん。だいぶ寒くなってきたよね。
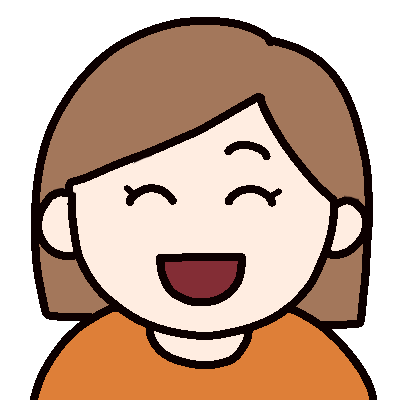
でも昨日は快晴、とても暖かい一日で、本当に小春日和だったね。
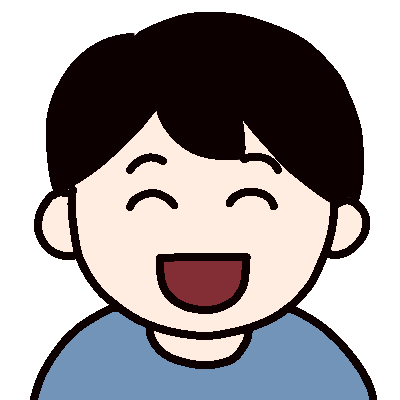
うちの家族は天気が良かったから昨日、公園に遊びに行ってきたよ!
小春日和(こはるびより)の例文
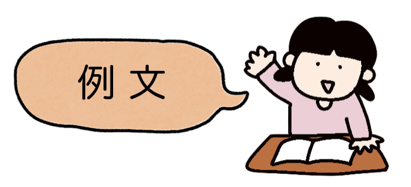
- 小春日和だったことから紅葉狩りに出かけた。
- 晴れた暖かい秋の気候のことを小春日和と言います。
- 小春日和が気持ちよく、家族全員で外出することになった。
- 最近肌寒くなってきたけど、今日は一転、暖かくて穏やかな気温で小春日和の一日となった。
- 小春日和となったことから果物狩りをすることとなった。





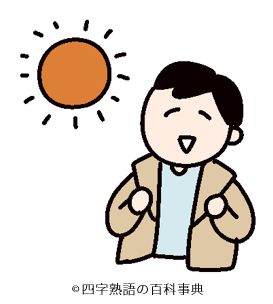






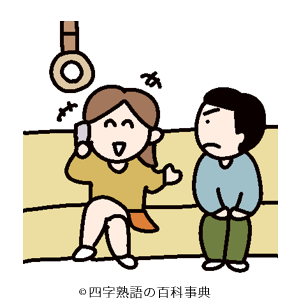




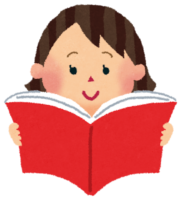



季節はもう冬に入っているのに、ほっこりとした暖かさが感じられるような日のことを指すんだ。