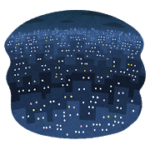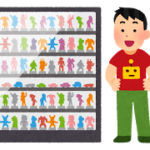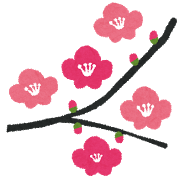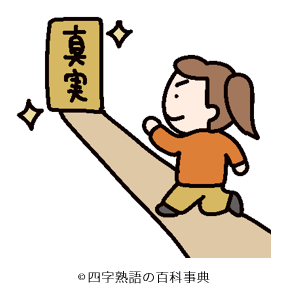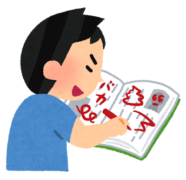哀矜懲創の意味(語源由来・出典・英語訳)

【四字熟語】
哀矜懲創
【読み方】
あいきょうちょうそう
【意味】
懲罰を与えるにしても、相手を思いやる情が必要であること。
「罪を悪んで人を悪まず」の心で懲らしめること。

「哀矜懲創」は、人を罰するときでも、相手のことを思いやる心が必要だという意味があるんだよ。

そやな。それはつまり、「怒るときでも、相手の気持ちを思うことが大事」ってことやな。
だれかを叱るときでも、その人の気持ちを理解して、思いやりを持つことが大切やんな。
これは、「人を思いやる心の大切さ」を教えてくれる言葉やで。
だれかを叱るときでも、その人の気持ちを理解して、思いやりを持つことが大切やんな。
これは、「人を思いやる心の大切さ」を教えてくれる言葉やで。
【語源・由来】
「哀矜」は悲しみ哀れむこと、「懲創」はこらしめることを意味します。特に、「哀矜」は同情する、不憫に思うことで、「矜」には「あわれむ」という意味があります。
【典拠・出典】
蘇軾「刑賞忠厚之至論」
【英語訳】
・punish kindly
・discipline with pity
哀矜懲創(あいきょうちょうそう)の解説
カンタン!解説
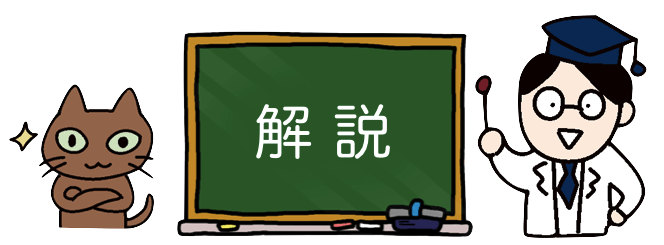
「哀矜懲創」っていうのは、ちょっと難しい四字熟語だけど、要するに「人を罰するときには、その人に対する思いやりの心が必要だよ」という意味なんだ。
なんで思いやりの心が必要かっていうと、罰っていうのはただ人をこらしめるためだけじゃなくて、その人が自分の間違いに気づいて、これからはもっと良い道を歩むためのきっかけになるようなものなんだよ。だから、人を罰するときには、その人のことを哀れんで、思いやりの心を持つことが大切なんだ。
「哀矜」っていうのは、他人のつらさや悲しさを感じ取ること。つまり、相手を思いやる心のことなんだ。「懲創」っていうのは、人をたしなめる、つまり罰を与えることを意味しているんだ。
この言葉の出どころは、蘇軾っていう人が書いた「省試刑賞忠厚之至論」っていう文章から来ているんだよ。蘇軾は中国の宋の時代の有名な文人で、彼の書いた文章からこの四字熟語が出てきたんだ。
哀矜懲創(あいきょうちょうそう)の使い方
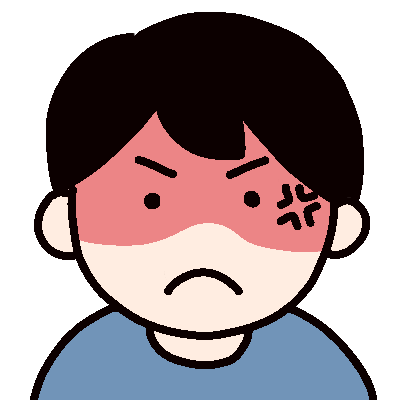
あれ?僕のシュークリームしらない?おやつのシュークリーム、冷蔵庫に入れてたはずなのに、ないんだよ!
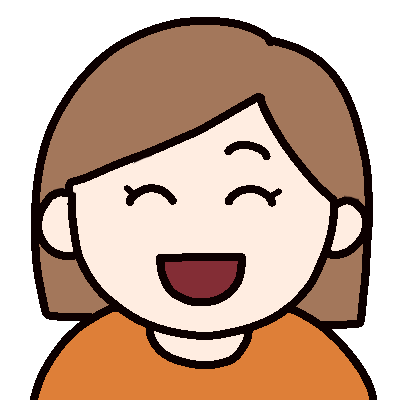
あ、あれ、私食べちゃったわ!
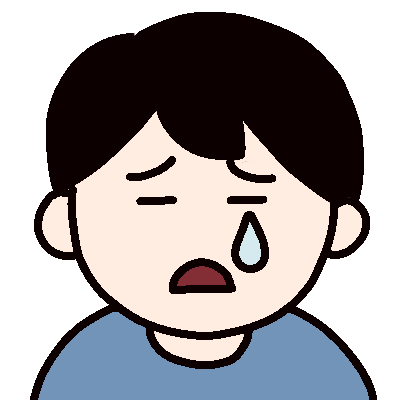
ええー!そんなぁぁ!
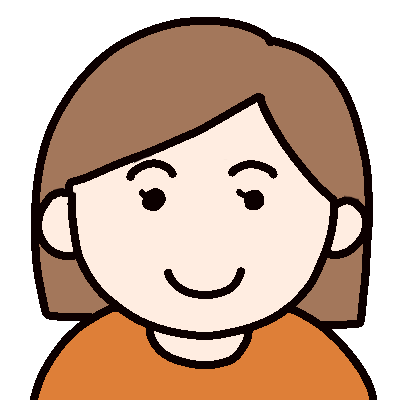
人には哀矜懲創が必要よ。まぁいいじゃないの。
哀矜懲創(あいきょうちょうそう)の例文
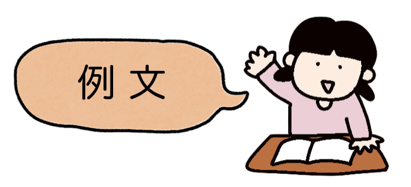
- どんな事件であっても、その裁判官は哀矜懲創を貫いた。
- 罪を裁く者は哀矜懲創の精神をもって事件に当たるべきだ。
- 自分の身内に被害者がいたら、哀矜懲創などできるだろうか。
- さすが大岡越前、哀矜懲創で事件を納めている。