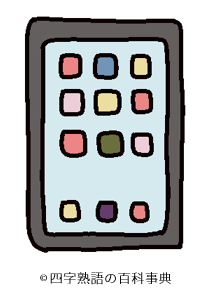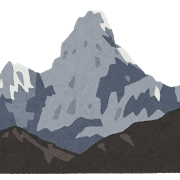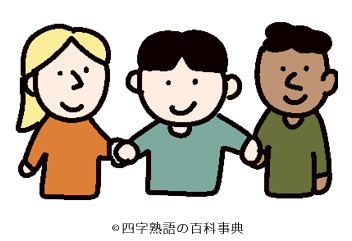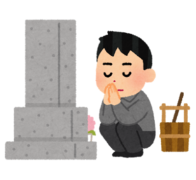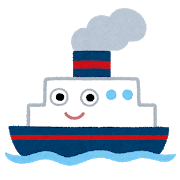軽薄短小の意味(語源由来・対義語)

【四字熟語】
軽薄短小
【読み方】
けいはくたんしょう
【意味】
軽くて薄く、短く小さいこと。
また、内容が薄っぺらくて中身がないことのたとえ。

「軽薄短小」という四字熟語は、物が軽くて薄く、短くて小さいという意味だけではなく、人が浅はかで軽々しい、そして何かと中身がないという意味もあるんだよ。

ほんなら、「物がさっとりと軽くて、薄くて小さい」って感じやな。
でも人間の場合は、「軽はずみで浅い、中身のない人」ってことやな。
何かと言えば、深く考えずに行動したり、真剣に物事に取り組まない人のことを指す言葉なんやで。
でも人間の場合は、「軽はずみで浅い、中身のない人」ってことやな。
何かと言えば、深く考えずに行動したり、真剣に物事に取り組まない人のことを指す言葉なんやで。
【語源・由来】
1980年代頃、電化製品などが小型軽量化したことを表した言葉。
また、社会の風潮を揶揄することにも使われてる。
【典拠・出典】
-
【対義語】
・重厚長大(じゅうこうちょうだい)
軽薄短小(けいはくたんしょう)の解説
カンタン!解説
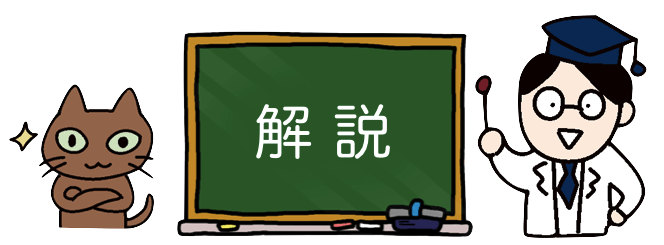
「軽薄短小」っていうのは、物が軽くて薄く、小さくて短いという意味だよ。例えば、小さいサイズの薄いノートパソコンとか、薄型のスマホとかが「軽薄短小」に当たるね。
でも、「軽薄短小」は、物の大きさや形だけじゃなくて、中身や内容についても使うんだ。つまり、内容が薄っぺらで、中身があまりないという意味もあるんだよ。たとえば、「軽薄短小な本」って言ったら、その本がページ数が少なくて、内容もあまり深くないという意味になるんだよ。
あと、商品について「軽薄短小な商品」と言ったら、その商品が小さくて軽く、あまり中身が詰まってない、っていう意味になるよ。例えば、プラスチック製の小さなおもちゃとか、内容の薄い情報誌とかが「軽薄短小な商品」になるね。
軽薄短小(けいはくたんしょう)の使い方
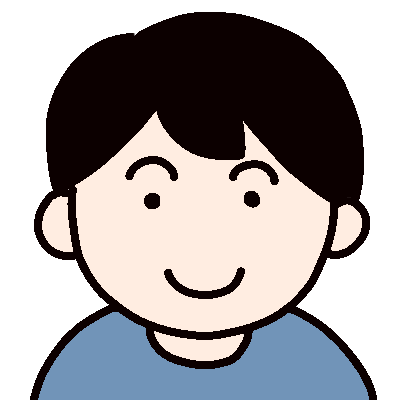
昔は、携帯電話があんなに重くて大きかったなんて、ともこちゃんは知っていたかい。
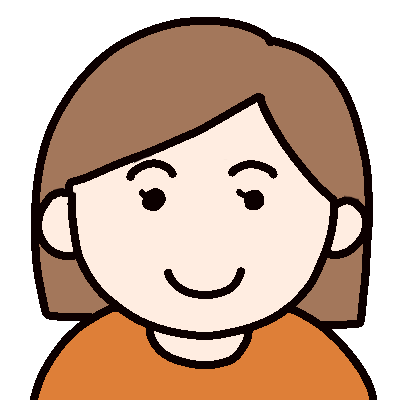
初めて知ったわ。もっと昔は、携帯電話なんてなかったんでしょう。
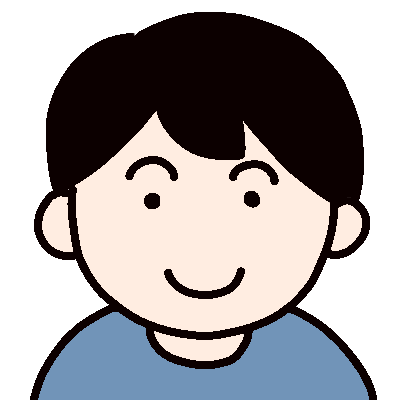
今は考えられないことだよね。
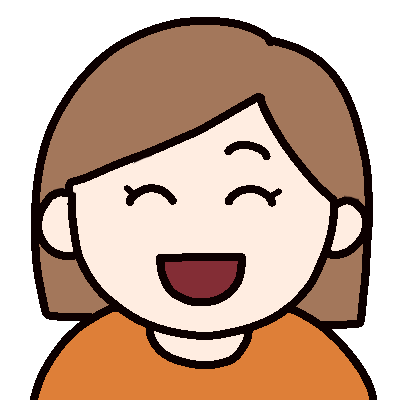
そうね。軽薄短小が進んで、本当に良かったと思うわ。
軽薄短小(けいはくたんしょう)の例文
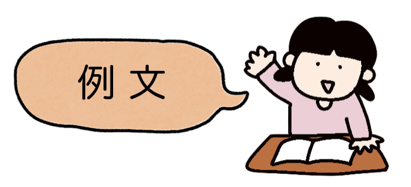
- 日本の産業は、軽薄短小化が進んだことで、大きく発展したのではないだろうか。
- 叔父は、軽薄短小な時代だと嘲笑していたけれど、今の世の中も捨てたものではないと思う。
- 特に電化製品は、軽薄短小したことで、とても便利になった。
- 重厚長大から、軽薄短小へと移り変わっている、激動の時代のようだ。
- 君たちは軽薄短小だと言われたけれど、そんなことを言っている彼の方が中身などないじゃないか。