長者三代の意味(語源由来・英語訳)

【四字熟語】
長者三代
【読み方】
ちょうじゃさんだい
【意味】
金持ちの家は三代までで、その後は続かないということ。
長者の家は三代よりは続かないということ。


それって、すなわち、「お金持ちの家でも、3代でお金持ちが続かへんことが多い」っていうことやな。
お金を持つって難しいけど、それを守り続けるのもまた難しいんやで。
これは、「お金持ちでも注意しないと、すぐに貧乏になる」ってことを教えてくれる言葉やな。
お金を持つって難しいけど、それを守り続けるのもまた難しいんやで。
これは、「お金持ちでも注意しないと、すぐに貧乏になる」ってことを教えてくれる言葉やな。
【語源・由来】
祖父が苦労して財産を蓄えても、その子が財産を使い、さらに孫も楽をして贅沢し浪費してしまうので、財産は三代で無くなってしまうことを意味しています。
【典拠・出典】
-
【英語訳】
A rich person is only three generations and it does not follow.
長者三代(ちょうじゃさんだい)の解説
カンタン!解説
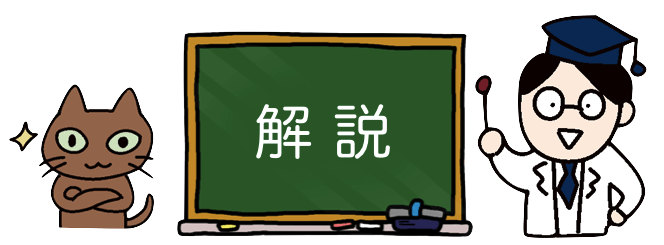
「長者三代」っていうのは、お金持ちの家が長く続かないという意味なんだよ。たとえば、おじいちゃんが一生懸命働いてお金をためたとしても、その子供たちはそのお金を使ってしまい、孫たちはもっと楽をして遊んでばかりいると、結局、そのお金は三代でなくなってしまうっていう意味だよ。
つまり、「長者三代」は、どんなに一生懸命働いて財産を作ったとしても、その次の世代やその次の世代がそれを浪費してしまって、最終的にはなくなってしまうという悲しい現実を表しているんだよね。だから、大切なのはお金を得るだけじゃなくて、それをどう管理するか、そしてそれを次の世代にどう教えるかだね。
長者三代(ちょうじゃさんだい)の使い方
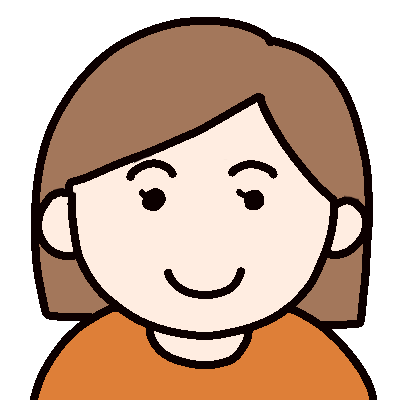
佐藤さんはお金持ちだよね。佐藤さんのおじいちゃんがすごいみたい。
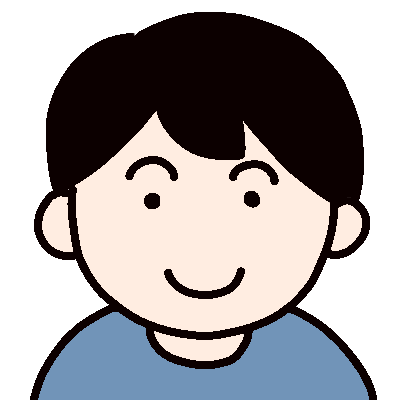
うん、聞いたことがある。大会社を作った人だって有名だよ。
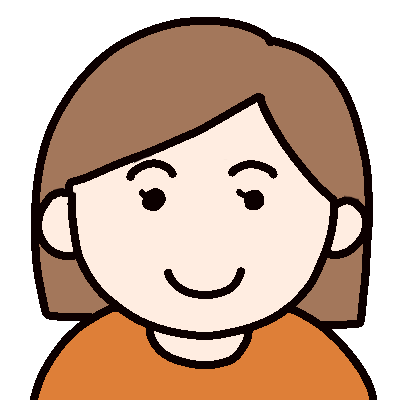
でも、時代の流れもあったり、最近は財産があまりないみたい。
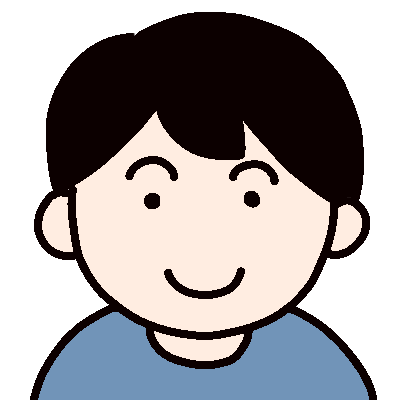
長者三代というから、どこも同じかもしれないね。
長者三代(ちょうじゃさんだい)の例文
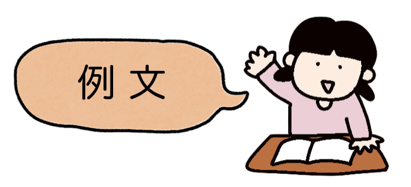
- 祖父が築いた財産はもう殆どないようだ。まさに長者三代だね。
- 長者三代と言うが、子どもや孫にしっかりと教育すれば、さらに財産を増やすことだって可能だ。
- お金があれば誰もが楽をしてしまう。長者三代も人間の性ともいえるのではないか。
- 長者三代は教育の重要性を示唆しているようで、苦労することは貴重な経験でもある。
- ライオンは子どもを崖から落とすと言われるように、長者三代とならないよう、子どもや孫に苦労を経験させることは大切だ。













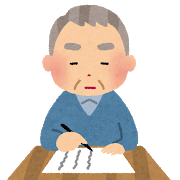

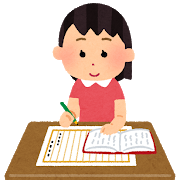





これは富の持ち続けることの難しさを教える言葉なんだ。