「月下氷人」の意味とは?(出典・類義語)

【四字熟語】
月下氷人
【読み方】
げっかひょうじん
【意味】
仲人。媒酌人。縁を取り持つ人。
【典拠・出典】
『晋書』,『続幽怪録』「四」
【類義語】
・月下老人(げっかろうじん)
唐の韋困が月明かりの下で出会った老人は、縁結びの本を読み、伏ルの中の赤い糸で結婚をする男女の足首を結ぶのだという。それから3歳ほどの女の子を指さして、韋困の結婚相手だと予言する。14年後、韋困は予言の娘と結婚する。
【英語訳】
go-between、matchmaker、Cupid
月下氷人(げっかひょうじん)の故事
故事を簡単に説明!
月下氷人(げっかひょうじん)の使い方
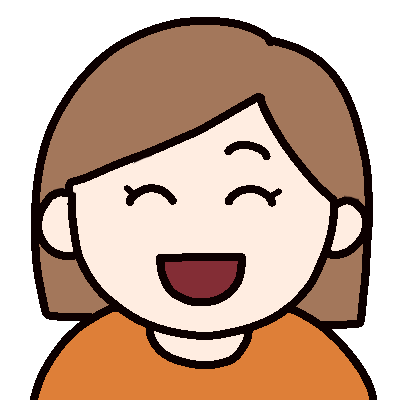
今日はとても素敵な話を聞いちゃったの!
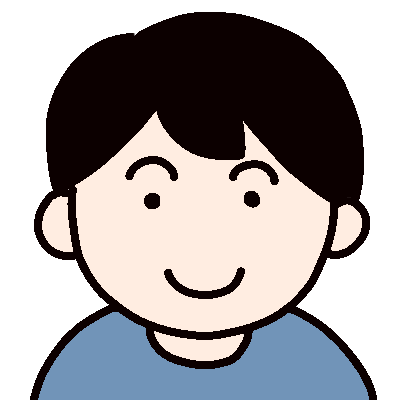
え?なになに?いったいどんな話なの?
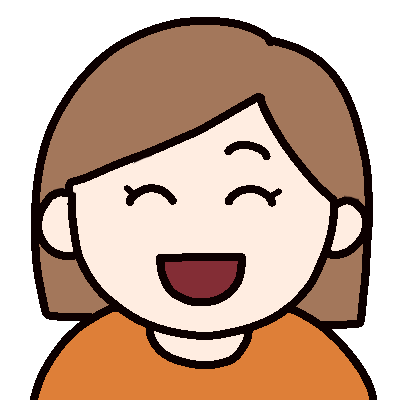
お父さんとお母さんが結婚した時の月下氷人だった2人が、のちに結婚して、今度はお父さんとお母さんがその2人の月下氷人になったんだって!
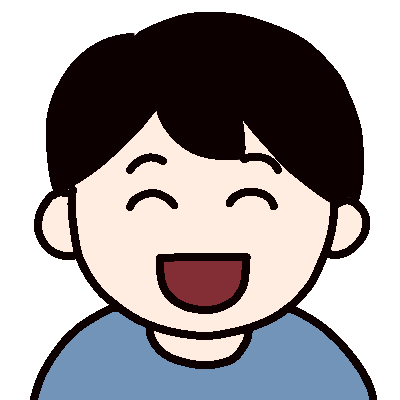
ドラマみたいな話だなあ!僕も素敵な人と出会いたいなあ~。
月下氷人(げっかひょうじん)の例文
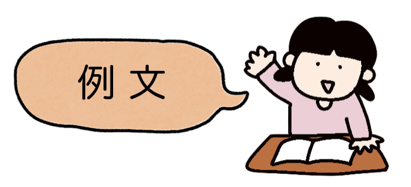
- 私の父と母の月下氷人は、私の今の担任の先生なのだから世間は狭いと思う。
- 僕と彼女が結婚した暁には、ぜひ君に月下氷人をお願いするよ。
- 僕と彼女が出会ったのは高校の部活動なので、月下氷人は部活の顧問の先生だと思う。
- 私にも早く月下氷人が現れないかしら、と言っている友人は、もう40歳を越えた。
- 実は結婚することになったんだ。月下氷人を頼めないだろうか。
- 夢で見た人と結婚することになった。そばにいたあの人が月下氷人なのかもしれない。
まとめ
月下は「続幽怪録」四、氷人は「晋書」索紞伝に掲載されているので、興味がある人はぜひ読んでみてほしい。月下氷人を待つよりも運命の人は自分で探した方が、他人任せにするよりもいいかもしれない。
















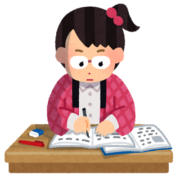

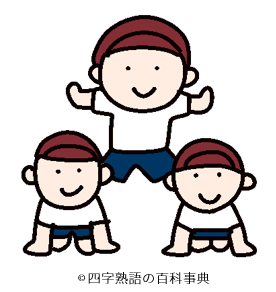


「月下氷人」は、中国の二つの伝説がもとになって生まれたことばです。
一つ目は、唐の時代の「月下老人」の話です。韋固という青年が旅の途中、月の光の下で本を読む老人に出会いました。老人は結婚を司る幽界の人だと言います。
老人は、袋の中に赤い縄を持っており、「この縄で男女の足をつなぐと二人は夫婦になる」と語ります。
韋固は、老人に運命の相手を尋ねると、三歳の少女だと言われました。結局、青年は後に成長したその少女と結婚することになります。これは「続幽怪録」という書物の中の「定婚店」という話です。
二つ目は、晋の時代の「氷人」の話です。狐策という役人が、氷の上に立ち、氷の下の人と話す夢を見ました。占い師の索紞に相談すると、索紞は「氷の上は陽、氷の下は陰で、これは男女を意味する。あなたは近いうちに仲人を務めることになる」と占いました。
その後、狐策は本当に仲人を務めることになります。こちらは「晋書」に載っている話です。
この二つの「月下老人」「氷人」の伝説が合わさり、「月下氷人」という言葉が生まれ、仲人の意味として使われるようになったのです。