異国情調の意味(語源由来・類義語・英語訳)

【四字熟語】
異国情調
【読み方】
いこくじょうちょう
【意味】
外国風の独特の雰囲気や趣き。
外国風の建物や外国人の風俗などから、影響を受ける。
また、外国らしい雰囲気や味わいに出会った時の気分をあらわす。


それはつまり、「外国の雰囲気が感じられる」ってことやな。
外国ならではの景色やものが作る、ちょっと特別な感じやで。
これは、「外国の独特な雰囲気を楽しむ」っていう気持ちを表してるんやな。
外国ならではの景色やものが作る、ちょっと特別な感じやで。
これは、「外国の独特な雰囲気を楽しむ」っていう気持ちを表してるんやな。
【語源・由来】
「異国」は外国。
医学者であり、小説家でもある『木下杢太郎(きのしたもくたろう)』が作った言葉。異国ムード(mood)に相当する日本語として用いられた。
昭和前期までは「異国情調」、昭和後期からは「異国情緒」として使われるのが一般的である。
【典拠・出典】
-
【類義語】
・異国情緒(いこくじょうちょ)
・異国趣味(いこくしゅみ)
【英語訳】
・Foreign atmosphere
・an exotic mood
異国情調(いこくじょうちょう)の解説
カンタン!解説
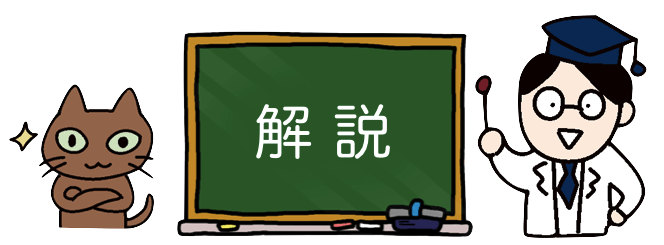
「異国情調」っていうのは、他の国の特別な雰囲気や魅力を感じることを表すんだよ。たとえば、外国風の建物を見たり、外国の習慣を体験したりすることで、その外国っぽさに触れる感じだよ。
また、「異国情調」は、違う国の特色や魅力に出会ったときに感じる気持ちも表すよ。なんていうか、海外旅行に行ったときに、新しい風景や食べ物、人々の生活に触れて、わくわくしたり、感動したりする感じさ。
この言葉は、昔は「異国情調」っていう風に使われてたんだけど、昭和の後半からは「異国情緒」っていう形に変わってきたんだよ。「異国」という部分は、医者でもあり小説家でもあった木下杢太郎さんが作った言葉で、他国のムード、つまり雰囲気を日本語で表すために使われたんだよ。
異国情調(いこくじょうちょう)の使い方
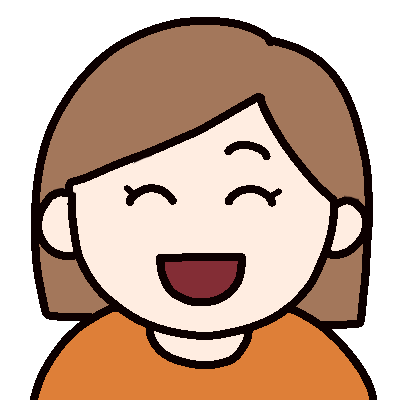
わあ! ここが中華街ね! たくさんの中華料理店があるわね~!
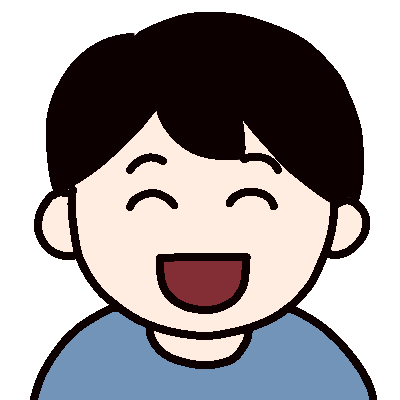
雑貨店や洋服屋まで中国風だね。あっ、チャイナ服も売ってるよ!
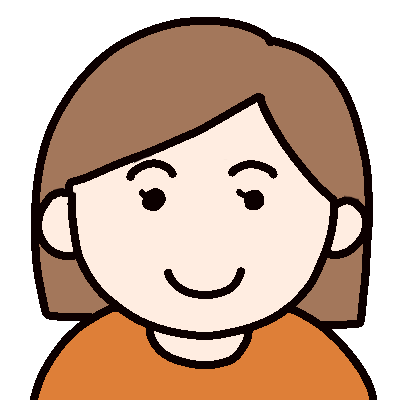
何て書いてあるのかしら? 中国語だから分からないわ。
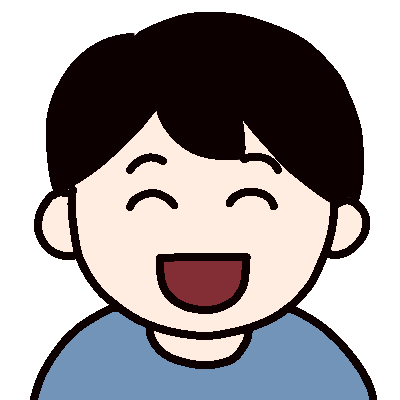
まさに異国情調満点! ここは日本じゃないみたいだね。
異国情調(いこくじょうちょう)の例文
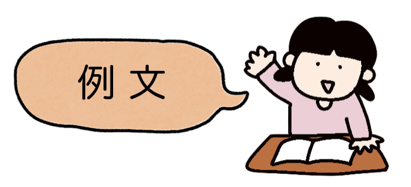
- グラバー園や見事なステンドグラスの教会、中華街にオランダ坂、長崎市は行き交う人々の日常の中に異国情調が息づく観光スポットです。
- 異国情調あふれる街
- 和の創作現場であるこの江戸切子工房において、西洋趣味を反映させた異国情調に富んだデザインが流行の兆しを見せている。
- 彼女の部屋には異国情調の豊かな豪華家具が配置されている。
- 怪しい異国情調の音楽
- 新人作曲家の彼女はスペイン帰りの帰国子女だ。そういうわけで、フラメンコのリズムを取り入れた異国情調が色濃い曲が多い。
- この港に来ると異国情調に対する憧れが強くなる。





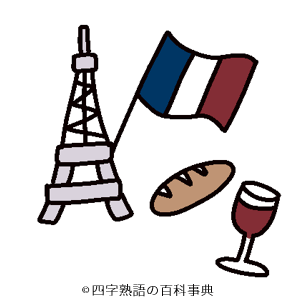















外国ならではの独特な感じ、つまり異国の情緒が感じられることを表現するんだ。