旗幟鮮明の意味(語源由来・類義語・英語訳)

【四字熟語】
旗幟鮮明
【読み方】
きしせんめい
「旗幟」を「きしょく」と読み誤まらない。
【意味】
主義主張や態度などがはっきりしているたとえ。立場や主張がはっきりしていること。自分の主義や持論、立場がはっきりとしていること。


ほんなら、「自分の考えや意見がハッキリしてる」ってことやな。
自分の旗をど真ん中に立てて、自分の意見をしっかりと示すんやな。
これは、「自分の意見をはっきりと表す大切さ」を教えてくれる言葉なんやで。
自分の旗をど真ん中に立てて、自分の意見をしっかりと示すんやな。
これは、「自分の意見をはっきりと表す大切さ」を教えてくれる言葉なんやで。
【語源・由来】
「旗幟」は旗・のぼり、戦場で敵と味方を区別する旗印のことの意味で、表立って示された主義主張や持論、態度のたとえです。「鮮明」は鮮やかではっきりしていること、はっきりと区別できることの意味です。旗じるしがはっきりして鮮やかであるという意味から、自分の主義や持論、立場を明確にする意味となっています。
【典拠・出典】
-
【類義語】
・一目瞭然(いちもくりょうぜん)
・灼然炳乎(しゃくぜんへいこ)
・明明白白(めいめいはくはく)
【英語訳】
making one’s attitude (position、stand) clear
unfurling and clearly showing one’s banner
旗幟鮮明(きしせんめい)の解説
カンタン!解説
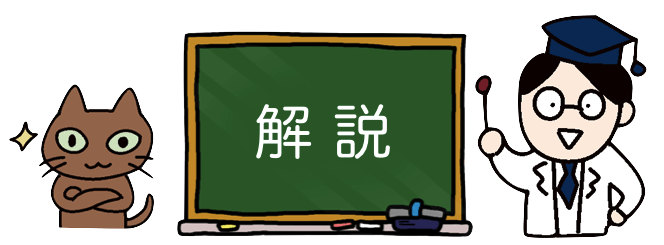
「旗幟鮮明」というのは、自分の考えや行動がハッキリしていて、誰が見ても明らかな状態を表す言葉だよ。
「旗幟」というのは、旗やのぼりのことで、これが立ってると、それが何のための旗なのか、一目でわかるよね。それと同じで、「旗幟鮮明」は、自分の主義や主張、行動などが一目でわかるぐらい明確であることを表すんだ。「鮮明」っていうのは、ハッキリとしていて、よく見えるという意味だよ。
たとえば、「旗幟鮮明な党」と言うときは、その政党が何を考えていて、何を目指していて、どういう行動をとるのかが、はっきりとしていて、誰が見てもわかるという意味になるんだよ。
旗幟鮮明(きしせんめい)の使い方
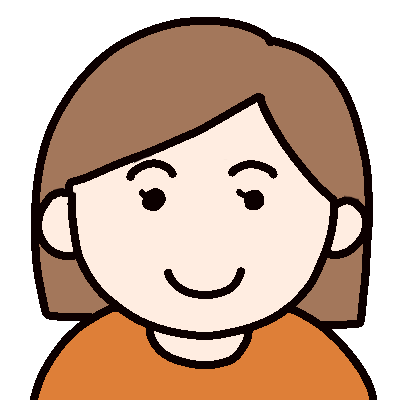
うちの野球部とサッカー部は人気が二分しているよね。
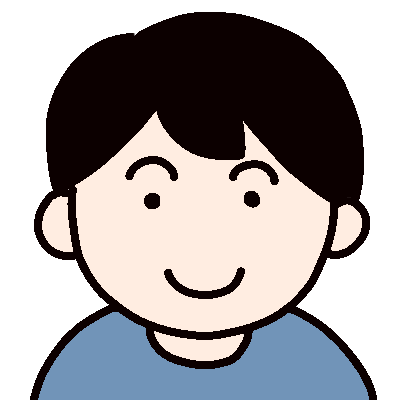
うん、僕はどちらも好きだよ。
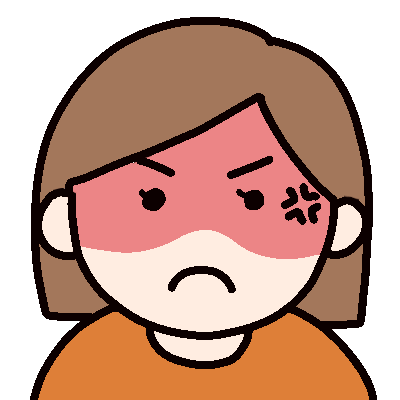
えー!当然サッカー部でしょ!はっきりして!旗幟鮮明にしなさいよ。
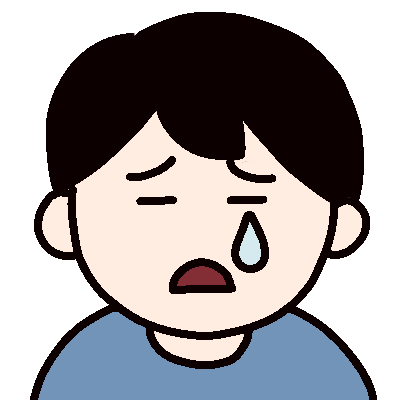
なかなか決められないよ。野球もサッカーも大好きだから。
旗幟鮮明(きしせんめい)の例文
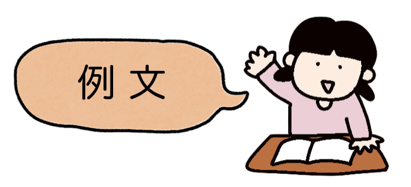
- その将軍は旗幟鮮明な理想主義者だと言われている。
- 天下分け目の関ヶ原の戦いは旗幟鮮明としない武将も多くいたと言われています。
- 旗幟鮮明にするということが、唯一の生き残るための方法となるだろう。
- 三国志の曹操は旗幟鮮明にしない武将を好まない性格の持ち主だった。
- あいまいな旗幟鮮明としない方法が、日本の玉虫色という語源の一部でした。
旗幟鮮明の文学作品などの用例
- N将軍は旗幟鮮明な理想主義者だ。<荒正人・漱石鴎外竜之介>
















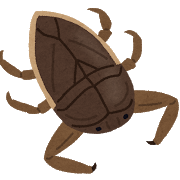
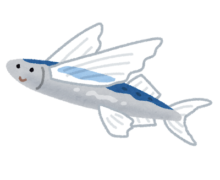



まるで、はっきりと色鮮やかな旗を掲げているように、自分の思いや意志が明らかにされているという意味だね。