一国一城の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)

【四字熟語】
一国一城
【読み方】
いっこくいちじょう
【意味】
一つの国と一つの城を示す。または、一つの国を領地とし、一つの城を所有すること。転じて、他からの指図や干渉を受けずに独立していること。
その一国一城を所有している者を「一国一城の主(あるじ)」と表現する。


ほんまやな。それは、「一つの国や城を自分のものにする」ってことやな。
つまり、自分の大切なものや地位を守るってことやな。
これは、「自分のものを大切にする」って教えてくれる言葉やで。
つまり、自分の大切なものや地位を守るってことやな。
これは、「自分のものを大切にする」って教えてくれる言葉やで。
【語源・由来】
江戸初期、徳川幕府は諸大名の軍事勢力を抑えるため、一国に一城だけを認め、他は破棄させた。これを「一国一城令(いっこくいちじょうれい)」という。
国の旧字体は國である。
【典拠・出典】
『別所長治記』
【類義語】
・独立独歩(どくりつどっぽ)
・独立自存(どくりつじそん)
・独立自全(どくりつじぜん)
・独立独行(どくりつどっこう)
・独立不撓(どくりつふとう)
【英語訳】
being independent
一国一城(いっこくいちじょう)の解説
カンタン!解説
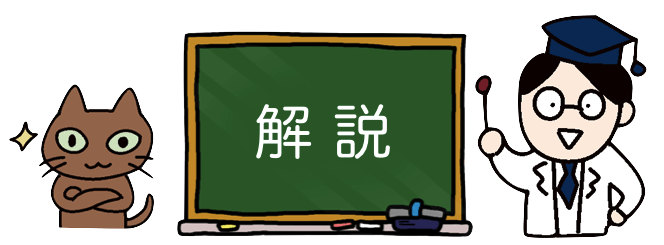
「一国一城」っていうのは、一つの国と一つの城、つまり自分だけのテリトリーを持つことを表すんだ。それから、他の人からうるさく言われずに、自分だけの世界を持っている、独立している状態を指すこともあるんだよ。
ほら、昔の日本では、徳川幕府っていう政府が、大名っていう地方のお偉いさんたちが力を持つのを防ぐために、一つの地方に一つの城しか持たせなかったんだ。他の城は全部壊させたんだよ。これを「一国一城令」と言うんだ。
この「一国一城」って言葉は、「別所長治記」っていう本から来てるんだよ。
なので、「一国一城」っていうのは、自分だけの独立した世界を持つこと、または、他の人から口出しをされずに、自分のやり方でやることを表すんだよ。例えば、「彼の部屋は一国一城のようだ」って言ったら、彼の部屋が彼だけの世界で、他の人が口出ししないって意味になるんだよ。
一国一城(いっこくいちじょう)の使い方
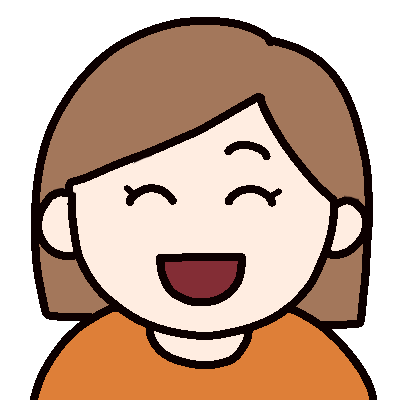
引っ越ししたんだって?
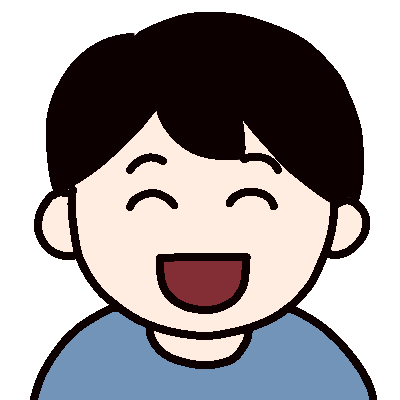
そうなんだ! 狭いけれどもやっと念願のマイホームを手に入れたよ!
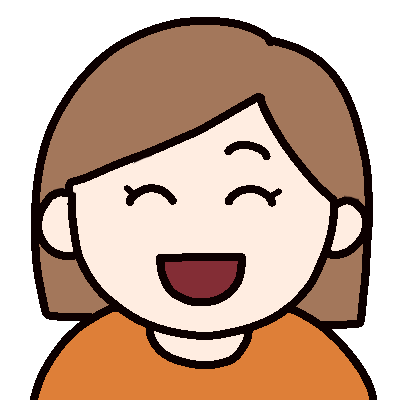
家を建てたの! すごいじゃない!!
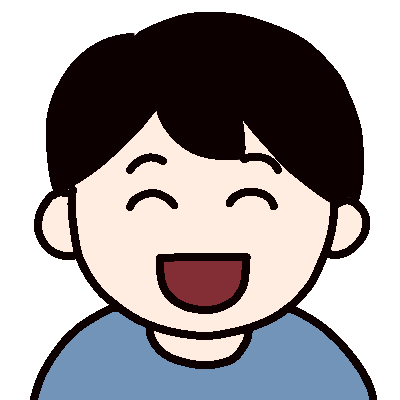
これで俺も晴れて一国一城の主というわけさ。
一国一城(いっこくいちじょう)の例文
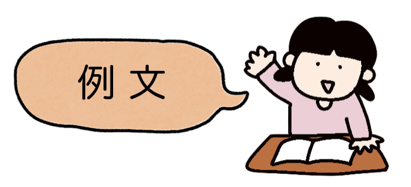
- 脱サラを決意し、小さな会社を興した。一国一城の主となったこれからが正念場だ。
- 今はフリーターだが、いずれ時代劇作家として一国一城になる夢を持っている。
- この部屋が自分の一国一城の活動拠点です。
- 私を信じてついてきてくれた従業員のおかげで、なんとか不況を乗り切る事ができました。この町工場は私にとっての一国一城です。
- 会社での彼は上司の言いつけには愛想よく従うが、家では違うらしい。一国一城の主気取りで、奥さんや子供に用を言いつけ、自分は何もせず威張っているそうだ。
「別所長治記」より
今度の御合戦は一国一城の小せり合とは各別なり
今度の御合戦は一国一城の小せり合とは各別なり
「秀吉と利休/野上弥生子」より
これらの言葉は一国一城のあてかい状をもらったより、宗次にはうれしい。











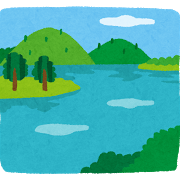

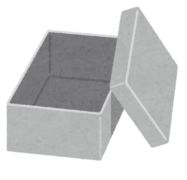







つまり、一つの地位や役職、または所有物を持つという意味があるよ。