夏炉冬扇の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)

【四字熟語】
夏炉冬扇
「冬扇夏炉」とも言う。
【読み方】
かろとうせん
【意味】
時期が外れてしまったため、無用なもの、役に立たないものを示す。
単に「あっても役に立たないもの、かえって邪魔になるもの」の意味で使うのは誤りで、正しくは「時期が外れているため役に立たない」です。


なるほどな。それはつまり、「時期外れで使えへんもの」ってことやな。
暑い夏に暖炉や、寒い冬に扇風機を使うような、そんな感じやな。
これは、「使い物にならないもの」を表す言葉やで。
暑い夏に暖炉や、寒い冬に扇風機を使うような、そんな感じやな。
これは、「使い物にならないもの」を表す言葉やで。
【語源由来】
夏の火鉢と冬の扇のことで、時季外れの無用なもの、転じて今となっては役に立たない人物やもの。例えば、君主の信用や寵愛を失った者、恋人に捨てられた女性の意味でも用いる。
【典拠・出典】
『論衡』逢遇
【類義語】
・冬扇夏鑪(とうせんかろ)
・六菖十菊(りくしょうじゅうぎく)
【英語訳】
・summer fires and winter fans
・useless things
夏炉冬扇(かろとうせん)の解説
カンタン!解説
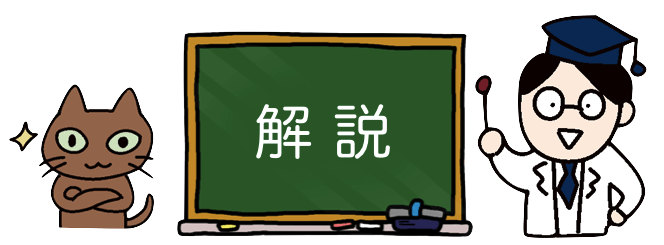
「夏炉冬扇」っていうのは、つまり、その場所やその時期には全然役に立たないもの、無駄なものを表す表現だよ。たとえば、真夏に囲炉裏を使ったり、真冬にうちわで涼んだりするのは無駄だよね。それと同じくらい、役に立たない言論や才能も「夏炉冬扇」って言えるんだよ。
でも、これは人に対しても使われることがあるんだ。「夏炉冬扇」と言われた人は、役立たず、無駄な存在ってことになるんだ。たとえば、王様や皇帝に信じられなくなった人や、愛を失った女性、寵愛を失った宮女などがこれに当たるよ。
ちなみに、「冬扇夏炉」って言い方もあるんだよ。どっちも同じ意味だから、好きな方を使っていいよ。この言葉の出どころは、「論衡」っていう本の中の「逢遇」って部分から来ているんだよ。
夏炉冬扇(かろとうせん)の使い方
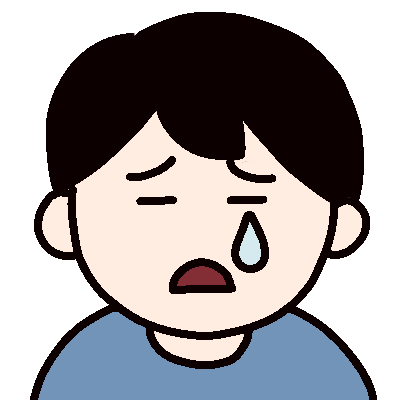
あーあ、まずった・・・・・・
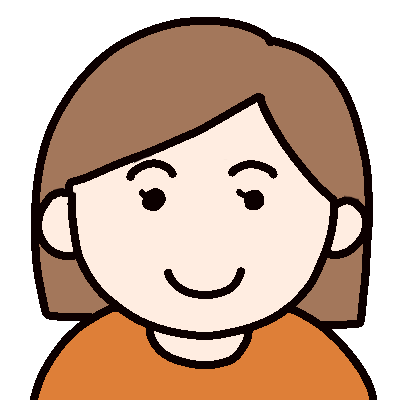
どうしたの? 元気ないわね。
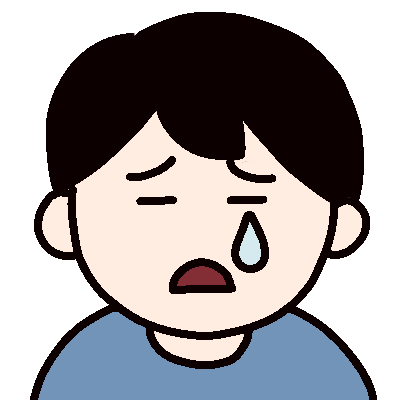
この前、友達に展覧会の招待券2枚を渡したんだけど・・・・・・どうやら別れちゃったみたいなんだよね。さらに、チケットも招待期限が過ぎてたみたいで。
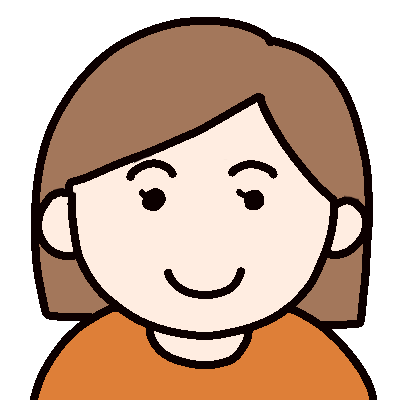
まさかの夏炉冬扇だったわけね・・・・・・
夏炉冬扇(かろとうせん)の例文
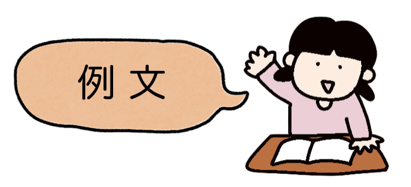
- このタイミングでの資料提出は、夏炉冬扇も同然だ。
- ここでは夏炉冬扇とも思えるこの品々も、時期が来れば重用されるだろう。
- あれほど上司から寵愛を受けていたにもかかわらず、今や彼は夏炉冬扇のごとく切り捨てられた。





















夏の暖炉や冬の扇風機のように、その時期では役立たないもの、という意味だ。