鶏鳴狗盗の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳)

【四字熟語】
鶏鳴狗盗
【読み方】
けいめいくとう
【意味】
小さな策を弄(ろう)する人や、くだらなかったり、つまらなかったりすることしかできない人のこと。
また、つまらないことでも、なにかの役に立つことがあるということ。


普段は大したことないかもしれへんけど、必要とされるときには一花咲かせるんやな。
これは、「自分の小さい能力も大切にする」っていうメッセージが込められてるんやで。
【語源・由来】
「鶏鳴(けいめい)」とは、鶏の鳴きまねをすること。
「狗盗(くとう)」とは、犬の様にこそこそと、わずかなものを盗むこと。また、いやしいことをして、人を欺くこと。
中国戦国時代に、秦(しん)の昭王に捕らえられた、斉(さい)の孟嘗君(もうしょうくん)が、犬の真似をして盗みをするのが得意な家臣に、白狐の皮衣を盗ませて昭王の愛妾に献上し、その口添えで釈放された。夜中に国境の函谷関(かんこくかん)まで来たが、関所の扉は一番鶏が鳴くまで開かないことになっていた。今度は鶏の鳴きまねのできる家臣に、一声鳴かせてみると、本物の鶏も鳴き出したことで門が開き、無事に逃れたという故事に基づいているとされる。
【典拠・出典】
『史記』「孟嘗君伝」
【類義語】
・竹頭木屑(ちくとうぼくせつ)
【英語訳】
person who resorts to petty tricks; person of small caliber who is only capable of petty tricks.
鶏鳴狗盗(けいめいくとう)の解説
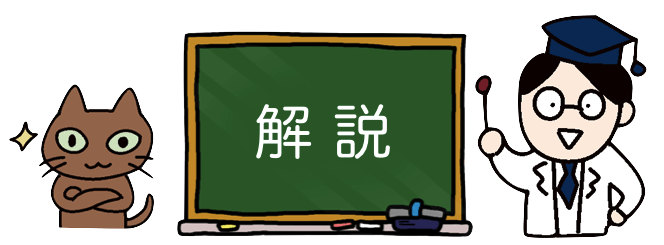
「鶏鳴狗盗」っていうのは、ちょっとしたことしかできない人や、大したスキルもない人を表す言葉だよ。でもね、逆にそれは「些細なことでも役に立つことがあるよ」という意味もあるんだ。
「鶏鳴」っていうのは、まるで鶏が鳴く真似をすることを指していて、「狗盗」っていうのは、犬みたいにこっそりと少しだけ物を盗むことを指しているんだよ。だから、この言葉は、ちょっとした悪さをする人のことを指すこともあるんだ。
なぜかというと、この言葉の出どころは、『史記』という古い中国の書物に書かれた「孟嘗君伝」という話から来ているんだよ。その話では、鶏の鳴きまねをする人やこっそりと物を盗む人も、ちょっとした役に立つことがある、と語られているんだよ。
鶏鳴狗盗(けいめいくとう)の使い方
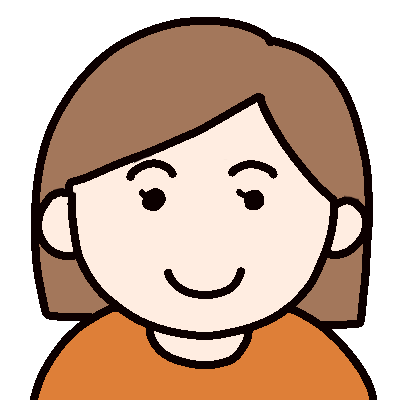
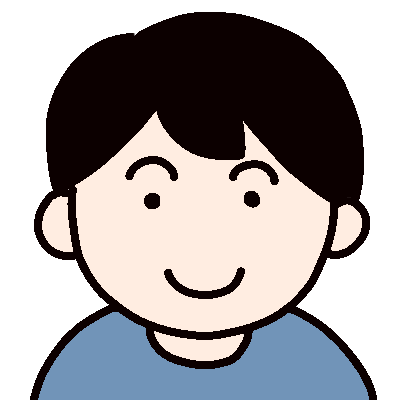
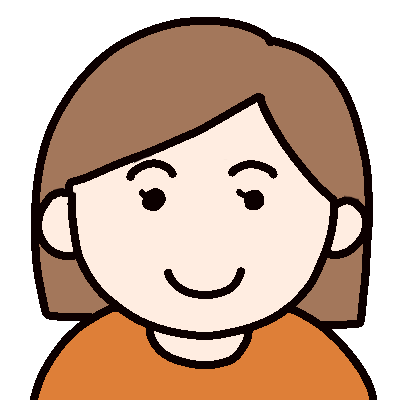
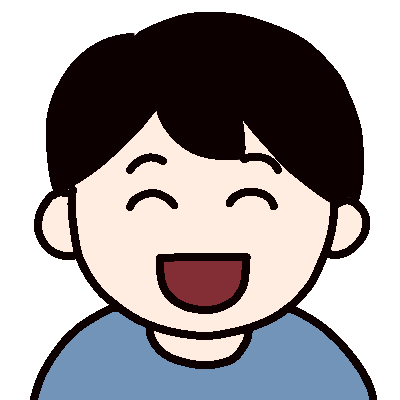
鶏鳴狗盗(けいめいくとう)の例文
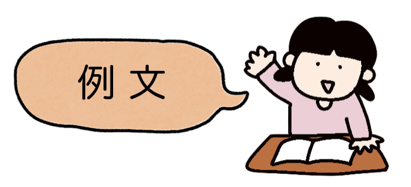
- 鶏鳴狗盗というけれど、なにが役に立つかはわからないじゃないか。
- 彼は鶏鳴狗盗の技能をたくさん持っている。
- 鶏鳴狗盗の術があったからこそ、彼は逃れることができたんだ。
- 鶏鳴狗盗ばかりだと、鼻で笑われた。
鶏鳴狗盗の文学作品などの用例
- いたずらに硬語を吐き、身に鶏鳴狗盗の術なくして、しかも治国平天下を談ず<犬養木堂・都人士>





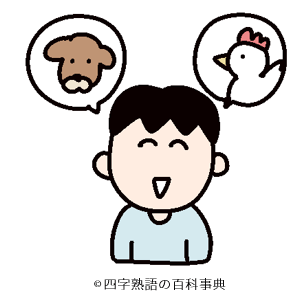









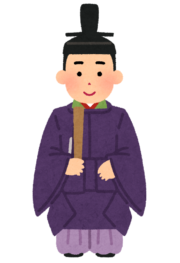
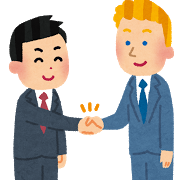




しかし、そういう小さな技能や芸でも、時と場合によっては役立つこともあるんだよ。