目次
臥薪嘗胆の意味(故事・出典・類義語・英語訳)

【四字熟語】
臥薪嘗胆
【読み方】
がしんしょうたん
【意味】
目的を達成するために機会を待ち、苦労を耐え忍ぶこと。


本来は仇討ちのために苦労するんやけど、どんなに大変でも目指すもんがあるから頑張る、っていう意味やねん。
これは、「目標を達成するための我慢強さ」を示す言葉なんやで。
【典拠・出典】
『史記』「越世家」,『十八史略』「春秋戦国」
【類義語】
・坐薪懸胆(ざしんけんたん)
・漆身呑炭(しっしんどんたん)
・呑炭漆身(どんたんしっしん)
【英語訳】
・going through thick and thin to attain one’s objective
・enduring unspeakable hardships for the sake of vengeance
・Perseverance under difficulties
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の解説
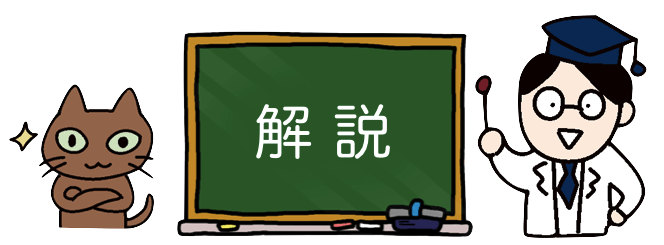
「臥薪嘗胆」っていうのは、将来の目標のために今は辛くても頑張り続けることを表すんだよ。
ちょうど、火を起こすたきぎの上で寝て、苦い胆をなめるほどの辛さを我慢するイメージだよ。
「臥」は寝ること、「薪」はたきぎ、「嘗」はなめること、「胆」は苦いきも、という意味があるんだ。
つまり、難しいことに立ち向かって、それを克服するために一生懸命努力し続けることを言うんだよ。
例えば、難しい試験に合格するために毎日たくさん勉強したり、将来プロのサッカー選手になるために毎日練習したりすることが「臥薪嘗胆」だね。
この言葉は、昔の中国の本『史記』や『十八史略』から来ていて、昔の人たちも大きな目標を達成するためには、今辛いことも我慢しなければならないと考えていたんだよ。
だから、目の前の困難に負けずに頑張り続けることが大切なんだね。
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の故事
【故事】
薪の中に寝て、苦い胆を嘗めることの意味。春秋時代、呉王夫差は、父の仇を忘れないために、薪の上で寝ることにより自分自身を苦しめ、その屈辱と志を忘れないようにして、越王勾践を破った。また、敗れた勾践も苦い獣の胆をなめることにより、その復讐心を忘れないようにして、その後、見事に呉王夫差を打ち破った。
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の使い方
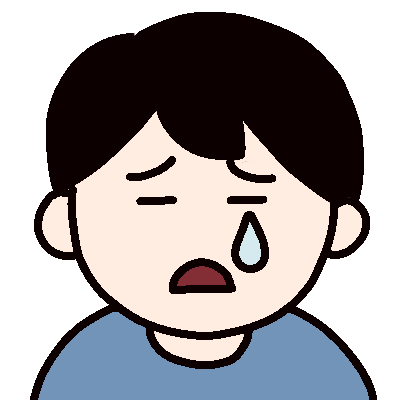
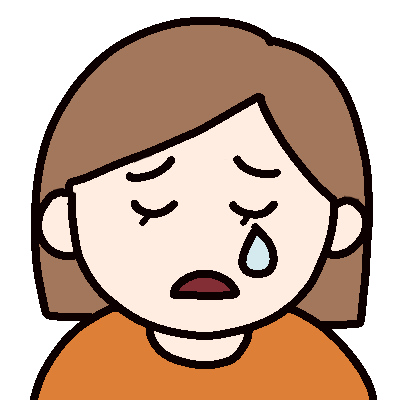
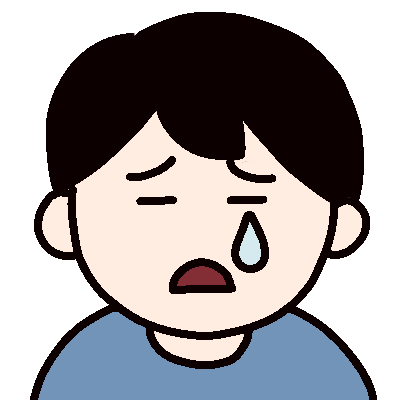
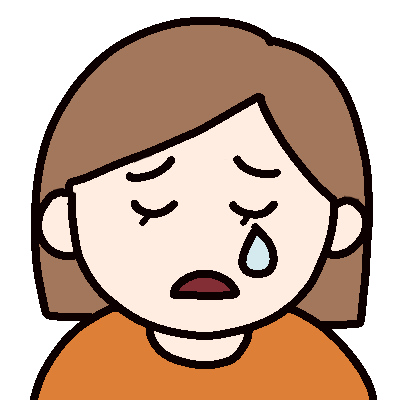
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の例文
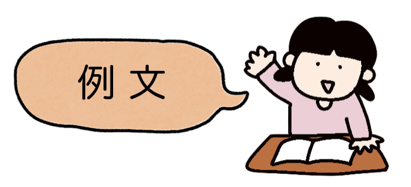
- 5年もの臥薪嘗胆の末、彼女は彼女を陥れた課長の椅子を奪回した。
- そこまでの深い執着と事の成就はまさに臥薪嘗胆に等しかった。
- 辛苦にくじけそうになったものの、頭をかすめた臥薪嘗胆の文字に気持ちを奮い立たせた。
- これまでの臥薪嘗胆の思いを、今こそここで成就しようではないか。
- 長きにわたる臥薪嘗胆が、彼女の風貌を一変させていた。













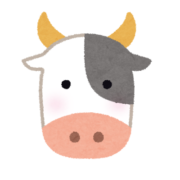

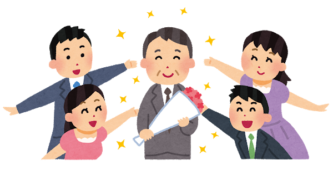





もともとは、仇を討つため、苦難を耐え続けるという意味だけど、一般的には、目的を達成するために大変な苦労を耐え忍ぶという意味で使われるんだ。