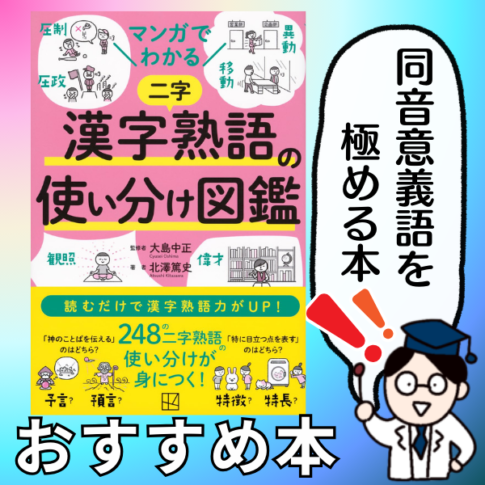四字熟語は私たちの毎日の生活にしっかりと根づいています。それは、四字熟語を使うことにより、表現がバシッと的確に決まるからです。
四字熟語は生き生きした表現を作る、だからこそ、中学の入学試験、そして高校、大学の入学試験にまで出題されるのです。
四字熟語のもとになっている漢字は、一字一字が固有の概念を備えた「語」であり、一字が一音節で発音されるという特徴をもっています。この漢語の特質を生かして、口ずさみやすい四字句、四音節の、しかも含蓄に富む意味内容を表現する漢語が四字熟語です。
この記事では、沢山ある四字熟語の中でも、厳選して最初に覚えておいたほうがよい最重要四字熟語を100個にしぼり意味と解説付きで掲載しました。
絶対に覚えておくべき有名な四字熟語を厳選しましたので、この記事で紹介している四字熟語は全て確実に覚えておきましょう!
小学校で習う有名な四字熟語は、小学生向けのよく使う四字熟語と意味一覧をご覧ください。
よく使う有名な四字熟語1000選は、【四字熟語1000選】よく使う有名な四字熟語意味付きをご覧ください。
当サイトより2022年中に最も人気があった四字熟語は、【2023年版】四字熟語人気ランキングTOP30をご覧ください。
当サイトの目次・逆引きは、「四字熟語一覧(逆引き検索)」をご確認ください。

目次
「あ行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

悪戦苦闘(あくせんくとう)

【意味】
不利な状況に苦しみながら、必死に戦ったり努力したりすること。

強い敵との戦いに、生きるか死ぬかの瀬戸際で挑むというイメージがあるんだ。

どんなに強い敵が相手でも、死ぬ気で戦って乗り越えるんやな。これは、「どんな困難でも最後までがんばる強さ」を表してる言葉やな。
暗中模索(あんちゅうもさく)
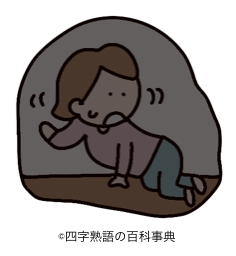
【意味】
手がかりもなしに、あれこれとやってみること。

暗闇の中で何かを手探りで探す、というイメージが込められているんだ。

暗闇の中で手を伸ばして何かを探すように、どうすればいいかわからへんときでも、手を動かして探し続けるんやな。これは、「迷ったときでも試行錯誤する大切さ」を教えてくれる言葉やな。
意気投合(いきとうごう)

【意味】
気持ちや考えが、相手をぴったり合うこと。


友達やパートナーとの関係が良好なときに使うんやろな。なるほどな、これは。「気が合う」っていう、心地よさを表す言葉なんやな。
異口同音(いくどうおん)
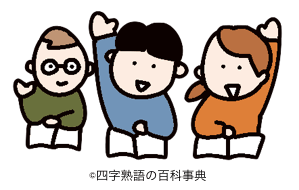
【意味】
多くの人がみな、口をそろえて同じことを言うこと。


これは、みんなが一致団結しているときに使うんやろな。「全員一致」の状況を表す言葉やな。
以心伝心(いしんでんしん)
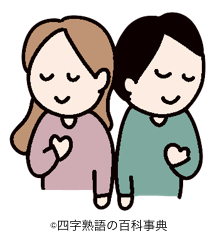
【意味】
ことばに出さなくても、互いの心が通じ合うこと。

もともとは禅宗の言葉で、教えたり学んだりすることを言葉に頼らず、心から心へと直接伝えることを意味していたんだ。

これは、「言葉だけではない、心からのコミュニケーションの大切さ」を教えてくれる言葉やで。
一期一会(いちごいちえ)
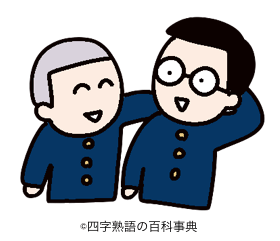
【意味】
一生に一度だけの大切な出会い。

元々は茶道の教えで、主人と客が一緒にいるその時その場を、二度と来ない貴重な瞬間と捉え、心から尊重し、全力で向き合うべきだという意味があるんだ。

その場その瞬間に全力で取り組む、これは「大切な時間を大切に生きる心構え」を教えてくれる言葉やで。
一日千秋(いちじつせんしゅう)
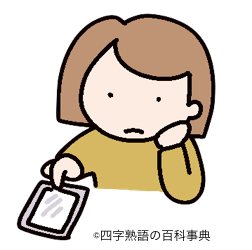
【意味】
非常に待ち遠しいようす。

何かを非常に強く期待していて、1日が千年のように長く感じるほど待ち遠しいという意味なんだ。もともとは「一日三秋」という言葉から派生したんだ。

楽しみや期待が強すぎて、時間がすごく遅く感じるんやな。これは、「楽しみや期待感を強く感じる状況」を表す言葉やで。
一念発起(いちねんほっき)

【意味】
あることを成しとげようと、新たに決心すること。

もともとは仏教の言葉で、心を一つにして悟りを開こうとする固い決意を示していたんだ。

なにか新しいことを始めたり、困難を乗り越えたりする時に使う、頑張る力を表す言葉やな。これは、「強い決心と努力」を大切にすることを教えてくれる言葉やで。
一網打尽(いちもうだじん)

【意味】
一度に全部をつかまえてしまうこと。

転じて、犯人などを一気に捕らえることを意味するようになったんだ。

これは、「効率よく問題を解決する」ことを教えてくれる言葉やで。
一喜一憂(いっきいちゆう)

【意味】
ささいなことで、喜んだり心配したりすること。

周りの状況に左右されて気持ちがコロコロ変わるという意味があるんだ。

何か小さなことで気分が上下するんやな。これは、「感情の安定」や「落ち着き」が大切やってことを教えてくれる言葉やで。
一挙両得(いっきょりょうとく)

【意味】
一つのことをして、二つの利益を得ること。

つまり、少ない労力で多くの利益を得る、という意味があるんだ。

これは、「効率的に良い結果を得る方法」を教えてくれる言葉やで。
一触即発(いっしょくそくはつ)
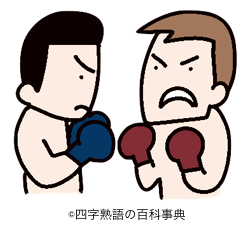
【意味】
ちょっとしたきっかけで、たいへんなことが起こりそうなようす。

ちょっとしたきっかけで大きな問題が起こりそうな、危険な状況を指すんだ。

なんかのきっかけで事態が悪化する可能性がある、危なっかしい状態やな。これは、「注意深さや慎重さ」が必要な状況を教えてくれる言葉やで。
一心不乱(いっしんふらん)

【意味】
一つのことに集中して、他のことを考えないこと。

他のものに気がそらず、一つのことに完全に熱中する、という意味があるんだ。

気がそらすことなく、目の前のことに全力で取り組むんやな。これは、「集中力」を大切にすることを教えてくれる言葉やで。
一石二鳥(いっせきにちょう)
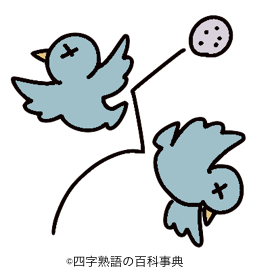
【意味】
一つのことをして、同時に二つの利益や成果を得ること。

つまり、一つの石を投げて二羽の鳥を同時に捕らえる、というイメージからきているんだ。

一つの行動で二つの結果を得るんやな。これは、「効率的に良い結果を得る方法」を教えてくれる言葉やで。
一長一短(いっちょういったん)

【意味】
よい面もあり、悪い面もあること。

つまり、長所と短所が両方存在する、完全ではない状態を指すんだ。

全てが完璧じゃなくて、良い面と悪い面が混じってるんやな。これは、「完全無欠なんてない、バランスが大切」ってことを教えてくれる言葉やで。
意味深長(いみしんちょう)

【意味】
ことばや行動のうらに、別の深い意味がかくれているようす。

人の言動や文学作品などによく使われる表現だね。

一見しただけではわからへんけど、よう考えると違う意味が隠れてるんやな。これは、「物事には表面だけじゃなく深い意味がある」ってことを教えてくれる言葉やで。
右往左往(うおうさおう)

【意味】
どうしていいかわからず、あわてふためいて、うろうろすること。

つまり、混乱して秩序がなくなってしまった状態を描いているんだ。

あたふたしてる状態を表してるんやな。これは、「落ち着いて行動する大切さ」を教えてくれる言葉やで。
栄枯盛衰(えいこせいすい)
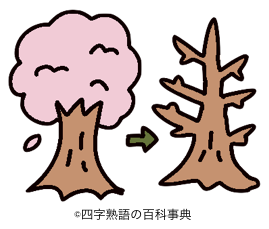
【意味】
栄えたり衰えたりすること。また、それをくり返す人の世。

つまり、栄えたり衰えたりを繰り返す、一定ではない状態を指しているんだ。

人生って常に変わっていくんやな。これは、「人生は変化するもの、だから落ち込まずに進むことが大切」ってことを教えてくれる言葉やで。
温故知新(おんこちしん)

【意味】
前に学んだことや昔のことがらをよく調べて、そこから新しい考え方や知識を見いだすこと。

つまり、過去を振り返って新しい発見をするという意味なんだ。

これは、「学んだことを忘れずに、新たな知識を得る大切さ」を教えてくれる言葉やで。
「か行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

快刀乱麻(かいとうらんま)
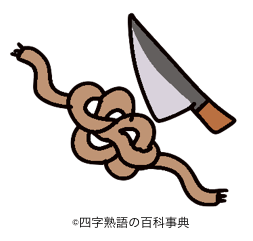
【意味】
こじれたりしていて難しい物事を、手ぎわよく処理すること。

まるで鋭い刀で絡まった糸をサッと切るように、難しい問題を解決するイメージがあるんだ。

シャープな刀でぐちゃぐちゃになった糸を切るように、大変そうな問題もサクッと解決できるんやな。これは、「問題解決のための冴えた判断力」を表してる言葉なんやで。
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)

【意味】
目的をとげるために、長い間大変な苦労をすること。

つまり、自分を厳しく律して、辛抱強く目標に向かって努力を続けるという意味があるんだよ。

寝るところも硬くて、食べ物も苦いけど、それでも頑張って目標に向かって努力し続けるんやな。これは、「目標に向かって困難に耐える強い意志」を表す言葉なんやで。
我田引水(がでんいんすい)
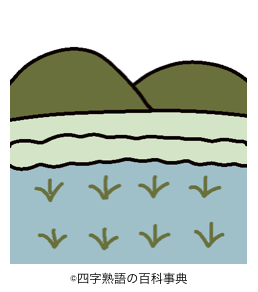
【意味】
自分に都合のいいように、言ったりしたりすること。

これは自分の田んぼにだけ水を引き入れる様子からこの言葉が生まれたんだ。

自分だけの田んぼに水を引いて、他の田んぼはほったらかし、そんなイメージやな。これは、「自分だけがいいことになるように行動する自己中心的な態度」を教えてくれる言葉やで。
画竜点睛(がりょうてんせい)

【意味】
物事を完成させるため、最後に加える大切な仕上げのこと。

文章や話などで重要な部分を強調して、全体をより引き立てることを例えているんだよ。「睛」は目玉を意味し、それが物事の大切なところを表すんだ。

でも、「画竜点睛を欠く」って言ったら、最後の大切な仕上げがないから、全体がなんとなく物足りない、そんな感じになるんやな。ちなみに、これは「竜を画いて睛を点ず」とも読むことができるんやで。
完全無欠(かんぜんむけつ)

【意味】
完全で、欠点や不足がまったくないようす。

「無欠」は欠けているところがないという意味です。ほぼ同じ意味を持つ言葉が重なることにより、全体の意味が強調されています。

「無欠」っていうのは、何も欠けてないってことなんやな。同じような意味の言葉が二つ続いてるから、その意味が強くなってるんやで。
危機一髪(ききいっぱつ)

【意味】
ひとつまちがえばたいへんなことになる、危険な状態。

つまり、一歩間違えば深刻な事態に陥るという意味なんだ。

つまり、ちょっとしたことで大ごとになりそうな状態ってことなんやな。
起死回生(きしかいせい)
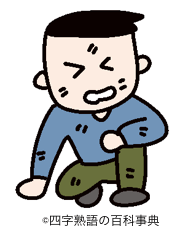
【意味】
今にもだめになりそうなものを、立ち直らせること。

もともとは、死にそうな人を医術で生き返らせるという意味があったんだ。それが転じて、どんなに困難な状況でも一気に立ち直る、という意味になったんだ。

ほんまにダメダメやったけど、なんとかして勢いを取り戻して立ち直るんやな。これは、「絶対にあきらめへん、いつでもチャンスはある」ってことを教えてくれる言葉なんやで。
疑心暗鬼(ぎしんあんき)

【意味】
疑う気持ちが強いと、何でもないことまで恐ろしく思われること。

暗闇で本当はいない亡霊が見えてしまうような、不安と恐怖の深まりを描いているんだ。

真っ暗なところで、本当はおらんお化けが見えてきたかのように、疑い出すと何でもないことまで怖く感じるんやな。これは、「疑いすぎると心が乱れる」ってことを教えてくれる言葉やで。
奇想天外(きそうてんがい)
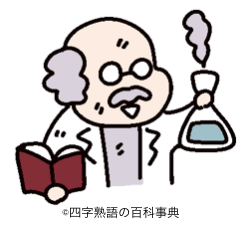
【意味】
ふつうでは思いもよらないほど、変わっていること。

非常にユニークで、他の誰も考えつかないような、奇抜なアイデアのことを言うんだ。

ふつうの人が思いもつかんような、めちゃくちゃユニークなことを考えたりするんやな。これは、「常識を超えた発想の大切さ」を教えてくれる言葉やで。
喜怒哀楽(きどあいらく)
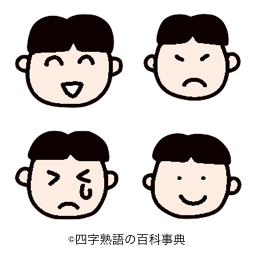
【意味】
人のもつさまざまな感情。喜び・怒り・悲しみ・楽しみのこと。

これらは我々の日常生活の中で絶えず経験する感情なんだ。

これらの感情は、僕らが生きていく中でいつも感じてる基本的な気持ちやな。これは、「人間が感じる様々な感情の大切さ」を教えてくれる言葉やで。
急転直下(きゅうてんちょっか)

【意味】
成り行きが急に変わって、解決に向かうこと。

なんとなく進んでいた状況が一瞬で大きく変わる、そのような急激な変化を指すんだ。

これは、「何事も突然変わる可能性がある」ってことを教えてくれる言葉やで。
玉石混交(ぎょくせきこんこう)

【意味】
よいものと悪いものとが、まざり合っているようす。

まるで宝石とただの石が混ざっているように、良いものとそうでないものが一緒になっている状態を表しているんだ。

宝石とただの石が一緒になったかのように、ええもんと悪いもんが一緒になっているんやな。これは、「ものごとはいろんな種類が混ざってることが多い」ってことを教えてくれる言葉やで。
空前絶後(くうぜんぜつご)

【意味】
今までにも、これからにもないような、非常にまれなこと。

非常にまれで特別な状況や事象を指す言葉なんだ。

めちゃくちゃレアで特別なことや出来事を表すんやな。これは、「特別な瞬間や出来事を大切にする」ってことを教えてくれる言葉やで。
言行一致(げんこういっち)

【意味】
言うことと行うこととが、一致していること。

つまり、言ったことをしっかりと実行する、という信念の表現なんだ。

これは、「言ったことはちゃんとやるべき」ってことを教えてくれる言葉やで。
巧言令色(こうげんれいしょく)

【意味】
口先だけのうまいことばや、うわべだけの愛想のいい顔つき。

つまり、実際の感情や考えとは違う行動を取り、他人に気に入られようとすることを表しているんだ。

本心とは違って、人に気に入られようとするんやな。これは、「見せかけだけの行動には気をつけるべき」ってことを教えてくれる言葉やで。
荒唐無稽(こうとうむけい)

【意味】
でたらめで、よりどころがないようす。

つまり、理由や証拠がなく、現実とはかけ離れた話を指すんだ。

これは、「根拠のない話には注意するべき」ってことを教えてくれる言葉やで。
呉越同舟(ごえつどうしゅう)

【意味】
敵と味方や仲の悪い者どうしが、いっしょにいたり、いっしょに行動したりすること。

また、そのような状況であっても、共通の問題や利害関心があれば、協力したり助け合ったりすることもあるという意味も含まれているんだ。

これは、「状況が変われば敵も味方になることもある」ってことを教えてくれる言葉やな。
孤軍奮闘(こぐんふんとう)
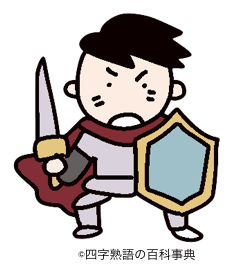
【意味】
助けもなしに、一人で懸命に努力すること。

一人や少数の人が、大きな困難や敵と戦う様子をイメージしているんだ。

これは、「一人でも強く立ち向かう勇気」を教えてくれる言葉やで。
虎視眈眈(こしたんたん)

【意味】
油断なく、じっと機会をねらっているようす。

まるで虎が獲物を狙い、鋭い目で見つめるような状態を指しているんだ。

とらが獲物を見つけるために、目を光らせてじっと見てるんやな。これは、「チャンスを見つけるためにはじっと待つ勇気」を教えてくれる言葉やで。
五里霧中(ごりむちゅう)

【意味】
見通しがつかず、どうしてよいかわからないようす。

まるで霧が濃くて視界が効かないように、どう行動すればいいか分からず困っているという意味だ。

これは、「見通しが悪くても前に進む勇気」を教えてくれる言葉やで。
言語道断(ごんごどうだん)

【意味】
あきれてことばにならないほど、ひどいこと。

もともとは仏教の言葉で、深淵な真理や究極的な状態は言葉では表現できないという意味があったんだ。

これは、「言葉では表せないほど驚きや憤りを感じる状況」を教えてくれる言葉やな。
「さ行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

再三再四(さいさんさいし)

【意味】
何度も何度も。

たとえば、何かを教えたり、注意したり、要求したりすることを何度も何度も繰り返す様子を表すのに使うんだ。

これは、「何回も繰り返すことの大切さ」を教えてくれる言葉やで。
三寒四温(さんかんしおん)
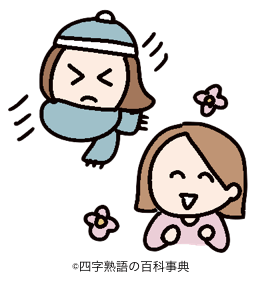
【意味】
冬の終わり、三日ほど寒い日が続くと、次の四日ほどは暖かいということ。また、そのように、だんだん気候が暖かくなること。

また、徐々に気候が暖かくなる様子を指すのにも使われるよ。

また、じわじわと春が近づいて、だんだん暖かくなってくるんやな。これは、「季節の変わり目や、変化を感じる時期」を教えてくれる言葉やで。
山紫水明(さんしすいめい)
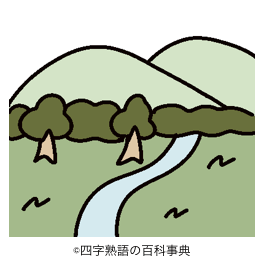
【意味】
海や山、川や湖などの、自然の景色が美しいこと。

特に、日の光に照らされた山が紫色にぼんやりと見え、川の水が透き通っているような美しい風景を想像させるよ。

これは、「自然の美しさと清潔さ」を感じさせる言葉やで。まるで、おとぎ話の中みたいな風景をイメージさせてくれるんやな。
自画自賛(じがじさん)

【意味】
自分で自分のしたことをほめること。

まるで、自分で描いた絵に自分でほめ言葉を書くような様子だね。

自分で作ったものに対して、「おいら、上手にできたな~」って自分で感心してるってことや。これは、「自己評価の高さ」を表してる言葉なんやで。
四苦八苦(しくはっく)

【意味】
非常に苦労すること。たいへんな苦しみ。

もともとは仏教の教えで、人間の生きていく中で避けては通れない様々な苦しみを示す言葉だよ。

これは、「困難を乗り越えるための努力」を表す言葉やで。
自業自得(じごうじとく)
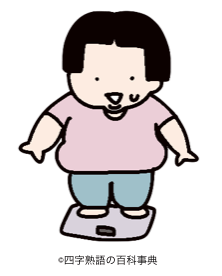
【意味】
自分がしたことの報いを、自分が受けること。

もともとは仏教の教えから来ていて、自分が行った行動の善悪によって、自分が楽しむものや苦しむものが決まるという考え方を示すよ。

これは、「自分の行動には必ず結果が返ってくる」って教えてくれる言葉やで。
獅子奮迅(ししふんじん)

【意味】
激しい勢いで活動しているようす。

この四字熟語は、とても力強く、猛烈に取り組む様子を表しているよ。

これは、「全力で挑む勢い」を表す言葉やで。
七転八倒(しちてんばっとう)

【意味】
ひどく苦しくて、転げ回ること。


質実剛健(しつじつごうけん)
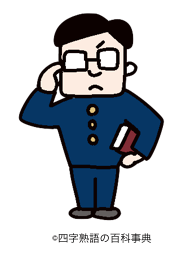
【意味】
飾り気がなくまじめで、心も体も強くたくましいこと。

これは、強さと堅実さを併せ持つ人を表すんだ。

これは、「見た目よりも中身、強さと真実性を大切にする人」を表す言葉やで。
四面楚歌(しめんそか)

【意味】
周りが敵や反対者ばかりで、味方が一人もいないこと。

この表現は、まるで自分だけが敵に囲まれているような状態を描いているんだ。

これは、「一人で大勢に立ち向かう大変さ」を表してるんやで。
弱肉強食(じゃくにくきょうしょく)
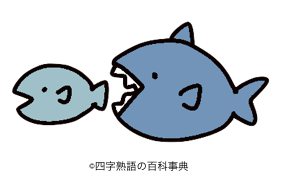
【意味】
強いものが、弱いものをえじきにして栄えること。

この言葉は生存競争の厳しさを示しているんだ。

強い者が弱い者をどうにでもする、そんな世界の厳しさを教えてくれる言葉やな。これは、「生きるための厳しい競争」を表してるんやで。
終始一貫(しゅうしいっかん)
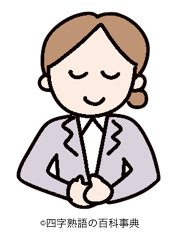
【意味】
最初から最後まで、態度や考えを変えずに貫き通すこと。

何かを始めた時の原則や考えを、最後まで変えることなく続けることを指すんだ。

最初に決めたことを最後まで変えずに続けるんやな。これは、「一貫性と信念」を教えてくれる言葉やで。
十人十色(じゅうにんといろ)
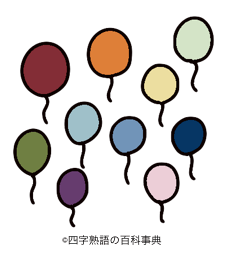
【意味】
好みや考え、性格などが、一人一人異なること。

十人いれば十通りの色、つまり人間の個性や特性があるという意味なんだ。

10人いたら、10人それぞれ違う好みや性格があるんやな。これは、「個性と多様性」を尊重する言葉なんやで。
取捨選択(しゅしゃせんたく)

【意味】
悪いものや不必要なものを捨て、よいものや必要なものを選び取ること。

つまり、何を保つべきで、何を放棄すべきかという判断をするという意味が込められているんだ。

これは、「大切なものとそうでないものを見分けて選ぶ」っていうことを教えてくれる言葉なんやな。
首尾一貫(しゅびいっかん)
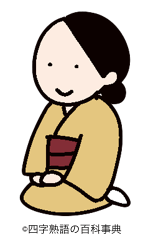
【意味】
最初から最後まで、一つの方針や態度で貫くこと。また、最初と最後とで矛盾がないこと。

つまり、ブレずに一つの目標や価値観に基づいて行動し続けることを表しているんだ。

これは、「どんなに時間が経っても自分の信念を守る強さ」を教えてくれる言葉やね。
順風満帆(じゅんぷうまんぱん)
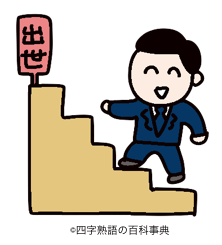
【意味】
物事がすべて、順調に進んでいるようす。

船が追い風を受けてスムーズに進む様子から来ているんだ。

風に乗ってサクサクと進む船みたいに、全てが思う通りに進んでいく状況やね。これは、「全てが順調に進む幸運」を表してる言葉なんやで。
正真正銘(しょうしんしょうめい)

【意味】
うそいつわりなく、本物であること。

まったくの真実で、偽りが一切ないことを指すんだ。

嘘偽りなく、まったくの真実なんやな。これは、「全くの本物であること」を強調する言葉やね。
枝葉末節(しようまっせつ)
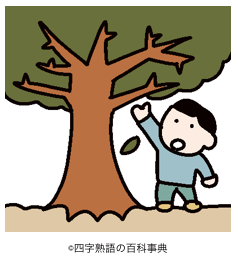
【意味】
物事の、重要でない部分。ささいなこと。

本質から離れた、重要でない部分を表しているんだ。

これは、「重要じゃない細かい事に目を向けすぎないこと」を教えてくれる言葉やね。
初志貫徹(しょしかんてつ)

【意味】
初めに決めた志を、最後まで貫き通すこと。

つまり、始めに定めた意志を変えずに、それを達成するまで努力し続けることだよ。

これは、「自分の目標を最後まで貫く強さ」を教えてくれる言葉やね。
支離滅裂(しりめつれつ)

【意味】
ばらばらでまとまりがなく、筋道が通っていないようす。


心機一転(しんきいってん)
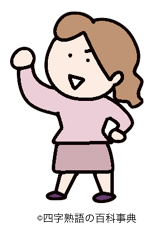
【意味】
あるきっかけから、心のもち方がすっかり変わること。

つまり、何かを機にして心持ちを良い方向に変えることを示しているんだ。

これは、「新たな気持ちでスタートを切る」っていうことを教えてくれる言葉やね。
針小棒大(しんしょうぼうだい)

【意味】
ささいで小さなことを、大げさに言うこと。

つまり、些細なことを大きく見せる、または語るという意味が込められているんだ。

本当は小さいことでも、大げさに誇張して話すんやな。これは、「物事を正確に伝える大切さ」を教えてくれる言葉やね。
森羅万象(しんらばんしょう)
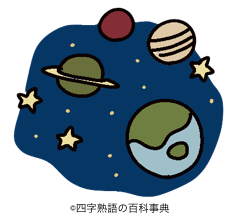
【意味】
この世にある、すべての物事。

つまり、天地の間にある全てのものや出来事、それら全てを含んでいるんだ。

空から地まで、ありとあらゆるものや出来事をさすんやな。これは、「世界にはさまざまなものや現象が存在する」っていうことを教えてくれる言葉やね。
晴耕雨読(せいこううどく)

【意味】
晴れた日は畑を耕し、雨の日は家にいて読書するというような、のどかで自由な生き方をすること。

晴れた日には畑を耕し、雨の日には家で読書をする、という穏やかな日々をイメージさせるんだ。

これは、「自然のリズムに合わせた穏やかな生活」を表してる言葉なんやで。
誠心誠意(せいしんせいい)
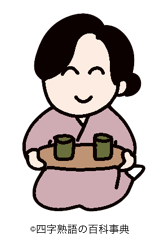
【意味】
まごころをこめて、物事を行うようす。

自分の利益を考えず、全心全意に相手に接する心持ちを指しているんだ。

これは、「真心で行動する大切さ」を教えてくれる言葉やね。
切磋琢磨(せっさたくま)

【意味】
学問や人格を高めようと努力すること。特に、友だちどうしが励まし合い競い合って、ともに向上しようとすること。

それに、友人と励まし合い、競争し合いながら、共に向上するという意味もあるんだ。

友達と一緒にがんばったり、お互いに競争したりしながら、一緒に成長するってことも含んでるんや。みんなで一緒に上を目指すっていう、やる気が出るような言葉やな。
絶体絶命(ぜったいぜつめい)

【意味】
追いつめられて、どうすることもできないこと。また、そのようす。

逃げ場がなく、もうどうにもならない、という状態をイメージするんだ。

もうどこにも逃げる場所がなく、どうしようもないほどに追い詰められてるさまやな。これは、「どんなにつらい状況でも諦めずに挑む」ことの大切さを教えてくれる言葉やな。
千載一遇(せんざいいちぐう)

【意味】
二度とないような、よい機会。

それは、次にいつ来るかわからないほどの特別な状況を指すんだ。

次にいつ来るかもわからんほどの、特別な状況やな。これは、「大チャンスが来たときはしっかりつかむべき」って教えてくれる言葉やな。
千差万別(せんさばんべつ)
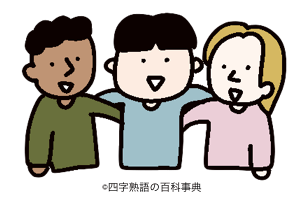
【意味】
多くのものが、それぞれに異なっていること。


これは、「世の中にはいろんな種類のものがある」ってことを教えてくれる言葉やな。
前代未聞(ぜんだいみもん)

【意味】
これまでに聞いたこともないような、めずらしいこと。

また、とても大きな出来事を表すときにも使われるよ。

それに、すごく大きな出来事にも使えるんやな。これは、「初めての経験や出来事に挑戦する大切さ」を教えてくれる言葉やな。
千変万化(せんぺんばんか)
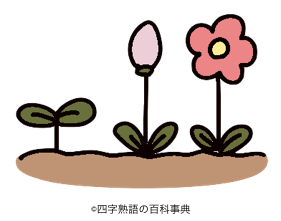
【意味】
目まぐるしく、さまざまに変化すること。


「た行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

大器晩成(たいきばんせい)

【意味】
大人物は、若いころは目立たず、年をとってから本当の力を示すようになるということ。

この言葉は、才能があるけれども現在は成功していない人に対して、時間をかけて成長することの大切さを教えてくれるんだ。

才能があるのに今はまだ成功していない人にも、「待ってても大丈夫、時間が経つときっと成功するで」って励ましてくれる言葉やな。
大胆不敵(だいたんふてき)
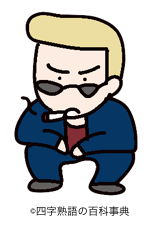
【意味】
度胸がすわっていて、恐れるようすがないこと。

自分がやろうとしていることに対して、全く怖がらずに進むという意味が含まれているんだ。

これは、「怖がらずに、大胆に行動する勇気」を表してる言葉なんやで。
大同小異(だいどうしょうい)

【意味】
似たり寄ったりで、大したちがいのないこと。

大枠は同じだけれど、ちょっとした部分で差があるということを表しているんだ。

これは、「大体は同じだけど微妙に違う」っていう状況を表してる言葉なんやで。
単刀直入(たんとうちょくにゅう)

【意味】
前置きなしに、いきなり話の中心に入ること。

これは、一人で一本の刀を持って、敵陣に突撃するということから来ているんだ。

これは、「すぐに肝心な話をする」っていう意味がある言葉なんやで。
朝令暮改(ちょうれいぼかい)

【意味】
決まりや命令などがむやみに変更されて、一定しないこと。

朝に出したルールが、その日の夕方にはもう変えられてしまうということからなんだ。

朝に言ったことが、もう夕方には変わってる。これは、「安定せんでいつも変わる状況」を表す言葉なんやで。
猪突猛進(ちょとつもうしん)
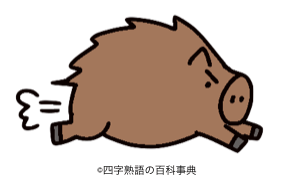
【意味】
周りには目もくれずに、がむしゃらに突き進むこと。

猪が一直線に進む姿を例えに使っているんだよ。

野生のいのししのように一点を見つめてずんずん進むんやな。これは、「向こう見ずに進む勢い」を表す言葉なんやで。
適材適所(てきざいてきしょ)

【意味】
その人の能力や性格に応じて、その人にふさわしい役目や仕事を割り当てること。

それぞれが一番活躍できる場所で仕事をするという意味があるんだ。

これは、「個々の才能を最大限に活かす」っていう意味がある言葉なんやで。
電光石火(でんこうせっか)

【意味】
動きが非常に速いこと。また、非常に短い時間のこと。

稲妻が光る瞬間や、石を打つときに出る火花がすぐに消えるような、一瞬の出来事を指すんだ。

これは、「超スピーディーな動きや、一瞬の時間」を表す言葉なんやで。
天真爛漫(てんしんらんまん)

【意味】
飾り気がなく無邪気で、明るいこと。

飾り気のない自然体で、生まれつきの純真さがそのまま表れている様子を指すんだ。

自分の素直な感情をストレートに表現し、明るく元気な態度を持つんやな。これは、「自然体で純真な様子」を表す言葉なんやで。
天変地異(てんぺんちい)
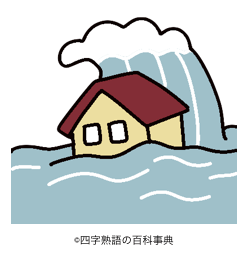
【意味】
天地間に起こる、自然の災害や異変。

天や地が大きく変化する、予想外の出来事を指す言葉なんだ。

これは、「自然に起こる大きな変化や珍事」を表す言葉なんやで。
東奔西走(とうほんせいそう)

【意味】
仕事や用事で、あちこち忙しく走り回ること。

とにかく慌ただしく、あちこち走り回る様子を指しているんだよ。

これは、「忙しくてあちこち走り回る状況」を表す言葉なんやで。
独立独歩(どくりつどっぽ)

【意味】
人に頼らず自分の力で、自分の信じるとおりに進んでいくこと。

自分で考え、自分の力で行動する、という強い意志が示されているんだ。

自分で決めたことは自分でやり遂げる、という意志が強いんやな。これは、「自立して自分の道を進む」を表す言葉なんやで。
「な行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

二束三文(にそくさんもん)
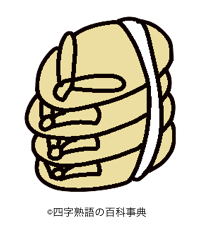
【意味】
値段が、非常に安いこと。

いくら多く売っても利益が出ないほどの安価で、物が投げ売りされる様子を表しているんだ。

これは、「投げ売り状態」を表す言葉なんやで。
日進月歩(にっしんげっぽ)
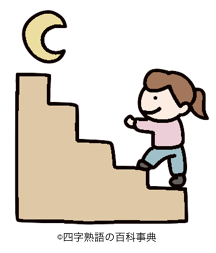
【意味】
日ごとに、月ごとに、どんどん進歩すること。

日ごと、月ごとに素晴らしい進歩がある、という高速な成長を指しているんだ。

日に日に、月に月に、すごく進歩していくんやな。これは、「急速に成長や進歩を続ける」てことを表す言葉なんやで。
「は行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

馬耳東風(ばじとうふう)

【意味】
人の意見や批判などには注意をはらわず、聞き流すこと。

春風が馬の耳に吹いても馬が何も感じないように、人の意見を感じずに聞き流す様子を描いているんだ。

これは、「他人の意見を無視する」を表す言葉なんやで。
波乱万丈(はらんばんじょう)
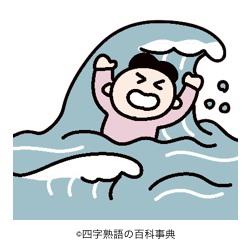
【意味】
変化が激しくて、劇的(げきてき)であること。

平穏な時もあれば、大きなトラブルもある。そんな人生を表しているんだ。

これは、「劇的な変化が続く状況」を表す言葉なんやで。
半信半疑(はんしんはんぎ)

【意味】
どうしても信じきれないでいるようす。

それが本当なのか、うそなのか、ちょっと判断できないような状態を示しているんだ。

これは、「はっきりとした判断がつかないとき」を表す言葉なんやで。
百戦錬磨(ひゃくせんれんま)
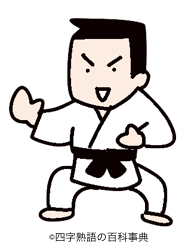
【意味】
多くの経験を積んで、きたえられていること。

数多くの試練を乗り越えて成長したことを示しているんだ。

これは、「たくさんの経験を積んで成熟した」てことを表す言葉なんやで。
百発百中(ひゃっぱつひゃくちゅう)

【意味】
弾丸や矢などが必ず命中すること。予想や計画がすべて当たること。


不言実行(ふげんじっこう)

【意味】
あれこれ言わず黙って、しなければならないことを行うこと。


付和雷同(ふわらいどう)
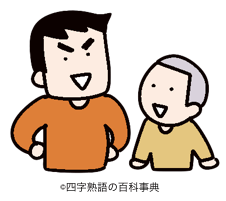
【意味】
自分にしっかりした考えがなくて、すぐ他人の考えに同調すること。


ただ人の後をついて行くだけじゃなく、自分で考えることも大切やってことを教えてくれる言葉やな。
粉骨砕身(ふんこつさいしん)

【意味】
力の限り努力すること。

これはまさに骨が粉になるほど、身体が砕けるほど一生懸命に頑張るというイメージから来ているんだ。

これは、「どんなに大変でも最後まで頑張る勇気」を教えてくれる言葉なんやで。すごいね~。
傍若無人(ぼうじゃくぶじん)
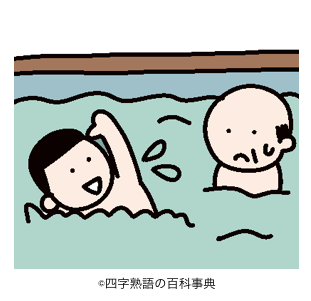
【意味】
あたりかまわず、勝手気ままにふるまうこと。また、そのようす。

他人の気持ちや立場を考えず、自分だけの思い通りに行動するという意味があるんだ。

これは、「他人のことも考えて行動することの大切さ」を教えてくれる言葉やな。
本末転倒(ほんまつてんとう)

【意味】
物事のだいじなことと、そうでないこととを、取りちがえること。

つまり、重要なこととそうでないことを混乱してしまう、という意味だよ。

これは、「大事なことをしっかりと理解することの大切さ」を教えてくれる言葉やな。
「ま行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

無我夢中(むがむちゅう)
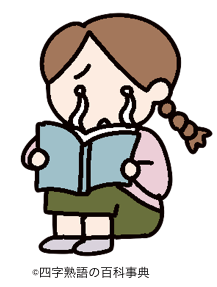
【意味】
我を忘れて、物事に熱中しているようす。

つまり、何かに夢中になりすぎて、自分がどうなるかすら気にしない、という意味だよ。

これは、「一つのことに集中する力」を教えてくれる言葉なんやな。
「や行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

有名無実(ゆうめいむじつ)

【意味】
名ばかりりっぱで、中身がないこと。

つまり、見た目だけが良くて中身がない、という意味だよ。

これは、「名前だけでなく実力も大切」ってことを教えてくれる言葉やな。
油断大敵(ゆだんたいてき)

【意味】
油断すると思わぬ失敗を招くから、油断は敵だと思って気をつけよ、ということ。


これは、「注意力が大切だ」ってことを教えてくれる言葉やな。
「ら行」最も有名な四字熟語(意味解説付き)

竜頭蛇尾(りゅうとうだび)

【意味】
初めは勢いが盛んで、終わりのほうになると振るわなくなるようす。

つまり、始めは竜の頭のように立派でも、終わりは蛇の尾のように小さくなってしまうという意味だよ。

これは、「最後まで気力を保つことの大切さ」を教えてくれる言葉やな。
臨機応変(りんきおうへん)

【意味】
その場その場の状況に応じて、適切な行動をとること。

つまり、場合によって自分の対応を変える、という意味だよ。

これは、「臨機応変に対応する能力」を教えてくれる言葉やな。