左顧右視【さこうし】の意味と使い方や例文(類義語)
【四字熟語】 左顧右視 【読み方】 さこうし 【意味】 むやみに左右を見渡すこと。ぐずぐずしているようすのたとえ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・右往左往(うおうさおう) ・右顧左眄(うこさべん) ・左顧右眄(さこう...
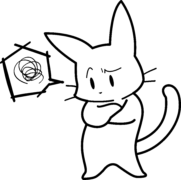 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左顧右視 【読み方】 さこうし 【意味】 むやみに左右を見渡すこと。ぐずぐずしているようすのたとえ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・右往左往(うおうさおう) ・右顧左眄(うこさべん) ・左顧右眄(さこう...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左顧右眄 【読み方】 さこうべん 【意味】 周りを気にして、なかなか決断を下さないこと。他人の様子をうかがって、決断をためらうこと。左を見たり右を見たりする意から。もとは、ゆったりと得意で余裕のある様子をい...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 殺伐激越 【読み方】 さつばつげきえつ 【意味】 楽音などが荒々しく激しいこと。 【典拠・出典】 - 殺伐激越(さつばつげきえつ)の使い方 殺伐激越(さつばつげきえつ)の例文 こんな殺伐激越に演奏するなんて...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 沙羅双樹 【読み方】 さらそうじゅ 【意味】 釈迦が八十歳で入滅したとき、臥床の四方にあった二本ずつの沙羅の木。釈迦の入滅を悲しんで、二本のうち一本ずつが枯れたともいい、入滅とともにそれらが白く枯れ変じたと...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三顧之礼 【読み方】 さんこのれい 【意味】 真心から礼儀を尽くして、すぐれた人材を招くこと。また、目上の人が、ある人物を信任して手厚く迎えること。 【語源・由来】 諸葛亮「前出師表」より。中国三国時代、蜀...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残念至極 【読み方】 ざんねんしごく 【意味】 非常に悔しくてたまらないこと。とても心残りであること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残念無念(ざんねんむねん) 残念至極(ざんねんしごく)の使い方 残念...
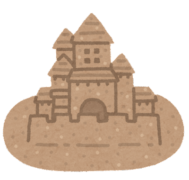 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 砂上楼閣 【読み方】 さじょうのろうかく 【意味】 基本がしっかりしていないために、物事が長続きしないこと。また、実現不可能なこと。一見、すばらしく思えることでも、実は、あまり確かなことではないということ。...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山川万里 【読み方】 さんせんばんり 【意味】 山川を越えて遠くへだたっていること。 【典拠・出典】 - 山川万里(さんせんばんり)の使い方 山川万里(さんせんばんり)の例文 山川万里の距離にいる高名なピア...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 猜忌邪曲 【読み方】 さいきじゃきょく 【意味】 他人をねたみそねむ、よこしまでまがった考え。 【語源由来】 「猜忌」は、他人をねたんだりにくんだりすること。「邪曲」は、よこしまで曲がっていること。 【典拠...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 才学非凡 【読み方】 さいがくひぼん 【意味】 学問において人並み優れた力を持っていること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・才気煥発(さいきかんぱつ) ・脱俗超凡(だつぞくちょうぼん) 才学非凡(さいが...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 罪障消滅 【読み方】 ざいしょうしょうめつ 【意味】 仏教で、生まれ変わって極楽へ行くのに妨げとなる悪い行いが、消え去ること。 【典拠・出典】 - 罪障消滅(ざいしょうしょうめつ)の使い方 罪障消滅(ざいし...
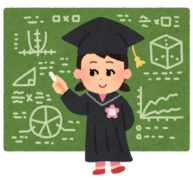 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 才芸器量 【読み方】 さいげいきりょう 【意味】 人間の才知や度量。 【典拠・出典】 - 才芸器量(さいげいきりょう)の使い方 才芸器量(さいげいきりょう)の例文 みなさんの才芸器量を測るために、特別な試験...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 才学博通 【読み方】 さいがくはくつう 【意味】 学問に広く通じていること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・該博深遠(がいはくしんえん) ・広才博識(こうさいはくしき) ・博学偉才(はくがくいさい) ・...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 最上無二 【読み方】 さいじょうむに 【意味】 この世に二つとなく、最もすばらしいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・至大至高(しだいしこう) 最上無二(さいじょうむに)の使い方 最上無二(さいじょう...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左提右挈 【読み方】 さていゆうけつ 【意味】 手をひいて互いに助け合うこと。協力し合うこと。 【典拠・出典】 『漢書』「帳耳伝」 左提右挈(さていゆうけつ)の使い方 左提右挈(さていゆうけつ)の例文 夏休...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 洒掃薪水 【読み方】 さいそうしんすい 【意味】 掃除や炊事をすること。日常の家事。 【典拠・出典】 - 洒掃薪水(さいそうしんすい)の使い方 洒掃薪水(さいそうしんすい)の例文 ともこちゃんは、洒掃薪水の...
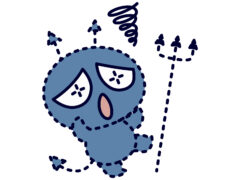 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 災難即滅 【読み方】 さいなんそくめつ 【意味】 わざわいが直ちに消え失せること。 【典拠・出典】 - 災難即滅(さいなんそくめつ)の使い方 災難即滅(さいなんそくめつ)の例文 健太くんは運が悪いので、家内...
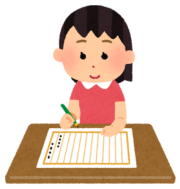 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 作文三上 【読み方】 さくぶんさんじょう 【意味】 文章を作る工夫をするのに、適した三つの場所。馬上(馬に乗っているとき)・枕上(寝床に入っているとき)・厠上(便所にいるとき)をいう。 【語源・由来】 宋の...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 座食逸飽 【読み方】 ざしょくいっぽう 【意味】 何もしないで、働かずに食うこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・拱手傍観(きょうしゅぼうかん) ・袖手旁観(しゅうしゅぼうかん) ・酔生夢死(すいせいむ...
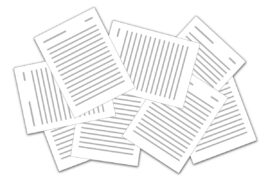 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 雑然紛然 【読み方】 ざつぜんふんぜん 【意味】 いろいろ入り交じってごたごたとしていること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・種種雑多(しゅじゅざった) ・参差錯落(しんしさくらく) ・紛擾雑駁(ふんじ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三界乞食 【読み方】 さんがいこつじき 【意味】 仏教で、他人の助けなしには、この世界のどこにも食が得られない状態。 【典拠・出典】 - 三界乞食(さんがいこつじき)の使い方 三界乞食(さんがいこつじき)の...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三界無宿 【読み方】 さんがいむしゅく 【意味】 仏教で、この世界のどこにも住む家がないこと。 【典拠・出典】 - 三界無宿(さんがいむしゅく)の使い方 三界無宿(さんがいむしゅく)の例文 景気が悪くなり、...
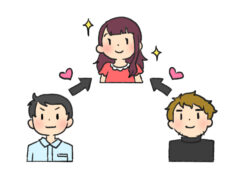 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三角関係 【読み方】 さんかくかんけい 【意味】 三者間の関係、特に三人の男女間の複雑な恋愛関係。 【典拠・出典】 - 三角関係(さんかくかんけい)の使い方 三角関係(さんかくかんけい)の例文 あの殺人事件...
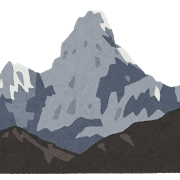 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山岳重畳 【読み方】 さんがくちょうじょう 【意味】 山々が幾重にも連なっていること。 【典拠・出典】 - 山岳重畳(さんがくちょうじょう)の使い方 山岳重畳(さんがくちょうじょう)の例文 健太くんの家は、...
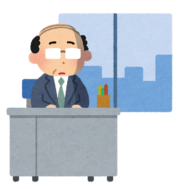 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 散官遊職 【読み方】 さんかんゆうしょく 【意味】 名ばかりでほとんど仕事のない官職。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残酷非道(ざんこくひどう) ・残忍酷薄(ざんにんこくはく) ・残忍薄行(ざんにんはっ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残虐無動 【読み方】 ざんぎゃくむどう 【意味】 道徳にそむいてむごたらしいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残酷非道(ざんこくひどう) ・残忍酷薄(ざんにんこくはく) ・残忍薄行(ざんにんはっこう...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三綱五常 【読み方】 さんこうごじょう 【意味】 儒教で、人として常に踏み行い、重んずべき道のこと。 【典拠・出典】 『文中子』天地 三綱五常(さんこうごじょう)の使い方 三綱五常(さんこうごじょう)の例文...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山光水色 【読み方】 さんこうすいしょく 【意味】 山や水の景色。山水の美。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・高山流水(こうざんりゅうすい) ・山紫水明(さんしすいめい) ・山容水態(さんようすいたい) ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三三九度 【読み方】 さんさんくど 【意味】 祝儀の際の献杯の礼法。多く、日本風の結婚式のときに新郎新婦が三つ組の杯で、それぞれの杯を3回ずつ合計9回やり取りすること。三三九献。 【典拠・出典】 - 三三九...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三思九思 【読み方】 さんしきゅうし 【意味】 何度も繰り返しじっくりと考えること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・審念熟慮(しんねんじゅくりょ) ・千里万考(せんりばんこう) ・沈思黙考(ちんしもっこ...
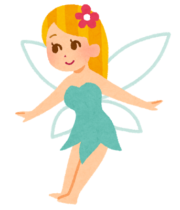 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山精木魅 【読み方】 さんせいもくみ 【意味】 山の精と木の精。山野の自然の精霊たちの総称。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・悪鬼羅刹(あっきらせつ) ・異類異形(いるいいぎょう) ・怨霊怪異(おんりょう...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三世因果 【読み方】 さんぜいんが 【意味】 仏教で、過去・現在・未来の三世にわたって、善悪の報いを受けるということ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・因果因縁(いんがいんねん) ・因果応報(いんがおうほ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三世十方 【読み方】 さんぜじっぽう 【意味】 三世と十方、すなわち無限の時間と無限の空間。 【典拠・出典】 - 三世十方(さんぜじっぽう)の使い方 三世十方(さんぜじっぽう)の例文 健太くんの道は、三世十...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山川草木 【読み方】 さんせんそうもく 【意味】 (人間や人工的なものに対して)自然に存在するものすべて。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・禽獣草木(きんじゅうそうもく) ・草木禽獣(そうもくきんじゅう)...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三段論法 【読み方】 さんだんろんぽう 【意味】 論理学における推理法で、二つの判断(前提)と第三の判断(結論)であるところの「大前提・小前提・結論」の組み合わせで、推理を行うこと。三段推理法。三段法。 【...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 残忍薄行 【読み方】 ざんにんはっこう 【意味】 むごくて人情味がないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残虐非道(ざんぎゃくひどう) ・残虐無動(ざんぎゃくむどう) ・残酷非道(ざんこくひどう) ・...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残忍非道 【読み方】 ざんにんひどう 【意味】 道理や人情に背き、むごいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残虐非道(ざんぎゃくひどう) ・残虐無動(ざんぎゃくむどう) ・残酷非道(ざんこくひどう) ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残忍冷酷 【読み方】 ざんにんれいこく 【意味】 情愛が薄くむごいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・残虐非道(ざんぎゃくひどう) ・残虐無動(ざんぎゃくむどう) ・残酷非道(ざんこくひどう) ・残忍...
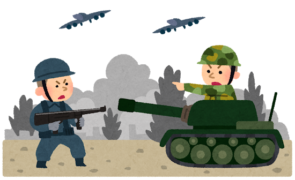 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蚕食鯨呑 【読み方】 さんしょくげいどん 【意味】 強大な国が、弱小な国を侵略していくこと。 【典拠・出典】 - 蚕食鯨呑(さんしょくげいどん)の使い方 蚕食鯨呑(さんしょくげいどん)の例文 A国が、蚕食鯨...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三草二木 【読み方】 さんそうにもく 【意味】 雨が降ると上草・中草・小草と大樹・小樹がそれぞれ成長することを、仏の教えによって機根の異なる衆生が等しく利益を受けるのにたとえた語。 【典拠・出典】 『法華経...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山村僻邑 【読み方】 さんそんへきゆう 【意味】 山奥の都会から遠く離れた村のこと。 【典拠・出典】 - 山村僻邑(さんそんへきゆう)の使い方 山村僻邑(さんそんへきゆう)の例文 健太くんは、山村僻邑に移住...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山溜穿石 【読み方】 さんりゅうせんせき 【意味】 小さな水滴でも、長く落ち続ければ石に穴を開けることができるということ。転じてわずかな力でも積み重なれば、大きな仕事が成し遂げられるということ。 【典拠・出...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三老五更 【読み方】 さんろうごこう 【意味】 中国、周代に、天子が父兄の礼をもって養った長老のこと。 【語源・由来】 「三老」も「五更」も長老の称。周代に老年で退職した人で有徳の士は天子から父兄の礼をもっ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三浴三薫 【読み方】 さんよくさんくん 【意味】 相手を大切に思う心をあらわす言葉。幾度も体を清め、幾度も香を塗り染めよい香りをつけて人を待つという意味。 【語源・由来】 「三」は幾度もという意味。「浴」は...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山容水態 【読み方】 さんようすいたい 【意味】 山の形と水のようす。山水の美しさを表す。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・三光水色(さんこうすいしょく) ・山容水色(さんようすいしょく) 山容水態(さん...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 讒謗罵詈 【読み方】 ざんぼうばり 【意味】 ありとあらゆる悪口をいうこと。 【語源・由来】 「讒謗」はそしること。「罵詈」は口ぎたなく相手をののしること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・悪口雑言(あっ...
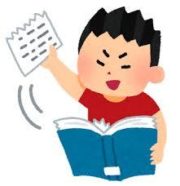 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残編断簡 【読み方】 ざんぺんだんかん 【意味】 書物の切れ端。 【語源・由来】 「残編」は散逸した残りの本。「断簡」は切れぎれになった書き物。断片の文書。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・断簡零墨(だん...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三平二満 【読み方】 さんぺいじまん 【意味】 十分ではないが、少しのもので満足し、心穏やかに過ごすこと。 【語源・由来】 「三」と「二」はともに数が少ないことを示し、少しのものでも心が穏やかで満足している...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三分鼎足 【読み方】 さんぶんていそく 【意味】 鼎の足のように天下を三分して三つの国が並び立つこと。 【語源・由来】 「鼎」は三本の足のある器で、三本の脚のバランスで立っている。 【典拠・出典】 『史記』...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 散文精神 【読み方】 さんぶんせいしん 【意味】 浪漫的・詩的感覚を排し、人生の実態をリアリズムの立場で冷静、客観的に見つめようとする小説執筆上の精神のあり方。日本の文壇でのみ用いられる文語用語。 【典拠・...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三百代言 【読み方】 さんびゃくだいげん 【意味】 詭弁を弄すること。また、その人。無責任な弁護士をののしっていう言葉。 【語源・由来】 「三百」は銭三百文のことで価値が低いという意味。「代言」は弁護士のこ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残杯冷炙 【読み方】 ざんぱいれいしゃ 【意味】 ひどい待遇や冷たい扱いをされること。恥辱や屈辱を受けるたとえ。貧しい食事や食べ残しで接待されるような屈辱を受けること。 【語源・由来】 「残杯」は他人が飲み...
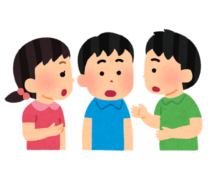 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三人文殊 【読み方】 さんにんもんじゅ 【意味】 一人ではよい知恵が浮かばなくても、三人が協力すればよい考えが出るものだということ。 【語源・由来】 「文殊」は釈迦の左にいて、知恵をつかさどると文殊菩薩のこ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残忍酷薄 【読み方】 ざんにんこくはく 【意味】 思いやりがなくむごいこと。 【語源・由来】 「残忍」と「酷薄」はともに、ひどく不人情で思いやりの気持ちがないという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
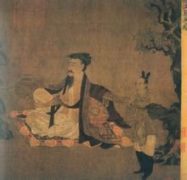 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山濤識量 【読み方】 さんとうしきりょう 【意味】 すぐれた識見や器量をもつ人のたとえ。 【語源・由来】 「山濤」は竹林の七賢の一人。「識」は知識や識見。「量」は器量や度量のこと。中国、晋の山濤は若いときか...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 讒諂面諛 【読み方】 ざんてんめんゆ 【意味】 人の悪口を言ってこびへつらうこと。 【語源・由来】 「讒諂」は他の人の悪口を言って人にへつらうこと。「面諛」は人の面前でこびへつらうこと。 【典拠・出典】 『...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 参天弐地 【読み方】 さんてんじち 【意味】 天や地と同じくらい大きな徳を積むこと。天地に匹敵するほどの気高い徳があること。 【語源・由来】 「参天」は、天と肩を並べるほど高いこと。天まで届くこと。「弐地」...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 斬釘截鉄 【読み方】 ざんていせってつ 【意味】 くぎや鉄を断ち切る。毅然として決断力があるたとえ。 【語源・由来】 「斬」と「截」はいずれも断ち切るということ。元は禅宗の言葉で、妄想や煩悩などの迷いをすっ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山中暦日 【読み方】 さんちゅうれきじつ 【意味】 俗世を離れて悠々と暮らすこと。 【語源・由来】 人里離れた山中に暮らせば月日の経つのも忘れるという意味。「暦日」はこよみのこと。「山中暦日無し」を略した言...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残息奄奄 【読み方】 ざんそくえんえん 【意味】 息も絶え絶えで、今にも死にそうなこと。いまにも滅びそうな苦しいさま。 【語源・由来】 「残息」は呼吸・いきづかいのこと。「奄」はおおう・ふさぐという意味で、...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山藪蔵疾 【読み方】 さんそうぞうしつ 【意味】 大事をなす大人物は多少欠点はあってもあらゆる人を包み込む器量があるということのたとえ。また、立派ですぐれたものにも、多少の欠点はあるものだということ。 【語...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三千世界 【読み方】 さんぜんせかい 【意味】 この世のすべてをいう。 【語源・由来】 仏教で須弥山を中心に、日・月など諸天を含むものを一世界とし、これを千合わせたものを小世界、それを千合わせて中世界。千が...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三尺童子 【読み方】 さんせきのどうじ 【意味】 子どものことで、だいたい七~八歳の子。成人に比して「小さな子どもでさえ」という意味も持つ。 【語源・由来】 二歳半で一尺と数えた。 【典拠・出典】 胡銓「上...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三聖吸酸 【読み方】 さんせいきゅうさん 【意味】 儒教の蘇東坡、道教の黄山谷、仏教の仏印禅師の三人が、桃花酸という酢をなめ眉をひそめる図。三教の一致を風刺するものとしてよく画題とされる。儒教・道教・仏教の...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三世一爨 【読み方】 さんせいいっさん 【意味】 親、子、孫の三世代の家族が一つ屋根の下に住まうこと。 【語源・由来】 「爨」はかまどのこと。三代の家族が、一つの竈で煮炊きして住むという意味から。 【典拠・...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三寸不律 【読み方】 さんずんふりつ 【意味】 長さ三寸という短い筆のこと。また、たった三寸の筆のように短いこと。 【語源・由来】 「不律」は筆のこと。長さわずかわずか三寸の筆の意味。 【典拠・出典】 - ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三十而立 【読み方】 さんじゅうじりつ 【意味】 三十歳で学識や道義上の自信を得て思想が確立すること。孔子がみずからの一生を回顧して述べた語。 【語源・由来】 「子曰く、吾十有五にして学に志す。三十にして立...
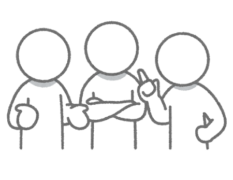 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三者鼎談 【読み方】 さんしゃていだん 【意味】 三人が向かい合って話をすること。また、その話 【語源・由来】 「鼎」はものを煮たり、祭器として用いたりする器。二つの手と三本の足がついている。 【典拠・出典...
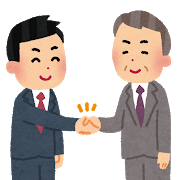 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三舎退避 【読み方】 さんしゃたいひ 【意味】 相手にとてもかなわないと思って遠慮する、恐れ避けること。 【語源・由来】 「舎」は軍隊の一日の行程で、一舎は三十里(当時の一里は四〇五メートル。三十里は訳十二...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 三者三様 【読み方】 さんしゃさんよう 【意味】 やり方や考え方などが、人それぞれで違うこと。 【語源・由来】 三人の人がいれば、三つのやり方や考え方などがあるという意味から。 【典拠・出典】 - 【類義語...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三尺秋水 【読み方】 さんじゃく(の)しゅうすい 【意味】 よくみがかれた剣のこと。 【語源・由来】 「三尺」は剣の標準的な長さのこと。「秋水」は秋の冷たく澄みきった水のこと。白く冴えわたった光を放つ剣を冷...
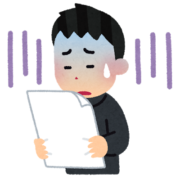 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三豕渉河 【読み方】 さんししょうか 【意味】 文字の誤り。文字を誤って読んだり書いたりすること。 【語源・由来】 昔、ある史官が「己亥渉河(己亥の年、河を渡る)」と書いてあるのを、「己」を「三」、「亥」を...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三思後行 【読み方】 さんしこうこう 【意味】 物事を行う場合に、よくよく考えたのちにはじめて実行に移すこと。 【語源・由来】 三たび考えたあとで実行するという意味から。本来は次の故事のように、「それほど慎...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残山剰水 【読み方】 ざんざんじょうすい 【意味】 戦乱のあとに残った荒廃した山や川や自然。また、滅ぼされた国の山水。 【語源・由来】 「剰」は「残」と同じ。「水」は川。 【典拠・出典】 杜甫「陪鄭広文遊何...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 斬衰斉衰 【読み方】 ざんさいしさい 【意味】 喪服の種類。 【語源・由来】 「斬衰」は喪服で最も重い三年の喪の期間に着るもので、断ち切ったままで縁縫いをしていないもの。「斉衰」は斬衰についで重い喪服で一年...
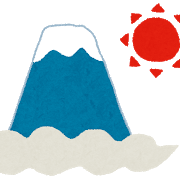 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山高水長 【読み方】 さんこうすいちょう 【意味】 人の品性が高大で高潔なたとえ。また、そうした功績や名誉が長く伝えられること。 【語源・由来】 「山高」は山がいつまでも高くそびえること。「水長」は川の水が...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 残膏賸馥 【読み方】 ざんこうしょうふく 【意味】 すぐれた人物や詩文の形容。人がいたあとに残る香気の意味。 【語源・由来】 「膏」はあぶる。「賸」は余に同じ。「馥」は香り。 【典拠・出典】 『新唐書』文芸...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三綱五常 【読み方】 さんこうごじょう 【意味】 三つの根本的な道徳と常に行うべき五つの道のこと。儒教で、人として常に踏み行い、重んずべき道のこと。 【語源・由来】 『白虎通義』より。三綱」は君臣・父子・夫...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三軍暴骨 【読み方】 さんぐんばくこつ 【意味】 大軍が戦争に大敗し、数多くの兵士が死ぬこと。戦いの激しさや悲惨さをいう。 【語源・由来】 「三軍」は周代に、一軍を一万二千五百人と決め、諸侯の大国は三万七千...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三薫三沐 【読み方】 さんくんさんもく 【意味】 相手を大切に思う心をあらわす語。 【語源・由来】 幾度の体を洗い清め、幾度も香を塗り染めよい香りをつけて人を待つという意味から。「薫」は香料を体に塗りつける...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三釁三浴 【読み方】 さんきんさんよく 【意味】 何度もからだに香を塗ってよい香りをつけ、何度もからだを洗い清めること。人を待つときなど相手を大切に思う情をいう。 【語源・由来】 「浴」は湯浴みすること。「...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 三跪九叩 【読み方】 さんききゅうこう 【意味】 清朝の敬礼法。 三度ひざまずき、九度頭を地につけて拝礼することをいう。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・三跪九拝(さんききゅうはい) ・三拝九叩(さんぱい...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 山簡倒載 【読み方】 さんかんとうさい 【意味】 酒浸りの人。 【語源・由来】 『蒙求』「山簡倒載」、『瀬説新語』「任誕」より。「山簡」は晋の人で温雅な性質であり、征南将軍になった。山濤の子。「倒載」は車に...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 山河襟帯 【読み方】 さんがきんたい 【意味】 自然の要害の堅固なことのたとえ。 【語源・由来】 白居易の詩より。山が襟のようにとり囲み、河が帯のようにめぐって流れている地形であるという意味から。 【典拠・...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三界流転 【読み方】 さんがいるてん 【意味】 いのちのあるものはすべて、前世、現世、来世の三世にわたって、生死を繰り返し迷い続けるということ。 【典拠・出典】 - 三界流転(さんがいるてん)の使い方 三界...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三界無安 【読み方】 さんがいむあん 【意味】 この世は、苦労が多くて、少しも心が安まることがないということ。 【語源・由来】 「三界」は仏教の世界観で、衆生が生まれて、死に輪廻する三つの領域、欲界、色界、...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 桟雲峡雨 【読み方】 さんうんきょうう 【意味】 かけ橋の付近に起こる雲と谷あいに降る雨のこと。 【語源・由来】 「桟」はかけ橋。険しい所に架けた木組みの橋。「峡」は山と山の間の谷。 【典拠・出典】 - 桟...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 察言観色 【読み方】 さつげんかんしき 【意味】 人の言葉をよく察し、顔つきをよく観察してあざむかれず、人の性質や考え方を見抜くこと。また、人の言葉をよく聞き分け、人の顔色を見抜く聡明さをいう。 【語源・由...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 沙中偶語 【読み方】 さちゅうのぐうご 【意味】 臣下がひそかに謀反の相談をすること。 【語源・由来】 「沙中」は砂の中、人気のない砂の上、「偶語」は向かい合って相談すること。漢の高祖劉邦が建国したとき、論...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蹉跎歳月 【読み方】 さたさいげつ 【意味】 ただ時間をむだにして、むなしく過ごすこと。 【語源・由来】 「蹉跎」はよい時期を失うこと、「歳月」は年月の意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・翫歳愒日(が...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左戚右賢 【読み方】 させきゆうけん 【意味】 親戚の者を低い地位(左)におき、賢者を高い地位(右)におくこと。 【語源・由来】 漢代は右を尊ぶのに対して、左をいやしいものとした。「戚」は親戚、一族、みうち...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 坐作進退 【読み方】 ざさしんたい 【意味】 立ち居振る舞いのこと。日常の動作。座る、立つ、進む、退くの意から。 【語源・由来】 「坐」は座る、「作」は立つ、「進」は進む、「退」は退くこと。 【典拠・出典】...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 瑣砕細膩 【読み方】 ささいさいじ 【意味】 情のこまやかなこと。 【語源・由来】 「瑣砕」はこまやかなこと。心を細やかにくだくこと。「細膩」はきめこまかなこと。 【典拠・出典】 『紅楼夢』「一回」 瑣砕細...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 左建外易 【読み方】 さけんがいえき 【意味】 道理にもとるやり方で勢力や権力を増すこと。また、地方で反乱を起こすこと。 【語源・由来】 「左」はよこしま、もとるという意味。「左建」はよこしまな方法で勢力を...
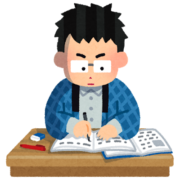 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 鑿壁偸光 【読み方】 さくへきとうこう 【意味】 苦学することのたとえ。壁に穴をあけて隣家の光をぬすんで学ぶという意味。 【語源・由来】 「鑿」はうがつ、穴を開けること。「偸」はぬすむこと。 前漢の匡衡が若...
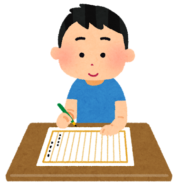 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 作文三上 【読み方】 さくぶんさんじょう 【意味】 文章を作る工夫をするのに、適した三つの場所。「馬上」馬に乗っているとき、「枕上」寝床に入っているとき、「厠上」便所にいるときをいう。 【典拠・出典】 『帰...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 削足適履 【読み方】 さくそくてきり 【意味】 目先のことに気をとられて、大事なことを忘れてしまうこと。本末を転倒して無理にものごとを処理するたとえ。 【語源・由来】 「削足」は足を削ること、「履」は靴のこ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 鑿窓啓牖 【読み方】 さくそうけいゆう 【意味】 さまざまな考え方に学んで、見識を広めること。 【語源・由来】 「鑿」はうがつ、穴をあける。「啓」はひらくという意味。「牖」は窓のこと。窓を開けて外光をたくさ...
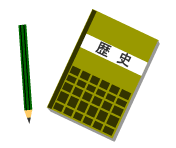 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 作史三長 【読み方】 さくしのさんちょう 【意味】 史書を著作する史家に必要な三つの長所。才知、学問、識見のこと。 【典拠・出典】 『新唐書』劉知幾伝。「史に三長あり、才・学・識なり」 作史三長(さくしのさ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 鑿歯尺牘 【読み方】 さくしせきとく 【意味】 晋の習鑿歯は、手紙で議論するのにすぐれていた。 【語源・由来】 「鑿歯」は晋の習鑿歯のこと。「尺牘」は手紙のこと。晋の習鑿歯は若いときから文章にすぐれていたが...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 坐臥行歩 【読み方】 ざがこうほ 【意味】 立ち居振る舞いをいう。座ったり、寝たり、歩いたりする。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・行住坐臥(ぎょうじゅうざが) ・挙止進退(きょししんたい) ・坐作進退(...
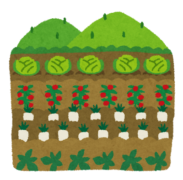 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 菜圃麦隴 【読み方】 さいほばくろう 【意味】 水をたたえずに、野菜や穀類を栽培する農耕地、すなわち畑のこと。 【語源・由来】 「菜圃」は野菜を植えた畑、菜園。「麦隴」は麦畑の意味。「圃」ははたけ、「隴」は...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 彩鳳随鴉 【読み方】 さいほうずいあ 【意味】 自分より劣る人に嫁がされること。また、それに不満を持つこと。転じて、夫人が夫をぞんざいに遇すること。 【語源・由来】 「鳳」は瑞鳥でおおとり、「鴉」はからす。...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 采椽不斲 【読み方】 さいてんふたく 【意味】 質素な建物のこと。 【語源・由来】 『韓非子』「五蠹」より。「采椽」は山から切り出したままの椽(家の棟から軒に渡して屋根を支える材木)のこと。「斲」は木を削る...
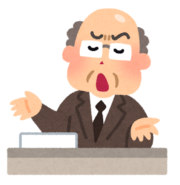 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 裁断批評 【読み方】 さいだんひひょう 【意味】 裁判官が判決を下すように、文芸作品を一段高いある基準で判定する批評の方法。ヨーロッパ十八世紀初頭まではこの方法が主流をしめていた。「裁断」は善悪や是非をはっ...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 灑掃応対 【読み方】 さいそうおうたい 【意味】 日常生活に必要な仕事や作法のこと。ふきそうじをすることと、応対すること。 【典拠・出典】 『大学章句』朱熹「序」 灑掃応対(さいそうおうたい)の使い方 灑掃...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 載籍浩瀚 【読み方】 さいせきこうかん 【意味】 数えきれないほどの書物があること。書籍に埋もれんばかりのさま。 【語源・由来】 「載籍」は、書類や書物のこと。「浩瀚」は、物が豊かなさま、書籍の巻数などが多...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 祭政一致 【読み方】 さいせいいっち 【意味】 神を祭ることと政治は一体であるという考え。または、そのような政治形態のこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・政教一致(せいきょういっち) 【対義語】 ・祭...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 採薪之憂 【読み方】 さいしんのうれい 【意味】 自分が病気を患っていることを謙遜していう言葉。 【語源・由来】 病に伏して、薪を採ることさえ、ままならないという意味。 【典拠・出典】 『孟子』「公孫丑・下...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 採薪汲水 【読み方】 さいしんきゅうすい 【意味】 自然に囲まれた環境で質素に暮らすこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・負薪汲水(ふしんきゅうすい) 採薪汲水(さいしんきゅうすい)の使い方 採薪汲水(...
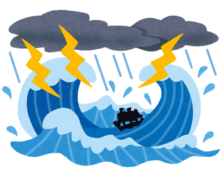 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 載舟覆舟 【読み方】 さいしゅうふくしゅう 【意味】 君主は人民によって支えられ、また、人民によって滅ぼされるということ。君主は人民を愛し、政治に安んじさせることが必要であるということをいう。転じて、人は味...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 犀舟勁檝 【読み方】 さいしゅうけいしゅう 【意味】 堅牢な船と強いかいのこと。 【語源・由来】 『後漢書』「張衡伝」より。「犀舟」は堅固な船のこと。「勁」は強いということ。「檝」は舟をこぐ櫂のこと。 【典...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 妻子眷族 【読み方】 さいしけんぞく 【意味】 妻と子、家族と血縁関係にある親族のこと。 【語源・由来】 「眷」はみうち、またかえりみる、目をかけるという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一族郎党(...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 在邇求遠 【読み方】 ざいじきゅうえん 【意味】 人として進むべき正しい道は自分自身の中に求めるべきなのに、哀れにも人は遠いところにそれを求めようとするという意味。 【語源・由来】 「邇」は「近」と同じで、...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 罪業消滅 【読み方】 ざいごうしょうめつ 【意味】 罪深き行いも、仏道修行により消し去ることができること。 【語源・由来】 仏教語で、「罪業」は罪となる行い。 【典拠・出典】 - 罪業消滅(ざいごうしょうめ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 歳寒松柏 【読み方】 さいかんしょうはく 【意味】 逆境や苦難の時にあっても、志や節操を失わないこと。冬の厳しい寒さにも、松や柏が緑の葉をつけているという意から。 【語源・由来】 「歳寒」は冬の季節、または...
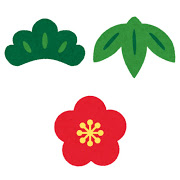 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 歳寒三友 【読み方】 さいかんさんゆう 【意味】 冬に友とすべき三つの植物、松と竹と梅。 【語源・由来】 「歳寒」は寒い季節、冬のこと。また、乱世・逆境のたとえ。松と竹は冬にも緑を失わず、梅は香り高い花を咲...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 採菓汲水 【読み方】 さいかきっすい 【意味】 厳しい仏道修行をすること。 【語源・由来】 「菓」は木の実のこと。仏に供えるために深山に入って、木の実をとり、花を摘み、水を汲むことから。 【典拠・出典】 『...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 塞翁失馬 【読み方】 さいおうしつば 【意味】 人生の幸不幸は予測できないので、いたずらに一喜一憂すべきではないということ。「塞翁」は中国の北方の塞の近くに住んでいた老人。 【語源由来】 あるとき、塞翁の飼...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三枝之礼 【読み方】 さんしのれい 【意味】 親に対して礼儀と孝行を重んじること。 【語源・由来】 鳩は木の枝にとまるとき、親鳩より三本下の枝にとまって親に対する礼儀を守るということから。「鳩に三枝の礼あり...
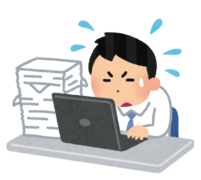 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 座薪懸胆 【読み方】 ざしんけんたん 【意味】 将来の成功や活躍のために、苦労をいとわず、つらい生活をじっと耐え忍ぶ意。つらい生活を耐えることで、敵愾心や闘志をかきたてること。 【語源・由来】 痛さをこらえ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 歳月不待 【読み方】 さいげつふたい 【意味】 時間は、あっという間に過ぎ去ってしまい、人の都合などかかわりないものだということ。年月は、無情に過ぎて行き、待ってはくれないという意味。 【典拠・出典】 陶潜...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 塞翁之馬 【読み方】 さいおうのうま 【意味】 幸いが転じて禍いになったり、不幸と思ったことが幸いになること。人生の幸不幸は、後になってみなければわからないということ。また、いたずらに喜んだり悲しんだりする...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 豺狼当路 【読み方】 さいろうとうろ 【意味】 悪い者たちが、わが物顔で、のさばっているさま。また、暴虐で、悪徳な人間が、重要な地位にあって権力を握っていること。 【語源・由来】 「豺狼」は山犬と狼、それら...
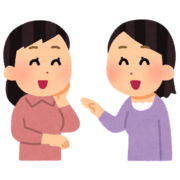 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語【四字熟語】 三人成虎 【読み方】 さんにんせいこ 【意味】 噓や噂が多くの人の話題になれば、みんながそれを信じてしまい、真実のようになってしまうということ。 【語源・由来】 「三人、虎を成す」と読み下す。 【典拠・出典...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三令五申の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 三令五申 【読み方】 さんれいごしん 【意味】 何度もくり返し命じること。 また、何度も言い聞かすこと。 【語源・由来】 三度命じて、五度重ねて言い聞かすことから。...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三面六臂の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三面六臂 【読み方】 さんめんろっぴ 【意味】 三つの顔と六つの腕をもつ意から、一人で何人分かの働きをすること。また、一人で多方面にわたって活躍すること。 【語源...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三面記事の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 三面記事 【読み方】 さんめんきじ 【意味】 日本において、日刊新聞の社会面のこと。 また、政治や経済以外の記事ということ。 【語源・由来】 新聞が4ページだった頃の、第...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語賛否両論の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【四字熟語】 賛否両論 【読み方】 さんぴりょうろん 【意味】 賛成意見と反対意見の二つがあること、またその二つのそれぞれの意見のこと。賛成と反対が対立して、意見がまとまらず、...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三年味噌の意味(語源由来) 【四字熟語】 三年味噌 【読み方】 さんねんみそ 【意味】 仕込みをして、三年目の味噌のこと。 熟成しておいしくなった味噌のこと。 勘定高く、けちなこと。 【語源・由来】 仕込みをして三年目の...
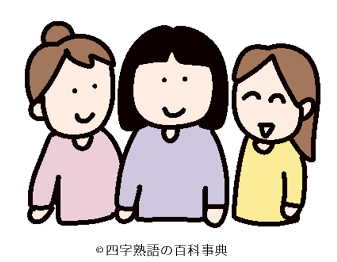 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三人三様の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三人三様 【読み方】 さんにんさんよう 【意味】 三人いれば、三人とも性格や行動、考えかたなどがそれぞれ違うこと。 【語源・由来】 やりかたや考え方が、それぞれ違...
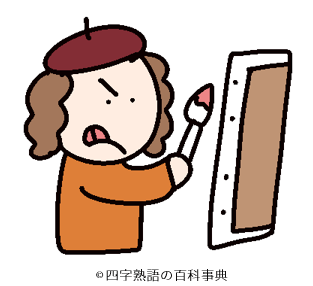 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語斬新奇抜の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 斬新奇抜 【読み方】 ざんしんきばつ 【意味】 物事の着想が独自で、それまでに類をみないほど新しいさま。それまでにないほど新しく、思いもよらないほど変わっているさ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三十六計の意味(語源由来・出典・英語訳) 【四字熟語】 三十六計 【読み方】 さんじゅうろっけい 【意味】 逃げるべき時には、どんな策略よりも、逃げることが一番の策であること。 いざという時には、逃げることが最も安全であ...
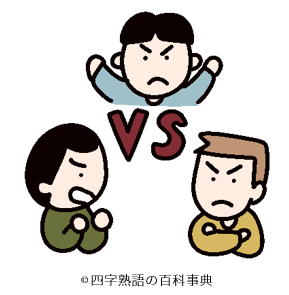 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三者鼎立の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三者鼎立 【読み方】 さんしゃていりつ 【意味】 互角の勢力を持つ三者が、並び存立していること。また、張り合って争うこと。 三つどもえ。 【語源・由来】 鼎...
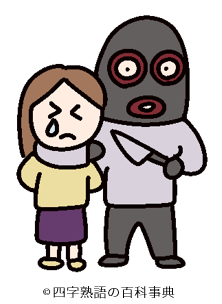 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧残酷非道の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 残酷非道 【読み方】 ざんこくひどう 【意味】 むごたらしくて、人の道に背いていること。 また、そのような振る舞いや行いのこと。 【語源・由来】 「残酷(ざんこく...
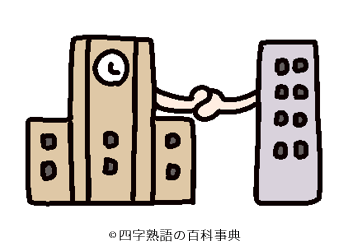 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語産学協同の意味(語源由来) 【四字熟語】 産学協同 【読み方】 さんがくきょうどう 【意味】 産業界と学校とが相互に協力し合って、研究や技術者教育の促進を図ること。 【語源・由来】 「産学(さんがく)」の、「産」とは、産...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧左支右吾の意味(語源由来・出典) 【四字熟語】 左支右吾 【読み方】 さしゆうご 【意味】 あれこれと手を尽くして逃れたり、言い逃れをしたりすること。 【語源・由来】 左を支えて、右を防ぎとどめるということから。 「支」...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語昨非今是の意味(語源由来・出典・英語訳) 【四字熟語】 昨非今是 【読み方】 さくひこんぜ 【意味】 今までのまちがいに気づくこと。 また、そのことによって、今までの過ちを悟って悔いること。 【語源・由来】 今日は正しく...
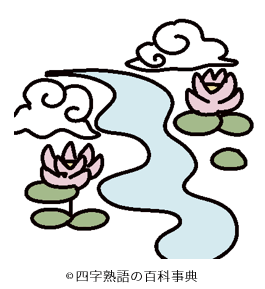 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語西方浄土の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 西方浄土 【読み方】 さいほうじょうど 【意味】 阿弥陀仏(あみだぶつ)がいるとされる、苦しみのない安楽の世界のこと。 【語源・由来】 西の方へ向かって、十万億土...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語才弁縦横の意味(語源由来) 【四字熟語】 才弁縦横 【読み方】 さいべんじゅうおう 【意味】 才気にあふれていて、巧みな弁舌を自由自在に駆使すること。 【語源・由来】 「才気(さいき)」とは、すぐれた頭の働き、頭脳の鋭く...
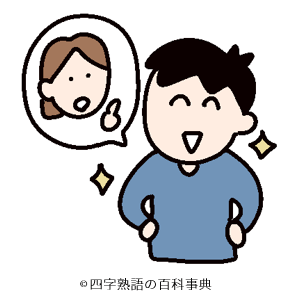 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語採長補短の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 採長補短 【読み方】 さいちょうほたん 【意味】 人の良いところを取り入れて、自分の短所や足りないところを補うこと。 また、物事のすぐれたところや余ったところから...
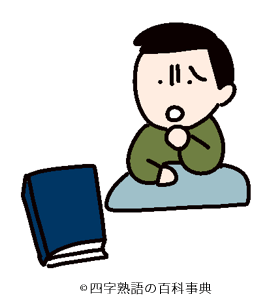 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語才子多病の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 才子多病 【読み方】 さいしたびょう 【意味】 才能のあるすぐれた人は、とにかく体が弱くて病気がちだということ。 【語源・由来】 「才知(さいち)」とは、才能のあ...
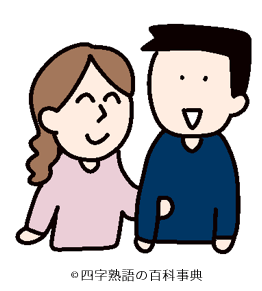 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語才子佳人の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 才子佳人 【読み方】 さいしかじん 【意味】 才知のすぐれた男性と、美人のほまれ高い女性。 【語源・由来】 「才子(さいし)」とは、才知のあるすぐれた男性のこと。 「佳人...
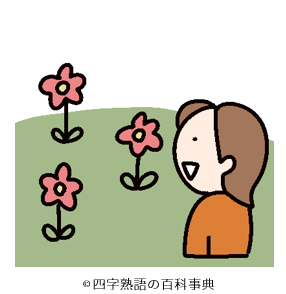 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語在在所所の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 在在所所 【読み方】 ざいざいしょしょ 【意味】 そこかしこ。あちらこちら。また、至るところ。 【語源・由来】 「在在」「所所」はともに、あそこここの村里、あちこちの場所...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語最後通牒の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 最後通牒 【読み方】 さいごつうちょう 【意味】 これ以上は、もう話し合いの余地がないと、相手方に通告すること。 【語源・由来】 もともとの意味は、国際文書のひとつ。 外...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語再起不能の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 再起不能 【読み方】 さいきふのう 【意味】 もう二度と、以前のようなよい状態には戻れないということ。 再びちからを得て活動したくても、できないということ。 【語...
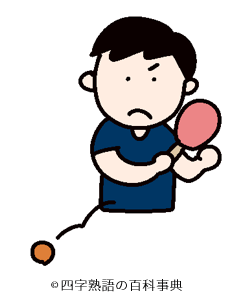 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語才気煥発の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 才気煥発 【読み方】 さいきかんぱつ 【意味】 すぐれた才能が外にあふれ出ること。またそのさま。 【語源・由来】 「才気」はすぐれた才能。すぐれた頭のはたらき。 ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語斎戒沐浴の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 斎戒沐浴 【読み方】 さいかいもくよく 【意味】 神仏に祈ったり、神聖な仕事をする前に、飲食や行動を慎んで、水を浴びて心身を清めること。 【語源・由来】 「...
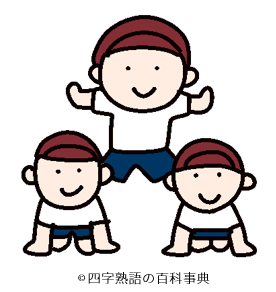 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三位一体の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三位一体 【読み方】 さんみいったい 【意味】 三者が協力して一体になることをいう。つまり、三つの別々の要素が、一つのもののように固く結びつくこと。三人が気持ちを...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三拝九拝の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三拝九拝 【読み方】 さんぱいきゅうはい 【意味】 何度も頭を下げること。何度も頭を下げて敬意や謝意を表すこと。また、手紙の末尾に記して敬意を表す語。 【語源・由...
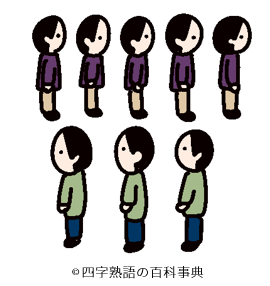 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三三五五の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 三三五五 【読み方】 さんさんごご 【意味】 あちらに三、こちらに五、というように散らばっていることから、人や家が散在するさまをあらわす。 また、少人数ずつ...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語残念無念の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 残念無念 【読み方】 ざんねんむねん 【意味】 とても悔しいさま。悔しくて悔しくてたまらないこと。 【語源由来】 「残念」も「無念」も、非常に悔しいことで、これを...
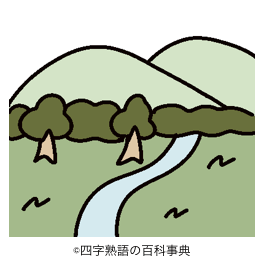 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語山紫水明の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 山紫水明 【読み方】 さんしすいめい 【意味】 自然の景色が清らかで美しいこと。太陽の光で照らされた山や川は清らかで澄んで見えること。 【語源由来】 「山紫...
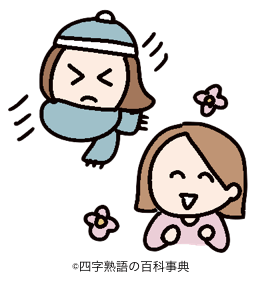 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語三寒四温の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 三寒四温 【読み方】 さんかんしおん 【意味】 冬に寒い日が三日続くと、暖かい日が四日続くという気候が繰り返されること。だんだんと暖かくなってくる気候に用いる場合もある。...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語才色兼備の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 才色兼備 【読み方】 さいしょくけんび 【意味】 すぐれた才能と美しい容姿の両方をもっていること。多くは女性についていう。 【語源由来】 「才」は才知・才能と顔か...
 「さ」で始まる四字熟語
「さ」で始まる四字熟語再三再四の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 再三再四 【読み方】 さいさんさいし 【意味】 繰り返し何度も。たびたび。 【語源由来】 「再三」は二度も三度もの意で、何度も、たびたびの意。「再四」は「再...