知恵分別【ちえふんべつ】の意味と使い方や例文(語源由来・類義語)
【四字熟語】 知恵分別 【読み方】 ちえふんべつ 【意味】 物事の道理がよく分かり、適切に判断することのできる力。 【語源・由来】 「知恵」は、物事の道理が分かり、適切に処理する心の働き。「分別」は、物事の道理をわきまえ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知恵分別 【読み方】 ちえふんべつ 【意味】 物事の道理がよく分かり、適切に判断することのできる力。 【語源・由来】 「知恵」は、物事の道理が分かり、適切に処理する心の働き。「分別」は、物事の道理をわきまえ...
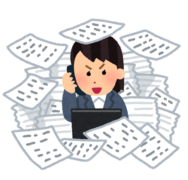 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知恵才覚 【読み方】 ちえさいかく 【意味】 物事の道理がよく分かり、機転が利くこと。 【語源・由来】 「知恵」は、物事の道理が分かり、適切に処理する心の働き。「才覚」は、才知があって、機転が利くこと。 【...
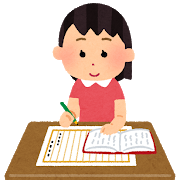 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 知行一致 【読み方】 ちこういっち 【意味】 知識と行為とに食い違いがなく、知っていて行わないことがないこと。 【語源・由来】 「知行」は、知識と行為。「一致」は、食い違いがなく同じになること。 【典拠・出...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 地水火風 【読み方】 ちすいかふう 【意味】 仏語。地と水と火と風。宇宙万物を構成する四つの元素。四大 (しだい) 。四大種。 【典拠・出典】 - 地水火風(ちすいかふう)の使い方 地水火風(ちすいかふう)...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 遅速緩急 【読み方】 ちそくかんきゅう 【意味】 遅いか速いか、緩やかか厳しいか。 【語源・由来】 「遅速」は、遅いことと速いこと。「緩急」は、緩やかなことと、厳しいこと。 【類義語】 ・前後緩急(ぜんごか...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 秩序整然 【読み方】 ちつじょせいぜん 【意味】 物事の順序が正しく整っていること。 【語源・由来】 「秩序」は、物事の正しい順序。「整然」は、きちんと整っていること。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ・物...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知徳兼備 【読み方】 ちとくけんび 【意味】 知識と道徳を兼ね備えていること。 【語源・由来】 「知徳」は、知恵と道徳。「兼備」は、かねそなえていること。 【典拠・出典】 - 知徳兼備(ちとくけんび)の使い...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠肝義胆 【読み方】 ちゅうかんぎたん 【意味】 忠義一徹の心。 【語源・由来】 「忠肝」は、忠義をつくす心。「義胆」は、正義を守る精神。正義を行う胆力。 【典拠・出典】 - 忠肝義胆(ちゅうかんぎたん)の...
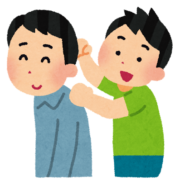 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠臣孝子 【読み方】 ちゅうしんこうし 【意味】 忠義心に富んだ家来と、親孝行な子。心から忠誠を尽くす臣下と、よく父母に仕える子。 【語源・由来】 「忠臣」は、忠義心に富んだ家来。「孝子」は、よく父母に仕え...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 茶番狂言 【読み方】 ちゃばんきょうげん 【意味】 底の見えすいた、下手な芝居。ばかげた振る舞い。 【語源・由来】 こっけいな即興寸劇。江戸歌舞伎の楽屋内で発生し、18世紀中ごろ一般に広まった。口上茶番と立...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 頂門一針 【読み方】 ちょうもんのいっしん 【意味】 相手の急所を鋭く突く適切な戒め。 【語源・由来】 「頂門」は、頭のてっぺん。鍼灸で、頭のいただきに針を打って治療することから。 【典拠・出典】 『荀卿論...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠臣貞女 【読み方】 ちゅうしんていじょ 【意味】 忠義心に富んだ家来と、節操の正しい女性。 【語源・由来】 「忠臣」は、忠義心に富んだ家来。「貞女」は、操が正しい女性。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
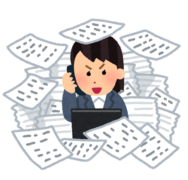 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知勇弁力 【読み方】 ちゆうべんりょく 【意味】 知恵と勇気をもって、適正に物事を判断し、処理する力。 【語源・由来】 「知勇」は、知恵と勇気。「弁力」は、物事をわきまえ、適正に処理する能力。 【典拠・出典...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠勇無双 【読み方】 ちゅうゆうむそう 【意味】 この上なく忠義心が厚く、勇敢であるさま。また、そのような人。 【語源・由来】 「無双」は、ならぶもののないほどすぐれたさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】...
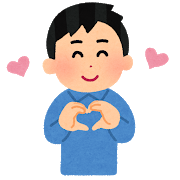 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 直情真気 【読み方】 ちょくじょうしんき 【意味】 偽りのない、本当のありのままの気持ち。 【語源・由来】 「直情」は、ありのままの気持ち。「真気」は、偽りのない本当の気持ち。 【典拠・出典】 - 直情真気...
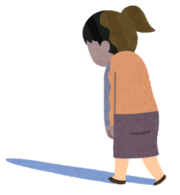 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 佇立瞑目 【読み方】 ちょうりつめいもく 【意味】 目をつぶって、長い間立ち尽くすこと。また、深い悲しみのために、目を閉じたままたたずむこと。 【語源・由来】 「佇立」は、長い間立ちつくすこと。「瞑目」は、...
 「じっくり考える」の四字熟語一覧
「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 佇立低徊 【読み方】 ちょうりつていかい 【意味】 ためらいのために、長い間立ちつくしたり行きつ戻りつしたりすること。 【語源・由来】 「佇立」は、長い間立ちつくすこと。「低徊」は、頭を垂れて物思いにふけり...
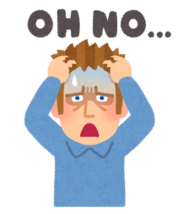 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈痛慷慨 【読み方】 ちんつうこうがい 【意味】 深く心に悲しみ、いきどおり嘆くこと。 【語源・由来】 「沈痛」は、深く心に悲しみ痛むこと。「慷慨」は、いきどおり嘆くこと。「慷」「慨」ともに、嘆く。 【典拠...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈毅雄武 【読み方】 ちんきゆうぶ 【意味】 気性が落ち着いていて強く、勇敢であること。 【語源・由来】 「沈毅」は、落ち着いていて強いこと。「雄武」は、男らしく勇ましいこと。 【典拠・出典】 - 沈毅雄武...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈着大胆 【読み方】 ちんちゃくだいたん 【意味】 度胸のすわった性格。 【語源・由来】 「沈着」は、おちついていること。物事に動じないこと。「大胆」は、きもったまの大きいこと。物事をおそれないこと。度胸が...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 聴取不能 【読み方】 ちょうしゅふのう 【意味】 相手側の意見を聞き取ることができないこと。 【語源・由来】 「聴息」は、聞き取ること。「不能」は、できないこと。なしえないこと。不可。 【典拠・出典】 - ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝耕暮耘 【読み方】 ちょうこうぼうん 【意味】 農耕に励むこと。 【語源・由来】 「耕」はたがやす。「耘」は草ぎるという意味。 【典拠・出典】 『輟耕録』「検田吏」 朝耕暮耘(ちょうこうぼうん)の使い方 ...
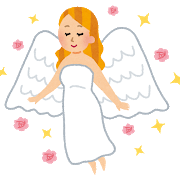 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沖和之気 【読み方】 ちゅうわのき 【意味】 天地間の調和した気のこと。 【語源・由来】 「沖和」は穏やかにやわらぐという意味。 【典拠・出典】 『列子』「天瑞」 沖和之気(ちゅうわのき)の使い方 沖和之気...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 竹帛之功 【読み方】 ちくはくのこう 【意味】 歴史に名を残すような功績や手柄のこと。 【語源・由来】 「竹」は、竹の札。「帛」は、絹の布。ともに古代中国で、紙のなかったころ文書を記す材料に使われた。 【典...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 枕流漱石 【読み方】 ちんりゅうそうせき 【意味】 強情で負け惜しみの強いこと。また、うまくこじつけて言い逃れをすること。 【語源・由来】 西晋の孫楚が隠遁を望み「石に枕し流れに漱ぐような自然な暮らしがした...
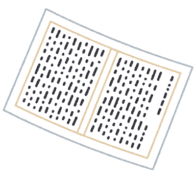 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈博絶麗 【読み方】 ちんぱくぜつれい 【意味】 文章などの意味や内容が深遠で広く表現が甚だ美しいこと。 【語源・由来】 「沈」は深いという意味。「絶」はこの上なく、非常にという意味。 【典拠・出典】 揚雄...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 沈著痛快 【読み方】 ちんちゃくつうかい 【意味】 落ち着きがあり、さっぱりとして心地よいこと。人の性質や芸術作品についていう語。 【典拠・出典】 - 沈著痛快(ちんちゃくつうかい)の使い方 沈著痛快(ちん...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 陳勝呉広 【読み方】 ちんしょうごこう 【意味】 ものごとの先駆けをなす人のこと。反乱の最初の指導者をもいう。 【語源・由来】 楚の人陳勝と呉広は秦の二世皇帝(紀元前二〇九年)のとき兵を挙げ、秦打倒の口火を...
 「じっくり考える」の四字熟語一覧
「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 沈思凝想 【読み方】 ちんしぎょうそう 【意味】 物事を深く考え、じっと思いをこらすこと。 【語源・由来】 「沈思」は深く考えること。「凝想」はじっと考えこむという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 陳蔡之厄 【読み方】 ちんさいのやく 【意味】 旅の途中で災難にあうたとえ。 【語源・由来】 孔子が諸国歴遊中に陳と蔡の国境近辺で、兵に囲まれ、食料が足りずに苦労した災難のこと。 【典拠・出典】 『史記』「...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 椿萱並茂 【読み方】 ちんけんへいも 【意味】 父と母がどちらも健在なこと。 【語源・由来】 「椿」は長寿の木で父にたとえられ、「萱」は通称わすれ草といい「憂いを忘れる」ということから主婦のいる部屋の前に植...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 枕戈待旦 【読み方】 ちんかたいたん 【意味】 戦いの備えをおこたらないこと。 【語源・由来】 戈を枕にして眠り、朝になるのを待つという意味。いつも戦場に身をさらしていること。 【典拠・出典】 『晋書』「劉...
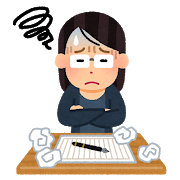 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈鬱頓挫 【読み方】 ちんうつとんざ 【意味】 詩文の風格が高く内容が深くて文章中の辞句の意味がすらすらと通らず、とどこおること。 【語源・由来】 「沈鬱」は気分が沈んで晴ればれとしないこと。出典ではこの話...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知略縦横 【読み方】 ちりゃくじゅうおう 【意味】 才知をはたらかせた計略を思いのままにあやつること。 【語源・由来】 「略」ははかりごと、「縦横」は自由自在という意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
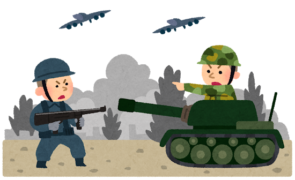 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 治乱興亡 【読み方】 ちらんこうぼう 【意味】 世の中がよく治まることと、乱れて亡びること。 【語源・由来】 「興亡」はおこることと、亡びること。 【典拠・出典】 欧陽脩「朋党論」 【類義語】 ・治乱興廃(...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【読み方】 ちょれきのざい 【意味】 役に立たない人やもの。自己の謙称。 【語源・由来】 「樗櫟」はおうちとくぬぎで役に立たない木、無用の材。無能の人。 【典拠・出典】 『荘子』「逍遥遊」 【類義語】 ・樗櫟散木(ちょれ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 樗櫟散木 【読み方】 ちょれきさんぼく 【意味】 役に立たない人やもの。自己の謙称。 【語源・由来】 「樗櫟」はおうちとくぬぎで役に立たない木、無用の材。無能の人。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・樗櫟之...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 豬突豨勇 【読み方】 ちょとつきゆう 【意味】 いのししのように勇ましい武者のこと。 【語源・由来】 漢の王莽が組織した軍隊の名。「豬突」はいのししのようにがむしゃらに突き進むこと。 【典拠・出典】 『漢書...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 佇思停機 【読み方】 ちょしていき 【意味】 しばらくの間その場に立ち止まって、あれこれ思いなやみ、こころのはたらきをやめてしまうこと。 【語源・由来】 「機」は心のはたらき・作用。 【典拠・出典】 『碧巌...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 直言骨鯁 【読み方】 ちょくげんこっこう 【意味】 遠慮しないで直言し、意志強固で人に屈しないこと。 【語源・由来】 「直言」は思っていることを遠慮なしでいうこと。「骨鯁」は君主のあやまちを諫める剛直な忠臣...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 直言極諫 【読み方】 ちょくげんきょっかん 【意味】 思ったことをはっきり言って強くいさめること。 【語源・由来】 「直言」は思ったことを状況を気にせずに言うこと。「極諫」は強くいさめていう、また強いいさめ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 直往邁進 【読み方】 ちょくおうまいしん 【意味】 ただ一すじに突き進む。ためらわずに突き進むこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・勇往邁進(ゆうおうまいしん) ・猪突猛進(ちょとつもうしん) 直往邁進...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 凋零磨滅 【読み方】 ちょうれいまめつ 【意味】 しぼみ落ちて滅びること。文物などが滅びなくなることにいう。 【語源・由来】 「凋」はしぼむ、「零」は落ちる、「磨滅」はすり減る、すり減りなくなるという意味。...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 重卵之危 【読み方】 ちょうらんのき 【意味】 きわめて危険なことのたとえ。 【語源・由来】 卵を積みかさねるといつくずれるかわからないからいう。 【典拠・出典】 『説苑』「正諫」 【類義語】 ・累卵之危(...
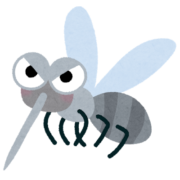 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝蠅暮蚊 【読み方】 ちょうようぼぶん 【意味】 つまらない小人物がはびこるたとえ。 【語源・由来】 人にまといつく朝の蠅と夕方の蚊。 【典拠・出典】 韓愈「雑詩」 朝蠅暮蚊(ちょうようぼぶん)の使い方 朝...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長幼之序 【読み方】 ちょうようのじょ 【意味】 年功者と年少者の間にある、当然守らなければならない社会的、道徳上の秩序のこと。 【語源・由来】 「長幼」は年長者と年少者、おとなと子供。 【典拠・出典】 『...
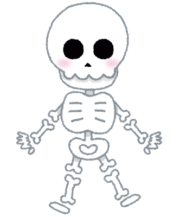 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝有紅顔 【読み方】 ちょうゆうこうがん 【意味】 人生の無常のたとえ。 【語源・由来】 若さにあふれている血色のよい美少年も、あっという間に白骨と化してしまうという意味。「朝(あした)に紅顔有りて、夕べに...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長夜之楽 【読み方】 ちょうやのたのしみ 【意味】 昼夜を通しての大宴会。夜が明けても窓や戸を閉じて灯をともし続けて酒宴を張ること。 【語源・由来】 殷の紂王が酒池肉林の大宴会をした故事から。一説にこの酒宴...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長夜之飲 【読み方】 ちょうやのいん 【意味】 昼夜を通しての大宴会。夜が明けても窓や戸を閉じて灯をともし続けて酒宴を張ること。 【語源・由来】 殷の紂王が酒池肉林の大宴会をした故事から。一説にこの酒宴は百...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 頂門金椎 【読み方】 ちょうもんのきんつい 【意味】 人の急所をついた適切な戒め。 【語源・由来】 「頂門」は頭の上。「金椎」は金属のつち。 【典拠・出典】 『佩文韻府』「黄庭堅」 【類義語】 ・頂門一針(...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 頂門一針 【読み方】 ちょうもんのいっしん 【意味】 人の急所をつく適切な戒め。頂門(頭のいただき)に刺した一本の針。 【典拠・出典】 『荀卿論』蘇軾 【類義語】 ・頂門金椎(ちょうもんのきんつい) ・当頭...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長目飛耳 【読み方】 ちょうもくひじ 【意味】 広く情報を収集し、物事を深く鋭く判断すること。遠方のことをよく見る目とよく聞くことのできる耳。 【典拠・出典】 『管子』「九守」 【類義語】 ・鳶目兎耳(えん...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥面鵠形 【読み方】 ちょうめんこくけい 【意味】 飢えのためにひどくやせ衰えているさま。 【語源・由来】 「鵠」はくぐい。 【典拠・出典】 『資治通鑑』「梁紀」 【類義語】 ・鳩形鵠面(きゅうけいこくめん...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長命富貴 【読み方】 ちょうめいふうき 【意味】 長生きして身分高く裕福であること。 【典拠・出典】 『旧唐書』「姚崇伝」 【類義語】 ・富貴長生(ふうきちょうせい) 長命富貴(ちょうめいふうき)の使い方 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長鞭馬腹 【読み方】 ちょうべんばふく 【意味】 強大な力があっても、思わぬ手近なところに力が及ばないことがあるということ。また、長すぎたり大きすぎて役に立たないこと。 【語源・由来】 鞭があまり長いとかえ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 雕文刻鏤 【読み方】 ちょうぶんこくる 【意味】 文章中の字や句を美しく飾ること。模様を彫刻し、金銀をちりばめること。 【語源・由来】 「雕文」は模様を彫刻すること。また彫刻された模様のこと。「鏤」はきざむ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 嘲風哢月 【読み方】 ちょうふうろうげつ 【意味】 風や月を題材にして詩歌を作ること。 【語源・由来】 「嘲風」は文章家のたわむれに作った詩文をそしる語。「哢月」は月をながめ楽しむこと。 【典拠・出典】 -...
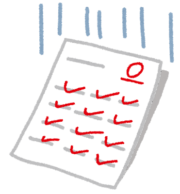 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 凋氷画脂 【読み方】 ちょうひょうがし 【意味】 苦労して効果のないたとえ。力を無用なところに用いるたとえ。 【語源・由来】 氷に彫り付けて、あぶらに画くという意味。 【典拠・出典】 『甲乙剰言』 【類義語...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 張眉怒目 【読み方】 ちょうびどもく 【意味】 眉をつり上げて目をむく。仁王さまのような荒々しい形相をいう。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・横眉怒目(おうびどもく) 張眉怒目(ちょうびどもく)の使い方 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 頂天立地 【読み方】 ちょうてんりっち 【意味】 堂々として誰にも頼らず生きているさま。また、正々堂々として志の遠大なさま。 【典拠・出典】 『五灯会元』「二○」 頂天立地(ちょうてんりっち)の使い方 頂天...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 糶糴斂散 【読み方】 ちょうてきれんさん 【意味】 豊作の年には政府が米を買い上げ、それを凶作の年に安く売ること。 【語源・由来】 「糶」は米穀を売り出すこと。「糴」は米穀を買い入れること。「斂」は収める、...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長枕大被 【読み方】 ちょうちんたいひ 【意味】 兄弟の仲むつまじいこと。また、交情が親密なこと。大きな夜着と長いまくら。寝具。 【語源・由来】 『春秋公羊伝』「宣公十五年」より。もとは夫婦の仲むつまじいこ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 喋喋喃喃 【読み方】 ちょうちょうなんなん 【意味】 小声で親しげに話しあうさま。男女がむつまじげに語りあうさま。 【語源・由来】 「喋喋」は口数多くしきりにしゃべるさま。「喃喃」は小声でささやくさま。 【...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 彫虫篆刻 【読み方】 ちょうちゅうてんこく 【意味】 取るに足りない小細工。虫の形や複雑な篆書の字を細かく刻みつけるように、文章を作るのに字句を美しく飾りたてること。 【語源・由来】 「彫」と「刻」はともに...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 冢中枯骨 【読み方】 ちょうちゅう(の)ここつ 【意味】 無能でとりえのない人のたとえ。 【語源・由来】 「冢」は墓のことで、墓の中の白骨のこと。 【典拠・出典】 『三国志』「蜀志・先主伝」 冢中枯骨(ちょ...
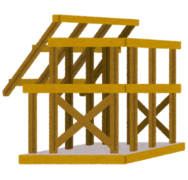 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝穿暮塞 【読み方】 ちょうせんぼそく 【意味】 建築・造営が頻繁であることのたとえ。 【語源・由来】 朝あなをあけたと思えば、その日の夕方にはもうふさぐこと。 【典拠・出典】 『南斉書』「東昏侯紀」 【類...
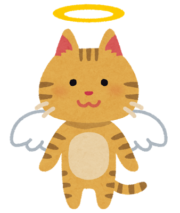 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝生暮死 【読み方】 ちょうせいぼし 【意味】 極めて短命なことのたとえ。朝生まれて夕方には死ぬという意味。 【語源・由来】 かげろうの類など生命の短いものを言った語。 【典拠・出典】 『爾雅』「釈虫・注」...
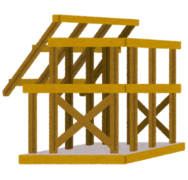 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝成暮毀 【読み方】 ちょうせいぼき 【意味】 建物の造営が盛んなことのたとえ。 【語源・由来】 朝に完成して夕べには壊すという意味。「毀」はこぼつ、こわすという意味。 【典拠・出典】 『宋書』「少帝紀」 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝齏暮塩 【読み方】 ちょうせいぼえん 【意味】 極貧のたとえ。 【語源・由来】 朝に塩づけの野菜を食べ、晩に塩をなめるような生活のこと。赤貧。「齏」はなます・あえもの・つけ物・粗食。 【典拠・出典】 韓愈...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長生不死 【読み方】 ちょうせいふし 【意味】 長生きして死なない。長生きして衰えない。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・長生不老(ちょうせいふろう) ・不老長生(ふろうちょうせい) ・不老長寿(ふろうち...
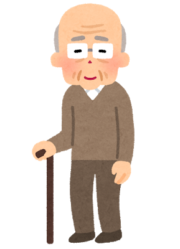 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長生久視 【読み方】 ちょうせいきゅうし 【意味】 長生きをすること。 【語源・由来】 「長生」は長生きをする、長命という意味。「久視」は永遠の生命を保つことで、「視」は「活」という意味。 【典拠・出典】 ...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 朝秦暮楚 【読み方】 ちょうしんぼそ 【意味】 住所が定まらず放浪することのたとえ。また、節操なく主義主張が常に変わるたとえ。 【語源・由来】 朝、秦国にいたと思うと、夕方には楚の国にいるという意味。 【典...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝真暮偽 【読み方】 ちょうしんぼぎ 【意味】 真偽の定めがたいたとえ。 【語源・由来】 朝方と夕方で真実と虚偽がくるくるかわるという意味。本来は白居易が道理をわきまえず節操なく変節する人々を風刺した言葉。...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝種暮穫 【読み方】 ちょうしゅぼかく 【意味】 朝植えて暮れには収穫すること。方針が一定しないこと。 【典拠・出典】 『漢書』「郊祀志」 朝種暮穫(ちょうしゅぼかく)の使い方 朝種暮穫(ちょうしゅぼかく)...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長袖善舞 【読み方】 ちょうしゅうぜんぶ 【意味】 事前に周到な準備がしてあれば事は成功しやすいということ。条件が整い拠り所があれば何事も成功しやすいこと。 【語源・由来】 長い袖の衣をまとっている人のほう...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 兆載永劫 【読み方】 ちょうさいようごう 【意味】 きわめて長い年月のこと。 【語源・由来】 「兆載」は兆であっても数えるほどの年月。「永劫」は長く久しい時。仏教の語。 【典拠・出典】 『無量寿経』「上」 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長江天塹 【読み方】 ちょうこうてんざん 【意味】 長江は天然の塹壕だということ。 【語源・由来】 「長江」は揚子江のこと。「塹」は城の周りの堀で、「天塹」は敵の攻撃を防ぐ、天然自然の堀のこと。 【典拠・出...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 懲羮吹膾 【読み方】 ちょうこうすいかい 【意味】 一度失敗したことに懲りて、必要以上に用心になりすぎること。 【語源・由来】 「羹」は肉・野菜などを熱く煮た汁(あつもの)。「膾」は生肉の冷たいあえもの(な...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝憲紊乱 【読み方】 ちょうけんびんらん 【意味】 国家のおきてが乱れること。 【語源・由来】 「朝憲」は国家が定めた法律や規則のこと。「紊乱」は道徳や秩序が乱れるという意味。 【典拠・出典】 - 朝憲紊乱...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 重見天日 【読み方】 ちょうけんてんじつ 【意味】 暗く苦しい状況から解放されて、以前の明るい状態に戻ること。 【語源・由来】 「重見」は重ねて見る、再び見ること。「天日」は太陽のこと。 【典拠・出典】 -...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 重熙累洽 【読み方】 ちょうきるいこう 【意味】 光明を重ねて広く恩恵が行きわたること。代々の天子が賢明で、太平が長く続くこと。 【語源・由来】 「重熙」は光明を重ねること。「洽」天子の徳があまねく行きわた...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 張冠李戴 【読み方】 ちょうかんりたい 【意味】 名と実が一致しないこと。 【語源・由来】 張さんのかんむりを李さんがかぶること。 【典拠・出典】 『留青日札』「張公帽賦」 張冠李戴(ちょうかんりたい)の使...
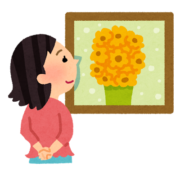 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 朝観夕覧 【読み方】 ちょうかんせきらん 【意味】 朝に見て夕べにも見る。朝な夕なに見る。 【語源由来】 書画などを愛玩すること。 【典拠・出典】 『歴代名画記』 朝観夕覧(ちょうかんせきらん)の使い方 朝...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 朝歌夜弦 【読み方】 ちょうかやげん 【意味】 朝から晩まで一日中遊楽に明け暮れること。朝はうたい、夜は音楽を奏すること。 【典拠・出典】 『杜牧』「阿房宮賦」 朝歌夜弦(ちょうかやげん)の使い方 朝歌夜弦...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝過夕改 【読み方】 ちょうかせきかい 【意味】 過ちを犯せばすぐに改めるたとえ。 【語源・由来】 朝方あやまちを犯せば夕べには改めるという意味。君子の態度をいう。 【典拠・出典】 『漢書』「翟方進伝」 朝...
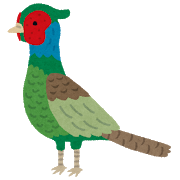 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥革翬飛 【読み方】 ちょうかくきひ 【意味】 家の造りが美しくて立派なこと。 【語源・由来】 「革」は翼、「翬」は雉のこと。鳥が翼をひろげ、美しい雉が飛ぶさま。宮殿の美しく立派なさまを例えた語。 【典拠・...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝改暮変 【読み方】 ちょうかいぼへん 【意味】 命令や法令がすぐに変わって定まらないこと。 【語源・由来】 朝に命令を出して、夕方にはもう変更するという意味。 【典拠・出典】 『漢書』「食貨志」 【類義語...
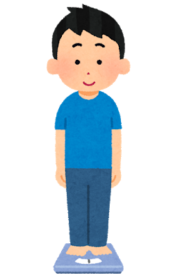 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 張王李趙 【読み方】 ちょうおうりちょう 【意味】 これといって取り柄のない平凡な人のこと。 【語源・由来】 張・王・李・趙はいずれも中国の姓のうち最もありふれたものであるということから。 【典拠・出典】 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝盈夕虚 【読み方】 ちょうえいせききょ 【意味】 人生のはかないことのたとえ。 【語源・由来】 朝に栄え夕べに滅びるという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・朝栄夕滅(ちょうえいせきめつ) ・諸行無...
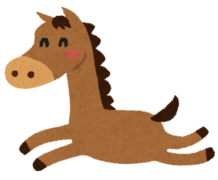 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 超軼絶塵 【読み方】 ちょういつぜつじん 【意味】 非常に軽やかに速く走ること。 【語源・由来】 「絶塵」は塵ひとつ立てずに、きわめて速く走るという意味。馬などが疾駆するさまをいう。 【典拠・出典】 『荘子...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝衣朝冠 【読み方】 ちょういちょうかん 【意味】 朝廷に出仕するときに着る制服やかんむり。正装。礼装。 【典拠・出典】 『孟子』「公孫丑・上」 朝衣朝冠(ちょういちょうかん)の使い方 朝衣朝冠(ちょういち...
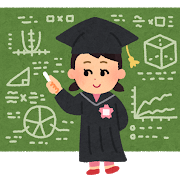 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 長安日辺 【読み方】 ちょうあんにっぺん 【意味】 遠く離れた地のこと。また、才知に富んでいること。 【語源・由来】 「長安」は地名で、中国王朝の都。「日辺」は太陽が輝く辺りという意味から、太陽のこと。 中...
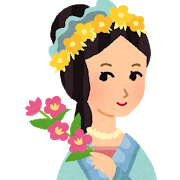 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 寵愛一身 【読み方】 ちょうあいいっしん 【意味】 多くの人の中から特別に目をかけられ、愛情を一人占めにすること。 【語源・由来】 「後宮の佳麗三千人、三千の寵愛一身に在り」による。 【典拠・出典】 白居易...
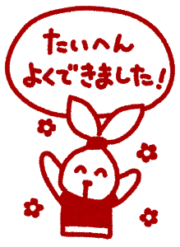 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 黜陟幽明 【読み方】 ちゅっちょくゆうめい 【意味】 正しい基準に従って人材を評価すること。 【語源・由来】 「黜陟」は退けることと官位を引きあげること。「幽明」は暗愚と賢明という意味。暗愚なものを退け、賢...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 仲連蹈海 【読み方】 ちゅうれんとうかい 【意味】 節操が清く高いたとえ。 【語源・由来】 「仲連」は中国、戦国時代の斉の人。清廉で拘束を好まない性質で仕官しなかった。「蹈海」は海に身を投げて死ぬこと。「蹈...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中流砥柱 【読み方】 ちゅうりゅうのしちゅう 【意味】 困難にあってもびくともせず、節義を曲げない人物のたとえ。 【語源・由来】 黄河の中に立って少しも動かない砥柱山。「中流」は川の流れの中ほど。「砥柱」は...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠勇義烈 【読み方】 ちゅうゆうぎれつ 【意味】 忠義で勇気があり、正義感が強くはげしいこと。 【典拠・出典】 - 忠勇義烈(ちゅうゆうぎれつ)の使い方 忠勇義烈(ちゅうゆうぎれつ)の例文 父さんは忠勇義烈...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 綢繆未雨 【読み方】 ちゅうびゅうみう 【意味】 前もって準備をしてわざわいを防ぐこと。 【語源・由来】 「綢繆」は固めふさぐ、つくろうこと。「未雨」はまだ雨が降らないうちにという意味。雨が降る前に巣の透き...
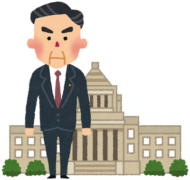 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中通外直 【読み方】 ちゅうつうがいちょく 【意味】 君子の心と行動が広く正しいことのたとえ。 【語源・由来】 「中通」は蓮の茎が空洞であることから、君子の心中に邪心のないたとえ。「外直」は蓮の茎の外形がま...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 躊躇逡巡 【読み方】 ちゅうちょしゅんじゅん 【意味】 ためらって進まないこと。 【語源・由来】 「躊躇」はためらう、ぐずぐずするという意味。「逡巡」はあとずさりする、ぐずぐずするという意味。ほぼ同意の熟語...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 昼想夜夢 【読み方】 ちゅうそうやむ 【意味】 目が覚めている昼に思ったことを、夜に寝て夢見ること。 【典拠・出典】 『列子』「周穆王」 昼想夜夢(ちゅうそうやむ)の使い方 昼想夜夢(ちゅうそうやむ)の例文...
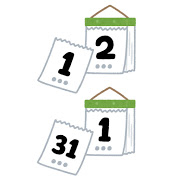 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 疇昔之夜 【読み方】 ちゅうせきのよ 【意味】 昨夜。ゆうべ。 【語源・由来】 「疇昔」はきのう・昨日・ゆうべ・むかし。 【典拠・出典】 『礼記』「檀弓・上」 疇昔之夜(ちゅうせきのよ)の使い方 疇昔之夜(...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 誅心之法 【読み方】 ちゅうしんのほう 【意味】 実際の行為として現れなくても、心の中が正しくなければ、それを処罰する筆法。 【語源・由来】 「誅心」は心の不純を罰すること。『春秋』はこうした筆法を用いてい...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 抽薪止沸 【読み方】 ちゅうしんしふつ 【意味】 わざわいなどの問題を根本から解決すること。 【語源・由来】 燃えているたきぎを竈から引き抜いて煮えたぎった湯をさますという意味。「抽」は抜き取ること。「沸」...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中秋名月 【読み方】 ちゅうしゅうのめいげつ 【意味】 陰暦八月十五日の夜の月。 【語源・由来】 「中秋」は陰暦八日の異称。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・中秋玩月(ちゅうしゅうがんげつ) 中秋名月(ち...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中秋玩月 【読み方】 ちゅうしゅうがんげつ 【意味】 仲秋の夜に雅な月見の宴会を催すこと。 【語源・由来】 「中秋」は仲秋に同じで陰暦八月の称。また狭義として八月十五日のこと。「玩月」は月をめでること。 【...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鋳山煮海 【読み方】 ちゅうさんしゃかい 【意味】 財を多く蓄えること。 【語源・由来】 「鋳山」は山の銅を採ってそれを溶かし、型に流しこんで銭を作ること。「煮海」は海水を煮て塩を造るという意味。 【典拠・...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠魂義胆 【読み方】 ちゅうこんぎたん 【意味】 忠義にあふれた心のこと。 【語源・由来】 「忠魂」は忠義のために死んだ人の魂。「義胆」は正義に強い心。 【典拠・出典】 滝沢馬琴「八犬士伝序」 忠魂義胆(ち...
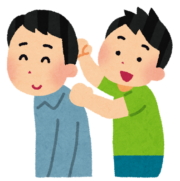 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠孝両全 【読み方】 ちゅうこうりょうぜん 【意味】 君主に対する忠義と両親に対する孝行を二つとも全うすること。忠義と孝行は一致するもので両方同時に全うできるという考え。これとは逆に「忠ならんと欲すれば孝な...
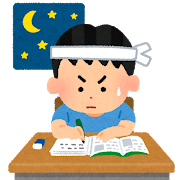 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 昼耕夜誦 【読み方】 ちゅうこうやしょう 【意味】 貧乏な生活のなかで勉学に励むこと。 【語源・由来】 「誦」はそらんじること。昼間は畑を耕して仕事をし、夜になってから書物をそらんじて勉強をするという意味か...
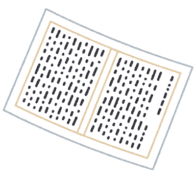 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 抽黄対白 【読み方】 ちゅうこうたいはく 【意味】 黄色や白色の美しい色を適切に配合する。巧みに四六駢儷文を作ること。 【語源・由来】 四六駢儷文は四字句と六字句を基本として対句など修辞を多用した美しい文。...
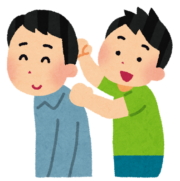 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠孝一致 【読み方】 ちゅうこういっち 【意味】 忠義と孝行はともに全うすることができること。また、天皇は日本国民という一大家族の家長であるという立場から、主君に忠節をつくすことと、親に孝行をつくすことが一...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中原之鹿 【読み方】 ちゅうげんのしか 【意味】 群雄が割拠して天子の位を争いあうこと。また、ある地位をねらって競争する意味にも用いる。 【語源・由来】 「中原」は当時の中国の中央であった黄河中流をさす。「...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中原逐鹿 【読み方】 ちゅうげんちくろく 【意味】 群雄が割拠して天子の位を争いあうこと。また、ある地位をねらって競争するという意味にも用いる。 【語源・由来】 「中原」は中国の中央であった黄河流域を指す。...
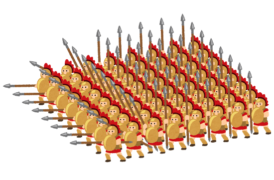 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 中権後勁 【読み方】 ちゅうけんこうけい 【意味】 戦略・陳容ともに整っていること。 【語源・由来】 「権」ははかりごとという意味で、「中権」は中央の軍に将軍がいて計略をめぐらすこと。「勁」は強いという意味...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠言逆耳 【読み方】 ちゅうげんぎゃくじ 【意味】 忠告は聞きにくいものだが、自分にとって真にためになるものだということ。 【語源・由来】 「逆耳」は聞きづらいこと。人からの忠告はとかく聞きにくいものだが、...
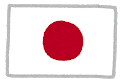 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠君愛国 【読み方】 ちゅうくんあいこく 【意味】 君に忠節をつくし、国を愛すること。 【典拠・出典】 陳傅良 忠君愛国(ちゅうくんあいこく)の使い方 忠君愛国(ちゅうくんあいこく)の例文 忠君愛国の精神が...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 着眼大局 【読み方】 ちゃくがんたいきょく 【意味】 ものごとを全体として大きくとらえること。 【語源・由来】 「大局」は小さな区切り(局)の全体。物事の細部にとらわれず、全体の姿を見て判断し対処するという...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 遅暮之嘆 【読み方】 ちぼのたん 【意味】 しだいに年をとっていくわが身を嘆くこと。 【語源・由来】 「遅暮」はだんだんと年をとること。 【典拠・出典】 『楚辞』「離騒」 遅暮之嘆(ちぼのたん)の使い方 遅...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 智謀浅短 【読み方】 ちぼうせんたん 【意味】 知恵や計画があさはかなこと。短慮なこと。 【語源・由来】 「智謀」は知恵のあるはかりごと。また知恵や計画。「浅短」は浅はかなこと、思慮が足りないこと。 【典拠...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 地平天成 【読み方】 ちへいてんせい 【意味】 世の中が平等で、万物が栄えること。また、地変や天災がなく、自然界が穏やかなこと。 【語源・由来】 「地平」は地変がなく世の中が平穏に治まること、「天成」は天の...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 蟄居屏息 【読み方】 ちっきょへいそく 【意味】 江戸時代、公家・武士に科した刑の一つ。家にこもって外出せず、息を殺して、おそれつつしむこと。 【語源・由来】 「蟄居」は家の中にとじこもっていること、隠れて...
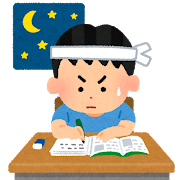 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 致知格物 【読み方】 ちちかくぶつ 【意味】 物事の本質をつきつめて理解し、知識を深めること。 【語源・由来】 「格」は至るという意味。「格物」は物事を究極までつきつめること。「致知」は知識を最高にまで深め...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知足不辱 【読み方】 ちそくふじょく 【意味】 節度を超えた欲望をもつことを戒めたもの。 【語源・由来】 分に安んじて満足することを知ればはずかしめを受けることもない。 【典拠・出典】 『老子』「四四章」 ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知足安分 【読み方】 ちそくあんぶん 【意味】 高望みをしないこと。自分の身分や境遇に応じ、分をこえて多くは望まないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・安分守己(あんぶんしゅき) ・一枝巣林(いっしそ...
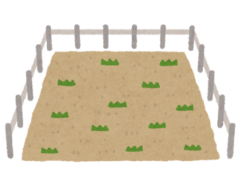 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 置錐之地 【読み方】 ちすいのち 【意味】 とがった錐の先をやっと突き立てることができるほどの狭い土地。わずかな空間。 【典拠・出典】 『荘子』「盗跖」 【類義語】 ・立錐之地(りっすいのち) ・立錐之土(...
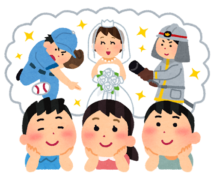 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知小謀大 【読み方】 ちしょうぼうだい 【意味】 力もないのに大きなことを企てること。 【語源・由来】 知力がないのにはかりごとだけは大きいという意味から。 【典拠・出典】 『易経』「繋辞・下」 知小謀大(...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 置酒高会 【読み方】 ちしゅこうかい 【意味】 盛大に酒宴を催すこと。 【語源・由来】 「置酒」は酒宴を設ける、酒盛りをするという意味。「高会」は盛大な宴会のこと。 【典拠・出典】 『漢書』「高帝紀」 置酒...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知者楽水 【読み方】 ちしゃらくすい 【意味】 知恵のある人は、知が滞ることなく自由に働き、そのさまが水に似ているので、水を好んで楽しむということ。 【典拠・出典】 『論語』「雍也」 【類義語】 ・仁者楽山...
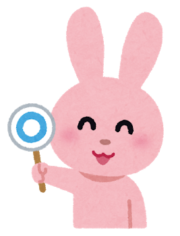 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知者不惑 【読み方】 ちしゃふわく 【意味】 本当に賢い人は、物事の道理をわきまえているので、判断を誤り迷うことはないということ。 【典拠・出典】 『論語』「子罕」 【類義語】 ・狐疑逡巡(こぎしゅんじゅん...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知者不言 【読み方】 ちしゃふげん 【意味】 物事をほんとうに知っているものは言わないものだ。真に知るものはあえて言葉で説明しようとはしないものだ。 【典拠・出典】 『老子』「五六章」 【類義語】 ・大智不...
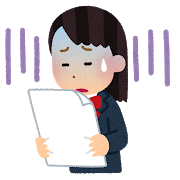 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 智者一失 【読み方】 ちしゃのいっしつ 【意味】 どんなに知恵がある人でも、時には過失があるということ。 【語源・由来】 「智者」は知恵のある人・賢者のこと。「一失」は千に一つの過失という意味。 【典拠・出...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 竹林七賢 【読み方】 ちくりんしちけん 【意味】 竹林で清談をかわした七人の隠者。 【語源・由来】 乱世のなか俗世間を避けて竹林で老子や荘子の思想を慕い、酒をくみかわし清談(俗世を離れた高尚な論談)を楽しん...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 竹苞松茂 【読み方】 ちくほうしょうも 【意味】 新築家屋の落成を祝う語。 【語源・由来】 「竹苞」は竹が叢り生えているように堅固なことで、家の下部構造をほめる語。「松茂」は松が青々と茂っているようにみごと...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 竹頭木屑 【読み方】 ちくとうぼくせつ 【意味】 役に立たないもののたとえ。また、細かなもの、つまらないものでも役立つことがあるのでおろそかにしないこと。 【語源・由来】 「竹頭」は竹の切れはし。「木屑」は...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 築室道謀 【読み方】 ちくしつどうぼう 【意味】 意見ばかり多くてまとまらず、物事が実現しないこと。 【語源・由来】 「築室」は家を建てること。「道謀」は道を行く人に相談するという意味。家を建てようとして道...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知己朋友 【読み方】 ちきほうゆう 【意味】 交際のある友人のすべてのこと。 【語源・由来】 「知己」は自分の真価をよく知ってくれる人という意味で、親しい友人をいう。「朋友」は友人・友だちのこと。 【典拠・...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 地角天涯 【読み方】 ちかくてんがい 【意味】 きわめて遠く離れていることのたとえ。またはるかに遠く辺鄙な場所のたとえ。天の果てと地のすみ。 【典拠・出典】 徐陵「武皇帝作相時与嶺南酋豪書」 【類義語】 ・...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 徴羽之操 【読み方】 ちうのそう 【意味】 正しい音楽のこと。 【語源・由来】 「徴羽」は五音(音楽の五つの音色、宮・商・角・徴・羽)の徴と羽。「操」はあやつる、うまくつかうという意味。 【典拠・出典】 『...
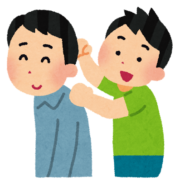 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 忠孝仁義 【読み方】 ちゅうこうじんぎ 【意味】 主君に対する忠義と親孝行、思いやりと正義のこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・忠君愛国(ちゅうくんあいこく) ・仁義忠孝(じんぎちゅうこう) 忠孝仁義...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 知崇礼卑 【読み方】 ちすうれいひ 【意味】 真の知者は知識が増せば増すほど、へりくだって礼を尽くすものだということ。 【語源・由来】 「崇」は積む。高くなること。「卑」はへりくだる。低くすること。 【典拠...
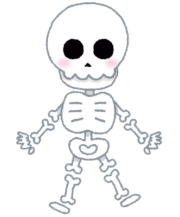 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 彫心鏤骨 【読み方】 ちょうしんるこつ 【意味】 身を削るような苦労をすること。苦心して詩文をつくること。 【語源・由来】 「鏤」は彫りつける、ちりばめるという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・苦心...
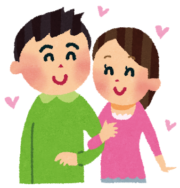 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 朝雲暮雨 【読み方】 ちょううんぼう 【意味】 男女の情愛のこと。 【語源・由来】 中国の楚の壊王が高唐に遊び昼寝をしていたとき、その夢の中で巫山の神女と情を交わし、別れるとき神女が「朝には雲となり夕には雨...
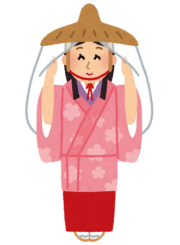 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 沈魚落雁 【読み方】 ちんぎょらくがん 【意味】 魚や雁も恥じらって、身を隠すほどの美人。 【語源・由来】 たとえ絶世の美女ともてはやされても、魚や鳥から見ればただの人にすぎず、恐れて逃げるだけだ、という意...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 池魚之禍 【読み方】 ちぎょのわざわい 【意味】 なんの関わりも無いのに、とんだ災難に巻き込まれること。また、巻き添えで無実の罪に問われること。 【語源・由来】 池に投げ込まれた宝玉を探すため、池の水をさら...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 池魚故淵 【読み方】 ちぎょこえん 【意味】 故郷を懐かしく思うこと。 【語源・由来】 池の魚は生まれた池を懐かしく思うということから。 【典拠・出典】 陶潜「帰園田居」 【類義語】 ・羈鳥旧林(きちょうき...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥尽弓蔵 【読み方】 ちょうじんきゅうぞう 【意味】 目的が達せられた後には、それまで重用されていた者が捨てられるということのたとえ。 【語源・由来】 鳥を射尽くしてしまうと、不必要となった弓がしまわれてし...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳥語花香 【読み方】 ちょうごかこう 【意味】 春ののどかな情景、風物のこと。 【語源・由来】 鳥の鳴き声と花の香りの意から。 【典拠・出典】 呂本中「庵居」 【類義語】 ・桃紅柳緑(とうこうりゅうりょく)...
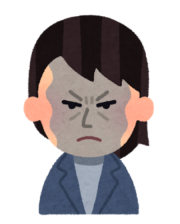 「ずる賢い」の四字熟語一覧
「ずる賢い」の四字熟語一覧【四字熟語】 長頸烏喙 【読み方】 ちょうけいうかい 【意味】 首が長く口がとがっていること。 【語源・由来】 「烏」はカラス。このような人相をした人物はカラスのように強欲・陰険で、苦労を共にすることはできても安楽を共に...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 池魚籠鳥 【読み方】 ちぎょろうちょう 【意味】 不自由な身の上、生活のこと。また、宮仕えのこと。 【語源・由来】 池の魚や籠かごの中の鳥が束縛されて不自由であることから。 「池魚」は池の中の魚。「籠鳥」は...
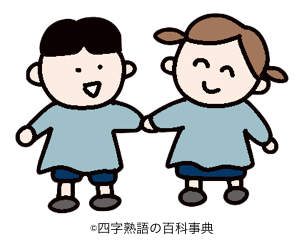 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語【四字熟語】 竹馬之友 【読み方】 ちくばのとも 【意味】 幼友達のこと。幼いころ竹馬に乗って、一緒に遊んだ友達の意。 【語源・由来】 中国晋の桓温は殷浩と並び称されることが不満で、少年のときに自分が捨てた竹馬を殷浩が拾...
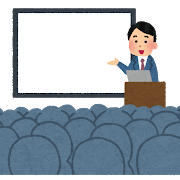 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 知行合一 【読み方】 ちこうごういつ 【意味】 知識と行為は一体であるということ。本当の知は実践を伴わなければならないということ。 【語源・由来】 中国明の時代、儒学者王陽明が、朱子学の大成者朱熹の先知後行...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語沈黙寡言の意味(類義語・対義語) 【四字熟語】 沈黙寡言 【読み方】 ちんもくかげん 【意味】 無口なこと。落ち着いていて言葉数が少ないこと。「寡」は少ない意。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・寡言沈黙(かげんちんもく...
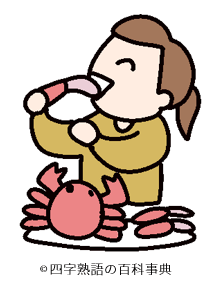 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語珍味佳肴の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 珍味佳肴 【読み方】 ちんみかこう 【意味】 めったに食べられない、たいへんおいしいごちそう。 【語源・由来】 「珍味」は珍しくおいしい食べ物、「佳肴」はうまいさかなの意...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語昼夜兼行の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 昼夜兼行 【読み方】 ちゅうやけんこう 【意味】 昼夜をわかたずに仕事をすること。また、昼も夜も休まず道を急行すること。 【語源・由来】 「昼夜」は昼と夜。一日中。...
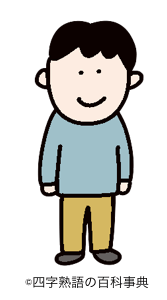 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語中肉中背の意味 【四字熟語】 中肉中背 【読み方】 ちゅうにくちゅうぜい 【意味】 太ってもいず、やせてもいず、背は高くもなく低くもない、バランスのとれた平均的な体格のこと。 【典拠・出典】 - 中肉中背(ちゅうにくちゅ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語中途半端の意味(語源由来) 【四字熟語】 中途半端 【読み方】 ちゅうとはんぱ 【意味】 物事が不完全で未完成なさま。どっちつかずで徹底しないこと。 【語源・由来】 「中途」は、道や物事の進行の中ほど。「半端」は、どっち...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語知勇兼備の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 知勇兼備 【読み方】 ちゆうけんび 【意味】 知恵も勇気も兼ね備えていること。 【語源・由来】 元は中国の趙の藺相如を褒め称えた言葉。 【典拠・出典】 『史記』「藺...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語魑魅魍魎の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 魑魅魍魎 【読み方】 ちみもうりょう 【意味】 様々な化け物。転じて、悪いことをたくらむ人物の例え。 【語源・由来】 「魑魅」は山林の精気から生じるとされる化け物。...
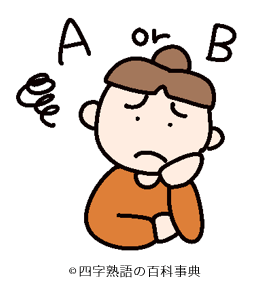 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語遅疑逡巡の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 遅疑逡巡 【読み方】 ちぎしゅんじゅん 【意味】 いつまでも疑い迷って、決断せずにためらうこと。 【語源・由来】 「遅疑」はいつまでも疑って決心できないこと。「逡巡」はた...
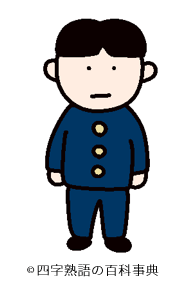 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語張三李四の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 張三李四 【読み方】 ちょうさんりし 【意味】 ありふれた平凡な人のたとえ。 どこにでもいるような普通の人のこと。 一般大衆。 ありふれていてつまらないもののこと...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語長者三代の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 長者三代 【読み方】 ちょうじゃさんだい 【意味】 金持ちの家は三代までで、その後は続かないということ。 長者の家は三代よりは続かないということ。 【語源・由来】 祖父が...
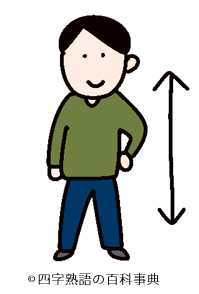 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語長身痩躯の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 長身痩躯 【読み方】 ちょうしんそうく 【意味】 身長が高く、痩せた体つきをしている男性のこと。 背丈が高く痩せた体。 【語源・由来】 「長身」は、背が高...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語丁丁発止の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 丁丁発止 【読み方】 ちょうちょうはっし 【意味】 激しく議論し合うさま。 剣や刀で音や火花を散らして激しく打ち合うような、激しく議論などを戦わせる様子。 【語源...
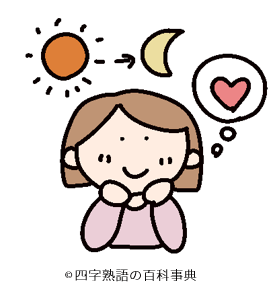 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧朝朝暮暮の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 朝朝暮暮 【読み方】 ちょうちょうぼぼ 【意味】 毎朝毎晩。いつも。 【語源・由来】 「朝朝」は毎朝、朝な朝なの意味で、「暮暮」は毎夕、夕な夕なの意味です。...
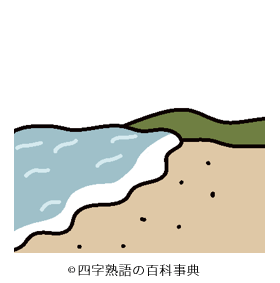 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語長汀曲浦の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 長汀曲浦 【読み方】 ちょうていきょくほ 【意味】 長く続く海岸。 曲がりくねりながらずっと続いている海辺や海岸線のこと。 【語源・由来】 「汀」はなぎさ・みぎわの意味で...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語跳梁跋扈の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 跳梁跋扈 【読み方】 ちょうりょうばっこ 【意味】 悪人などがはびこり、我がもの顔に振る舞うこと。 世間から疎まれるような人たちが好き勝手に振舞い、横暴な態度をと...
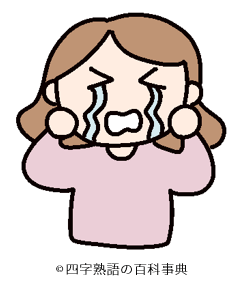 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語直情径行の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 直情径行 【読み方】 ちょくじょうけいこう 【意味】 周りの事などおかまいなしに、自分の感情のおもむくままに行動すること。 相手の気持ちや周りの状況...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語沈着冷静の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 沈着冷静 【読み方】 ちんちゃくれいせい 【意味】 冷静で落ち着いているさま。 何事にも落ち着いて、物事に動じないこと。 【語源・由来】 「沈着」は驚いたり取り乱...
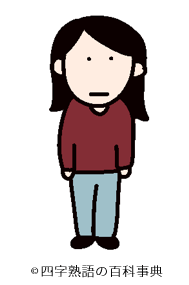 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語直立不動の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 直立不動 【読み方】 ちょくりつふどう 【意味】 ・真っすぐ立って、少しも身動きしないこと ・かかとをそろえてまっすぐに立ち、じっとして動かないこと。 【語源由来】 「直...
 「じっくり考える」の四字熟語一覧
「じっくり考える」の四字熟語一覧沈思黙考の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 沈思黙考 【読み方】 ちんしもっこう 【意味】 沈黙して深く考えること。 【語源・由来】 「沈思」は、深く考え込むこと。いろいろと思案すること。 「黙考」は、黙っ...
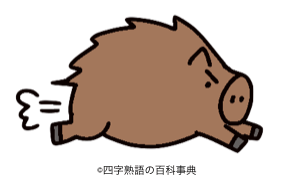 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語猪突猛進の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 猪突猛進 【読み方】 ちょとつもうしん 【意味】 周囲の人のことや状況を考えずに、一つのことに向かって猛烈な勢いで突き進むこと。 【語源・由来】 「猪突」は、イノ...
 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語朝令暮改の意味(出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 朝令暮改 【読み方】 ちょうれいぼかい 【意味】 朝に出した命令を夕方にはもう改めること。方針などが絶えず変わって定まらないこと。 【典拠・出典】 『漢書』「食貨志」...
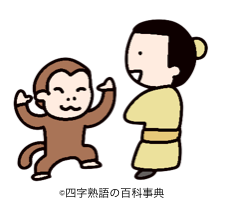 「ち」で始まる四字熟語
「ち」で始まる四字熟語朝三暮四(ちょうさんぼし)の意味とは?(出典・類義語) 【四字熟語】 朝三暮四 【読み方】 ちょうさんぼし 【意味】 目の前の違いに心を奪われて、結果が同じになることに気がつかないこと。また、ことば巧みに人をだますこと。...