富貴福禄【ふうきふくろく】の意味と使い方や例文(語源由来・類義語)
【四字熟語】 富貴福禄 【読み方】 ふうきふくろく 【意味】 富や身分。幸福。 【語源・由来】 「富貴」は、富と身分。「福禄」は、幸福。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・栄耀栄華(えいようえいが) ・富貴栄華(ふうきえ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴福禄 【読み方】 ふうきふくろく 【意味】 富や身分。幸福。 【語源・由来】 「富貴」は、富と身分。「福禄」は、幸福。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・栄耀栄華(えいようえいが) ・富貴栄華(ふうきえ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風贅露宿 【読み方】 ふうさんろしゅく 【意味】 風を食し露に寝るの意で、野宿すること。露営。 【語源・由来】 「露宿」は、屋外に寝ること。野宿。露臥。露次。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・風餐雨臥(ふ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風清弊絶 【読み方】 ふうせいへいぜつ 【意味】 風習がよくなって、悪事や弊害がなくなること。 【語源・由来】 「風清」は風習がよくなること。「風」は社会の気風・習俗。「弊」は悪事・害になるようなこと。「絶...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風前之灯 【読み方】 ぶうぜんのともしび 【意味】 身の危険が眼前に迫って、落命の危機にさらされているたとえ。また、人の命や物事のはかないことのたとえ。 【語源・由来】 風にさらされ消え入りそうな灯火の意か...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不羈自由 【読み方】 ぶきじゆう 【意味】 何の束縛もなく、自分の意志によって行動できること。 【語源・由来】 「不羈」は、独莫されないこと。「羈」は、つなぐ。束縛する。「自由」は、自分の意志によって行動す...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不屈不撓 【読み方】 ふくつふとう 【意味】 決してくじけないこと。 【語源・由来】 「不屈」「不撓」ともに、くじけないこと。「撓」は、くじける。 【典拠・出典】 『漢書』「叙伝」 【類義語】 ・独立不撓(...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 無事安穏 【読み方】 ぶじあんのん 【意味】 これといった事件もなく、世の中や暮らしが穏やかで安らかなさま。 【語源・由来】 「安穏」は、異変がなく穏やかなこと。「無事」は、心配事がないこと。 【典拠・出典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮声切響 【読み方】 ふせいせっきょう 【意味】 軽い音声と重々しい響き。声・響き・リズムの軽重や高下をいう。また、古い漢語の平声と仄声のこと。 【語源・由来】 「浮声」は軽やかに浮き上がった声。「切響」は...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不昧不落 【読み方】 ふまいふらく 【意味】 物欲に惑わされたり、品性が落ちたりしないこと。 【語源・由来】 「不昧」は、物欲に惑わされないこと。「不落」は、堕落しないこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 風狂無頼 【読み方】 ふうきょうぶらい 【意味】 常軌を逸し、無法な行いをしながら、芸術や哲学など風雅に徹すること。 【語源・由来】 「風狂」は、風雅に徹すること。常軌を逸していること。また、その人。「無頼...
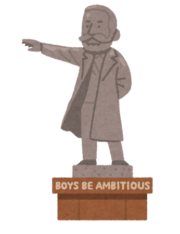 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雲之志 【読み方】 ふううんのこころざし 【意味】 風雲に乗じて大事をなそうとする志。 【語源・由来】 「風雲」は、龍が風と雲とを得て天に昇るように、英雄豪傑などが世に頭角を表す好い機会。また、世が大きく...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文武兼備 【読み方】 ぶんぶけんび 【意味】 学問と武術の両方の能力を兼ね備えていること。 【語源・由来】 「文武」は、学問と武術。「兼備」は、兼ね備えていること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・好学尚...
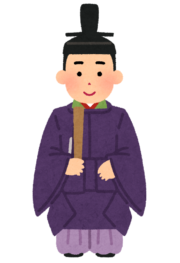 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 分憂之寄 【読み方】 ぶんゆうのき 【意味】 国司(諸国におかれた地方官)のこと。 【語源・由来】 「分憂」は憂えを分かつ、共に憂えること。「寄」はつとめ・任務のこと。民衆と憂えを分かつ任務という意味から。...
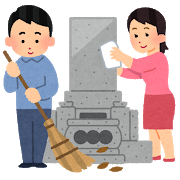 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 墳墓之地 【読み方】 ふんぼのち 【意味】 生まれ故郷のこと。 【語源・由来】 「墳墓」は墓のこと。先祖代々の墓のある土地という意味から、転じて故郷のことをいう。また、一生そこで暮らそうと心に決めている土地...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 分崩離析 【読み方】 ぶんぽうりせき 【意味】 組織がちりぢりばらばらにくずれること。 【語源・由来】 「分崩」はばらばらにくずれること。「離析」ははなれ別れる、ばらばらになる、分裂するという意味。国が治ま...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蚊虻之労 【読み方】 ぶんぼうのろう 【意味】 取るに足りない技能のこと。 【語源・由来】 「蚊虻」は虫の蚊と虻のことで、つまらないことのたとえ。「労」は労力のこと。蚊や虻の労力という意味で、些細な技能をい...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蚊虻走牛 【読み方】 ぶんぼうそうぎゅう 【意味】 小さなものが強大なものを制すること。また、ささいなことが原因となって大事件や災難を引きおこすこと。 【語源・由来】 「蚊虻」は蚊と虻のこと。「走」は逃げる...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 聞風喪胆 【読み方】 ぶんぷうそうたん 【意味】 うわさや評判を聞いて驚きびっくりすること。 【語源・由来】 「聞風」はうわさを耳にすることで、風聞と同じ意味。「喪胆」は胆をつぶす。びっくりすること。どこか...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文武一途 【読み方】 ぶんぶいっと 【意味】 文官と武官の区別がないこと。 【語源・由来】 「文武」は文の道と武の道のこと。「一途」は同じ道のこと。 【典拠・出典】 - 文武一途(ぶんぶいっと)の使い方 文...
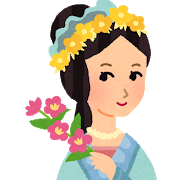 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉白黛墨 【読み方】 ふんぱくたいぼく 【意味】 美人のこと。 【語源・由来】 「粉白墨黒」とあるのにもとづく。「粉白」はおしろい、「黛墨」は眉ずみのこと。おしろいをつけて顔を白くし、眉ずみをつけて黒く整っ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文恬武嬉 【読み方】 ぶんてんぶき 【意味】 天下太平なこと。 【語源・由来】 「恬」は安らかなことで、文官も武官も心安らかに世の平和を楽しむこと。 【典拠・出典】 韓愈「平淮西碑」 文恬武嬉(ぶんてんぶき...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文人墨客 【読み方】 ぶんじんぼっかく 【意味】 詩文や書画などの優雅なものに携わること。 【語源・由来】 「文人」は詩や文章を書く人。「墨客」は書画にすぐれた人、書家や画家のこと。 【典拠・出典】 - 【...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 焚書坑儒 【読み方】 ふんしょこうじゅ 【意味】 思想・学問・言論を弾圧すること。 【語源・由来】 「焚書」は書物を焼き捨てること。「坑」は穴埋めにすること。「儒」は儒者のこと。 書物を焼き捨て、儒学者を生...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉飾決算 【読み方】 ふんしょくけっさん 【意味】 会社が経営内容を実際よりもよく見せるために、損益計算などの数字を過大もしくは過少表示して決算すること。 【語源・由来】 「粉飾」は、よく見せようとして、う...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文章絶唱 【読み方】 ぶんしょうのぜっしょう 【意味】 きわめてすぐれた文章、詩歌のこと。 【語源・由来】 「絶唱」は、このうえなくすぐれた詩歌の意。 【典拠・出典】 『鶴林玉露』「伯夷伝赤壁賦」 文章絶唱...
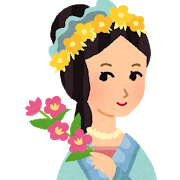 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉粧玉琢 【読み方】 ふんしょうぎょくたく 【意味】 女性の容貌が美しいことのたとえ。 【語源・由来】 「粉粧」は化粧の意。「玉琢」は宝を磨く意。女性が化粧をして玉を磨いたように美しいこと。 【典拠・出典】...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文従字順 【読み方】 ぶんじゅうじじゅん 【意味】 文章の筋がとおっていて、表現もよどみなくわかりやすいこと。 【語源・由来】 「従」「順」はともに、順調にはこぶ、さからわないこと。 【典拠・出典】 韓愈「...
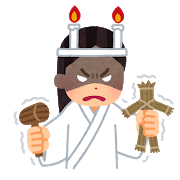 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 粉愁香怨 【読み方】 ふんしゅうこうえん 【意味】 美人がうらみ悲しむ姿の形容。 【語源・由来】 「粉」「香」は化粧した美しい顔のことで、「愁」「怨」はうれいうらむこと。 【典拠・出典】 丁鶴年「故宮人詩」...
 「ちょうどよい」の四字熟語一覧
「ちょうどよい」の四字熟語一覧【四字熟語】 文質彬彬 【読み方】 ぶんしつひんぴん 【意味】 外見の美しさと内面の実質がよく調和していること。人の文雅であってしかも飾りけの無いことの形容。 【語源・由来】 「文」は表面の美しさ・外見のこと。「質」は中...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蚊子咬牛 【読み方】 ぶんしこうぎゅう 【意味】 痛くもかゆくもないこと。また、自分の実力をわきまえずに行動すること。 【語源・由来】 「子」は接尾語。蚊が牛を咬むということから。 【典拠・出典】 - 【類...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 分合集散 【読み方】 ぶんごうしゅうさん 【意味】 離れたり集まったりすること。また、協力したり反目したりすること。 【語源・由来】 「集散」は集まることと散ること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・離合...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 文芸復興 【読み方】 ぶんげいふっこう 【意味】 十四世紀末から十六世紀初めにかけてイタリアを中心として全ヨーロッパにひろがった、ギリシャ・ローマ・の古典文化を手本とする学術上・芸術上の革新運動のこと。ルネ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 刎頸之交 【読み方】 ふんけいのまじわり 【意味】 首を切られても悔いないほど、固い友情で結ばれた交際。心を許し合った非常に親密な交際。 【語源・由来】 「刎頸」は刀で頸(首)を刎ねること。たとえ首を刎ねら...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 武陵桃源 【読み方】 ぶりょうとうげん 【意味】 俗世間から離れた別天地。理想郷のこと。 【語源・由来】 「武陵」は中国の地名。「桃源」は俗世間を離れた別天地のこと。 武陵の漁師が、川をさかのぼって桃林の奥...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 夫里之布 【読み方】 ふりのふ 【意味】 中国古代の税法の一。夫布と里布のこと。 【語源・由来】 「布」は銭のことをいう。夫布は職業のない者に課す税。「里」は居宅に桑麻を植えない者に課す税のこと。 【典拠・...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不埒千万 【読み方】 ふらちせんばん 【意味】 このうえなくふとどきなこと。非常にけしからぬさま。 【語源・由来】 「不埒」はけしからぬこと。ふとどきなこと。「埒」はもと乗馬などの囲いのこと。「千万」は形容...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 蜉蝣一期 【読み方】 ふゆうのいちご 【意味】 人生の短くはかないことのたとえ。 【語源・由来】 「蜉蝣」はかげろう、「一期」は一生のこと。かげろうの成虫は、数時間から数日の命と短いことから、はかないことに...
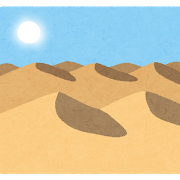 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不毛之地 【読み方】 ふもうのち 【意味】 草木や穀物が生じないやせた土地のこと。また、新しい発見もよい結果も得られないこと。 【語源・由来】 「毛」は地上に生える草木や穀物のこと。文化や人間が育たないこと...
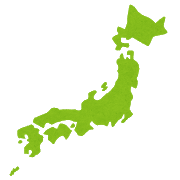 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 榑木之地 【読み方】 ふぼくのち 【意味】 東方にある太陽が昇る地のこと。また、日本の異称。 【語源・由来】 「榑木」は神木の名で、東方の日の出る所にあって、この木から太陽がのぼるといわれる。 【典拠・出典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 普遍妥当 【読み方】 ふへんだとう 【意味】 どんな場合にも真理として承認されること。 【語源・由来】 「普遍」はすべてのものに共通に存すること。「妥当」は適切にあてはまること。時間や空間を超越して、一時的...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 布韈青鞋 【読み方】 ふべつせいあい 【意味】 旅行のときの服装のこと。 【語源・由来】 「布韈」は布で作った脚半のこと。「青鞋」はわらじのこと。 【典拠・出典】 - 布韈青鞋(ふべつせいあい)の使い方 布...
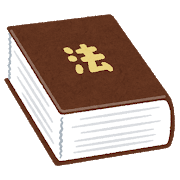 「したたか」の四字熟語一覧
「したたか」の四字熟語一覧【四字熟語】 舞文弄法 【読み方】 ぶぶんろうほう 【意味】 法を都合のいいように解釈すること。法の条文を曲解して濫用すること。 【語源・由来】 「舞」「弄」ともに、もてあそぶ、思うように動かすこと。 【典拠・出典】 『...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不抜之志 【読み方】 ふばつのこころざし 【意味】 物事にくじけない強い意志のこと。 【語源・由来】 「不抜」は抜きとることができない、堅くて動かないこと。堅固な意志のこと。 【典拠・出典】 『南史』「沈約...
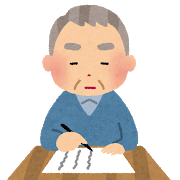 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不買美田 【読み方】 ふばいびでん 【意味】 子孫を甘やかし安楽な生活をさせるような財産を残さないこと。 【語源・由来】 「家を冨ますに良田を買うを用いざれ、書中、自ずから千鐘の粟有り」より。また、西郷隆盛...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 腐敗堕落 【読み方】 ふはいだらく 【意味】 精神がたるみ乱れて、弊害が多く生じる状態になること。 【語源・由来】 「腐敗」がくさりくずれること。「堕落」は正しい健全な状態を失って、悪い状態になること。 【...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 敷天之下 【読み方】 ふてんのもと 【意味】 世界中。 【語源・由来】 「敷」はあまねく広いこと。天のあまねくおおうところのこと。 【典拠・出典】 『詩経』「周頌・般」 敷天之下(ふてんのもと)の使い方 敷...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 普天率土 【読み方】 ふてんそつど 【意味】 天のおおう限り、地のつづく限りのすべての地。王の領土のこと。 【語源・由来】 「普天」は大空。「率土」は人の行くところ、土地から土地へつづくこと。「普天の下、率...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 釜底抽薪 【読み方】 ふていちゅうしん 【意味】 問題を解決するためには根本の原因を取り除かなければならないというたとえ。 【語源・由来】 魏収の文より。釜の湯の煮えたぎるのを止めるためには釜の下のたきぎを...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 物論囂囂 【読み方】 ぶつろんごうごう 【意味】 世間のうわさが騒がしいこと。 【語源・由来】 「物論」は世の中のうわさ・世間の評判のこと。「囂囂」は多くの声が騒がしいという意味。 【典拠・出典】 - 【類...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 仏足石歌 【読み方】 ぶっそくせきか 【意味】 仏足石の歌碑にきざまれた和歌の形式で、三十一音の短歌の末尾にさらに七音加えた形。 【語源・由来】 奈良の薬師寺の仏足石碑に二十一首、『古事記』『万葉集』にも一...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 物議騒然 【読み方】 ぶつぎそうぜん 【意味】 世論が騒がしいこと。 【語源・由来】 「物議」は世間のうわさ・世論。「騒然」はがやがやと騒がしいという意味。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・物情騒然(ぶつ...
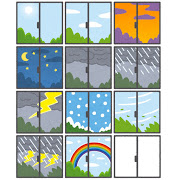 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 物換星移 【読み方】 ぶっかんせいい 【意味】 自然界の眺めや時世が変わり改まること。 【語源・由来】 「物換」は物事が変わること。「星移」は歳月が経過すること。 【典拠・出典】 王勃「滕王閣詩」 物換星移...
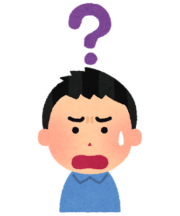 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不知案内 【読み方】 ふちあんない 【意味】 知識や心得がなく、物事の事情やようすがよくわからないこと。 【語源・由来】 「不知」は知らない、わからないということ。「案内」は物事の内情のこと。 【典拠・出典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 二股膏薬 【読み方】 ふたまたこうやく 【意味】 定見がなく、あっちへついたり、こっちへついたりすること。 【語源・由来】 「二股」は内股のこと。「膏薬」は練り薬のこと。股の間に塗った薬は、歩いているうちに...
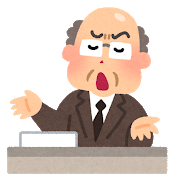 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮石沈木 【読み方】 ふせきちんぼく 【意味】 大衆の理に反した無責任な言論が威力をもつこと。 【語源・由来】 『三国志』「魏書・孫礼伝」より。水に沈むはずの石を浮かせ、水に浮くはずの木を沈めるような道理に...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 附贅懸疣 【読み方】 ふぜいけんゆう 【意味】 無用なもののこと。 【語源・由来】 「贅」「疣」はともにこぶ・いぼのこと。ついてぶらさがっているこぶやいぼということ。 【典拠・出典】 『荘子』「駢拇」 附贅...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 負薪之病 【読み方】 ふしんのへい 【意味】 自分の病気の称。 【語源・由来】 「負薪」は薪を背負うこと。「憂」は病気のこと。薪を背負った疲れで病気になること。また、病気で薪を背負えなくなること。 【典拠・...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 負薪之憂 【読み方】 ふしんのうれい 【意味】 自分の病気の称。 【語源・由来】 「負薪」は薪を背負うこと。「憂」は病気という意味。薪を背負った疲れで病気になること。また、病気で薪を背負えなくなること。 【...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 負薪汲水 【読み方】 ふしんきゅうすい 【意味】 自然の中で簡素な生活を営むこと。 【語源・由来】 たきぎを採り、谷川の水を汲むということから。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・採薪汲水(さいしんきゅうす...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 不将不迎 【読み方】 ふしょうふげい 【意味】 過ぎ去ったできごとをくよくよと悔やみ、まだ来ないことにあれこれ心を悩ますことをしないこと。 【語源・由来】 去るものを送ったり、来るものを迎えたりしないこと。...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 膚受之愬 【読み方】 ふじゅのうったえ 【意味】 身にさしせまった痛切な訴えのこと。 【語源・由来】 「膚受」は肌身にしみるような痛切なこと。「愬」は困難や不平を申し立てるという意味。知らないうちに肌に垢が...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 俛首帖耳 【読み方】 ふしゅちょうじ 【意味】 人にこびへつらう卑しい態度のこと。 【語源・由来】 「俛」は伏せるという意味。「帖耳」は頭を伏せること。「帖」は垂れるという意味で、「帖耳」は耳をだらりと垂れ...
 「ひそか」の四字熟語一覧
「ひそか」の四字熟語一覧【四字熟語】 附耳之言 【読み方】 ふじのげん 【意味】 秘密は漏れやすいし、すぐに広まるものだということ。 【語源・由来】 耳に口をつけてする内緒話でも、千里も離れている所まで聞こえてしまうものだということから。「附耳...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不失正鵠 【読み方】 ふしつせいこく 【意味】 物事の重要な点を正確にとらえること。的をはずさず急所をつくこと。 【語源・由来】 「正鵠」は弓の的の真ん中の黒い星(図星)のことをいう。転じて、物事の要点・急...
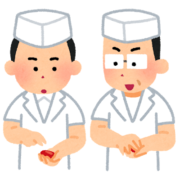 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 父子相伝 【読み方】 ふしそうでん 【意味】 学術や技芸などの奥義を父からわが子だけに伝えること。 【語源・由来】 「相伝」は、代々伝えること。「子」は、通常男子をさした。女子は、「女」という。 【典拠・出...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 巫山之夢 【読み方】 ふざんのゆめ 【意味】 男女の情交をいう。 【語源・由来】 「巫山」は一説に中国、湖北省の山の名。ここに神女が住んでいたとされる。 戦国時代、楚の壊王が高唐に遊び昼寝をしていたとき、そ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 巫山雲雨 【読み方】 ふざんうんう 【意味】 男女の情交をいう。 【語源・由来】 「巫山」は一説に中国、湖北省の山の名。ここに神女が住んでいたとされる。 戦国時代、楚の壊王が高唐に遊び昼寝をしていたとき、そ...
 「じっくり考える」の四字熟語一覧
「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 俯察仰観 【読み方】 ふさつぎょうかん 【意味】 仰いで天文を見、うつむいて地理を知ること。 【語源・由来】 仰いだり、うつむいたりして観察すること。 【典拠・出典】 『易経』「繋辞・上」 【類義語】 ・仰...
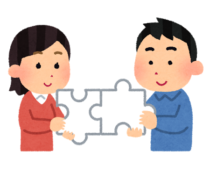 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 夫妻牉合 【読み方】 ふさいはんごう 【意味】 夫婦は一つの物の半分ずつで、両方を合わせて初めて完全になるということ。 【語源・由来】 「牉」は半ば・わかれるという意味。「牉合」は二つにわかれたものを合わせ...
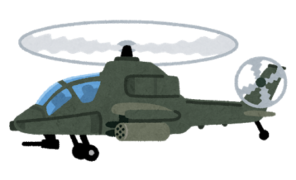 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富国強兵 【読み方】 ふこくきょうへい 【意味】 国の経済力を高め、軍事力を増強すること。国を冨まし兵を強くするという意味。 【典拠・出典】 『戦国策』「秦策」 富国強兵(ふこくきょうへい)の使い方 富国強...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不耕不織 【読み方】 ふこうふしょく 【意味】 生産的な仕事をしないこと。またはそのような身分。武士。 【語源・由来】 「不耕」は耕さない。「不織」は織らないという意味。 封建時代、農民は耕して作物を得ても...
 「じっくり考える」の四字熟語一覧
「じっくり考える」の四字熟語一覧【四字熟語】 不言之教 【読み方】 ふげんのおしえ 【意味】 言葉にして言わずに、相手に体得させることができる教えのこと。 【語源・由来】 「不言」は言葉に出してとやかく言わないこと。特に、老荘の「無為自然」の教えをいう...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 不繋之舟 【読み方】 ふけいのふね 【意味】 心にわだかまりがなくさっぱりしていて無心なこと。また、定めなく流れただよっていること。 【語源・由来】 「不繋」はつなぎとめていないということ。 【典拠・出典】...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 腹誹之法 【読み方】 ふくひのほう 【意味】 口に出さなくても、心の中で非難すれば罰するという法律のこと。 【語源・由来】 「誹」はそしるという意味。「腹誹」は口にはいわず心の中でそしること。 【典拠・出典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不虞之誉 【読み方】 ふぐのほまれ 【意味】 思いがけなく得た名誉のこと。 【語源・由来】 「不虞」は思いがけない・意外ということ。 【典拠・出典】 『孟子』「離婁・上」 【対義語】 ・求全之毀(きゅうぜん...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 覆水不返 【読み方】 ふくすいふへん 【意味】 一度犯した誤りはもとどおりにはならないということ。また離婚した夫婦の仲はもとにもどらないということ。 【語源・由来】 「覆水」はこぼれた水。「覆水盆に返らず」...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 覆車之戒 【読み方】 ふくしゃのいましめ 【意味】 前者の失敗を見て、同じ失敗をしないよう戒めにすること。 【語源・由来】 「覆車」は車がひっくりかえること。前の車がひっくりかえるのを見て、後から行く車が用...
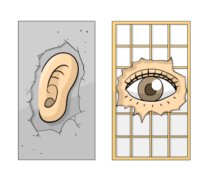 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 伏寇在側 【読み方】 ふくこうざいそく 【意味】 身辺の注意を怠らず、言動も慎むべきだということ。 【語源・由来】 「牆に耳あり、伏寇側(かたわ)らに在り」より。「伏寇」は隠れている盗賊のこと、「在側」はす...
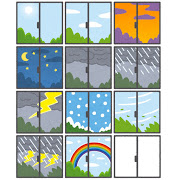 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 覆雨翻雲 【読み方】 ふくうほんうん 【意味】 世の人の態度や人情がうつろいやすいことのたとえ。 【語源・由来】 手のひらを上に向けると雲になり、下に向けると雨になるという意味で、人の心が簡単に変わることを...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 俯仰之間 【読み方】 ふぎょうのかん 【意味】 ほんのわずかな間のこと。 【語源・由来】 「俯」はうつむくこと、「仰」はあおむけになること。うつむいたり、仰いだりするごくわずかな時間をいう。 【典拠・出典】...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不羈奔放 【読み方】 ふきほんぽう 【意味】 なにものにもとらわれることなく、自分の思うままに振る舞うこと。 【語源・由来】 「奔放」は束縛されず思うままに振る舞うこと。「羈」はつなぎとめることで、「不羈」...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不羈之才 【読み方】 ふきのさい 【意味】 何事にも拘束されないのびのびした才能。学才がすぐれていることをいう。非凡の才。 【語源・由来】 「羈」はつなぐという意味から、校則や束縛の意。 【典拠・出典】 『...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不刊之書 【読み方】 ふかんのしょ 【意味】 永久に滅びることなく伝わる書物。不朽の名著。 【語源・由来】 「刊」はけずるという意味。昔は文字を木簡や竹簡に書き、誤りなどは刀で削ったことから、「不刊」は滅び...
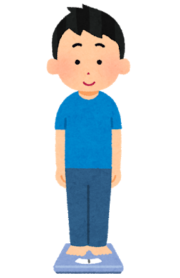 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮花浪蕊 【読み方】 ふかろうずい 【意味】 取り柄のない平凡なさまのたとえ。 【語源・由来】 「浮」も「浪」も、ともにあてにならないことで、「蕊」は花のしべ。実を結ばないむだ花のこと。 【典拠・出典】 韓...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮家泛宅 【読み方】 ふかはんたく 【意味】 船の中に住まうこと。漂泊して暮らすことから、転じて、放浪する隠者の生活。 【語源・由来】 「泛」は浮かぶ、浮かべるという意味。 【典拠・出典】 顔真卿「浪跡先生...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 夫家之征 【読み方】 ふかのせい 【意味】 中国周代の税の一。民衆で一定の仕事を持たない者に、罰金として出させた。 【語源・由来】 「夫家」は夫婦、「征」は税をとりたてること。農民の一組の夫婦に与えられる田...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮瓜沈李 【読み方】 ふかちんり 【意味】 夏の優雅な遊びをいう。 【語源・由来】 魏文帝の文より。水に瓜を浮かべ、李(すもも)を沈めること。 【典拠・出典】 『文選』曹丕「与朝歌令呉質書」 浮瓜沈李(ふか...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不解衣帯 【読み方】 ふかいいたい 【意味】 あることに不眠不休で専念すること。衣服を着替えることもしないで仕事に熱中すること。 【典拠・出典】 『漢書』「王莽伝・上」 【類義語】 ・昼夜兼行(ちゅうやけん...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不壊金剛 【読み方】 ふえこんごう 【意味】 きわめて堅固でこわれないこと。また、志をかたく守って変えないたとえ。 【語源・由来】 「金剛」は梵語(古代インド語)の漢訳で堅固という意味。「不壊」はこわれない...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮雲之志 【読み方】 ふうんのこころざし 【意味】 不正な手段で得た財産や地位は、自分とは関係がないはかないものだという考え方。 【語源・由来】 「浮雲」は空に浮かぶ雲のことで、すぐに散ってしまうはかないも...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮雲朝露 【読み方】 ふうんちょうろ 【意味】 たよりなくはかないもののたとえ。 【語源・由来】 「浮雲」は空に浮かぶ雲のことで、たよりなく定まらないことのたとえ。「朝露」は朝方におりる露のことで、すぐに消...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 巫雲蜀雨 【読み方】 ふうんしょくう 【意味】 遠く離れ離れになっている夫婦がお互いを思い合っていることのたとえ。 【語源・由来】 巫山の雲と蜀の雨。 【典拠・出典】 李賀「琴曲歌辞」 巫雲蜀雨(ふうんしょ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮雲驚竜 【読み方】 ふうんきょうりゅう 【意味】 筆勢がきわめて自由闊達で勢いがあるさま。 【語源・由来】 浮き雲のように自由でのびのびしており、天に昇る竜のように勢いのあることから。 【典拠・出典】 『...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 浮雲翳日 【読み方】 ふうんえいじつ 【意味】 悪人が政権を握って世の中が暗くなることのたとえ。また、邪悪な家臣が君主の英明をおおい善政が行われないこと。 【語源・由来】 浮雲が日光をさえぎるという意味。「...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風流韻事 【読み方】 ふうりゅういんじ 【意味】 詩歌や書画などの風流な遊び。また、自然を友とするような優雅な趣味。 【語源・由来】 「風流」は上品で趣があること。「韻事」は詩歌や書画など風流な遊びのこと。...
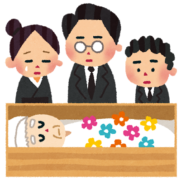 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風木之悲 【読み方】 ふうぼくのかなしみ 【意味】 父母が亡くなってしまって、孝行を尽くすことができない嘆き。 【語源・由来】 「風木」は風にゆれる木のこと。木が静止したいと思っても、風が止まないと静止でき...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風俗壊乱 【読み方】 ふうぞくかいらん 【意味】 世の中の健全な風俗や習慣が乱れること。 【語源・由来】 「風俗」は風習・しきたりのこと。「壊乱」は壊れ乱れること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・傷風敗...
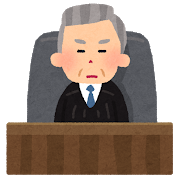 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風霜之任 【読み方】 ふうそうのにん 【意味】 司法官のこと。 【語源・由来】 「風霜」は風と霜で、峻厳・峻烈なさまのたとえ。「任」は任務という意味。不法を糾弾することが峻烈な任務ということから。 【典拠・...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風霜高潔 【読み方】 ふうそうこうけつ 【意味】 清らかに澄んだ秋の景色のたとえ。 【語源・由来】 「風霜」は風と霜のこと。風は高い空を吹き、霜は白く清らかであること。 【典拠・出典】 欧陽脩「酔翁亭記」 ...
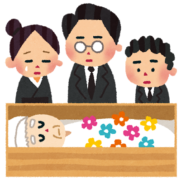 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風樹之歎 【読み方】 ふうじゅのたん 【意味】 父母が亡くなってしまって、孝行を尽くすことができない嘆き。 【語源・由来】 「風樹」は風に揺れる木のこと。木が静止したいと思っても、風が止まないと静止できない...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風餐露宿 【読み方】 ふうさんろしゅく 【意味】 風にさらされ、露にぬれ野宿をすること。転じて、旅の苦労、野宿の苦しみのたとえ。 【語源・由来】 「餐」は食べたり飲んだりすることで、「風餐」は風にさらされて...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風餐雨臥 【読み方】 ふうさんうが 【意味】 旅の苦しみや野外での仕事の苦しみ。また、野宿をすること。 【語源・由来】 「風餐」は風に吹かれて食事をすること。「雨臥」は雨にうたれながら寝ること。 【典拠・出...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風月玄度 【読み方】 ふうげつげんたく 【意味】 人と長いあいだ会っていないこと。また、心が清く私欲のない人を思うこと。 【語源・由来】 「風月」はすがすがしい風と美しい月。「玄度」は人名。 中国、晋の劉惔...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴利達 【読み方】 ふうきりたつ 【意味】 富んで位高くなること。立身出世すること。 【語源・由来】 「利達」は利益を得て、高い地位や官職に就くこと。 【典拠・出典】 『孟子』「離婁・下」 富貴利達(ふう...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴福沢 【読み方】 ふうきふくたく 【意味】 富んで位高く幸福なこと。天が人に与える富貴や恩沢。 【語源・由来】 「富貴」は財産があり、身分が高いこと。「福沢」は幸福とめぐみ。 【典拠・出典】 『近思録』...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴浮雲 【読み方】 ふうきふうん 【意味】 財産や地位ははかなく頼りにならないものだということ。また。名利に心を動かされることなく、名利など関係がないということ。また、不正をして得た地位は、浮雲のようには...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風紀紊乱 【読み方】 ふうきぶんらん 【意味】 社会風俗や規律が乱れること。特に男女間の交遊についていう。 【語源・由来】 「風紀」は、風俗や風習など、日常生活におけるきまり。特に男女関係についていう。「紊...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴在天 【読み方】 ふうきざいてん 【意味】 富も位も天命によるので人の思うようにはいかないこと。 【典拠・出典】 『論語』「顔淵」 富貴在天(ふうきざいてん)の使い方 富貴在天(ふうきざいてん)の例文 ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 富貴栄華 【読み方】 ふうきえいが 【意味】 富んで身分が高く栄えときめくこと。 【語源・由来】 「富貴」は財産があって身分が高いこと。「栄華」は草木が栄え茂ることから、栄ときめくこと。 【典拠・出典】 『...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風岸孤峭 【読み方】 ふうがんこしょう 【意味】 いかめしくて厳しく、角立って人と融和しないために孤独なこと。 【語源・由来】 「風岸」は性質が角立って人と融和しないこと。「孤峭」は性質がけわしく世間から孤...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風鬟雨鬢 【読み方】 ふうかんうびん 【意味】 風にくじけずり雨に洗われる。風雨にさらされ苦労して勤労すること。 【語源・由来】 「鬟」はわげ、頭の上に束ね輪にした髪型。「鬢」はびん、耳ぎわの髪の毛。髪の毛...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雲月露 【読み方】 ふううんげつろ 【意味】 なんの役にも立たない、自然の風景を詠んだだけの詩文のこと。 【語源・由来】 風に吹かれる雲と月光にひかる露の玉という意味で、自然の風物のこと。また、花鳥風月を...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雨対牀 【読み方】 ふううたいしょう 【意味】 兄弟が会うこと。 【語源・由来】 「牀」は床に同じで、兄弟が床を並べて夜の雨音をたがいに心静かに聞くことから転じた。 唐の韋王物の詩に「風雪夜」「対牀眠」の...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風雨凄凄 【読み方】 ふううせいせい 【意味】 風が吹き雨が降って、寒く冷たいさま。 【語源・由来】 「風雨」は風と雨・あらしのこと。「淒淒」は寒く冷たくて底冷えがすること。乱世の意味の用いることもある。 ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 馮異大樹 【読み方】 ふういたいじゅ 【意味】 謙虚でおごりたかぶらない人のたとえ。 【語源・由来】 「馮異」は後漢の将軍。馮異は謙譲の徳をもち、所掌が手柄話をするときはいつも大樹の下に遠のいていたので、軍...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 布衣之交 【読み方】 ふいのまじわり 【意味】 身分や地位などを問題にしない心からの交際。また、庶民的なつきあい。 【語源・由来】 「布衣」は麻の布で作った庶民の衣服のことで、転じて庶民のこと。 【典拠・出...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 布衣之極 【読み方】 ふいのきょく 【意味】 庶民として最高の出世のこと。 【語源・由来】 「布衣」は布で作った衣服のこと、転じて無位無官の人をいう。「極」は物事の最高、最上という意味。 【典拠・出典】 『...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 奮闘努力 【読み方】 ふんとうどりょく 【意味】 気を奮い起こし、努め励むこと。 【語源・由来】 「奮闘」は力を出して戦うこと。「努力」は力を尽くし励むこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・精励恪勤(せ...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 不断節季 【読み方】 ふだんせっき 【意味】 一日一日を節季のつもりで、借金をしないでまじめな商売をしていれば、決算期になっても困ることはないということ。 【語源・由来】 「不断」は、日常・平生のこと。「節...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風櫛雨沐 【読み方】 ふうしつうもく 【意味】 雨風にさらされて、苦労をすることのたとえ。 【語源・由来】 「風櫛」は風が髪をくしけずり、「雨沐」は雨が体を洗うこと。風雨にさらされながらも仕事で奔走すること...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 釜底游魚 【読み方】 ふていのゆうぎょ 【意味】 死が目前に迫っていることのたとえ。 【語源・由来】 釜の中で煮られる直前の魚ということから。 【典拠・出典】 『後漢書』「張綱伝」 【類義語】 ・小水之魚(...
 「のんき」の四字熟語一覧
「のんき」の四字熟語一覧【四字熟語】 釜中之魚 【読み方】 ふちゅうのうお 【意味】 死が迫っていること。危険が迫っているのを知らずに、のんびりしていることをたとえていう。 【語源・由来】 火にかけられる釜の中で魚が煮られることも知らずに泳いで...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 釜魚甑塵 【読み方】 ふぎょそうじん 【意味】 非常に貧しいという意。 【語源・由来】 甑に塵がつもり、鍋にはボウフラが沸き炊事をすることができないほど非常に貧しいということから。 【典拠・出典】 - 【類...
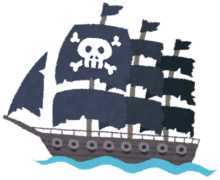 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 風魚之災 【読み方】 ふうぎょのわざわい 【意味】 海上の暴風による災難のこと。また、海賊や外敵などによる災難のこと。 【語源・由来】 「風」は海上の暴風、「魚」は鰐魚(わに)などの災いをもたらす悪魚の意。...
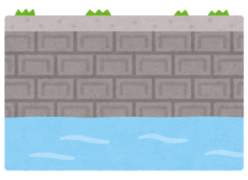 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 焚琴煮鶴 【読み方】 ふんきんしゃかく 【意味】 琴を焼いてつるを煮る意で、殺風景なこと。また、風流心のないことのたとえ。 【語源・由来】 「焚」は焼く意。 【典拠・出典】 『義山雑纂』李商隠「殺風景」 【...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 鳧趨雀躍 【読み方】 ふすうじゃくやく 【意味】 喜んで小躍りするさま。 【語源・由来】 「鳧趨」はカモが小走りに歩く。このとき、カモの体が左右に揺れ踊るようにみえることから。「雀躍」はスズメが踊ること。ま...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 不易流行 【読み方】 ふえきりゅうこう 【意味】 いつまでも変化しない本質的なものを忘れない中にも、新しく変化を重ねているものをも取り入れていくこと。また、新味を求めて変化を重ねていく流行性こそが不易の本質...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語【四字熟語】 奮励努力 【読み方】 ふんれいどりょく 【意味】 気力を奮い起こして励むこと。 【語源・由来】 「奮励」は気力を奮い起こして努めること。「努力」はあることを実現するために努める意。 【典拠・出典】 - 【類...
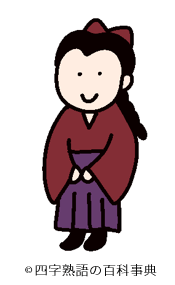 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語文明開化の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 文明開化 【読み方】 ぶんめいかいか 【意味】 人間の知恵、知識が進んで、世の中が進歩し開けること。特に明治初期の思想・文化・制度の近代化、西洋化した現象。 【語源・由来...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語文武両道の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 文武両道 【読み方】 ぶんぶりょうどう 【意味】 学芸と武道の意。また、その両方にすぐれていること。 【語源・由来】 「文」は学問・文事。「武」は武道。「両道」は二つの方...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語無礼千万の意味(類義語) 【四字熟語】 無礼千万 【読み方】 ぶれいせんばん 【意味】 はなはだしく礼儀にはずれていること。失礼なこと。 「千万」は、はなはだしいことを強調する意。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・失礼...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不立文字の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 不立文字 【読み方】 ふりゅうもんじ 【意味】 悟りの境地は、言葉で教えられるものではなく、心から心へ伝えるものだということ。悟りの境地は、言葉で表せるものではないから、...
 「ちょうどよい」の四字熟語一覧
「ちょうどよい」の四字熟語一覧不偏不党の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 不偏不党 【読み方】 ふへんふとう 【意味】 特定の主義や思想にかたよらず、いずれの党派にも加わらないこと。偏ることなく、公正・中立な立場をとること。 【語源・由来...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語舞文曲筆の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 舞文曲筆 【読み方】 ぶぶんきょくひつ 【意味】 故意に語句を飾りたて、また、事実を曲げて書くこと。 【語源・由来】 「舞文」は文章を飾り立てること。「曲筆」は事実を曲げ...
 「はっきりしない」の四字熟語一覧
「はっきりしない」の四字熟語一覧不得要領の意味(語源由来) 【四字熟語】 不得要領 【読み方】 ふとくようりょう 【意味】 話の要点がはっきりせず、何を言いたいのかよくわからないこと。 【語源・由来】 「要領」は、着物の腰と襟の部分。転じて、物事の要と...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不撓不屈の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 不撓不屈 【読み方】 ふとうふくつ 【意味】 どんな苦労や困難にもくじけないさま。 【語源・由来】 「撓」は、木の枝などがたわむ。転じて、くじける。「屈」は、主義主...
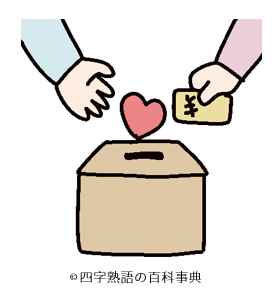 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語物心両面の意味 【四字熟語】 物心両面 【読み方】 ぶっしんりょうめん 【意味】 物質的な面と精神的な面の両面。金銭・物品などの形に見えるものと、応援・激励など心に関係していること。 【典拠・出典】 - 物心両面(ぶっし...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語物情騒然の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 物情騒然 【読み方】 ぶつじょうそうぜん 【意味】 世の中が騒々しく、人の心が落ち着かないこと。 【語源・由来】 「物情」は世間の様子。人々の心。「騒然」は騒がしいさま。...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語夫唱婦随の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 夫唱婦随 【読み方】 ふしょうふずい 【意味】 夫婦の仲が非常によいことのたとえ。夫が言い出し、妻が従うこと。 【語源・由来】 夫の考えに妻が従うと夫婦関係がうまく...
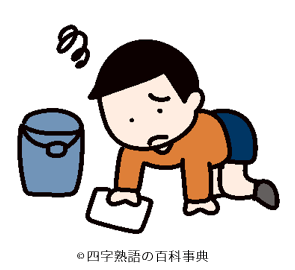 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧不承不承の意味(語源由来) 【四字熟語】 不承不承 【読み方】 ふしょうぶしょう 【意味】 いやいやながらも、やむをえず物事を行うこと。 【語源・由来】 「不承」は嫌だと思いながらも承知する意。「不承」を重ねて意味を強調...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不惜身命の意味(語源由来・出典) 【四字熟語】 不惜身命 【読み方】 ふしゃくしんみょう 【意味】 仏道のために身も命も惜しまないこと。 【語源・由来】 「不惜」は、惜しまないこと。「身命」は、からだと命。 【典拠・出典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語無事息災の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 無事息災 【読み方】 ぶじそくさい 【意味】 病気や災難や、心配事もなく平穏に暮らしていること。 【語源・由来】 「無事」は心配事、異変がないこと。「息災」は災いを防ぎ止...
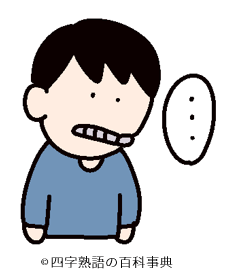 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不言不語の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 不言不語 【読み方】 ふげんふご 【意味】 口に出して何も言わず、黙っていること。 【語源・由来】 言う、語る意の言語の「言」「語」のそれぞれに打消しの意の「不」を添えた...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語伏竜鳳雛の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 伏竜鳳雛 【読み方】 ふくりょうほうすう 【意味】 才能がありながら、機会に恵まれず、実力を発揮できないでいる者のたとえ。また、まだ世間に知られずにいる優れた人物、...
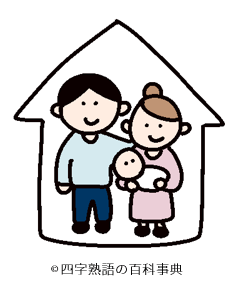 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語福徳円満の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 福徳円満 【読み方】 ふくとくえんまん 【意味】 幸福や財産に恵まれ、満ち足りているさま。 【語源・由来】 「福徳」は、幸福と利益。「円満」は、満ち足りているさま。 【典...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不倶戴天の意味(語源由来・出典) 【四字熟語】 不倶戴天 【読み方】 ふぐたいてん 【意味】 同じ世には一緒にはいない、同じ天の下には生かしてはおけないと思うほど恨み・怒りの深いこと。もとは父の仇を言った。 【語源・由来...
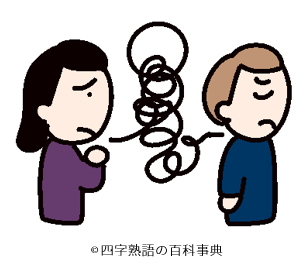 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語複雑多岐の意味(語源由来・類義語・対義語) 【四字熟語】 複雑多岐 【読み方】 ふくざつたき 【意味】 事情などが入り組んでいて多方向に枝分かれしていくので、全体を把握するのが非常にわかりにくいさま。 【語源・由来】 「...
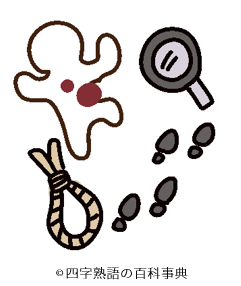 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語複雑怪奇の意味(語源由来) 【四字熟語】 複雑怪奇 【読み方】 ふくざつかいき 【意味】 非常にわかりにくく、あやしく不思議なこと。様々な要素が絡み合っていて、理由や原因などがよくわからないこと。またはその様子。 【語源...
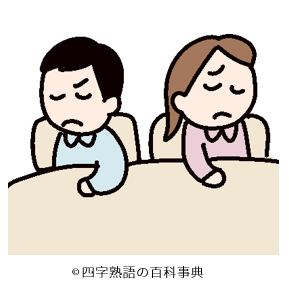 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不協和音の意味 【四字熟語】 不協和音 【読み方】 ふきょうわおん 【意味】 高さの異なる二つ以上の音が同時に響く時、調和せず協和しない状態にある和音。 心をあわせて仲良くせず、不調和な関係のたとえ。 【典拠・出典】 -...
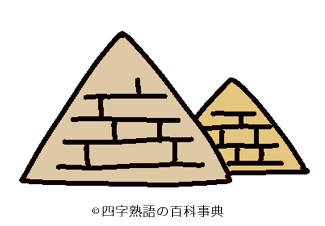 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不朽不滅の意味 【四字熟語】 不朽不滅 【読み方】 ふきゅうふめつ 【意味】 永遠に朽ち滅びないこと。また長く残るほどすぐれていること。 【典拠・出典】 - 不朽不滅(ふきゅうふめつ)の解説 不朽不滅(ふきゅうふめつ)の...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不可思議の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 不可思議 【読み方】 ふかしぎ 【意味】 常識では考えられないこと。物事の奥底が深く、考えてもよく理解できず、ことばでも的確に表現できないさまや現象。また、一般に原因も定...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不可抗力の意味(語源由来) 【四字熟語】 不可抗力 【読み方】 ふかこうりょく 【意味】 人間の力ではどうにもさからうことのできない巨大な力や事態。 法律用語で、必要と認められる注意や予防などの十分な対策を構じても、なお...
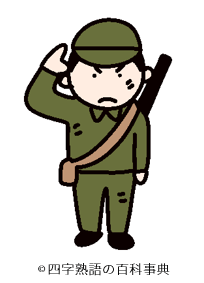 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語武運長久の意味(語源由来) 【四字熟語】 武運長久 【読み方】 ぶうんちょうきゅう 【意味】 戦場での幸運が長く続くこと。または、出征した兵がいつまでも無事なこと。 【語源・由来】 「武運」は、戦闘での勝負の運。「長久」...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧風林火山(ふうりんかざん)の意味とは?(出典) 【四字熟語】 風林火山 【読み方】 ふうりんかざん 【意味】 戦いにおける四つの心構え。風のようにすばやく動き、林のように静かに構え、火の如く激しく侵略し、山のようにどっし...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧風流三昧の意味(語源由来・類義語) 【四字熟語】 風流三昧 【読み方】 ふうりゅうざんまい 【意味】 自然に親しみ、詩歌や書画などの優雅な遊びにふけること。「風流」は上品で優雅な趣のあること。「三昧」は、あることに熱中し...
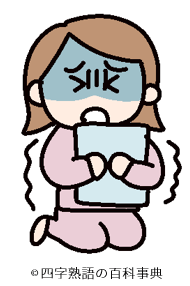 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語風声鶴唳の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 風声鶴唳 【読み方】 ふうせいかくれい 【意味】 怖じ気づいていて、ささいなことにも恐れおののくことのたとえ。 【語源・由来】 「風声」は風の音。「鶴唳」は鶴の鳴く...
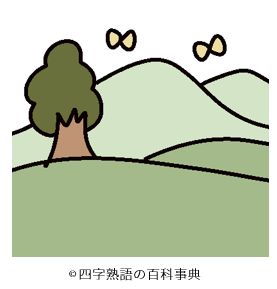 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語風光明媚の意味(語源由来) 【四字熟語】 風光明媚 【読み方】 ふうこうめいび 【意味】 自然の景色が清らかで澄んでいて美しいこと。 【語源・由来】 「風光」は自然の景色、風景。「明媚」は景色が清らかで澄んでいて美しい様...
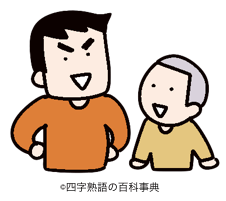 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語付和雷同の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 付和雷同 【読み方】 ふわらいどう 【意味】 自分にしっかりとした考えがなく、他人の言動にすぐ同調すること。 【語源・由来】 「付和」は定見をもたず、すぐ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不老長寿の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 不老長寿 【読み方】 ふろうちょうじゅ 【意味】 いつまでも年をとらず、長生きすること。 【語源・由来】 「不老」は老いないこと、「長寿」は長生き・長命なことから...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不眠不休の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 不眠不休 【読み方】 ふみんふきゅう 【意味】 眠ったり休んだりしないこと。休まず事に当たることをいう。 【語源・由来】 「不眠」は、眠らないこと。「不休」は、休...
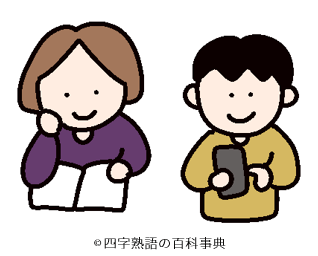 「ちょうどよい」の四字熟語一覧
「ちょうどよい」の四字熟語一覧不即不離の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 不即不離 【読み方】 ふそくふり 【意味】 二つのものの関係が深すぎもせず、離れすぎもしないこと。つかず離れず、ちょうどよい関係にあること。 【語源・由来】 「即...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語粉骨砕身の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 粉骨砕身 【読み方】 ふんこつさいしん 【意味】 力の限り懸命に働くこと、力の限り努力すること。 【語源由来】 骨を粉にし、身を砕くほど、力を尽くすというこ...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不老不死の意味(出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 不老不死 【読み方】 ふろうふし 【意味】 いつまでも年をとらず、死なないこと。 【典拠・出典】 『列子』「湯問」 【類義語】 ・不老長寿(ふろうちょうじゅ) ・長生...
 「ふ」で始まる四字熟語
「ふ」で始まる四字熟語不平不満の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 不平不満 【読み方】 ふへいふまん 【意味】 ある物事や状態に対して、心持ちが穏やかでなく落ち着かないようす。 【語源・由来】 「不平」は、心がたいらかで...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧不言実行の意味(語源由来・類義語・対義語) 【四字熟語】 不言実行 【読み方】 ふげんじっこう 【意味】 あれこれ言わず黙って、しなければならないことを行うこと。 【語源由来】 「不言」は、ことさら何も言わないこと。しな...