仁義道徳【じんぎどうとく】の意味と使い方や例文
【四字熟語】 仁義道徳 【読み方】 じんぎどうとく 【意味】 人として守るべき正しい道。また、その道にかなう生き方をすること。 【典拠・出典】 - 仁義道徳(じんぎどうとく)の使い方 仁義道徳(じんぎどうとく)の例文 健...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 仁義道徳 【読み方】 じんぎどうとく 【意味】 人として守るべき正しい道。また、その道にかなう生き方をすること。 【典拠・出典】 - 仁義道徳(じんぎどうとく)の使い方 仁義道徳(じんぎどうとく)の例文 健...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 従容自若 【読み方】 しょうようじじゃく 【意味】 ゆったりとして落ち着き払い、心の動じないようす。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・鷹揚自若(おうようじじゃく) ・神色自若(しんしょくじじゃく) ・湛然...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 獅子身中 【読み方】 しししんちゅう 【意味】 内部の者でありながら、害を及ぼす者のこと。また、恩を受けていながら裏切って害悪をなす者のこと。もとは、仏の弟子でありながら仏教に害をなす者をさす。獅子の体内に...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 寺社仏閣 【読み方】 じしゃぶっかく 【意味】 てらとやしろ。寺院と神社。社寺。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・神社仏閣(じんじゃぶっかく) 寺社仏閣(じしゃぶっかく)の使い方 寺社仏閣(じしゃぶっかく...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 商売繁盛 【読み方】 しょうばいはんじょう 【意味】 商いがうまくゆき、大いに利益を得ること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・千客万来(せんきゃくばんらい) ・門前成市(もんぜんせいし) 商売繁盛(しょ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自信満満 【読み方】 じしんまんまん 【意味】 自信に満ちあふれたさま。 【典拠・出典】 - 自信満満(じしんまんまん)の使い方 自信満満(じしんまんまん)の例文 自信満満だった健太くんは、自分が負けるとは...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 社交辞令 【読み方】 しゃこうじれい 【意味】 社交上のあいさつ。また、相手をただ喜ばせるためだけの、うわべのあいさつ。リップサービス。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・外交辞令(がいこうじれい) ・虚礼...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 常備不懈 【読み方】 じょうびふかい 【意味】 常日頃から怠らず備えておくこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・有備無患(ゆうびむかん) 常備不懈(じょうびふかい)の使い方 常備不懈(じょうびふかい)の...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 焦眉之急 【読み方】 しょうびのきゅう 【意味】 危険や急用が切迫している事態のこと、またその度合いを強調していう。眉が焦げるほど火の勢いが迫ってきて危険であるという意味。緊急事態。 【語源・由来】 「焦眉...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 攘臂疾言 【読み方】 じょうひしつげん 【意味】 うでまくりをして、はやくちに話すこと。得意げな様子。 【典拠・出典】 『呂氏春秋』「驕恣」 攘臂疾言(じょうひしつげん)の使い方 攘臂疾言(じょうひしつげん...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 笑比河清 【読み方】 しょうひかせい 【意味】 厳しい性格で、笑顔をほとんど見せないこと。 【語源・由来】 古代中国の北宋の裁判官包拯は、ほとんど笑うことがなかった。これを人々が、今までに澄んで清くなったこ...
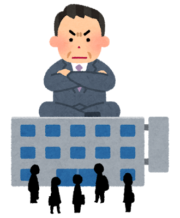 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 賞罰之柄 【読み方】 しょうばつのへい 【意味】 賞罰を行う権力のこと。 【典拠・出典】 『呂氏春秋』「義賞」 賞罰之柄(しょうばつのへい)の使い方 賞罰之柄(しょうばつのへい)の例文 彼は賞罰之柄を持って...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 松柏之寿 【読み方】 しょうはくのじゅ 【意味】 長生き。長寿を祝うことば。また、節度を守って変わらないこともいう。松や柏の木が、いつも緑の葉を保ち、樹齢が長いことから。 【語源・由来】 「松柏と亀鶴と、其...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 躡足附耳 【読み方】 じょうそくふじ 【意味】 注意するときに、相手を傷つけないような配慮が大切であるということ。 【典拠・出典】 『史記』「淮陰侯伝」 躡足附耳(じょうそくふじ)の使い方 躡足附耳(じょう...
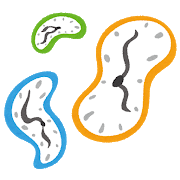 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 消息盈虚 【読み方】 しょうそくえいきょ 【意味】 移ろい行く時間の流れ。生と死や盛衰が繰り返されて変化し続けていくこと。時の移り変わり。 【典拠・出典】 『易経』「剥」 消息盈虚(しょうそくえいきょ)の使...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 小人之勇 【読み方】 しょうじんのゆう 【意味】 思慮の浅い人の、ただ血気にはやる勇気。 【典拠・出典】 『荀子』「栄辱」 【類義語】 ・匹夫之勇(ひっぷのゆう) 小人之勇(しょうじんのゆう)の使い方 小人...
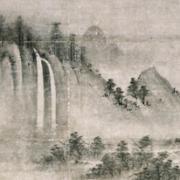 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 瀟湘八景 【読み方】 しょうしょうはっけい 【意味】 瀟湘地方の八つの景勝。山市晴嵐・漁村夕照・遠浦帰帆・瀟湘夜雨・煙寺晩鐘・洞庭秋月・平沙落雁・江天暮雪をいう。北宋の宋迪 (そうてき) がこれを描き、画題...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 清浄寂滅 【読み方】 しょうじょうじゃくめつ 【意味】 道家の教えと仏家の教え。 【典拠・出典】 韓愈「原人」 清浄寂滅(しょうじょうじゃくめつ)の使い方 清浄寂滅(しょうじょうじゃくめつ)の例文 断捨離を...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 牀上施牀 【読み方】 しょうじょうししょう 【意味】 無意味な重複、新味のないこと、独創性のないことのたとえ。 【語源・由来】 床の上に床を張るという意味から。 【典拠・出典】 『顔氏家訓』「序致」 【類義...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 蕉風俳諧 【読み方】 しょうふうはいかい 【意味】 松尾芭蕉とその一派の俳風。言葉の面白みより、言外の余情を重んじ、さび・しおりなどの新しい意意識に基づく作風を起こし、俳諧を芸術的に大成した。 【典拠・出典...
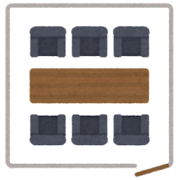 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 昭穆倫序 【読み方】 しょうぼくりんじょ 【意味】 先祖の霊を祀っている宗廟の順番に決まりがあるということ。 【語源・由来】 「昭穆」は、中国の宗廟 (そうびょう) での霊位の席次。太祖を中央とし、向かって...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 畳牀架屋 【読み方】 じょうしょうかおく 【意味】 重複して、無駄なことをすること。床の上に床を張り、屋根の上にさらに屋根を作るという意味。また、真似ばかりしていることもいう。 【語源・由来】 「畳」は、重...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 直指人心 【読み方】 じきしにんしん 【意味】 人の心を直に指差すこと。禅宗の悟りを示した語で、「直指人心見性成仏」といい、坐禅によって自己の本来の心性を見極めれば、それが仏の悟りに他ならないということ。 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 熟読三思 【読み方】 じゅくどくさんし 【意味】 文章を繰り返し読んで、内容を幾度も考えてじっくり思案すること。 【語源・由来】 「熟読」は、繰り返し詳しく読むこと。内容をよく味わって読むこと。「三思」は、...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自立自存 【読み方】 じりつじぞん 【意味】 他人に頼らず、自分の才覚で生活すること。 【語源・由来】 「自立」は、自分で生計を立てること。「自存」は、自ら生存していくこと。 【典拠・出典】 『荀子』脩身 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自性清浄 【読み方】 じしょうしょうじょう 【意味】 心の本性はもともとすべての穢れを離れた清らかなものであるということ。特に人間の心に関していう。 【典拠・出典】 - 自性清浄(じしょうしょうじょう)の使...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 親戚知己 【読み方】 しんせきちき 【意味】 親族と知人のこと。親類、一族に加えて、友人や知り合いなど。 【語源・由来】 「親戚」は、親や身内、血縁や婚姻によってつながっている人。親類。「知己」は、ごく親し...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 審念熟慮 【読み方】 しんねんじゅくりょ 【意味】 自分の思いを明らかにするために、十分に念を入れて考えること。 【語源・由来】 「審念」は、思いを明らかにすること。「熟慮」は、十分に念を入れて考えること。...
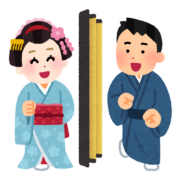 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尋花問柳 【読み方】 じんかもんりゅう 【意味】 花を探したり、柳を問い求めたりして春の景色を楽しむこと。のち転じて、花柳を妓女にたとえて、花柳界に遊ぶことのたとえ。 【語源・由来】 「尋花」は花を探りめで...
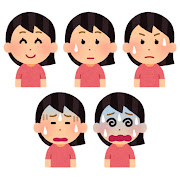 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 辛酸甘苦 【読み方】 しんさんかんく 【意味】 1つらさや楽しみ。 2転じて、経験を積み、世事・人情によく通じていること。 【語源・由来】 「辛酸」は辛さとすっぱさ。転じて、辛く苦しいこと。「甘苦」は、甘さ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 順従謙黙 【読み方】 じゅんじゅうけんもく 【意味】 相手にすなおに従い、控えめであまり自説などを主張しないこと。 【語源・由来】 「順従」は、すなおに従うこと。「謙黙」は、控えめであまりしゃべらない。 【...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 春風秋雨 【読み方】 しゅんぷうしゅうう 【意味】 春の風や秋の雨の意。春の風が吹いたり、秋の雨が降ったりして過ぎていく長い年月。 【典拠・出典】 - 春風秋雨(しゅんぷうしゅうう)の使い方 春風秋雨(しゅ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生死事大 【読み方】 しょうじじだい 【意味】 生き死にの問題は重大であり、それをいかに超越するかが最大事であること。生死を繰り返す、この世の迷いを捨てて悟りを開くことは、いま生きているこの時しかなく、最も...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 正直一徹 【読み方】 しょうじきいってつ 【意味】 うそいつわりを言うことなく、ひとすじに貫き通そうとする性格。 【語源・由来】 「正直」は、うそいつわりを言わないこと。「一徹」は、思いこんだら、あくまで通...
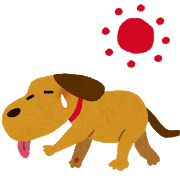 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 焦唇乾舌 【読み方】 しょうしんかんぜつ 【意味】 唇や舌が乾くほどに辛苦すること。大いに焦燥すること。また、大いに言い争うことのたとえ。大いに焦るさまに用いられることもある。 【語源・由来】 唇が焦げ舌が...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生死無常 【読み方】 しょうじむじょう 【意味】 仏語。人生ははかなく、無常であるということ。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・生死不定(しょうじふじょう) 生死無常(しょうじむじょう)の使い方 生死無常...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生死流転 【読み方】 しょうじるてん 【意味】 衆生が煩悩を捨てられず、解脱することもなく、苦しい生死の世界を果てることもなく巡ること。仏教の世界では、人間は生死を繰り返して、六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・...
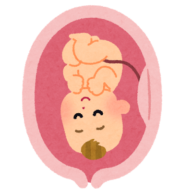 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生死不定 【読み方】 しょうじふじょう 【意味】 いつ生まれて、いつ死ぬのかは、わからないということ。また、仏教のことばとしては、人生は、はかなくむなしいものだという意味。 【語源・由来】 「不定」は、仏教...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 情緒纒綿 【読み方】 じょうしょてんめん 【意味】 情緒が深くて離れがたいさま。 【語源・由来】 「情緒」は、おりにふれて起こる、さまざまな思い・感情・気分。「纒綿」は、心にまとわりついて離れないさま。 【...
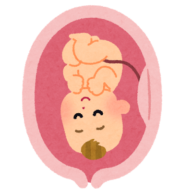 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生生世世 【読み方】 しょうじょうせぜ 【意味】 生まれ変わり死に変わりして限りなく多くの世を経る意。現世も来世も永遠に。いつまでも。 【典拠・出典】 『南史』「王敬則伝」 【類義語】 ・未来永劫(みらいえ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 相如四壁 【読み方】 しょうじょしへき 【意味】 司馬相如は若いころ非常に生活に困り、家はただ四方の壁しかなかった故事。 【語源・由来】 「相如」は漢代の人、司馬相如。賦ふに巧みで、のちに武帝に重用された。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 焦心苦慮 【読み方】 しょうしんくりょ 【意味】 心を痛めて、あれこれ思いをめぐらし悩むこと。 【語源・由来】 「焦心」は気をもむこと。「苦慮」は心を悩まし考えること。 【典拠・出典】 - 焦心苦慮(しょう...
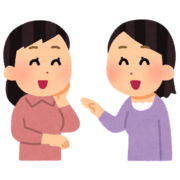 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 饒舌多弁 【読み方】 じょうぜつたべん 【意味】 よくしゃべって口がまわること。必要以上に口数が多いこと。おしゃべり。 【語源・由来】 「饒舌」は、口数が多いこと。多弁なこと。おしゃべり。「多弁」は、口数の...
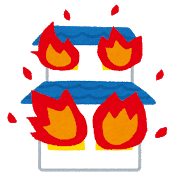 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 焦頭爛額 【読み方】 しょうとうらんがく 【意味】 事前の予防を考えた者を賞さず、末端の些末なものを重視するたとえ。根本を忘れ、些末なことを重視するたとえ。また、処理に手こずりせっぱつまって苦労することのた...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 重厚謹厳 【読み方】 じゅうこうきんげん 【意味】 つつしみ深く、重々しく落ち着いていること。 【語源・由来】 「重厚」は、重々しく落ち着いていること。「謹厳」は、つつしみ深くおごそかなこと。 【典拠・出典...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 受胎告知 【読み方】 じゅたいこくち 【意味】 大天使ガブリエルが、処女マリアにキリストの懐妊を告げたこと。カトリック教会では、これを記念して3月25日を祝日とする。聖告。 【典拠・出典】 - 受胎告知(じ...
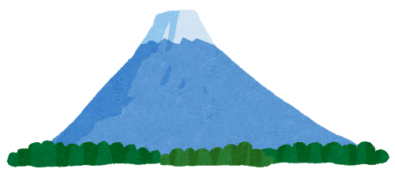 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 至大至高 【読み方】 しだいしこう 【意味】 これ以上ないほど大きく高いこと。 【語源・由来】 「至」は、この上なく、の意味で、「大」「高」をそれぞれに強調する語。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・最上無...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 七花八裂 【読み方】 しちかはちれつ 【意味】 ばらばらに裂け砕けること。 【典拠・出典】 - 七花八裂(しちかはちれつ)の使い方 七花八裂(しちかはちれつ)の例文 健太くんの一言で、クラスは七花八裂となり...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 七十二湾 【読み方】 しちじゅうにわん 【意味】 多くの湾のこと。 【典拠・出典】 - 七十二湾(しちじゅうにわん)の使い方 七十二湾(しちじゅうにわん)の例文 世界には、七十二湾があるが、美しい湾を認定す...
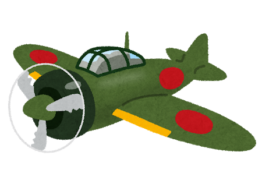 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 七生報国 【読み方】 しちしょうほうこく 【意味】 幾度もこの世に生まれ変わり、国の恩に報いること。国の恩を非常に感じていることのたとえ。 【語源・由来】 「七生」は、仏教で、七たび(幾度も)生まれ変わるこ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 質朴剛健 【読み方】 しつぼくごうけん 【意味】 誠実で飾り気がなく、心身が強くしっかりとしていること。 【語源・由来】 「質朴」は、誠実で飾り気がないこと。「剛健」は、強くしっかりしていること。また勇まし...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 釈近謀遠 【読み方】 しゃくきんぼうえん 【意味】 身近なところや今をおろそかにして、いたずらに遠いところや、はるか将来のことばかり考えること。実際的なことを考えず、迂遠なことをするたとえ。また、身近なとこ...
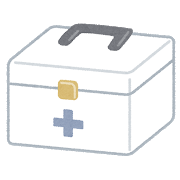 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自家薬籠 【読み方】 じかやくろう 【意味】 自分の薬箱の中にある薬品。自分の思うままにできるもののたとえ。また、自分に手なずけて、思うままにできる人物のたとえ。 【語源・由来】 「自家」は、自分の家。転じ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 時機到来 【読み方】 じきとうらい 【意味】 ちょうどよい機会がめぐってくること。 【語源・由来】 「時期」は、適当な時期、ころあい。「到来」は、やってくること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・好機到来...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 至孝貞淑 【読み方】 しこうていしゅく 【意味】 女性が家庭を守り、この上なく親孝行で、しとやかなこと。 【語源・由来】 「至孝」は、この上なく親孝行なこと。「貞淑」は、女性が正しく節操を守り、しとやかなこ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自己顕示 【読み方】 じこけんじ 【意味】 自分の存在や価値を、ことさら人前で見せつけようとすること。また、自分の成功や功績をひけらかすこと。 【語源・由来】 「顕」は、あきらかにする。「顕示」は、はっきり...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自在不羈 【読み方】 じざいふき 【意味】 自分の思いのままに行動し、誰にも束縛されないこと。 【語源・由来】 「自在」は、自分の思いのままなこと。「不羈」は、束縛されないこと。「羈」は、つなぐ。束縛する。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 時時刻刻 【読み方】 じじこくこく 【意味】 時間の経過に合わせた、その時その時。過ぎていく時間のようす。また、間断なく、次々と物事が経過するさま。だんだんと、次第に。 【語源・由来】 「時時」は、過ぎ行く...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 自主独立 【読み方】 じしゅどくりつ 【意味】 他者からの保護や助力なしに、自分の力で事にあたることや、その精神。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・独立自存(どくりつじそん) ・独立自尊(どくりつじそん)...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 掌中之珠 【読み方】 しょうちゅうのたま 【意味】 自分のいちばん大事なたからもの。手の中に握りしめている大切な珠玉という意味。最愛の妻や子どもをさす場合が多い。 【語源・由来】 「掌中」は、手のひらの中。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 守護聖人 【読み方】 しゅごせいじん 【意味】 カトリック教会で、個人・職業・身分・聖堂・都市・国家などについて、その保護者、代祷 (だいとう) 者として敬われている聖人。 【典拠・出典】 - 守護聖人(し...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 松柏之操 【読み方】 しょうはくのみさお 【意味】 志や主義を曲げずに信念を貫くこと。どんな困難にあっても、節操を変えずに守り通すこと。松や柏(コノテガシワ)は、冬の寒さにあっても、その美しい緑を変えずにい...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秋風蕭条 【読み方】 しゅうふうしょうじょう 【意味】 夏の盛りを過ぎて草木も彼れ、秋風が吹くのもさびしいようす。また、盛んだった勢いが衰えて、ものさびしくなることのたとえ。 【語源・由来】 「秋風」は、秋...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四海天下 【読み方】 しかいてんか 【意味】 全世界。世間の全て。 【語源・由来】 「四海」「天下」ともに、世界・世間の全てをいう。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一天四海(いってんしかい) 四海天下(...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 色相世界 【読み方】 しきそうせかい 【意味】 肉眼で見ることができる世界、この世のこと。 【語源・由来】 「色相」は、仏教で、肉眼で見える姿・形。 【典拠・出典】 - 色相世界(しきそうせかい)の使い方 ...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 借花献仏 【読み方】 しゃっかけんぶつ 【意味】 自分がやらなければいけないことを人に頼って行うこと。 【語源・由来】 仏に花を供えるために、花を人に借りるということから。 【典拠・出典】 『過去現在因果経...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 春蕪秋野 【読み方】 しゅんぶしゅうや 【意味】 春の雑草と秋の野原のこと。転じて、現実離れした風雅な文人をからかう語。 【語源・由来】 「春蕪」は、春の雑草。「秋野」は、秋の野原。 【典拠・出典】 『楚辞...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 十日一水 【読み方】 じゅうじついっすい 【意味】 細かく注意して入念に作品を完成させること。または、その作品のこと。 【語源・由来】 一つの川を描くのに、十日間かけたということから。 【典拠・出典】 杜甫...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秋日荒涼 【読み方】 しゅうじつこうりょう 【意味】 秋のものさびしい風景を表す語。 【語源・由来】 「秋日」は、秋の日。秋の季節。「荒涼」は、景色などの荒れはててものさびしいこと。 【典拠・出典】 「岳鄂...
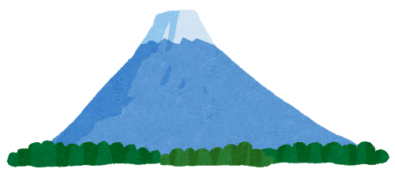 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秀色神采 【読み方】 しゅうしょくしんさい 【意味】 すぐれた風景や様子のこと。 【語源・由来】 「秀色」は、美しい色。「神采」は、精神と風采。また、すぐれた風采。 【典拠・出典】 - 秀色神采(しゅうしょ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秋天一碧 【読み方】 しゅうてんいっぺき 【意味】 秋の空が見渡す限り青一色であること。澄み切った秋の空の形容。 【語源・由来】 「秋天」は、秋の空。「一碧」は、見渡す限り青一色であること。「碧」は、青緑。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秋風冽冽 【読み方】 しゅうふうれつれつ 【意味】 寒々と吹く秋風のように、厳しく冷たいこと。 【語源・由来】 「冽冽」は、風や寒さが厳しいさま。 【典拠・出典】 『文選』左思「雑詩」 【類義語】 ・秋風凛...
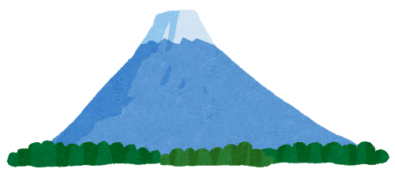 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 秀麗皎潔 【読み方】 しゅうれいこうけつ 【意味】 清くけがれがなく、気品があってうるわしいさま。 【語源・由来】 「秀麗」はすぐれていてうるわしいこと。「皎潔」は、白く清いこと。けがれのないこと。 【典拠...
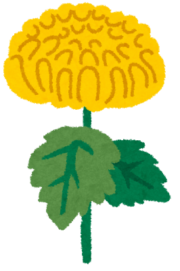 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 春蘭秋菊 【読み方】 しゅんらんしゅうぎく 【意味】 春の蘭と秋の菊。花の時期は異なるものの、どちらもそれぞれに美しいということ。転じて、いずれもすばらしく、優劣を付けがたいことのたとえ。 【典拠・出典】 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 晶瑩玲瓏 【読み方】 しょうえいれいろう 【意味】 透き通り、宝石のように美しいこと。 【語源・由来】 「晶瑩」は透き通っているさま。「玲瓏」は金属や玉などが美しいさえた音をたてるさま。また、音声の澄んで響...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 常山蛇勢 【読み方】 じょうざんのだせい 【意味】 統一がとれていて、欠陥やすきがまったくないこと。どこをとっても整然として、うまく組み立てられている文章や態勢のこと。また、先陣・後陣と右陣・左陣のどれもが...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 常住不滅 【読み方】 じょうじゅうふめつ 【意味】 仏教で、いつも変わらず、滅びることの無いこと。 【典拠・出典】 - 常住不滅(じょうじゅうふめつ)の使い方 常住不滅(じょうじゅうふめつ)の例文 栄枯盛衰...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 蕭条無人 【読み方】 しょうじょうむにん 【意味】 だれもいなくて寂しいさま。 【語源・由来】 「蕭条」は、ものさびしいさま。しめやかなさま。 【典拠・出典】 - 蕭条無人(しょうじょうむにん)の使い方 蕭...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 支葉碩茂 【読み方】 しようせきも 【意味】 支族まで繁栄する。本家はもとより分家まで栄えること。 【語源・由来】 「支葉」は枝葉。幹の対語。「碩」は大きいという意味。 【典拠・出典】 『漢書』「叙伝」 支...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 乗桴浮海 【読み方】 じょうふふかい 【意味】 世を嘆き、逃げ出すこと。 【語源・由来】 いかだに乗って、陸を離れ海へ逃げるという意味から。 【典拠・出典】 『論語』「公冶長」 乗桴浮海(じょうふふかい)の...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 傷風敗俗 【読み方】 しょうふうはいぞく 【意味】 よい風俗を乱して、社会を害すること。 【語源・由来】 「傷」は傷つけ損なう。「敗」はやぶり損なう。「風」「俗」は風俗・風紀の意。 【典拠・出典】 『魏書』...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 初秋涼夕 【読み方】 しょしゅう(の)りょうせき 【意味】 秋のはじめの涼しい夜のこと。 【語源・由来】 「初秋」は、秋のはじめ。はつあき。「涼夕」は涼しい夜。月の美しい、涼しい風が吹く秋の夜。 【典拠・出...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 紫瀾洶湧 【読み方】 しらんきょうゆう 【意味】 波が立ちさわぐさま。 【語源・由来】 「紫瀾」は、初夏、花茎の先に紅紫色の花をつけるラン科の多年草。山地に自生し、観賞用に栽培もされる。朱蘭。「洶湧」は、水...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 晨烟暮靄 【読み方】 しんえんぼあい 【意味】 朝の霧と夕方のもや。 【語源・由来】 晨煙」は朝早くの霧。「暮靄」は日暮れのもや。霧やもやで霞んでいる、早朝や日暮れの風景を表す語。 【典拠・出典】 『文選』...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 深山窮谷 【読み方】 しんざんきゅうこく 【意味】 人が立ち入らない、奥ふかい山とふかい谷。 【語源・由来】 「深山」は、奥ふかい山。おくやま。みやま。「窮谷」はふかい谷。 【典拠・出典】 『春秋左氏伝』「...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人生羈旅 【読み方】 じんせいきりょ 【意味】 人生という旅。人の一生を旅にたとえた言い方。 【語源・由来】 「人生」は、人の一生。「羈旅」は、旅行。 【類義語】 ・人生行路(じんせいこうろ) 人生羈旅(じ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人生朝露 【読み方】 じんせいちょうろ 【意味】 人の一生は、日が出ればすぐに乾いてしまう朝の露のようである。人生はかないことのたとえ。 【語源・由来】 「人生」は、人の一生。「朝露」は、朝の露。 【典拠・...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四則演算 【読み方】 しそくえんざん 【意味】 四則(加法、減法、乗法、除法の四つの計算の総称)を用いてする演算。四則算。加減乗除。 【典拠・出典】 - 四則演算(しそくえんざん)の使い方 四則演算(しそく...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神社仏閣 【読み方】 じんじゃぶっかく 【意味】 神道の神を祀るところや、仏教の寺。 【語源・由来】 「神社」は、もと、神のやしろ、転じて、神道の神を祀るところ。「仏閣」は、寺の建物。寺院。 【典拠・出典】...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 消長盛衰 【読み方】 しょうちょうせいすい 【意味】 栄えることと、衰えること。 【語源・由来】 「消長」は、消えることと生ずること。「盛衰」は、栄えることと衰えること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 消長遷移 【読み方】 しょうちょうせんい 【意味】 衰退と繁栄、情勢がうつりかわること。 【語源・由来】 「消長」は、衰えることと盛んになること。「遷移」は、うつりかわること。 【典拠・出典】 - 消長遷移...
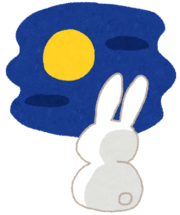 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 嘯風弄月 【読み方】 しょうふうろうげつ 【意味】 自然の風景に親しみ、風流を好んで楽しむこと。 【語源・由来】 「嘯」は口をすぼめて声を長く引いて歌を口ずさむさまで、「嘯風」は風に合わせて歌うこと、「弄月...
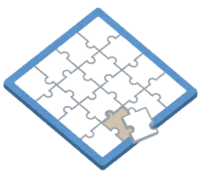 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 続短断長 【読み方】 ぞくたんだんちょう 【意味】 過不足がないよううまい具合に整えること。 【語源・由来】 「続」は継ぐこと。短いものを継ぎ、長いものを断ち切るという意味。 【典拠・出典】 「続短」は『荀...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 辛労辛苦 【読み方】 しんろうしんく 【意味】 辛い苦労のこと。 【語源・由来】 「労苦」を分けて両方に「辛(つらい)」の字を加えた形の語。「辛労」も「辛苦」も非常な苦しみ。 【典拠・出典】 - 【類義語】...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 深厲浅掲 【読み方】 しんれいせんけい 【意味】 その場の状況に応じて適切な処理をすること。 【語源・由来】 「厲」は高くあげるという意味。「掲」は着物のすそをからげること。川が深ければ着物を高くたくしあげ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 蜃楼海市 【読み方】 しんろうかいし 【意味】 現実性に乏しい考えや理論。また、根拠がなくありもしないこと。 【語源・由来】 「蜃楼」「海市」ともに蜃気楼のことで、大気の密度や日光の反射の関係で、遠方の物体...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 深慮遠謀 【読み方】 しんりょえんぼう 【意味】 深く考え将来のことまで見通して計画を立てること。また、その計画。 【典拠・出典】 『文選』賈誼「過秦論」 【類義語】 ・遠謀深慮(えんぼうしんりょ) ・深謀...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 新涼灯火 【読み方】 しんりょうとうか 【意味】 初秋の涼しさは読書にふさわしい。 【語源・由来】 「新涼」は秋の初めの涼しさ。「灯火」は灯火の下で読書をするという意味を略した語。 【典拠・出典】 - 【類...
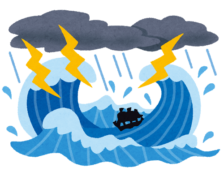 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 迅雷風烈 【読み方】 じんらいふうれつ 【意味】 はげしいかみなりと猛烈な風。 【語源・由来】 「迅雷」は天地をとどろかす激しい雷。「風烈」は烈風に同じ、暴風のこと。 【典拠・出典】 『礼記』「玉藻」 【類...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人面桃花 【読み方】 じんめんとうか 【意味】 美人の顔と桃の花。かつて美人と出会った場所に行っても、今はもう会えないという場合にいう言葉。また、内心で思いながら会うことのできない女性をいう。 【語源・由来...
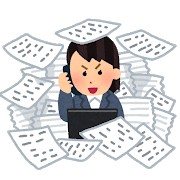 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 晨夜兼道 【読み方】 しんやけんどう 【意味】 昼夜の区別なく急行すること。仕事を急いで行うこと。 【語源・由来】 「晨」は朝、早朝。「晨夜」は朝と夜、朝早くから夜遅くまで。「兼道」は行程を倍にして行く、大...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 瞋目張胆 【読み方】 しんもくちょうたん 【意味】 大いに勇気をうちふるうさま。 【語源・由来】 「瞋目」は目玉をむきだすこと。「張胆」は肝っ玉を大きくふくらますこと。恐ろしい場面に直面しても、目をらんらん...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心満意足 【読み方】 しんまんいそく 【意味】 きわめて満ち足りた気分になること。 【語源・由来】 「心満」、「意足」ともに、心が満ち足りること。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ・欲求不満(よっきゅうふま...
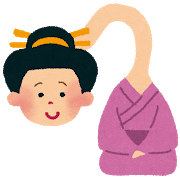 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人面獣身 【読み方】 じんめんじゅうしん 【意味】 顔は人間で身体は獣。妖怪を形容する語。 【語源・由来】 「人面」は人の顔。「獣身」はけだもののからだ。 【典拠・出典】 『史記』「五帝紀・注」 人面獣身(...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 脣亡歯寒 【読み方】 しんぼうしかん 【意味】 密接な関係にあるものの一方が滅びると片方も危うくなること。 【語源・由来】 唇がなくなると歯が寒くなるという意味から。唇がなくなると歯が寒くなるという意味から...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神仏混淆 【読み方】 しんぶつこんこう 【意味】 神道と仏教をうまく融合し調和させること。 【語源・由来】 「混淆」は入り混じること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・神仏習合(しんぶつしゅうごう) ・本...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 振臂一呼 【読み方】 しんぴいっこ 【意味】 つとめてみずから奮起するたとえ。 【語源・由来】 腕を振るい声を上げて自分を奮い立たせることをいう。「臂」はひじ・うで。 【典拠・出典】 『文選』李陵「答蘇武書...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心頭滅却 【読み方】 しんとうめっきゃく 【意味】 心の中の雑念を取り去ること。どんな困難に出会っても心の中から雑念を取り去れば苦しさを感じないという意味。 【語源・由来】 「心頭」はこころ、胸のうちという...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 塵飯塗羹 【読み方】 じんぱんとこう 【意味】 実際になんの役にも立たないもの、とるに足りないもののこと。 【語源・由来】 子供のままごと遊びのちりの飯と泥のあつもの(吸い物)という意味から。 【典拠・出典...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神荼鬱塁 【読み方】 しんとうつりつ 【意味】 門を守る神の名前。 【語源・由来】 「神荼」「鬱塁」は古代中国における兄弟の神の名。ともに門を守る神で、百鬼を支配し、従わないものは捕えて、虎に食わさせたとい...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尽忠報国 【読み方】 じんちゅうほうこく 【意味】 忠義を尽くして国の恩に報いること。 【語源・由来】 「尽忠」は君主や国家に忠誠心を尽くすこと。「報国」は国の恩に報いるという意味。 中国宋の岳飛は忠誠心に...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心地光明 【読み方】 しんちこうめい 【意味】 心が清らかで正しく広いこと。 【語源・由来】 「心地」は心・精神のこと。「光明」は仏の心身から放つ明るい光のこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・公平無私...
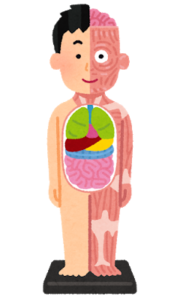 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身体髪膚 【読み方】 しんたいはっぷ 【意味】 からだ全体のこと。 【語源・由来】 からだと髪の毛と皮膚で、からだ全体をいう。父母から受けついだ大切なものの意味がこめられている。 【典拠・出典】 『孝経』「...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 迅速果断 【読み方】 じんそくかだん 【意味】 物事をすばやく決断し、思いきって行うこと。 【語源・由来】 「迅速」は、非常にすばやいこと。「果断」は物事を大胆に実行するという意味。 【典拠・出典】 - 【...
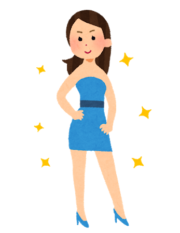 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尽善尽美 【読み方】 じんぜんじんび 【意味】 完璧で欠けるものがないこと。 【語源・由来】 りっぱさと美しさをきわめているという意味から。 【典拠・出典】 『論語』「八佾」 【類義語】 ・完全無欠(かんぜ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神仙思想 【読み方】 しんせんしそう 【意味】 俗世から抜け出して不老・長生の世界に生きようという考え。 【語源・由来】 「神仙」は神通力を持っている仙人。仙人の住む世界を「仙境」と呼び人間の理想郷とした。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 鐘鳴鼎食 【読み方】 しょうめいていしょく 【意味】 富貴の人の生活。 【語源・由来】 「鐘鳴」は鐘を鳴らして時を告げること。「鼎食」はかなえを並べて食事をすること。富貴な家では大勢の人に食事の合図の鐘を鳴...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 生滅滅已 【読み方】 しょうめつめつい 【意味】 生と滅、生きることと死ぬことがなくなって、ともに存しないこと。生滅無常の現世を離れて生死を超越した涅槃に入ること。 【語源・由来】 仏教の語。 【典拠・出典...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 笑面夜叉 【読み方】 しょうめんやしゃ 【意味】 顔は笑っていても心の底に一物あること。陰険な人や裏表のある人にいう。 【語源・由来】 「笑面」は笑顔。「夜叉」は人を害する猛悪な鬼神。 【典拠・出典】 『説...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 将門有将 【読み方】 しょうもんゆうしょう 【意味】 立派な家柄からは必ずすぐれた人材が出るということ。 【語源・由来】 「将門」は代々将軍が出る家柄のこと。「有将」は将軍があらわれるという意味。将軍の家門...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 逍遥自在 【読み方】 しょうようじざい 【意味】 俗事をはなれて気ままに楽しむこと。 【語源・由来】 「逍遥」はぶらつくという意味から、気ままに楽しむこと。「自在」は束縛や支障がなく思いのままであるという意...
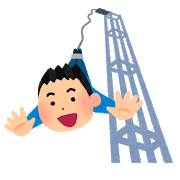 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 従容就義 【読み方】 しょうようしゅうぎ 【意味】 ゆったりと落ち着いて、恐れることなく正義のために身を投げ出すこと。 【語源・由来】 「従容」はゆったりと落ち着いていること。「就義」は身を殺しても正義に従...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 従容不迫 【読み方】 しょうようふはく 【意味】 ゆったりと落ち着いていて、あわてないこと。 【語源・由来】 「従容」はゆったりと落ち着いていること。「不迫」はあわてないという意味。 【典拠・出典】 - 【...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 晨星落落 【読み方】 しんせいらくらく 【意味】 しだいに仲のよい友人がいなくなること。また、友人が年とともにだんだん死んでいなくなること。 【語源・由来】 明け方の空に残っていた星が一つ一つ消えていくとい...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 逍遥法外 【読み方】 しょうようほうがい 【意味】 法律を犯した者が罰を受けないで自由に生活していること。 【語源・由来】 「逍遥」はぶらつく、気ままに歩くこと。「法外」は法律の外という意味。法律の外側を自...
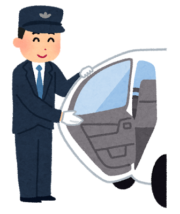 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 乗輿車駕 【読み方】 じょうよしゃが 【意味】 天子の乗る車。天子の使う物。転じて、天子のこと。 【語源・由来】 「乗輿」と「車駕」とも天子の行幸中に乗る車の称。 【典拠・出典】 『独断』「上」 乗輿車駕(...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 薪水之労 【読み方】 しんすいのろう 【意味】 人に仕えて骨身を惜しまず働くこと。また、たきぎをとったり水を汲んだりするというような日常の雑事を指す場合もある。 【語源・由来】 たきぎをとったり水を汲んだり...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 乗輿播越 【読み方】 じょうよはえつ 【意味】 天子が都を落ち延びて他国をさすらうこと。 【語源・由来】 「乗輿」は君主が乗る馬車、天子の乗り物。「播越」は移り逃れること。居場所を失って他国をさまようこと。...
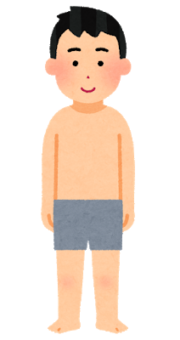 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 常鱗凡介 【読み方】 じょうりんぼんかい 【意味】 ごくありふれた人のたとえ。普通の魚やごくありふれた貝類。 【典拠・出典】 韓愈「応科目時与人書」 常鱗凡介(じょうりんぼんかい)の使い方 常...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 上漏下湿 【読み方】 じょうろうかしゅう 【意味】 貧乏なあばら家のさま。屋根からは雨が漏り、床からは湿気が上がってくるという意味。 【典拠・出典】 『荘子』「譲王」 【類義語】 ・上漏旁風(じょうろうぼう...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 杵臼之交 【読み方】 しょきゅうのまじわり 【意味】 身分にこだわらない交際。主人と使用人との身分の違いを超えた交際。 【語源・由来】 「杵臼」はきねとうす。後漢の公孫穆が学費がなくて呉祐の家に雇われて臼つ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 嗇夫利口 【読み方】 しょくふりこう 【意味】 身分は低いが、口が達者な男のこと。 【語源・由来】 「嗇夫」は下級役人のこと。張釈之が、前漢の文帝の供をして虎圏(上林苑の中の動物園)に登ったとき、文帝が帳簿...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 諸子百家 【読み方】 しょしひゃっか 【意味】 中国の戦国時代 (前 403~221) に輩出した多数の思想家の総称。「子」とは先生,「家」とは学派のことである。『漢書』によれば,189家があげられており,...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 処女脱兎 【読み方】 しょじょだっと 【意味】 始めはたいしたことのないように見せかけて、後には見違えるほどの力を発揮するたとえ。始めは少女のようにしとやかに弱々しくみせかけて相手を油断させ、後にはうさぎの...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 助長抜苗 【読み方】 じょちょうばつびょう 【意味】 成長を助けようとして力をかすことがかえって成長を妨げること。 【語源・由来】 宋の農夫が稲の成長を助けようとして苗をひっぱたら、かえって苗が枯れてしまっ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 初転法輪 【読み方】 しょてんぼうりん 【意味】 釈尊が悟りを開いたのち、初めて行った鹿野苑の説法のこと。 【語源・由来】 「転法輪」は仏の教えを説くこと。 【典拠・出典】 - 初転法輪(しょてんぼうりん)...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 諸法無我 【読み方】 しょほうむが 【意味】 いかなる存在も不変の本質を有しないという仏教の根本思想。宇宙間に存在する有形・無形のすべての事物や現象は我(生滅変化を離れた永遠不滅の存在とされるもの)ではない...
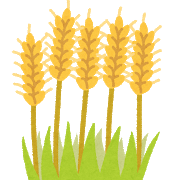 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 黍離之歎 【読み方】 しょりのたん 【意味】 祖国が滅亡したことを嘆くこと。東周の大夫が西周の宮殿に黍が生い茂っているのを見て嘆いた「黍離」という詩から。 【典拠・出典】 『詩経』「王風・黍離」 【類義語】...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 芝蘭玉樹 【読み方】 しらんぎょくじゅ 【意味】 すぐれた人材。すぐれた子弟。また、すぐれた人材を輩出すること。 【語源・由来】 「芝」は瑞兆とされた霊芝。「蘭」はふじばかまで香草。「玉樹」は美しい木。 【...
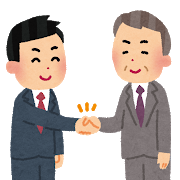 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 芝蘭結契 【読み方】 しらんけっけい 【意味】 美しくうるわしい交際。君子や善人などすぐれた人の交際にいう。 【語源・由来】 「芝」は霊芝。「蘭」はふじばかま。ともに香気高い草で、君子や善人にたとえる。 【...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 芝蘭之室 【読み方】 しらんのしつ 【意味】 善人(良き友)のたとえ。 【語源・由来】 「芝」は霊芝。「蘭」はふじばかま。ともに香草で、善人にたとえる。 【典拠・出典】 『孔子家語』「六本」 芝蘭之室(しら...
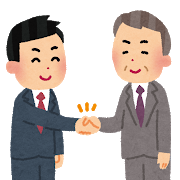 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 芝蘭之交 【読み方】 しらんのまじわり 【意味】 美しくうるわしい交際。君子や善人などすぐれた人の交際にいう。 【語源・由来】 「芝」は霊芝。「蘭」はふじばかま。ともに香気高い草で、君子や善人にたとえる。 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 至理名言 【読み方】 しりめいげん 【意味】 きわめて道理にかなったすぐれた言葉のこと。 【語源・由来】 「至理」はきわめて正しい道理のこと。「名言」はすぐれた言葉という意味。 【典拠・出典】 - 至理名言...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 事理明白 【読み方】 じりめいはく 【意味】 物事の道理・筋道がきわめてはっきりしている。物事の道理が明白であるという意味。 【語源・由来】 仏教語で「事理」は本体と現象という意味。物事の道理がきちんと通っ...
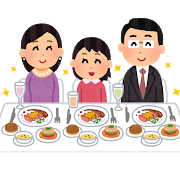 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 持粱歯肥 【読み方】 じりょうしひ 【意味】 ご馳走を食べること。また、ご馳走を食べられる身分になること。上等な食物を盛った器を手に持ち肥えた肉を食べるという意味。 【語源・由来】 「持粱」は上等な食物の盛...
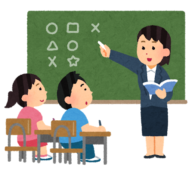 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 緇林杏壇 【読み方】 しりんきょうだん 【意味】 学問所、講堂のこと。 【語源・由来】 「緇林」は樹木がおい茂った林のこと。孔子が黒いとばりのような緇帷の林に遊び、杏の花が咲く木の下の土の壇(一段高いところ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 眥裂髪指 【読み方】 しれつはっし 【意味】 激しくいきどおるさま。まなじりが裂け髪が天をつくという意味。 【語源・由来】 「眥裂」は怒りで眼を大きく見開くこと。「髪指」は怒りで髪の毛が逆立って天を突き上げ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 指鹿為馬 【読み方】 しろくいば 【意味】 道理の通らないことを無理に押し通すこと。また、間違いを認めず押し通すこと。鹿を指差し馬とするという意味。 【語源・由来】 秦の趙高は始皇帝の死後、権力を独占しよう...
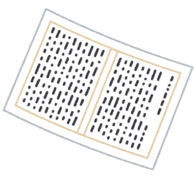 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 四六駢儷 【読み方】 しろくべんれい 【意味】 四字句と六字句の対句を多く用いた修辞的な文体。四六駢儷文のこと。 【語源・由来】 「駢」は馬を二頭並べて車につなぐこと。「儷」は一対になって並ぶことの意から。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人為淘汰 【読み方】 じんいとうた 【意味】 動植物の遺伝・突然変異を利用して人工的に優秀な新種を作ること。バイオテクノロジー。動植物は自然淘汰が自然の法則であるが、バイオテクノロジーは人為的に淘汰を行う。...
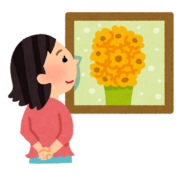 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神韻縹渺 【読み方】 しんいんひょうびょう 【意味】 芸術作品のもつたいそう奥深くすぐれた趣のこと。 【語源・由来】 「神韻」は人間わざとは思えないようなすぐれた趣のこと。「縹渺」は遠くはるかという意味。 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心願成就 【読み方】 しんがんじょうじゅ 【意味】 神仏などに心から念じていると願いはかなえられる。 【語源・由来】 「心願」は神仏などに心の中でかける願(がん)。心からの願い。 【典拠・出典】 - 心願成...
 「こだわらない」の四字熟語一覧
「こだわらない」の四字熟語一覧【四字熟語】 人間青山 【読み方】 じんかんせいざん 【意味】 世の中は広いので、志を貫くには故郷を離れてどこに死に場所を求めようともかまわないということ。 【語源・由来】 「人間」は世の中。「青山」は墓のある山。また骨...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心悸亢進 【読み方】 しんきこうしん 【意味】 心臓の鼓動が高まり、どきどきと激しく打つこと。運動の後や感情の動きにより、動悸が高まること。 【語源・由来】 「心悸」は心臓の鼓動、動悸。「亢進」はたかぶるこ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 新鬼故鬼 【読み方】 しんきこき 【意味】 新たに死んで霊魂となったものと昔からの霊魂。 【語源・由来】 「鬼」は霊魂という意味。 【典拠・出典】 『春秋左氏伝』「文公二年」 新鬼故鬼(しんきこき)の使い方...
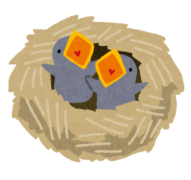 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 晨去暮来 【読み方】 しんきょぼらい 【意味】 朝方に去って夕暮れにもどる。 【語源・由来】 野鳥が朝に巣を飛び立ち餌を求め、夕暮れに巣にもどることをいう。「晨」は朝、早朝の意味。 【典拠・出典】 『漢書』...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 辛苦遭逢 【読み方】 しんくそうほう 【意味】 ひどい困難や苦しみにであうこと。 【語源・由来】 「辛苦」はからさと苦さ。転じて、つらく苦しいこと。 【典拠・出典】 文天祥「過零丁洋」 辛苦遭逢(しんくそう...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身軽言微 【読み方】 しんけいげんび 【意味】 身分が低くて、言うことが人に重んじられないこと。 【語源・由来】 「微」は卑しいという意味。身分が卑しくて、言葉が軽んじられるという意味。 【典拠・出典】 『...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人権蹂躙 【読み方】 じんけんじゅうりん 【意味】 国家が国民の基本的人権を侵害すること。また、強い立場の者が弱い立場の者の人権を侵犯すること。「蹂躙」は踏みにじること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身言書判 【読み方】 しんげんしょはん 【意味】 人物を重用するときの基準とするもの。容姿と言葉と文字の文章。唐代の官吏登用試験でも人物鑑定の基準。 【典拠・出典】 『新唐書』「選挙志」 身言書判(しんげん...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心慌意乱 【読み方】 しんこういらん 【意味】 あわてふためいて何がなんだかわからなくなる。 【語源・由来】 「心慌」はあせってあわてふためくこと。「意乱」は精神が錯乱すること。 【典拠・出典】 - 【類義...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 真人大観 【読み方】 しんじんたいかん 【意味】 道理を極めた人は、物事の全体を見通すので判断を誤らないということ。 【語源・由来】 「真人」は物事に深く通じて道理をわきまえた人、「大観」は大局から判断する...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人心収攬 【読み方】 じんしんしゅうらん 【意味】 多くの人の気持ちをうまくつかんでまとめること。また、人々の信頼を得ること。 【語源・由来】 「人心」は多くの人の心のこと、「攬」は「持」と同じで、「収攬」...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 心神耗弱 【読み方】 しんしんこうじゃく 【意味】 精神が衰弱して判断力が乏しくなり正常な行動ができないこと。心神喪失よりは軽い状態。 【語源・由来】 「心神」は、心・精神。「耗弱」は、すり減いって弱くなる...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人心洶洶 【読み方】 じんしんきょうきょう 【意味】 世界の人々の心が騒ぎ動揺すること。 【語源・由来】 「人心」は多くの人の心のこと、「洶洶」はどよめき騒ぐさま。 【典拠・出典】 『唐書』「陸贄伝」 人心...
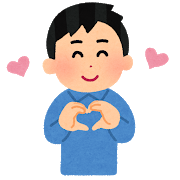 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 身心一如 【読み方】 しんしんいちにょ 【意味】 仏教で、肉体と精神は分けることができないもので、一つのものの両面であるということ。 【語源・由来】 「身心」はからだと心のこと。「一如」は真理の現れ方は違っ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 薪尽火滅 【読み方】 しんじんかめつ 【意味】 人が死ぬこと。 【語源・由来】 「薪尽」はたきぎが尽きること。「火滅」は火が消えること。仏教で、釈迦の入滅のことをいった語で、転じて、人の死をいう。 【典拠・...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心織筆耕 【読み方】 しんしょくひっこう 【意味】 文筆で生活すること。 【語源・由来】 心で機を織り、筆で田を耕して生活するという意味。唐の王勃が人に頼まれて文を作り、謝礼の金帛で車がいっぱいになったこと...
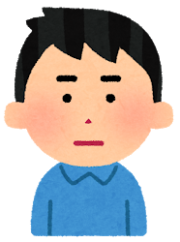 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神色自若 【読み方】 しんしょくじじゃく 【意味】 落ち着いて顔色一つ変えないさま。 【語源・由来】 「神色」は精神と顔色。「自若」は物事にあわてず落ち着いているさま。 【典拠・出典】 『晋書』「王戎伝」 ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 参商之隔 【読み方】 しんしょうのへだて 【意味】 遠く離れて会うことのないたとえ。また夫婦や兄弟の別離や仲たがいのたとえ。 【語源・由来】 杜甫の詩より。「参」は参星(しんせい)(オリオン座の星)。「商」...
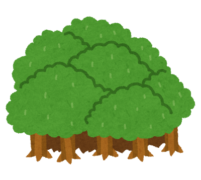 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尋章摘句 【読み方】 じんしょうてきく 【意味】 こまかいところに気をとられ、大局的なものの見方ができないこと。 【語源・由来】 「尋章」は一章のことを考えるという意味。「摘句」は一句を取り出すこと。文章や...
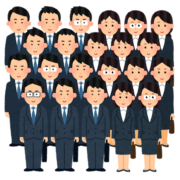 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 尋常一様 【読み方】 じんじょういちよう 【意味】 他と変わりなく、ごくあたりまえなさま。 【語源・由来】 「尋常」はあたりまえ、「一様」は行動・状態などが他と変わらないこと。 【典拠・出典】 - 尋常一様...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 浸潤之譖 【読み方】 しんじゅんのそしり 【意味】 水が次第に物にしみこむように、中傷の言葉が徐々に深く信じられるようになること。 【語源・由来】 「譖」は悪口、讒言という意味。 【典拠・出典】 『論語』「...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人主逆鱗 【読み方】 じんしゅげきりん 【意味】 君主や権力者のひどい怒りを買うことのたとえ。 【語源・由来】 「人主」は君主。「逆鱗」は触れると怒り、人を食いころすという竜ののどにさかさまに生えているうろ...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 仁者楽山 【読み方】 じんしゃらくざん 【意味】 どっしりと安定して動かない山を愛するということ。 【語源由来】 仁徳者は安らかにゆったりとして心が動くことがないから。 【典拠・出典】 『論語』「雍也」 【...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 仁者無敵 【読み方】 じんしゃむてき 【意味】 仁徳者には天下に敵対する者のないことをいう。 【語源・由来】 仁徳者が為政者の位にあれば仁愛の政治を施し、人民を分け隔てることなく愛することからいう。 【典拠...
 「いつも」の四字熟語一覧
「いつも」の四字熟語一覧【四字熟語】 仁者不憂 【読み方】 じんしゃふゆう 【意味】 仁徳者は常に正しい道を行くので悩むことがない。 【語源・由来】 「知者は惑わず、仁者は憂えず、勇者は懼れず」による。仁徳者は常に道理に従い自分にやましいことが...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 斟酌折衷 【読み方】 しんしゃくせっちゅう 【意味】 事情をくみとってほどよくはからい、その中をとること。 【語源・由来】 「斟酌」は事情をくみとりはからうこと。「折衷」は過不足を調節して、その中をとるとい...
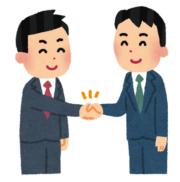 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 脣歯輔車 【読み方】 しんしほしゃ 【意味】 お互いに助け合う密接な関係。 【語源・由来】 「輔車」は車のそえ木と荷台。また、頬骨(輔)と下顎の骨(車)という説もある。「脣歯」は唇と歯。これらのように一方が...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人事天命 【読み方】 じんじてんめい 【意味】 人間として最善の努力を尽くして、結果は静かに運命にまかせること。 【語源・由来】 「人事」は人間のなしうる事柄。 「天命」は自然に身に備わった運命という意味。...
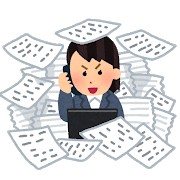 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 進取果敢 【読み方】 しんしゅかかん 【意味】 物事に積極的に取り組み、決断力に富んでいること。 【語源・由来】 「進取」は物事に進んで取り組むこと。「果敢」は決断力に富んでいるということ。 【典拠・出典】...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 参差錯落 【読み方】 しんしさくらく 【意味】 ふぞろいな物が入り混じっている様。 【語源・由来】 「参差」は長短ふぞろいのさま。「錯落」は入り混じること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・参差不斉(しん...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 慎始敬終 【読み方】 しんしけいしゅう 【意味】 物事を始めから終わりまで気を引き締めてやりとおすこと。また、物事をするには始めと終わりが肝心だということ。 【語源・由来】 「慎」も「敬」も注意深く行う意。...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神算鬼謀 【読み方】 しんさんきぼう 【意味】 人間離れした巧みな計略のこと。 【語源・由来】 「算」と「謀」はともに、はかりごとのこと。神や鬼がめぐらしたはかりごとという意味から。 【典拠・出典】 - 【...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神采英抜 【読み方】 しんさいえいばつ 【意味】 心も風采も人にぬきん出てすぐれていること。 【語源・由来】 「神采」は精神と風采のこと。 【典拠・出典】 『陳書』「江総伝」 神采英抜(しんさいえいばつ)の...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 深根固柢 【読み方】 しんこんこてい 【意味】 物事の基礎をしっかり固めること。 【語源・由来】 「根」「柢」はともに木の根のことで、物事の基本・基礎のたとえ。木の根を深く強固なものにするという意味から。 ...
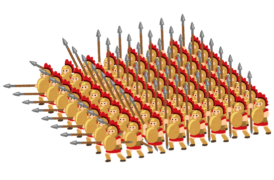 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人口稠密 【読み方】 じんこうちゅうみつ 【意味】 人や家がびっしりとすきまなく集まっていること。 【語源・由来】 「稠密」は込み合っていること。密集していること。 【典拠・出典】 - 人口稠密(じんこうち...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 心広体胖 【読み方】 しんこうたいはん 【意味】 心が広く穏やかであれば、外見上の体もゆったりと落ち着いて見えるということ。 【語源・由来】 「心広」は心が広く大きいこと。「胖」はゆたか・のびやかという意味...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 深溝高塁 【読み方】 しんこうこうるい 【意味】 深い掘割と高いとりで。堅固な城塞。また、守りの堅牢なこと。 【語源・由来】 「溝」はみぞで、ここではお堀という意味。「塁」は土石を重ねて作った小城。 【典拠...
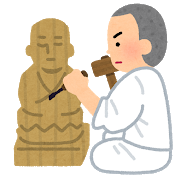 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 神工鬼斧 【読み方】 しんこうきふ 【意味】 人間わざとは思えないほどすぐれた細工や作品のこと。 【語源・由来】 「神工」は神の細工のこと。「鬼斧」は鬼が斧をふるった細工という意味。神わざ・名人芸のことをい...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 人口膾炙 【読み方】 じんこうかいしゃ 【意味】 広く世間の評判となり、もてはやされること。 【語源・由来】 「膾」はなますで、生の肉を細かく刻んだもの。「炙」はあぶり肉のこと。どちらも誰の口にも合って、好...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 漿酒霍肉 【読み方】 しょうしゅかくにく 【意味】 非常にぜいたくなことのたとえ。酒を水のように肉を豆の葉のようにみるという意味。 【語源・由来】 「漿」は沸かして冷ました水。また、こんず(酢の一種)。「霍...
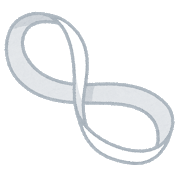 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 常住不断 【読み方】 じょうじゅうふだん 【意味】 ずっと続いていて絶えないこと。 【語源・由来】 「常住」は仏教語で、過去・現在・未来にわたって生滅変化することなく、常に存在するという意味。「不断」も絶え...
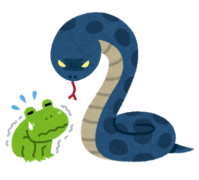 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 銷鑠縮栗 【読み方】 しょうしゃくしゅくりつ 【意味】 意気が阻喪して縮み上がっておそれること。 【語源・由来】 「銷鑠」はとろけるという意味から、意気消沈すること。「縮栗」は縮み上がっておそれること。「栗...
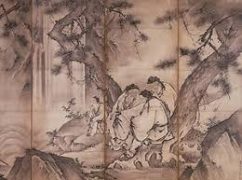 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 商山四皓 【読み方】 しょうざんのしこう 【意味】 商山に隠れた四人の老人。 【語源・由来】 「商山」は陝西省商県にある山の名。「四皓」はあごひげと眉がみな白かったので、「皓」(白いという意味)と呼ばれた四...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 小国寡民 【読み方】 しょうこくかみん 【意味】 国土が小さくて、人口が少ないこと。 【語源・由来】 「寡民」は人民が少ないこと。老子が唱えた国家の理想像として有名な言葉。 【典拠・出典】 『老子』「八○章...
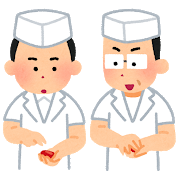 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 上行下効 【読み方】 じょうこうかこう 【意味】 上の者がすると、下の者がそれを見習うこと。 【語源・由来】 「効」はならう・まねるという意味。 【典拠・出典】 『旧唐書』「賈曾伝」 【類義語】 ・上行下従...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 笙磬同音 【読み方】 しょうけいどうおん 【意味】 人が心を合わせて仲良くするたとえ。各楽器の音が調和するという意味。 【語源・由来】 「笙」は管楽器の名。「磬」は打楽器の名で、石で作る。「同音」は多くの楽...
 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 上求菩提 【読み方】 じょうぐぼだい 【意味】 菩薩が上に向かって悟りの道を求めること。菩薩が行う自利の行。 【語源・由来】 「上求」は上に求めること。「菩提」は煩悩を断ち切って正しい知恵を得、悟りを開くこ...
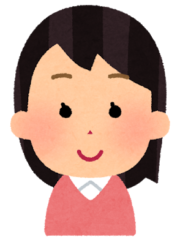 「し」で始まる四字熟語
「し」で始まる四字熟語【四字熟語】 小家碧玉 【読み方】 しょうかへきぎょく 【意味】 貧しい家庭に育った美しい娘のこと。また、とるにたらないような家の大事な宝物のこと。 【語源・由来】 「小家」は貧しい家、また、自身の家の謙称。「碧玉」は青...