冠婚葬祭【かんこんそうさい】の意味と使い方や例文(出典・語源由来)
【四字熟語】 冠婚葬祭 【読み方】 かんこんそうさい 【意味】 慣習的に定まった慶弔の儀式の総称。 【語源由来】 「冠」は元服・成人式、「婚」は婚礼、「葬」は葬儀、「祭」は祖先の祭礼。 【典拠・出典】 『礼記』礼運 冠婚...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 冠婚葬祭 【読み方】 かんこんそうさい 【意味】 慣習的に定まった慶弔の儀式の総称。 【語源由来】 「冠」は元服・成人式、「婚」は婚礼、「葬」は葬儀、「祭」は祖先の祭礼。 【典拠・出典】 『礼記』礼運 冠婚...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 過剰防衛 【読み方】 かじょうぼうえい 【意味】 自分の身を守るために、正当として許される一定の限度を超えて反撃すること。 【語源由来】 「過剰」は必要以上に多くあること。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 回光返照 【読み方】 かいこうへんしょう 【意味】 自己を振り返り、反省して修行すること。死に際に息を吹き返すこと。 【語源由来】 「返照」は、光の照りかえすこと。夕日の輝き。夕照。ゆうひ。(仏教で)内省す...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 懐才不遇 【読み方】 かいさいふぐう 【意味】 才能がありながら、世に認められないこと。運がわるく、地位や境遇に恵まれないこと。 【語源由来】 「不遇」は、時に遇わないこと。運がわるく才能にふさわしい地位や...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 冠履顛倒 【読み方】 かんりてんとう 【意味】 上下の順序が逆なこと。また、そのさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・本末転倒(ほんまつてんとう) ・冠履倒易(かんりとうえき) 冠履顛倒(かんりてんとう...
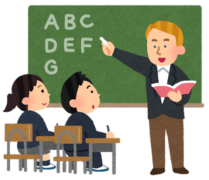 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 簡明率直 【読み方】 かんめいそっちょく 【意味】 飾りけがなく、簡潔でわかりやすいこと。 【語源由来】 「簡明」は、簡潔でわかりやすいこと。簡単明瞭。「率直」は、飾りけがなくありのままなこと。素直で飾りけ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 感孚風動 【読み方】 かんぷふうどう 【意味】 人の心を感動させ、感化すること。 【語源由来】 「感孚」は、相手のまごころを感動させること。「孚」は、まこと。「風動」は、風が草木を動かすようになびき動かすこ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 唐草模様 【読み方】 からくさもよう 【意味】 織物・染物・蒔絵などで、蔓草が絡み這う様子を図案化したもの。 【語源由来】 「唐草」はウマゴヤシの別称。 【典拠・出典】 - 唐草模様(からくさもよう)の使い...
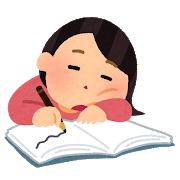 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寡聞浅学 【読み方】 かぶんせんがく 【意味】 学問や知識が浅く、経験が少ないこと。 【語源由来】 「寡聞」は、見聞が狭く浅いこと。謙遜していうときの語。「浅学」は、学問や知識が未熟なこと。また、その人。自...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家内狼藉 【読み方】 かないろうぜき 【意味】 家の中がひどく散らかって乱雑であること。 【語源由来】 「狼藉」は乱れていて無秩序なこと。 【典拠・出典】 - 家内狼藉(かないろうぜき)の使い方 家内狼藉(...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家庭円満 【読み方】 かていえんまん 【意味】 家族が仲よく暮らすこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・家族団欒(かぞくだんらん) ・家内安全(かないあんぜん) 家庭円満(かていえんまん)の使い方 家庭...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 闊達豪放 【読み方】 かったつごうほう 【意味】 気持が大きく快活で、大らかな性格。また、堂々としていて力強いさま。 【語源由来】 「豁達」は心が広く細かいことにこだわらないこと。「豪放」は小さなことにこだ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 活火激発 【読み方】 かっかげきはつ 【意味】 火山が爆発するように炎が激しくわきおこること。 【語源由来】 「活火」は火が激しく燃えている様子。「激発」は爆発すること。 【典拠・出典】 - 活火激発(かっ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 干将莫邪 【読み方】 かんしょうばくや 【意味】 名剣のこと。 【故事】 「呉越春秋」闔閭内伝の故事から。中国の呉の刀工干将が呉王の命で剣を作るとき、妻莫邪の髪を炉の中に入れて初めて会心の作を得た。その二振...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 観測気球 【読み方】 かんそくききゅう 【意味】 1 高空の大気の状態を調べるために打ち上げる気球。 2 敵地の偵察や砲弾の着弾状態などを観測するために上げる気球。 3 世論や相手の反応などを探るために、わ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 加減乗除 【読み方】 かげんじょうじょ 【意味】 四種類の基本的な計算方法を総称した呼び名。足し算、引き算、かけ算、割り算。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・四則演算(しぞくえんざん) 加減乗除(かげんじ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 回天動地 【読み方】 かいてんどうち 【意味】 天を驚かし、地を動かすこと。転じて、時勢を一変させ、世の中をひどく驚かす出来事、驚くべき様子。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・驚天動地(きょうてんどうち)...
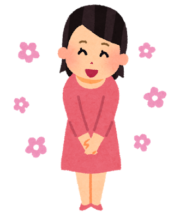 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 感恩報謝 【読み方】 かんおんほうしゃ 【意味】 恩を感じた人に最高の礼をもって報いるということ。「感謝」の語源になった言葉。 【語源・由来】 「感恩」とは、うけた恩をありがたく思うこと。「報謝」とは、恩に...
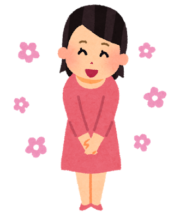 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 感恩戴徳 【読み方】 かんおんたいとく 【意味】 心からありがたく思って感謝感激するさま。恩に着て敬愛の念を持つこと。 【典拠・出典】 - 感恩戴徳(かんおんたいとく)の使い方 感恩戴徳(かんおんたいとく)...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 呵呵大笑 【読み方】 かかたいしょう 【意味】 大声をあげて笑うこと。 【語源・由来】 「呵呵」は、からからと大声で笑うさまをいう。 【典拠・出典】 『景徳伝灯録』「八」 【類義語】 ・破顔大笑(はがんたい...
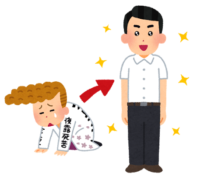 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 頑廉懦立 【読み方】 がんれんだりつ 【意味】 高潔な人格に感化されて、よい方向に向かうこと。「頑」は欲が深いこと。「廉」は心にけがれがないこと。欲が深いものも改心して清廉な人となり、意気地がないものも奮起...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 冠履倒易 【読み方】 かんりとうえき 【意味】 人の地位や立場、また、物事の価値が上下逆さまで秩序が乱れているさま。本来頭にかぶるべき冠を足につけ、足にはくべき履を頭にかぶる意から。「倒」は逆さまになる意。...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 感奮興起 【読み方】 かんぷんこうき 【意味】 心に深く感じて奮い立つこと。 【語源由来】 「感奮」は心を揺り動かされて奮い立つこと。「興起」は奮いおこること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・一念発起(...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 勧百諷一 【読み方】 かんぴゃくふういつ 【意味】 益よりも害の多いこと。百の華美を勧めて一の節約を遠回しにいさめる意で、無用のことばかり多くて、役に立つことが少ない意。「百を勧めて一を諷す」とも読む。 【...
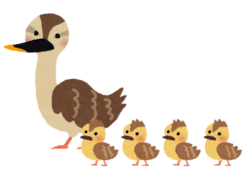 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 銜尾相随 【読み方】 かんびそうずい 【意味】 車や動物などが切れ目なく連なって進むこと。「銜」は口にくわえる意で、「銜尾」は前を行く馬の尾をあとの馬がくわえること。「相随」はつきしたがって進む意。「銜尾相...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 汗馬之労 【読み方】 かんばのろう 【意味】 物事を成功させるためにあれこれ奔走する労苦のたとえ。 【語源・由来】 「汗馬」は、馬に汗をかかせることで、戦功を得るために戦場を駆けめぐること。また、それによっ...
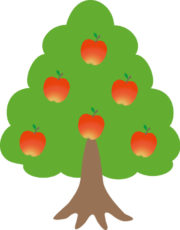 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 甘棠之愛 【読み方】 かんとうのあい 【意味】 人民の善政を行う人に対する思慕の情が深いこと。「甘棠」はからなし、こりんごの木。 【語源・由来】 人民が周の召公の善政に感じて、召公がその下で休んだ甘棠の木を...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 管中窺豹 【読み方】 かんちゅうきひょう 【意味】 見識の非常に狭いたとえ。管の穴から豹を見る意。一つの斑紋しか見えないことからいう。「管中より豹を窺う」とも読む。 【典拠・出典】 『晋書』「王献之伝」 【...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 奸智術数 【読み方】 かんちじゅっすう 【意味】 よこしまな知恵と計略のこと。 【語源由来】 「奸智」とは、悪賢い知恵、悪知恵のこと。「術数」とは、はかりごと、たくらみのこと。 【典拠・出典】 - 【類義語...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 邯鄲之歩 【読み方】 かんたんのほ 【意味】 本来の自分を忘れて、やたらと他人の真似をしたため、両方ともうまくいかなくなってしまうことのたとえ。 【語源・由来】 「邯鄲」は、中国戦国時代、趙の都となった都市...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 干戚羽旄 【読み方】 かんせきうぼう 【意味】 武の舞と文の舞のこと。夏の禹王が始めた舞楽。 【語源・由来】 「干戚」はたてとまさかりを持って舞う、武の舞のこと。「羽旄」は雉の羽と旄牛の尾で作った飾りを持っ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 坎井之蛙 【読み方】 かんせいのあ 【意味】 広い世間を知らないで、自分だけの狭い見識にとらわれていること。「井の中の蛙、大海を知らず」の慣用句で知られている。 【語源・由来】 「坎井」は、くずれた井戸のこ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 甘井先竭 【読み方】 かんせいせんけつ 【意味】 才能がある者ほど、その才能が早く衰えやすいことのたとえ。また、才能を見せびらかす者は、他の者よりも先に災難に遭うということのたとえ。 【語源・由来】 「甘井...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 玩人喪徳 【読み方】 がんじんそうとく 【意味】 人を軽く見てあなどると、自分の徳を失うことになるということ。「人を玩べば、徳を喪う」とも読む。 【語源・由来】 「玩人」は人をもてあそびあなどること。 【典...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 顔常山舌 【読み方】 がんじょうざんのした 【意味】 過酷な刑を受けてもなお、主君や国家に忠節を尽くすこと。「顔常山」は人の名で、顔杲卿のこと。 【語源・由来】 中国の唐の常山の太守顔杲卿は、玄宗の忠臣であ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含沙射影 【読み方】 がんしゃせきえい 【意味】 陰険な方法で人を害すること。 【語源・由来】 「含沙」は、中国南部にすむいさご虫という怪虫で、砂を口に含んで人の影に吹きつけると、その人は高熱を出して死ぬと...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 岸芷汀蘭 【読み方】 がんしていらん 【意味】 水辺で、草花が香り高く咲き乱れている様子。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・郁郁青青(いくいくせいせい) 岸芷汀蘭(がんしていらん)の使い方 岸芷汀蘭(がん...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寒山拾得 【読み方】 かんざんじっとく 【意味】 中国唐代中期の寒山と拾得の二人の高僧。二人とも奇行が多く、詩人としても有名だが、その実在すら疑われることもある。拾得は天台山国清寺の食事係をしていたが、近く...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 翫歳愒日 【読み方】 がんさいかいじつ 【意味】 怠惰に過ごし、月日を無駄にすること。「歳を翫び日を愒る」とも読む。 【語源・由来】 「翫」はもてあそぶこと。「愒」はむさぼること。 【典拠・出典】 『春秋左...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寒江独釣 【読み方】 かんこうどくちょう 【意味】 冬の川で雪の中一人で釣りをする人の姿。もと柳宗元の「江雪」の中でうたわれたもので、のち多くの画題となった。 【典拠・出典】 柳宗元「江雪」 寒江独釣(かん...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 歓欣鼓舞 【読み方】 かんきんこぶ 【意味】 大喜びするたとえ。喜びきわまって手を打って舞う意。 【語源由来】 「鼓舞」は鼓を打って舞うこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・歓喜抃舞(かんきべんぶ) ・...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 管窺蠡測 【読み方】 かんきれいそく 【意味】 非常に見識が狭いこと。 【語源・由来】 「管窺」は管を通して天を見ること。「蠡測」はほら貝(一説にひさご)で海の水を測ることで、きわめて狭い見識で大事を測るこ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 歓喜抃舞 【読み方】 かんきべんぶ 【意味】 大喜びするたとえ。喜びきわまって手を打って舞う意。 【語源・由来】 「抃舞」は手を打って喜び舞うこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・歓欣鼓舞(かんきんこぶ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 官官接待 【読み方】 かんかんせったい 【意味】 地方自治体の職員が中央官僚を公金(税金)を使ってもてなすこと。「官官」は役人どうし、公務員どうしの意。 【語源由来】 地方の公務員が中央の役人を接待して、...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寒巌枯木 【読み方】 かんがんこぼく 【意味】 世俗を超越して無心の境地にあること。枯れた木と冷たい岩のことで、禅宗では「枯木」「寒巖」を情念を滅却するもののたとえとしていう。 【典拠・出典】 - 【類義語...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 緩歌慢舞 【読み方】 かんかまんぶ 【意味】 ゆるやかに歌い、ゆるやかに舞うこと。 【典拠・出典】 白居易「長恨歌」 緩歌慢舞(かんかまんぶ)の使い方 緩歌慢舞(かんかまんぶ)の例文 うららかな午後のひと時...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 頷下之珠 【読み方】 がんかのしゅ 【意味】 めったに手に入れることができない貴重なもののこと。 【語源由来】 「頷下」はあごの下。「珠」は宝石の意。黒い竜のあごの下にあるという玉のことで、命がけで求めなけ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含牙戴角 【読み方】 がんがたいかく 【意味】 牙や角をもつもの。獣の類。「牙を含み角を戴く」とも読む。 【典拠・出典】 『淮南子』「修務訓」 含牙戴角(がんがたいかく)の使い方 含牙戴角(がんがたいかく)...
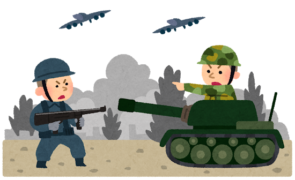 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 干戈倥偬 【読み方】 かんかこうそう 【意味】 戦いで忙しいこと。「倥偬」は忙しい・あわただしい意。 【語源由来】 「干戈」は盾と矛、転じて、戦い・戦争のこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・干戈不息(...
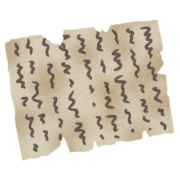 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 韓海蘇潮 【読み方】 かんかいそちょう 【意味】 韓愈と蘇軾の文体を評した語のこと。唐の韓愈の文章は海のように広々としており、北宋の蘇軾の書いた文章は、潮のように力強い起伏があるということ。 【典拠・出典】...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含英咀華 【読み方】 がんえいしょか 【意味】 文章のすぐれた部分をよく味わって、心の中に蓄積すること。また、詩文に妙味があることのたとえ。「英を含み花を咀う」とも読む。 【語源・由来】 「含英」は美しいも...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含飴弄孫 【読み方】 がんいろうそん 【意味】 老人が気楽に隠居生活をすること。「弄孫」は孫とたわむれる意。飴をなめながら、孫と遊ぶことをいう。「飴を含んで孫を弄ぶ」とも読む。 【語源由来】 「含飴」は飴を...
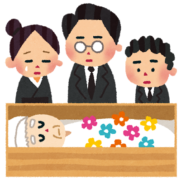 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 銜哀致誠 【読み方】 がんあいちせい 【意味】 哀切な気持ちと誠の心をささげて死者を弔うこと。「銜」は心に抱く意で、「銜哀」は哀しみを抱くこと、「致誠」は真心をささげる意。人の死を悼む時に用いる語。「哀を銜...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 河梁之吟 【読み方】 かりょうのぎん 【意味】 親しい人を送る時の別れがたい気持ちのこと。「河梁」は橋のこと。 【故事】 李陵の詩より。匈奴に捕らわれた漢の李陵が、中国本土に還る蘓武に「手を携えて河梁に上る...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 下陵上替 【読み方】 かりょうじょうたい 【意味】 世の中が大いに乱れた様子。下克上が行われている世をいう。下の者が上をしのいで、上の者が衰える意。「陵」はしのぐ意。「下陵ぎ上替る」と訓読する。 【語源・由...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 烏之雌雄 【読み方】 からすのしゆう 【意味】 是非や善悪が区別しにくく、判断しにくいこと。 【語源・由来】 烏は雄も雌も色が黒くて判別しにくいという意味から。 【典拠・出典】 『詩経』「小雅・正月」 【類...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 瓜剖豆分 【読み方】 かぼうとうぶん 【意味】 瓜や豆を割るように分裂・分割すること。 【典拠・出典】 『文選』鮑照「蕪城賦」 【類義語】 ・豆分瓜剖(とうぶんかぼう) ・豆剖瓜分(とうぼうかぶん) 瓜剖豆...
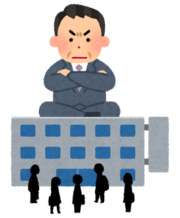 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 瓦釜雷鳴 【読み方】 がふらいめい 【意味】 賢者が相応の評価をされず、能力のない者が重要な地位について、いばることのたとえ。また、讒言が用いられるたとえ。 【語源・由来】 「瓦釜」は、素焼きの土製の釜で、...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 禍福無門 【読み方】 かふくむもん 【意味】 災いや福はその人自身が招くものだということ。わざわいや幸福がやってくるのに一定の入り口があるわけではなく、その人が悪行をはたらけば禍が入り、善行をすれば福が入る...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 禍福糾纆 【読み方】 かふくきゅうぼく 【意味】 災いと福とは、交互にやって来るということ。「禍福は糾(あざな)える縄(なわ)のごとし」と読むこともある。 【語源由来】 「纆」は三つより(一説に二つより)の...
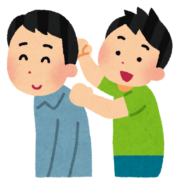 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家貧孝子 【読み方】 かひんこうし 【意味】 家が貧しいと孝行な子供ができるということ。また、人は逆境のときこそ真価があらわれるということ。「孝子」は親孝行な子供の意。 【語源・由来】 「家貧しくして孝子出...
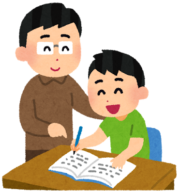 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 過庭之訓 【読み方】 かていのおしえ 【意味】 父の教えのこと。また家庭での教育のこと。「訓」は教え、教訓。 【故事】 「論語」季氏より。孔子がその子である鯉が庭を通った時呼び止めて詩や礼を学ぶように教えた...
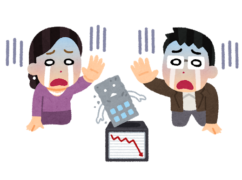 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 華亭鶴唳 【読み方】 かていかくれい 【意味】 過去の栄華を懐かしく思い、現状を嘆くさま。「華亭」は地名。「鶴唳」は鶴の鳴き声のこと。 【語源・由来】 晋の陸機がまさに殺されようとしたとき、かつて華亭で鶴の...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 刮目相待 【読み方】 かつもくそうたい 【意味】 人や物事の成長や進歩を待ち望むこと。また、今までとは違った目で相手を見ること。「刮目」は、目を見開いてよく見ること。「相待」は、相手を待ちかまえること。目を...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 活剥生呑 【読み方】 かっぱくせいどん 【意味】 他人の詩文などをそっくり盗用すること。また、他人の言葉や考えを鵜呑みにして受け売りするだけで、独自性・創造性のないことのたとえ。 【語源・由来】 「生呑」は...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 豁達大度 【読み方】 かったつたいど 【意味】 心が広くて情け深く、度量の大きいこと。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・寛仁大度(かんじんたいど) 豁達大度(かったつたいど)の使い方 豁達大度(かったつた...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 割鶏牛刀 【読み方】 かっけいぎゅうとう 【意味】 取るに足りない小さなことを処理するのに、大げさな方法を用いるたとえ。小さな物事を裁くのに、大人物や大げさな方法・手段などは必要ないということ。また、それら...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 活計歓楽 【読み方】 かっけいかんらく 【意味】 喜びのある楽しい生活。また、 その生活をすること。ぜいたくざんまいの生活。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・贅沢三昧(ぜいたくざんまい) 【対義語】 ・質...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 恪勤精励 【読み方】 かっきんせいれい 【意味】 全力を尽くし仕事や勉学に励んで、怠らないこと。精力を傾けて集中して事にあたること。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・勤倹力行(きんけんりっこう) ・精励恪...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 渇驥奔泉 【読み方】 かっきほんせん 【意味】 勢いが激しいこと。また、書の筆勢が力強いこと。「奔」は勢いよく走る意。のどが渇いた駿馬が、泉に向かって勢いよく走り寄るという意味から。「渇駿、泉に奔る」とも読...
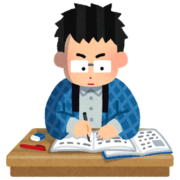 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 軻親断機 【読み方】 かしんだんき 【意味】 中途で志をすててはいけないという教え。 【語源・由来】 「軻」は孟子(孟軻)のこと。「軻親」は孟子の母親のこと。「断機」は織り布を断ち切ること。 【典拠・出典】...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 雅人深致 【読み方】 がじんしんち 【意味】 世俗を離れた風流な人の趣深いさま。「致」は趣・ようすの意。 【語源・由来】 「雅人」は俗を離れた風流な人・奥ゆかしい人。 【典拠・出典】 『世説新語』「文学」 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 禾黍油油 【読み方】 かしょゆうゆう 【意味】 物が勢いよくみごとに生長するさま。「油油」は草などがつやつやとして勢いがよいさまをいう。 【語源・由来】 「禾」は稲、「黍」はキビのこと。 【典拠・出典】 『...
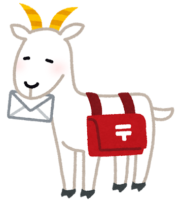 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家書万金 【読み方】 かしょばんきん 【意味】 家族からの手紙は、何よりもうれしいということ。 【語源・由来】 「家書」は、家から届いた手紙のこと。「万金」は、大金の意。出典の「烽火三月に連なり、家書万金に...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 華胥之夢 【読み方】 かしょのゆめ 【意味】 昼寝のこと。また、よい夢のこと。 【語源・由来】 中国の伝説上の聖天子である黄帝は、ある日、昼寝をして夢の中で華胥という国へ行ったところ、そこは平和な理想郷であ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家常茶飯 【読み方】 かじょうさはん 【意味】 ごく平凡なありふれたこと。また、とるに足りないこと。 【語源・由来】 「茶飯」は、毎日の食事やお茶のこと。毎日ご飯を食べ、お茶を飲むようにという意から。 【典...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 和氏之璧 【読み方】 かしのへき 【意味】 この世にめったにないほどの宝物のこと。 【語源・由来】 中国春秋時代、楚の卞和が山中で宝玉の原石を手に入れて、厲王に献上したが、つまらない石と見られて左足を切られ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 歌功頌徳 【読み方】 かこうしょうとく 【意味】 人の手柄や徳をほめたたえて歌うこと。「頌徳」は人徳の高さをほめたたえる意。「功を歌い徳を頌う」とも読む。 【語源由来】 「歌功」は功績をたたえて歌うこと。 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 夏侯拾芥 【読み方】 かこうしゅうかい 【意味】 学問を修めるのが大切なこと。漢の夏侯勝が、学問を修めれば官職を得ることなど地面のごみを拾うように容易だと教えたことから。「拾芥」はごみを拾う意味で、物事のた...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 家鶏野雉 【読み方】 かけいやち 【意味】 ありふれた古いものを遠ざけて、珍しく新しいものを大切にすること。「雉」はきじ。家で飼っている鶏を嫌って、野性のきじを好むこと。 【故事】 中国晋代の庾翼は、はじめ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 鶴翼之囲 【読み方】 かくよくのかこみ 【意味】 左右に長く広がった陣形をめぐらすこと。 【語源・由来】 「鶴翼」は鶴が翼を広げたときのように、左右に長く張りだした陣形。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 廓然大悟 【読み方】 かくねんたいご 【意味】 疑いの心が晴れて確信すること。もとは仏教のことば。 【語源・由来】 「廓然」は、心がからりと開けているさま。「大悟」は、至高の真理を悟ること。 【典拠・出典】...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 格致日新 【読み方】 かくちにっしん 【意味】 物事の道理や本質を追い求めて知識を深め、日々向上していくこと。「日新」は日ごとに新しくなる、日ごとに向上する意。「格致日に新たなり」とも読む。 【語源由来】 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 革故鼎新 【読み方】 かくこていしん 【意味】 古い制度や習慣を改めて新しいものにすること。「革故」「鼎新」ともに、古い物事を改めること。革新の意。 【語源・由来】 「革は故きを去るなり、鼎は新しきを取るな...
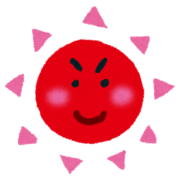 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 赫赫明明 【読み方】 かくかくめいめい 【意味】 勢い良くハッキリと明るい様子。 【典拠・出典】 『詩経』「大雅・大明」 【類義語】 ・明明赫赫(めいめいかくかく) 赫赫明明(かくかくめいめい)の使い方 赫...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 諤諤之臣 【読み方】 がくがくのしん 【意味】 正しいと思うことを直言する人のこと。 【典拠・出典】 『史記』「商君伝」 【類義語】 ・折檻諫言(せっかんかんげん) 諤諤之臣(がくがくのしん)の使い方 諤諤...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 河魚腹疾 【読み方】 かぎょのふくしつ 【意味】 国家が腐敗して、内部から崩壊すること。「腹疾」は腹の病気の意。 【語源・由来】 「河魚」は川に住む魚のこと。魚の腐敗は腹内から始まることから。 【典拠・出典...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蝸牛角上 【読み方】 かぎゅうかくじょう 【意味】 どうでもいいような、つまらないことで争うことのたとえ。 【語源・由来】 「蝸角」は、カタツムリの角の意から転じて、きわめて狭いこと、また、小さいことのたと...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 夏癸殷辛 【読み方】 かきいんしん 【意味】 夏王朝の桀王と殷王朝の紂王。ともに古代の暴君。 【語源・由来】 「癸」は桀王の名。「辛」は紂王の名。「夏」、「殷」はともに王朝の名。 【典拠・出典】 張衡「東京...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 河漢之言 【読み方】 かかんのげん 【意味】 言葉が天の川のように果てしなくとりとめのないこと。また虚言(ほら)をいう。 【語源・由来】 「河漢」は天にかかる天の川のこと。 【典拠・出典】 『荘子』逍遥遊 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 下学之功 【読み方】 かがくのこう 【意味】 手近で初歩的なことから学んで、徐々に進歩向上してゆくこと。「下学」は手近で初歩的なことを学ぶ意。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・下学上達(かがくじょうたつ)...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 花街柳巷 【読み方】 かがいりゅうこう 【意味】 酒色を供することを職業とする遊郭・色町のこと。昔、色町には多く柳や花が植えられていたとも、艶めかしい遊女を柳や花にたとえたともいわれる。「花柳」は、この語の...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 餓狼之口 【読み方】 がろうのくち 【意味】 非常に欲が強く、残忍な人のこと。 【語源・由来】 「餓狼」は飢えたおおかみのことで、残忍で強欲な人のたとえ。 【典拠・出典】 『晋書』 餓狼之口(がろうのくち)...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 苛政猛虎 【読み方】 かせいもうこ 【意味】 民衆にとって過酷な政治は、人食い虎よりももっと恐ろしいということ。 【語源・由来】 あるとき、孔子が墓の前で泣いている婦人を見かけた。泣いている訳をたずねると、...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 画虎類狗 【読み方】 がこるいく 【意味】 才能のない者が本物をまねても、似ているだけで実際は違うものになってしまうということ。「虎を画いて狗に類す」とも読む。 【語源・由来】 「類」は似ること。絵の才能が...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 檻猿籠鳥 【読み方】 かんえんろうちょう 【意味】 自由を奪われて自分の思い通りに生きることが出来ない境遇のたとえ。 【語源・由来】 白居易の「籠鳥檻猿倶に未だ死せず、人間相見るは是何れの年ぞ」(かごの鳥も...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 頑迷固陋 【読み方】 がんめいころう 【意味】 頑固で視野が狭く、道理をわきまえないさま。また、自分の考えに固執して柔軟でなく、正しい判断ができないさま。頭が古くかたくななさま。 【語源由来】 「頑迷」はか...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 魁塁之士 【読み方】 かいるいのし 【意味】 さかんでたくましい人のこと。「魁」は大きい・すぐれている意 【語源・由来】 「魁塁」はすぐれてたくましいさま。 【典拠・出典】 『漢書』「飽宣伝」 魁塁之士(か...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 誨盗誨淫 【読み方】 かいとうかいいん 【意味】 財物を納めた倉庫の戸締りを怠ったり、女性がなまめかしい格好をしてあでやかな化粧をしたりすることは、盗賊に盗みを教え、異性にみだらなことをせよと言っているよう...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 廻天之力 【読み方】 かいてんのちから 【意味】 天下の情勢を一変させるほどの大きな力。また、困難な状況を一変させるほどの大きな力。 【語源・由来】 「回天」は、天を回転させる意から転じて、天下の形勢を一変...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋天蓋地 【読み方】 がいてんがいち 【意味】 天をおおい、地をおおうこと。全ての世界に広く隅々まで行き渡ること。「天を蓋い地を蓋う」とも読む。 【典拠・出典】 - 蓋天蓋地(がいてんがいち)の使い方 蓋天...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 喙長三尺 【読み方】 かいちょうさんじゃく 【意味】 しゃべることがきわめて達者なこと。 【語源・由来】 「喙」はくちばしのこと。くちばしの長さが三尺もあるという意味から。 【典拠・出典】 『荘子』「徐無鬼...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 膾炙人口 【読み方】 かいしゃじんこう 【意味】 広く世間の評判となり、もてはやされていること。 【語源・由来】 「膾」はなますで、生の肉を細かく刻んだもの。「炙」はあぶり肉のこと。どちらも誰の口にもあって...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 亥豕之譌 【読み方】 がいしのか 【意味】 文字の書き誤りのこと。「譌」は誤りの意。「亥」と「豕」とが、字形が似ているので書き誤りやすいことから。 【典拠・出典】 『呂氏春秋』「察伝」 【類義語】 ・烏焉魯...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 睚眥之怨 【読み方】 がいさいのうらみ 【意味】 ほんのわずかなうらみ。「睚」「眥」はともににらむ意。ほんのちょっとにらまれる程度のうらみの意。 【典拠・出典】 『史記』「范雎伝」 睚眥之怨(がいさいのうら...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開権顕実 【読み方】 かいごんけんじつ 【意味】 仮の姿であることを打ち明けて、真の姿を明らかにすること。「権」は仮の意、仏教で、三乗(悟りに至る三つの実践の方法)が仮の教えであり、一乗(仏法には一つの真実...
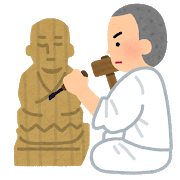 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開眼供養 【読み方】 かいげんくよう 【意味】 新たに造った仏像に目を入れて、仏の魂を迎える儀式。 開眼供養(かいげんくよう)の使い方 開眼供養(かいげんくよう)の例文 今日、お墓を購入したので、僧侶を呼び...
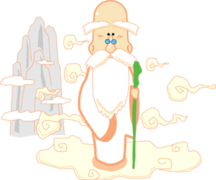 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 荷衣蕙帯 【読み方】 かいけいたい 【意味】 世俗を超越している人(仙人や隠者)の衣服 のこと。 【語源・由来】 「荷衣」ははすの葉で編んだ衣のこと。「蕙帯」はかおり草の帯のこと。 【典拠・出典】 「楚辞」...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海角天涯 【読み方】 かいかくてんがい 【意味】 二つの地がきわめて離れていることのたとえ。天の果て、海の角という意味。 【典拠・出典】 徐陵「武皇帝作相時与嶺南酋豪書」 【類義語】 ・地角天涯(ちかくてん...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋瓦級甎 【読み方】 がいがきゅうせん 【意味】 屋根の瓦と階段の敷き瓦のこと。甎は敷き瓦の意。 【語源由来】 「蓋」はおおうこと。「級」は階段・きざはし。 【典拠・出典】 「韓愈」 蓋瓦級甎(がいがきゅう...
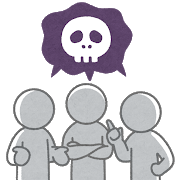 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 誨淫誨盗 【読み方】 かいいんかいとう 【意味】 悪事を人に教えること。財物を納めた倉庫の戸締りを怠ったり、女性がなまめかしい格好をしてあでやかな化粧をしたりすることは、盗賊に盗みを教え、異性にみだらなこと...
 「いろいろな動作」の四字熟語一覧
「いろいろな動作」の四字熟語一覧【四字熟語】 瑰意琦行 【読み方】 かいいきこう 【意味】 考えや行いが普通の人とは違って優れていること。 【語源・由来】 「瑰意」は、普通と異なった、めずらしく優れた心のこと。「琦行」は、普通ではない行為、変わった行い...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語閑話休題の意味(語源由来・出典) 【四字熟語】 閑話休題 【読み方】 かんわきゅうだい 【意味】 それはさておき。ともかく。話が横道にそれたのを本筋に戻すときにいう語。主として文章中で用いる。 【語源・由来】 「閑話」は...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語顔面蒼白の意味 【四字熟語】 顔面蒼白 【読み方】 がんめんそうはく 【意味】 恐怖やけがなどのために、顔色が青ざめて見えるさま。 【典拠・出典】 - 顔面蒼白(がんめんそうはく)の解説 顔面蒼白(がんめんそうはく)の使...
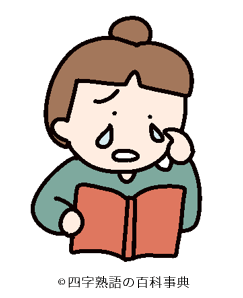 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語感情移入の意味 【四字熟語】 感情移入 【読み方】 かんじょういにゅう 【意味】 自然の風物や芸術作品に対して自分の感情を投射し、それと一体になること。一九世紀末にリップスらが提唱した美学における根本概念。転じて、一般に...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語感謝感激の意味(語源由来) 【四字熟語】 感謝感激 【読み方】 かんしゃかんげき 【意味】 たいへん感謝し感激していることを戯れていった言葉。 【語源・由来】 「乱射乱撃雨霰」のもじり。 【典拠・出典】 - 感謝感激(か...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語我武者羅の意味(類義語) 【四字熟語】 我武者羅 【読み方】 がむしゃら 【意味】 向こう見ずにひたすら突き進むこと。他のことを考えずひたすらあることに専念すること。また血気にはやること。「我武者」でも同意で、「我貧(が...
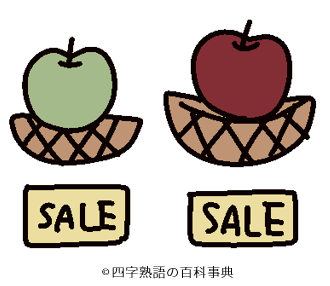 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語過当競争の意味 【四字熟語】 過当競争 【読み方】 かとうきょうそう 【意味】 同業の企業が市場占有率を拡大しようとして起こる過度の競争状態。価格が引き下げられ、正常以下の利潤しか得られない。 【典拠・出典】 - 過当競...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語勝手気儘の意味(類義語) 【四字熟語】 勝手気儘 【読み方】 かってきまま 【意味】 他人のことは気にせず、自分のしたいように行動すること。また、そのさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・得手勝手(えてかって) 勝手...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語各個撃破の意味 【四字熟語】 各個撃破 【読み方】 かっこげきは 【意味】 ①敵の勢力がいくつにも分散しているうちに、その一つ一つを別々に撃ち破ること。 ②関係者が大勢いる場合、関係者一人一人を別々に説得すること。 【典...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語過小評価の意味(対義語) 【四字熟語】 過小評価 【読み方】 かしょうひょうか 【意味】 その実力や価値などを実質以下に判断すること。みくびること。 【典拠・出典】 - 【対義語】 ・過大評価(かだいひょうか) 過小評価...
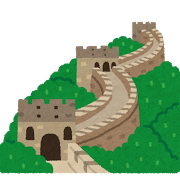 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 階前万里 【読み方】 かいぜんばんり 【意味】 万里の彼方の出来事も近く階前の出来事と同じであるとの意。 遠方の地の行政上の得失も、天子にははっきりとわかっており、臣下が欺くことはできないことをいう。 【語...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語官尊民卑の意味(語源由来・英語訳) 【四字熟語】 官尊民卑 【読み方】 かんそんみんぴ 【意味】 政府・官吏を尊く、民間・人民を卑しいとすること 【語源・由来】 「官尊」官吏、官庁を尊ぶ 「民卑」官位などのない一般の人を...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開源節流 【読み方】 かいげんせつりゅう 【意味】 財源を開拓して流出を節約すること、または収入を増やして支出を抑える健全財政のこと。 【語源由来】 「開源」は水源を開発すること。「節流」は水流量を調節する...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 改弦易轍 【読み方】 かいげんえきてつ 【意味】 法律や制度を改変すること。易轍」は車輪の軸幅を変える意。 【語源・由来】 「改弦」は弦楽器の弦を張りかえ調子を改めること。 【典拠・出典】 『晋書』「江統伝...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 眼中之釘 【読み方】 がんちゅうのくぎ 【意味】 自分に害をなすもののたとえ。邪魔者、いやなやつ、憎らしい人などのたとえ。眼の中の釘(目の中の障害物)の意から。類句として「眼中抜釘(眼中より釘を抜く)」があ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語歓天喜地の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 歓天喜地 【読み方】 かんてんきち 【意味】 大喜びすること。思わず小躍りするような大きな喜び。身の置き所がないほどのたいへんな喜びをいう。 天を仰いで喜び...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 肝胆相照 【読み方】 かんたんそうしょう 【意味】 お互いに心の奥底までわかり合って、心から親しくつき合うこと。心の底まで打ち明け深く理解し合っていること。転じて、心の底、まごころ。また、肝臓と胆嚢が近くに...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 簡単明瞭 【読み方】 かんたんめいりょう 【意味】 単純で易しく、わかりやすいさま。わかりやすく、はっきりしているさま。 【語源・由来】 「簡単」はわかったり、したりするのに手間がかからないようす。また、こ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語完全燃焼の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 完全燃焼 【読み方】 かんぜんねんしょう 【意味】 最後まで全力を尽くすこと。持てる力の全てを出し切り努力して励むこと。 きれいに燃え尽きるさま。 【語源...
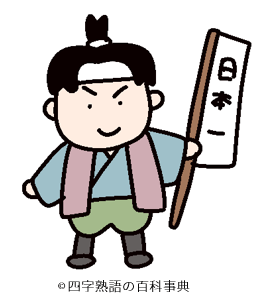 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語勧善懲悪の意味(出典・類義語) 【四字熟語】 勧善懲悪 【読み方】 かんぜんちょうあく 【意味】 善良な人や善良な行いを奨励して、悪者や悪い行いを懲らしめること。 【典拠・出典】 『春秋左氏伝』「成公一四年」 【類義語】...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語https://idiom-encyclopedia.com/category/%E5%85%B8%E6%8B%A0/%E5%8F%B2%E8%A8%98/ 【四字熟語】 韓信匍匐 【読み方】 かんしんほふく 【意味】 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寛仁大度 【読み方】 かんじんたいど 【意味】 心が広くて情け深く、度量の大きいこと。人の性質にいう語。小事にこだわらないこと。 【語源・由来】 人の性質に対して使われる。「寛仁」は心が広くて情が厚いこと。...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 頑執妄排 【読み方】 がんしゅうもうはい 【意味】 分別ができず、ただ一つのことに執着して他を排除すること。 【語源・由来】 「頑」はかたくなに。 「執」はとりついて離れない意味。 「妄」はでたらめな幻。妄...
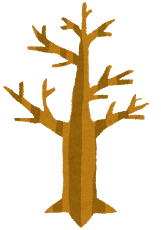 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寒山枯木 【読み方】 かんざんこぼく 【意味】 ものさびしい山と枯れた木々。冬枯れの厳(きび)しい風景をあらわした言葉。 【語源・由来】 「寒山」はひっそりとしてさびしい山。 「枯木」は枯れて、葉が見えない...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語換骨奪胎の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 換骨奪胎 【読み方】 かんこつだったい 【意味】 古人の詩文をもとに独自の作品を作ること。他人の詩文、また表現や着想などに創意工夫を加えて自分のものとして作...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開宗明義 【読み方】 かいそうめいぎ 【意味】 巻頭で全書の主旨を明らかにすること。冒頭で概要を述べること。 【語源・由来】 「開宗」主となる考えを開く「明義」道義に基づいて明らかにする 【典拠・出典】 『...
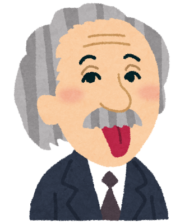 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋世之才 【読み方】 がいせいのさい 【意味】 世を覆い尽くし圧倒するほど勇壮な才能、またそれほどの才能を持った人 【語源・由来】 「蓋世」史記 項羽本紀より「力は山を抜き、気は世を覆う」 世を覆い尽くし圧...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海誓山盟 【読み方】 かいせいさんめい 【意味】 変わることがない愛情を固く誓うこと 【語源・由来】 「海誓」海の誓い。海という存在のように変わることのない誓い、約束。 「山盟」山の誓い。盟は誓いのこと。山...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開心見誠 【読み方】 かいしんけんせい 【意味】 まごころをもって人に接し、かくしだてしないこと。「見誠」は誠意をあらわす意。 【語源・由来】 「開心」はまごころを示す、胸の中を開くこと。 【典拠・出典】 ...
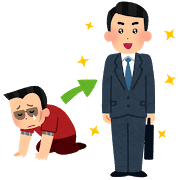 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 回心転意 【読み方】 かいしんてんい 【意味】 過去を悔いて心を入れ替えること 【語源・由来】 「回心」かいしん又は、えしん。 キリスト教などで、過去の罪の意思や生活を悔い改めて神の正しい信仰へ心を向けるこ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語下意上達の意味(語源由来・対義語・英語訳) 【四字熟語】 下意上達 【読み方】 かいじょうたつ 【意味】 下位のものの意見を上位のものに伝えること 【語源・由来】 「下意」下々の者の意見 「上達」下々のことが、朝廷、上官...
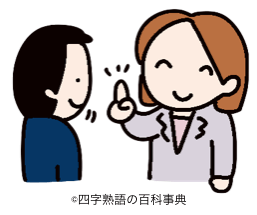 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語外柔内剛の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 外柔内剛 【読み方】 がいじゅうないごう 【意味】 外見は物柔らかで、心の中がしっかりしていること。 【語源・由来】 「外柔」外見は柔らかく、弱く壊...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海市蜃楼 【読み方】 かいししんろう 【意味】 蜃気楼のこと。転じて非現実な考えや根拠のないこと。 【語源・由来】 「蜃」とは大蛤のこと。古くは大蛤が吐く息によって、空中に楼閣が現れると言われていた。「海市...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語鎧袖一触の意味(語源由来・出典・対義語・英語訳) 【四字熟語】 鎧袖一触 【読み方】 がいしゅういっしょく 【意味】 鎧の袖でちょっと相手に触れるくらいの力で、たやすく相手を倒すこと。 【語源・由来】 江戸時代後期に頼山...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語回山倒海の意味(語源由来・出典・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 回山倒海 【読み方】 かいざんとうかい 【意味】 非常に勢いが盛んであること 【語源由来】 「回山」山を回し「倒海」をひっくり返すほどの勢いから、非...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語眼高手低の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 眼高手低 【読み方】 がんこうしゅてい 【意味】 眼識は高くても、実際の技能や能力は低いこと。 知識はあり、あれこれ批評するが、実際にはそれをこなす能力がないこと...
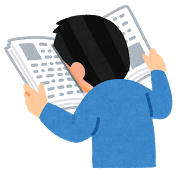 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 眼光紙背 【読み方】 がんこうしはい 【意味】 書物などの読解力が高いこと。 書物や文字の表面だけでなく、深い内容・意味まで鋭く洞察力を働かせて読むたとえ。 【語源・由来】 「眼光紙背に徹す(がんこうしはい...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語眼光炯炯の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 眼光炯炯 【読み方】 がんこうけいけい 【意味】 目がきらきらと鋭く光るさま。 物事のすべてを見抜いているような、人を圧倒する目のこと。 【語源・由来】 「眼光」...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 顔厚忸怩 【読み方】 がんこうじくじ 【意味】 あつかましく恥知らずな者の顔にも、さすがに深く恥じているようすが表れること。 非常に恥じ入ることを謙遜した言い回し。顔にもありありと恥じ入る色が出るという意味...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語頑固一徹の意味(語源由来・類義語・対義語・英語訳) 【四字熟語】 頑固一徹 【読み方】 がんこいってつ 【意味】 非常にかたくなで、一度決めたらあくまでも自分の考えや態度を変えようとしないさま。または、そういう性質。 他...
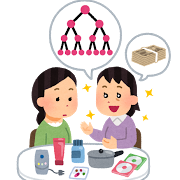 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 甘言蜜語 【読み方】 かんげんみつご 【意味】 甘いことばやうまい話。 相手に取り入ったり、相手の気を引いたりするための甘いことば。おべっか。 相手をついその気にさせてしまうような、うまい話についても用いる...
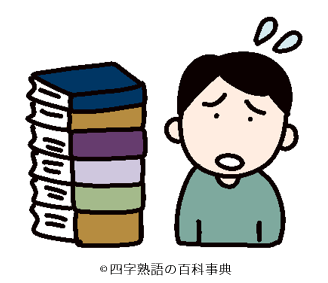 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語汗牛充棟の意味(語源由来・出典・類義語) 【四字熟語】 汗牛充棟 【読み方】 かんぎゅうじゅうとう 【意味】 蔵書がきわめて多いことの形容。転じて、多くの書籍。 物の多いたとえ。 【語源・由来】 「牛(うし)に汗(あせ)...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 緩急剛柔 【読み方】 かんきゅうごうじゅう 【意味】 寛大に接したり、厳しく接したり、時には頑固に、時には柔和に、相手にあわせた適切な対応が自在にできること。 状況に応じ、適切に対処できること。 【語源・由...
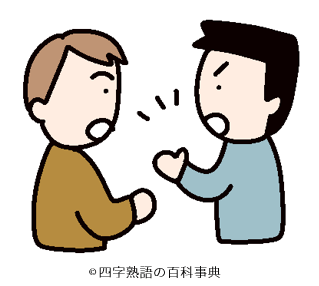 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語侃侃諤諤の意味(語源由来・出典・類義語・英語訳) 【四字熟語】 侃侃諤諤 【読み方】 かんかんがくがく 【意味】 遠慮せず、正しいと思うことを主張して議論すること。また議論のさかんなことをいう。 ひるまず述べて盛んに議論...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 轗軻不遇 【読み方】 かんかふぐう 【意味】 世に受け入れられず行き悩むさま。 事が思い通りにいかず行き悩み、ふさわしい地位や境遇に恵まれないさま。 【語源・由来】 「轗軻」は道が平坦(へいたん)でないさま...
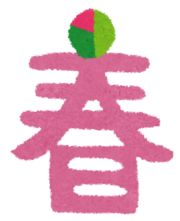 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 閑花素琴 【読み方】 かんかそきん 【意味】 静かに美しく咲いた花と、装飾のない簡素な琴。 閑静な春の雰囲気を醸(かも)し出すもののたとえ。 【語源・由来】 「閑」は静か。「閑花」で静かに咲く花。 「素琴」...
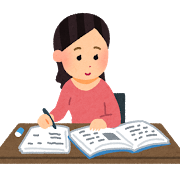 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 戒驕戒躁 【読み方】 かいきょうかいそう 【意味】 驕らず焦らず騒がず、慎んで静かに堅実にやりなさいということ。 【典拠・出典】 - 【英語訳】 ・do it solidly without being a...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 間不容髪 【読み方】 かんふようはつ 【意味】 すぐにということ。非常に差し迫ったさま。髪の毛一本も容れられないほど事と事の間にすきまがないこと。 【典拠・出典】 『説苑』正諫 間不容髪(かんふよう...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 管鮑之交 【読み方】 かんぽうのまじわり 【意味】 互いによく理解し合っていて、利害を超えた信頼の厚い友情のこと。きわめて親密な交際のこと。「管」は春秋時代、斉の名宰相の管仲。「鮑」は鮑叔牙が。単に鮑...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 含哺鼓腹 【読み方】 がんぽこふく 【意味】 人々が豊かで、太平な世を楽しむたとえ。食べ物を口に含み、満腹になって腹つづみをうつ意から。「哺を含み腹を鼓す」と訓読する。 【語源・由来】 「哺」は口に...
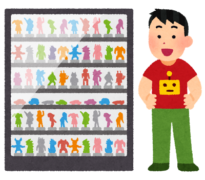 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 玩物喪志 【読み方】 がんぶつそうし 【意味】 無用なものに熱中して、本業がおろそかになること。「玩」はもてあそぶ、むさぼる意。「喪志」は志を失う意。遊びや趣味などに心を奪われ、これをもてあそんでばか...
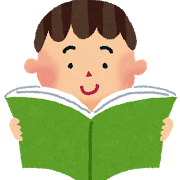 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開巻有益 【読み方】 かいかんゆうえき 【意味】 読書は大変ためになるものだということ。本を開けば、何かしら得るところがあるということ。 【語源由来】 「開巻」は書物を開く意味から「読書」を示します。「有益...
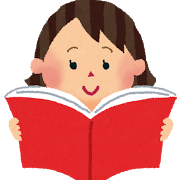 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開巻劈頭 【読み方】 かいかんへきとう 【意味】 物語のはじまりのこと。 【語源由来】 「開巻」は書物のはじめの部分、書き出し。 「劈頭」の「劈」は「裂ける」から転じて「真っ向(まっこう)」の意味で、「頭」...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 蓋棺事定 【読み方】 がいかんじてい 【意味】 死んでからはじめてその人物の評価が定まるということ。また、生前の評価はあてになら ないということ。 【典拠・出典】 杜甫「君不見簡蘇徯」 【英語訳】 ・a p...
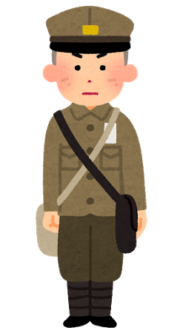 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 肝脳塗地 【読み方】 かんのうとち 【意味】 むごたらしい死にざまや殺され方のこと。また、忠誠を誓って、どんな犠牲も惜しまないことのたとえ。死者の腹から内臓が飛び出し、頭が割られて脳味噌が出て泥まみれ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 汗馬刀槍 【読み方】 かんばとうそう 【意味】 戦場において、馬に汗をかかせて骨を折り、刀ややりを使って戦い、戦功をたてること。 【語源・由来】 「汗馬」とは、馬に汗をかかてほねをおること。戦功をた...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 奸佞邪知 【読み方】 かんねいじゃち 【意味】 心が曲がっていて悪知恵が働き、人にこびへつらうこと。また、そのさま。 【典拠・出典】 - 【類義語】 ・海千山千(うみせんやません) ・狡猾佞奸(こうか...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語艱難辛苦の意味(語源由来・類義語・英語訳) 【四字熟語】 艱難辛苦 【読み方】 かんなんしんく 【意味】 非常な困難にあって苦しみ悩むこと。つらい目にあって悩むこと。 【語源由来】 「艱」「難」はともにつらい、苦し...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 環堵蕭然 【読み方】 かんとしょうぜん 【意味】 家が非常に狭く、みすぼらしくさびしいさま。物さびしく荒れ果てたさま。 【語源由来】 「環堵」は小さく狭い家のこと。四方それぞれ一堵の家の意。 「環」...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 撼天動地 【読み方】 かんてんどうち 【意味】 活動がめざましいこと、人々を驚かすほどの大きな出来事のたとえ。また、音声がきわめて大きいことのたとえ。 【語源由来】 「撼」は、揺り動かす。天地を揺り動...
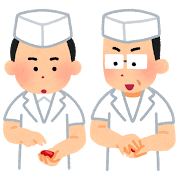 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 外寛内明 【読み方】 がいかんないめい 【意味】 他人にはやさしく、自分には厳しいこと。 外部に対しては寛大に接し、自分自身はよく省みて明晰に己を知り、身を慎むということ。 【典拠・出典】 『蒙求』 【類義...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海闊天空 【読み方】 かいかつてんくう 【意味】 海や空がきわまりなく広がっていること。ここから転じて気性がさっぱりしていて度量が大きく、何のわだかまりもないたとえ。また、言葉や発想などが限りなく広がるたと...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 改過自新 【読み方】 かいかじしん 【意味】 自分の過ちを改めて、気分を新たにすること。自らを省み、そして進歩向上すること。 【語源由来】 「改過」は過ちを認めること、「自新」は改心して気分を一新すること、...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海外奇談 【読み方】 かいがいきだん 【意味】 なんの根拠もないでたらめな話のこと。作り話。インチキな話。「面白くこしらえた話」という意味があります。 【語源由来】 誰も行ったことのない外国の話はどうとでも...
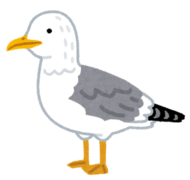 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 海翁好鴎 【読み方】 かいおうこうおう 【意味】 捕まえようとする気持ちを察すると鳥は近寄ってこないことから転じて、野心を人に知られては目的を達成しにくくなるということ。 【語源・由来】 カモメと遊んでいた...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 改易蟄居 【読み方】 かいえきちっきょ 【意味】 武士の家禄を没収して士籍から除く刑罰と、表門を閉めさせ一室で謹慎させる刑のこと。 【語源由来】 「改易」も「蟄居」も江戸時代、武士に課した罰のこと。 【典拠...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 解衣推食 【読み方】 かいいすいしょく 【意味】 人を深くおもいやること。 人に恩を施すこと、人を重用すること。 【語源由来】 「解衣」は自分の着ている衣を脱いで、相手に与えることを意味し、「推食」は自分の...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 格物致知 【読み方】 かくぶつちち 【意味】 事物の道理を追究し、それを理解して、知識や学問を深め得ること。 【語源由来】 中国思想史の用語で、朱子学と陽明学とでは同じ四字熟語でも少し意味が違ってきます。 ...
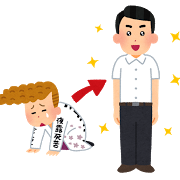 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 改邪帰正 【読み方】 かいじゃきせい 【意味】 悪行を改め、正しいことをするように改心すること。 悪事から足を洗い、正しい方へ向かおうとすること。 【類義語】 ・棄邪従正(きじゃじゅうせい) ・背邪向正(は...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 外巧内嫉 【読み方】 がいこうないしつ 【意味】 うわべはとりつくろっているが、内心ではねたんでいること。 【語源由来】 「外巧」は外面の修飾が巧みなことを意味し、「内嫉」は心の中でねたむ様を示します。 【...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 会稽之恥 【読み方】 かいけいのはじ 【意味】 敗戦の恥辱。他人から受けたひどいはずかしめ。 【語源由来】 「会稽)」は中国の山の名前で、春秋時代の呉と越の戦場跡のことです。 「会稽の恥を雪ぐ」は、他人から...
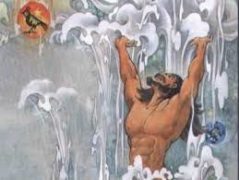 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 開天闢地 【読み方】 かいてんへきち 【意味】 天地の始まりのこと。 これまでの歴史に無いような大きな出来事のこと。 【語源由来】 「闢」は、「はじめる」を意味。 中国古代の伝説上の天子・盤古(ばんこ)が天...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 凱風寒泉 【読み方】 がいふうかんせん 【意味】 親子の情愛の深い例え。特に母子についていうことが多い。親孝行な子がその母を慕う情の甚だ深いことのたとえ。 【語源・由来】 慈愛に満ちた母の情を例えたもの。「...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 和気香風 【読み方】 かきこうふう 【意味】 のどかな陽気とともに、良い香りが満ちていること。穏やかな小春日和についていう場合が多い。 【語源由来】 「和気」は穏やかな気候のこと。「香風」はよい香りや、よい...
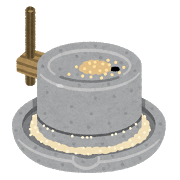 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 磑風舂雨 【読み方】 がいふうしょうう 【意味】 羽蟻の群れなどが石臼を回すようにぐるぐると回って飛ぶときには風が吹き、杵で臼をつくように、上に下にと飛ぶときには雨になるという言い伝え。 物事の兆し、前兆な...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 鶴寿千歳 【読み方】 かくじゅせんざい 【意味】 長寿、長命のこと。鶴は千年の寿命を保つという意味。 【語源・由来】 鶴寿千歳の「鶴寿」とは鶴の寿命。「千歳」は千年の意味。 【典拠・出典】 『淮南子』「説林...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 鶴立企佇 【読み方】 かくりつきちょ 【意味】 待ち遠しく思うこと。待ち望むこと。首を長くして待つ。 【語源・由来】 鶴が立っている姿のように首を伸ばし、つま先立って待ち望むという意味から。 鶴立企佇の「企...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 花言巧語 【読み方】 かげんこうご 【意味】 巧みに飾り立てられているが、内容のないうわべだけの言葉。 【語源・由来】 花言巧語の「花言」とはうわべばかりの実のない言葉のこと、「巧語」は飾り立てた言葉。 【...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 花鳥月露 【読み方】 かちょうげつろ 【意味】 自然に起こる美しい景色を例える言葉。 【語源・由来】 花鳥月露という四時熟語は読んで字の如く、花、鳥、月夜に露がおりると言う意味である。 【典拠・出典】 - ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 花天月地 【読み方】 かてんげっち 【意味】 春の花が咲き月夜地上を照らして明るい美しい景色のこと。 【語源・由来】 春に咲く花が空いっぱいに美しく咲き乱れ、月の光が大地を明るく照らしている風景という意味か...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寒花晩節 【読み方】 かんかばんせつ 【意味】 年老いてからの節義を全うすること。人としての正しい道を踏み行うこと。 【語源・由来】 「節義」とは、節操と道義。冬の花は長い間その香りを保っていることから、人...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 関関雎鳩 【読み方】 かんかんしょきゅう 【意味】 夫婦仲が良くむつまじいこと。仲むつまじいことの例えとして使われる。 【語源・由来】 「関関」とは鳥が和やかに鳴き交わす声の形容。「雎鳩」は水鳥の名前、みさ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寡廉鮮恥 【読み方】 かれんせんち 【意味】 よこしまな心をもち、恥知らずなさま。節操がないさま。 【語源・由来】 「寡」も「鮮」も少ない。「廉」は心が清く正しいさま。 【典拠・出典】 『史記』「司馬相如伝...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 苛斂誅求 【読み方】 かれんちゅうきゅう 【意味】 税金などを情け容赦なく取り立てること。また、そのようなむごい政治のこと。 【語源・由来】 「苛」はむごい、また、責め立てる意。「斂」はおさめる、集める意。...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 華麗奔放 【読み方】 かれいほんぽう 【意味】 極めて華やかで思うままに振る舞うこと。 【語源・由来】 「華麗」は極めて華やかなこと。「奔放」は思うままに振る舞うことから。 【典拠・出典】 - 【英語訳】 ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 臥竜鳳雛 【読み方】 がりょうほうすう 【意味】 才能がありながら、機会に恵まれず、実力を発揮できないでいる者のたとえ。また、将来が期待される有望な若者のたとえ。 【語源・由来】 「竜」は、想像上の動物。「...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 迦陵頻伽 【読み方】 かりょうびんが 【意味】 声が美しいもののたとえ。とても美しい声で鳴くという想像上の鳥の名前。ヒマラヤ山中、あるいは極楽浄土にすむという。 【語源・由来】 梵語(ぼんご)のカラヴィンカ...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 寡聞少見 【読み方】 かぶんしょうけん 【意味】 見識が狭いこと。また、世間知らずなこと。自分を謙遜するときによく用いる。 【語源・由来】 「寡」は少ない意。「寡聞」は見聞の狭いこと。見聞きしてきたものが少...
 「か」で始まる四字熟語
「か」で始まる四字熟語【四字熟語】 禍福得喪 【読み方】 かふくとくそう 【意味】 不幸にあったり、幸福になったり、出世して成功したり、位を失ったりすること。 【語源・由来】 「禍」はわざわい、不幸。「福」はさいわい、幸福。「得」は出世するこ...